本日の朝日新聞の特集に、「教養はどこへ」という論説があり、三人の論者が述べられていました。
教養といえば、硬いですが、学び続けることができること。
ネットは、教養を阻害する危険性も存在します。
自身の考え方に近い情報が集まってくる「フィルターバブル現象」が起きるため。
学び続けるための姿勢がきちんとしていれば、克服できます。
その姿勢は、自分を外から見るもう一人の自分がいるということ。「メタ認知」。
学べば学ぶほど、自分が何も知らないという思いが強くなる。
ただ、そんな中でも、政治となると、最善の知見を持って、決断を出さないとならない。
できる限り、現場の人からの知見を得た上で、結論を出したい。
多くの問いのある自分の中での迷いだけど、学ぶことは、本当に大事だと思います。
学ぶこと自体が、リラクゼーションにもなる。
ただ、時間的余裕もなければ、学ぶこと自体ができないのも事実。
学べる機会はたくさんできるような仕掛けは、行政へも提案していければと思います。
すでに、その仕掛けは、中央区はたくさん持っていますが、さらに、利用しやすく。子ども達にも、開かれたものへ。
*****朝日新聞2025.4.5*****
「教養」はどこへ、論説の中での論者の結論
⚫️批評家 大澤 聡(おおさわ さとし)さん
自分の島の知を元手に、他の島の地へ憶測を働かせる共通点を探れることが教養、それも読書から。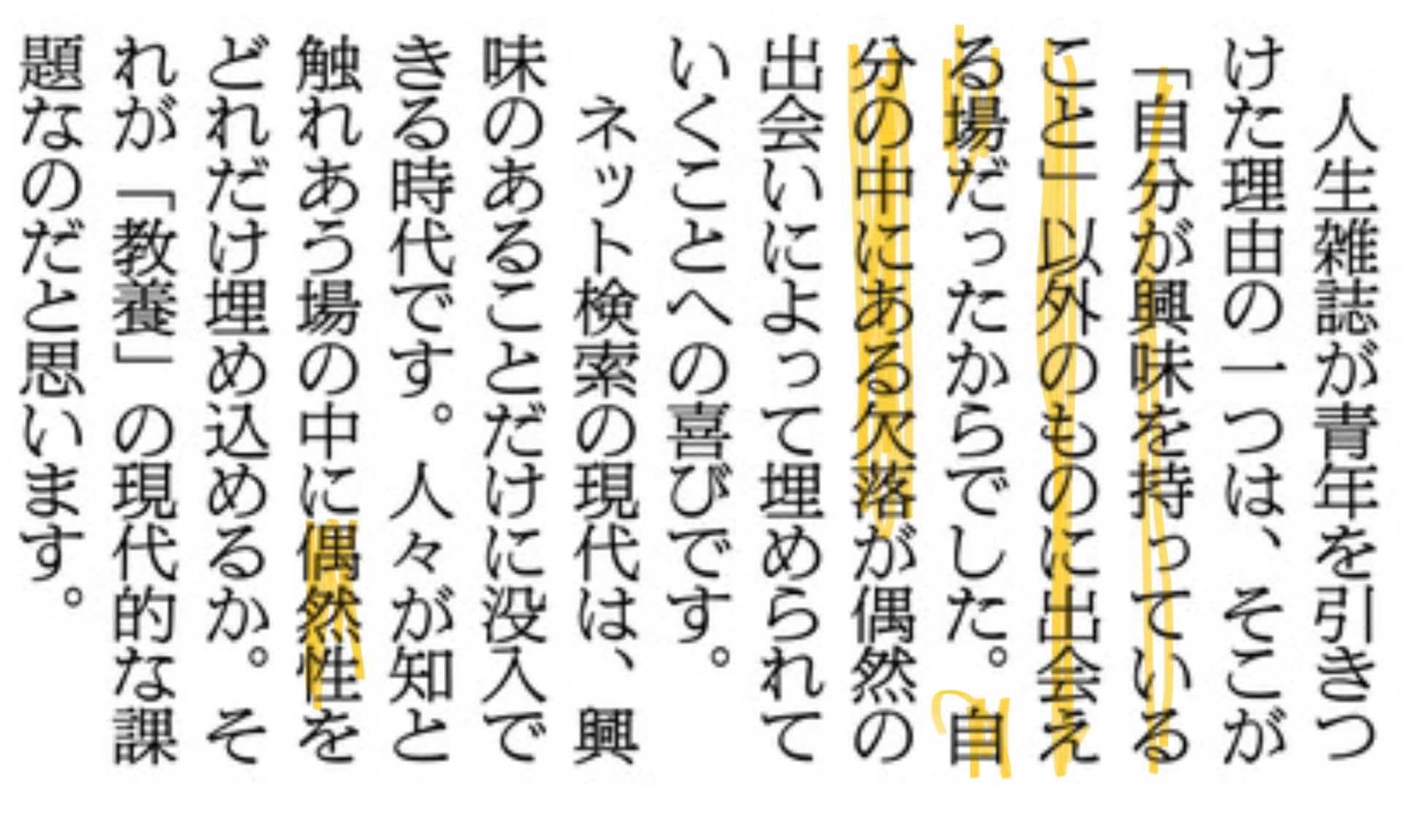
⚫️ドイツ文学研究者 高田 里恵子(たかだ りえこ)さん
教養が、文学・哲学・芸術から、ボランティア活動や田舎暮らしに変わった。
⚫️歴史社会学者 福間良明(ふくま よしあき)さん
知と触れ合う場の中の偶然性、自分の中にある欠落が偶然の出会いによって埋められていくことの喜びがある。

























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます