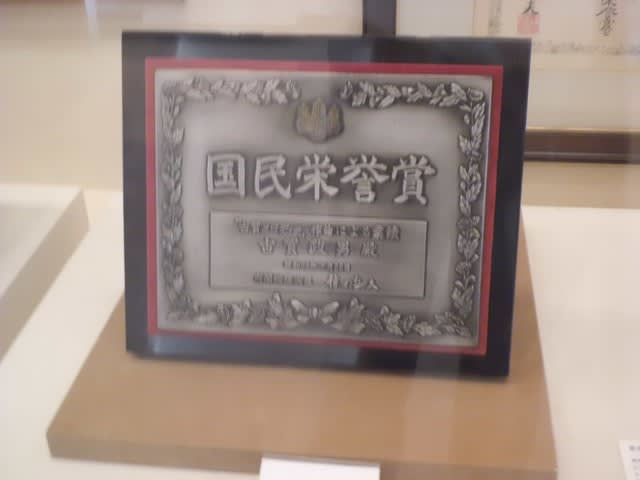先般開催された「海沼 實の唱歌・童謡にんげん史~西条八十 (童謡誕生100年記念)」の中で、海沼実氏は、西条八十が軍歌・軍国歌謡も作詞していたことも触れていましたが、去る23日にブログにアップした記事ではこのことは触れませんでした。 唱歌・童謡を主に記事を考えていたからです。今回、西条八十が作詞した軍歌、軍国歌謡について取り上げます。
「軍歌とは、兵士を鼓舞して士気を高めるために作られたものや兵士の間で歌われた歌であり、軍国歌謡は、国民に対して戦意高揚を広く浸透させるために作られたもので。両者は明確に別ものと言える」と海沼氏は前置きして、最もよく知られている軍歌「同期の桜」について、西条八十が作詞した「二輪の桜」が元歌であり、『君と僕とは 二輪の桜 積んだ土嚢の蔭に咲く どうせ花なら散らなきゃならぬ 見事散りましょ皇国(くに)のため』という歌詞にあるように陸上戦闘の兵士を歌ったものである。現在歌われる『同期の桜』は特攻隊をイメージしている方が多いと思う。」と説明がありました。
さらに、海沼実氏は、講演の中で、「軍歌はもう聴きたくない、という方もおられるかもしれないが、今日は少しだけ時間を頂きたい」として、鶴田浩二が歌う「同期の桜」(台詞入り)を流しました。歌を聞きながら涙を流している方も多く見られました。私も目頭が熱くなりました。
ところで、西條八十は、支那事変での南京陥落の際の上海海軍陸戦隊の戦闘などを念頭に、講談社の雑誌『少女倶楽部』【昭和13年(1938年)2月号】に「二輪の桜」を発表しました。翌年の昭和14年(1939年)7月に 「二輪の桜」を基にした「戦友の唄」がキングレコードから発売されています。
「同期の桜」は、昭和19年(1944年)の後半以降から海軍内で広まっていったと言われていますが、作詞者(替え歌作成者)は帖佐裕中尉で、江田島の海軍兵学校内にあった「戦友の唄」のレコードを聴いてメロディーを覚え、歌詞を変えて歌っていたとされています。海軍内で歌が広まっていくうちに、少しづつ歌詞が変えられ、現在に伝わっているとされています。なお、帖佐裕中尉は、海軍兵学校卒業の後、昭和19年(1944年)9月に山口県大津島で創設された「回天隊」の創設メンバーの一人として搭乗員の訓練指導を行っていました。
「二輪の桜」
西条八十詞 雑誌『少女倶楽部』【昭和13年(1938年)2月号】
君と僕とは二輪のさくら
積んだ土嚢の陰に咲く
どうせ花なら散らなきゃならぬ
見事散りましょ 皇國(くに)のため
君と僕とは二輪のさくら
同じ部隊の枝に咲く
もとは兄でも弟(おとと)でもないが
なぜか氣が合うて忘られぬ
君と僕とは二輪のさくら
共に皇國(みくに)のために咲く
昼は並んで 夜は抱き合うて
弾丸(たま)の衾(ふすま)で結ぶ夢
君と僕とは二輪のさくら
別れ別れに散らうとも
花の都の靖國神社
春の梢で咲いて会ふ
「戦友の唄(二輪の桜)」
作詞:西条八十 作曲:大村能章 歌:樋口静雄 【昭和14年(1939年)7月】
(一)
君と僕とは 二輪の桜
同じ部隊の 枝に咲く
血肉分けたる 仲ではないが
なぜか気が合うて 離れられぬ
(二)
君と僕とは 二輪の桜
積んだ土嚢の 影に咲く
咲いた花なら 散るのは覚悟
見事散りましょう 国のため
(三)
君と僕とは 二輪の桜
別れ別れに 散ろうとも
花の都の 靖国神社
春のこずえで 咲いて会う
「同期の桜」
作詞:帖佐裕 他 作曲:大村能章
(一)
貴様と俺とは 同期の桜
同じ兵学校の 庭に咲く
咲いた花なら 散るのは覚悟
見事散りましょ 国の為
(二)
貴様と俺とは 同期の桜
同じ兵学校の 庭に咲く
血肉分けたる 仲ではないが
何故か気が合うて 別れられぬ
(三)
貴様と俺とは 同期の桜
同じ航空隊の 庭に咲く
仰いだ夕焼け 南の空に
未だ還らぬ 一番機
(四)
貴様と俺とは 同期の桜
同じ航空隊の 庭に咲く
あれ程誓った その日も待たず
なぜに死んだか 散ったのか
(五)
貴様と俺とは 同期の桜
離れ離れに 散ろうとも
花の都の 靖国神社
春の梢に 咲いて会おう
〆
「軍歌とは、兵士を鼓舞して士気を高めるために作られたものや兵士の間で歌われた歌であり、軍国歌謡は、国民に対して戦意高揚を広く浸透させるために作られたもので。両者は明確に別ものと言える」と海沼氏は前置きして、最もよく知られている軍歌「同期の桜」について、西条八十が作詞した「二輪の桜」が元歌であり、『君と僕とは 二輪の桜 積んだ土嚢の蔭に咲く どうせ花なら散らなきゃならぬ 見事散りましょ皇国(くに)のため』という歌詞にあるように陸上戦闘の兵士を歌ったものである。現在歌われる『同期の桜』は特攻隊をイメージしている方が多いと思う。」と説明がありました。
さらに、海沼実氏は、講演の中で、「軍歌はもう聴きたくない、という方もおられるかもしれないが、今日は少しだけ時間を頂きたい」として、鶴田浩二が歌う「同期の桜」(台詞入り)を流しました。歌を聞きながら涙を流している方も多く見られました。私も目頭が熱くなりました。
ところで、西條八十は、支那事変での南京陥落の際の上海海軍陸戦隊の戦闘などを念頭に、講談社の雑誌『少女倶楽部』【昭和13年(1938年)2月号】に「二輪の桜」を発表しました。翌年の昭和14年(1939年)7月に 「二輪の桜」を基にした「戦友の唄」がキングレコードから発売されています。
「同期の桜」は、昭和19年(1944年)の後半以降から海軍内で広まっていったと言われていますが、作詞者(替え歌作成者)は帖佐裕中尉で、江田島の海軍兵学校内にあった「戦友の唄」のレコードを聴いてメロディーを覚え、歌詞を変えて歌っていたとされています。海軍内で歌が広まっていくうちに、少しづつ歌詞が変えられ、現在に伝わっているとされています。なお、帖佐裕中尉は、海軍兵学校卒業の後、昭和19年(1944年)9月に山口県大津島で創設された「回天隊」の創設メンバーの一人として搭乗員の訓練指導を行っていました。
「二輪の桜」
西条八十詞 雑誌『少女倶楽部』【昭和13年(1938年)2月号】
君と僕とは二輪のさくら
積んだ土嚢の陰に咲く
どうせ花なら散らなきゃならぬ
見事散りましょ 皇國(くに)のため
君と僕とは二輪のさくら
同じ部隊の枝に咲く
もとは兄でも弟(おとと)でもないが
なぜか氣が合うて忘られぬ
君と僕とは二輪のさくら
共に皇國(みくに)のために咲く
昼は並んで 夜は抱き合うて
弾丸(たま)の衾(ふすま)で結ぶ夢
君と僕とは二輪のさくら
別れ別れに散らうとも
花の都の靖國神社
春の梢で咲いて会ふ
「戦友の唄(二輪の桜)」
作詞:西条八十 作曲:大村能章 歌:樋口静雄 【昭和14年(1939年)7月】
(一)
君と僕とは 二輪の桜
同じ部隊の 枝に咲く
血肉分けたる 仲ではないが
なぜか気が合うて 離れられぬ
(二)
君と僕とは 二輪の桜
積んだ土嚢の 影に咲く
咲いた花なら 散るのは覚悟
見事散りましょう 国のため
(三)
君と僕とは 二輪の桜
別れ別れに 散ろうとも
花の都の 靖国神社
春のこずえで 咲いて会う
「同期の桜」
作詞:帖佐裕 他 作曲:大村能章
(一)
貴様と俺とは 同期の桜
同じ兵学校の 庭に咲く
咲いた花なら 散るのは覚悟
見事散りましょ 国の為
(二)
貴様と俺とは 同期の桜
同じ兵学校の 庭に咲く
血肉分けたる 仲ではないが
何故か気が合うて 別れられぬ
(三)
貴様と俺とは 同期の桜
同じ航空隊の 庭に咲く
仰いだ夕焼け 南の空に
未だ還らぬ 一番機
(四)
貴様と俺とは 同期の桜
同じ航空隊の 庭に咲く
あれ程誓った その日も待たず
なぜに死んだか 散ったのか
(五)
貴様と俺とは 同期の桜
離れ離れに 散ろうとも
花の都の 靖国神社
春の梢に 咲いて会おう
〆