広州
平成30年 我が国の政官界の実態は、隣国の官吏に同化するように極似してきた。それは欲望の同化であろう。
政、官、経、加えて報道界もつづく。総ては虚を実と装い、本(もと)の無い知は大偽のために用いて、隠し、恫喝さえする。
俯瞰して眺めてみると、旧時代の人間科学ともいえる隣国の事象データーにことごとく符合するものがある。
それは本姓として是認された世界なのか。それとも人間の自傷行為のような欲望なのか。
清濁は併せ呑むと聞くが、欲望から自噴した毒は止め処なく社会を覆っている。
あえて、寒山寺の拾得和尚のように愚者をあざけ哂うつもりはないが、行き着くところくらいはオセッカイしてみたい。

昇(しょう) 官(かん) 発(はつ) 財(ざい)
官吏は昇進するたび財を発する、また民はそれを嘲りつつも倣うものだ
己れ自身を正すことなくして、天下万民を指導することはできない。
私利私欲を抑えながら天理と一体になってこそ、万民の意に添うことが出来るはずだ・・
・日本の経済繁栄と同時に、公々然として氾濫しているのは「偽 私 放 奢」だ。これを除かなければ政治を行おうとしても、行う方法がない・・
(文中より)
佐藤 慎一郎 先生
寶田 時雄 対談清話より 平成5年作製
《昇官発財》とは
学問の目的は「財」にあり。
学問するところ地位があり。
地位あるところ権力と財を発す。

そのⅡ 本文
(1)貪らざるを以て寶(タカラ)と為す
春秋時代、宋の宰相に子カンという人がいた。廉潔を以て聞えた人であったという。ある人が、この子カンに玉(ギョク)を献上しようとした時、子カンは
「私は貪らないことを寶としている。あなたは玉を寶としている。もしあなたが献上しようとしている玉を貰ったら、私は貪らないという寶を失ってしまうし、またもしあなたが献上しようとしている玉を私に献上してしまえば、あなたにも宝は無くなってしまう。結局、二人とも宝を失ってしまうことになるから、お断りする」と言って之を退けたという(左氏、襄、十五)
(2)廉にして化有り
戦国時代、斉の第三十一代宣王(前456~前405年)の時、田稜(テンショク)という宰相がいた。その時、彼は下役の者から莫大な賄賂を貰い、その金を母に贈った。
ところが彼の母は、その金の出所を問い詰め、
「不義の金は受け取ることはできない。不孝の子は我が子ではない」
と云って、これを拒んだ。
田稜宰相は、心から恥じ。そのことを宣王に言上し、断罪を願い出た。宣王は、田宰相の母の清廉なのに感動し、母には賞金を賜い、田宰相の罪は許した。
「穫母廉にして化有り」(列女伝、母儀伝)
田稜の母は清廉で、ついに息子の田稜宰相を感化したという言葉が残っている。
(3)子牛を留む
後漢の第十四代献帝(1 8 9~220年)の時、時苗という人が安徽省寿春県の県令となった。時苗は若い時から清廉な人であった。時苗が転勤する時、
「私がこの県に来た時には牛を連れてやって来たが、その牛が、此処で、一匹の小牛を生んだ。この小牛は、この土地のものである。だから、私はこの小牛は、此処にこのまま留めて置いて去る」
といって転勤していった。(三国志 魏志 常林伝 注)

天安門 筆者
(4)「清白宰相」(清廉潔白な宰相)
北宋時代の進士で杜衍(トエン)いう人がいた。第四代仁宗(1o22~1o63年)のとき、多くの弊害を改革した名宰相である。
彼が宰相の時も、贈答品や贈物などを、彼の家に届けに来る者が一人もいなかった。それで、その時の人々は、彼のことを
「清白宰相」(清廉潔白な宰相)と称したという。
「笣苴(ホウショ)(贈答品、賄賂)、貨殖(金儲けをするような品物)、敢えて門に到らず」(渕鑑類函)と記されている
(5)両袖清風
明代には、地方官が参内して拝謁する時、その地方の特産物を、時の権力者や皇帝に贈るのが慣例であった。
明の第三代永楽帝(圭402~1424年)の時の進士、干謙が、巡撫(主として軍務を掌る)に任ぜられた時、その悪弊を断つべく、一物も持たずして入京した。
そして自分が、北京に持って来たものは
「面袖清風」(干謙、入京詩)
だけだ、という詩を作ったという。それ以来、清廉な官吏を形容するのに「両袖清風」と云うようになった。
銅臭紛々の官界
後漢の第十一代桓帝(146~1 6 7年)、第十二代霊帝(168~189年)時代の童謡に
「寒素清白も濁れること泥の如し」とある。
貧しい生活をしていても、代々操を保っている家のことを「寒素」といい、また代々清廉潔白を保っている家のことを「清白」といって、昔はこれを表彰してきたが、後漢の桓帝、霊帝の時代には、それが乱れてしまった。これを歎いた童謡である と云う(諸桟敷次著、「中国古典名言事典」、500買)
「五寒」参考
いくつかの事例を拾ってみることにしよう。
(1) 人みな銅臭を悪む
後漢の第十二代霊帝の頃には、銭を以て官爵を貿うことは、公然行われていた。
郡守(郡を治める役)、九豪(九人の大臣の中の一人)を歴任した崔烈という人も、銭500万を出して、司徒(丞相)という高官を買っている。漢代では丞相のことを`「大司徒」と称し、大司馬(軍事をつかさどる)、大司空(法務の長)とともに、三公に列せられるほどの高位高官であった。そのようなポストを金で買ったというのである。
その時、その崔烈の息子が、父に対して、
「人、みなその銅臭を悪む」
世間の人々は、あなたのことを、銅臭(金銭のにおい)が紛々としていると云って、みないみ嫌っていますよと、云ったと記録されている。
(2) 金が裁く裁判
中国では大昔から
「千金は死せず、百金は刑せられず」(周、尉繚子)
千金を出せば、当然死刑の者でも死刑にならないし、百金出せば、当然刑せられるべき者でも刑は受けない。すべて金次第であると云われてきている。
漢の諺に、「廷尉(裁判を掌る官)の獄、平らからなること砥の如し。銭有れば生き、銭無ければ死す」 □
又魯褒(ロホウ)(晋南陽の人)の銭神論に、「死も生か使む可く、生も殺さ使む可し」(清、通俗論)とある。
砥石の面のように公平な裁判でさえ、金銭の力は人間の生命を左右するだけの力をもっていると云うのである。
(3) 銭で動く官吏登用試験
唐の第六代、玄宗の天宝時代(742~756年)の進士で、礼部侍郎(礼節の次官)の職にあった張謂という人があった。彼の詩に
「世人交わりを結ぶに黄金を須(もち)う。黄金多からざれば、交わり深からず。たとえ然諾暫くは相許すも、終には是れ悠々行路の心」と云うのがある。
(4) 同じ《、唐の第七代粛宗(756~762年)時代に、皇帝を諌める「諌議大夫」に抜擢された高適という人がある。彼は気節の高い人で、文字通りに皇帝に直言したため、君側の高官たちは、彼を正視することができず、みな横目で見たという。その彼に
「世入交わりを結ぶを解せざるは、ただ黄金を重んじ、人を重んぜざればなり」
という詩がある。それは、金銭第一、人間不在の当時の世相を、諷したものであろう。
同じく、唐の人の書いた本に、
「当今の選、銭に非ざれば、行われず」(朝野合載)とある。
唐の鄭アンいう人が吏部侍郎(吏部の次官)となって、文官の採用とか、勲等の階級をきめたりする役目を荷っていた。
その鄭アンが官吏登用の面接試験に立ち会った時、受験者の一入が自分の靴ひもに“百銭”をつなぎとめていたので、問い詰めてみると、“この頃の試験は、銭を使わなければ、どうにも、うまくいきませんからね”と答えたという。《明大の替玉事件、日本の選挙は銭挙》

馬賊の頭目 1989 筆者談
(5) 金で買売される官位
「生来読まず半言の書。ただ黄金をもって身の貴きを買う」
(末、黄堅編、「古文真宝」)
生まれてからこのかた、一言半句の書も読んだこともない。ただ金銭をもって高位高官を買うだけだという。
清朝時代でも、金銭を出して文武官員となった人のことを「損納出身」と公然と云っていた。政府に納めた金額に応じて官職を買ったり、一品以下従九品に至る品級を買うことは制度として保障されていたのである。 「例 補欠献金」
そればかりではない。官吏として当然やらねばならない任務にしても、金銭を「損納」することによって、公然と免除されることが規定されている。民を愚弄すること、甚しいというほかはない。
清朝は亡ぼされたのではない。自ら亡んだのである。
(6) 中飽
中飽の「飽」とは、腹一杯に食べるということである。中飽とは中間に立つ者の腹が脹れるという意味である。具体的に云うと
「凡そ公款は、上は国に帰さず、下は民に帰さず、中間の手を経た人が之を侵呑(公金をごまかして着服する)したばあい之を中仙と言う、」(六部成語補遺)
この中飽という言葉は、韓非子(?~前233年)がすでに使っているが、ここでは清朝時代の中飽状況をお伝えしておこう。
「其の地方官たるや、総督と巡撫は司道に取る。司道は府州県官に取り、府州県官は則ち人民より掊克(ほうこく)(苛税を課して搾取する)す。是を以て、人民の負担いよいよ重し。その官に輸納(納税)し、以て地方及び中央の公費に供するものは、僅か一分に過ぎず。その餘は則ち尽く官吏の手中に帰し、以てその私嚢(自分のふところ)を豊かにす。名付けて中飽と曰う」(清国行政法汎論)と記録されている。
総督とは地方長官で、直隷総督一人、両江総督一入。巡撫とは天下を巡行して軍民を安撫する役。司道とは、布政司(清末には総督、巡撫に直属していた。一省の民政を管掌)、按察使(按察使を以て一省の司法長官とす)塩運司(塩に関する事務を掌る)、糧道(運送事務を掌る)のごとである。
要するに中飽とは、政府の倉庫は空になり、万民は餓えに苦しむが、その中間における姦吏たちの財布は一杯になるということである.
「飽暖必らず淫欲を生ず」
腹一杯食べ暖かに着ている者には、淫心が起り、必ずロクなことはない。
ところが「官清衛役痩」
上官が清廉であれば、役所の小役入たちは痩せてしまうと云う俗言もある。

佐藤先生ご家族 新京
(7)賄賂は公然と行なわれていた
後漢に楊震という非常に博学な人で、関西の孔子とまで称された人がいた。
王密という人が楊震の所へ来て、金十斤を出して、暮夜だから誰にも分からないからと云って贈ろうとした。
楊震は「天知る、地知る、我知る、子知る」(後漢書、楊奥伝)
それなのに、どうして知る者が無いなどと言えるだろうかと言って、披を戒めた。王密は非常に恥じ入って去ったという。
なかなか味のある、さっぱりした一宵の清話である。
ところが実際の中国社会では、賄賂は、世間憚らず公然と行なわれていたようである
「官児不打送礼的」(官吏は贈物を持って来る者は叩かない)という俗諺は、今日でもそのまま生き続けている。
・
大体下役の者が賄賂を送り。上役がこれを受取る。大抵の場合は、みな密かに行なっている。ところが日が経つにつれて、大胆となり、入に知られることなど怖れもせず、公然と之れを行なっている。
法令を掌る役、人などが、色々探聞して、官吏の非行を指摘して懲戒を要請する公文書は、その罪を称して、「賄賂公行」と公然と書いている、と説明している(六部成赳)
「閣官便佞(ベンネイ)の徒、内外こもごも結び、転じて相引進し、賄賂公行、賞罰無く、綱紀ホウ乱す」(南史、陳、張貴紀伝)という記録がある。
宦官や口先ばかり巧みで実のない連中が、内外互いに結託し、さらに転じて互いに引き立てあい、賄賂は世間を憚ることなく公然と行なわれるようになり、賞罰は無く、国家の綱紀は乱れ切っていた。
南北朝時代、陳の後主 第五代(582~589年)の紀張麗華は、十歳の時選ばれて宮殿に入った。その性は聡恵(才智のすぐれたこと)で、多くの官署の悛入たちが奏上に来た時には、後主は何時も華麗を膝に抱いたまま一緒に事を決していた。遂には扱主の寵をたのんで、権力を弄び、綱紀を斎乱した。
陳の禎明(587~589)の末、隋兵が台城(江蘇省江寧県北)を陥(おとし)入れた時、後主は張、孔二入の妃と共に井戸の中に陰れたが、ついに捕えられて斬に処されている。
とにかく、宮廷や政府に勧めている者は、互いにかばいあいながら、“昇官発財”だけを考えているのだから、どうにもならない。
「同悪相すくいあって、自ら天を絶つ」連中の巣窟が、宮廷であり、官庁であるようだ
私たちは
「悪小なるを以て、之を為すことなかれ」
と学んでいるのに、彼ら役人どもは、たがいに競いあって
「悪小なるを以て、之を為さざること勿れ」と励んでいるようである。
現在の中国大度の一般社会や官界を見ても、賄賂をうけて法を枉(ま)げたり、私腹を肥やしている実状は、目に余るものが多いようである。
例えば、日本に留学に来ている留学生に、聞いてみればすぐわかる。賄賂を出さずに来ている者が居るとしたら、それは大幹部の子女であろう。
つづく

 言うべきことは、云う 後藤田正晴
言うべきことは、云う 後藤田正晴























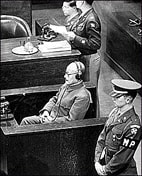





















 児玉源太郎の観人則(人物をみる眼)
児玉源太郎の観人則(人物をみる眼) 後藤新平
後藤新平



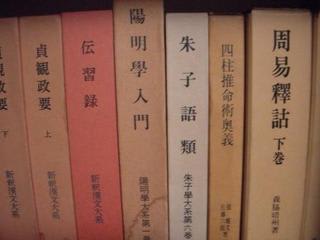



 整理整頓
整理整頓
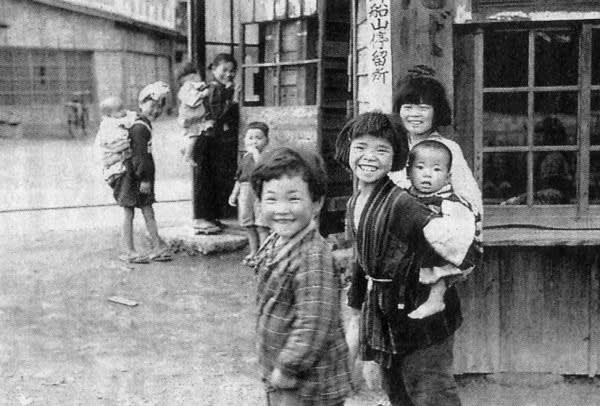





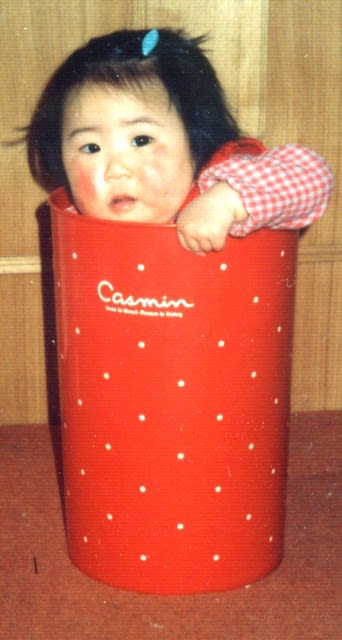



 それは「人間考学」から生ずる英知の欠落でもあった。
それは「人間考学」から生ずる英知の欠落でもあった。










 台北小年鑑護署 (鑑別所)
台北小年鑑護署 (鑑別所)
 台湾台北看守所(刑務所)
台湾台北看守所(刑務所)  小学校の自治運営
小学校の自治運営 






