
津軽岩木
※ 懐・・・カネ勘定
雅(みやび)心までとは思わないが、下衆な下心を隠すような騒がしい人間が増えてきた。
軽薄と見た大衆に迎合し、商業売文に勤しみ、紙離れの昨今は名を知らしめて口舌の輩になり漫談並みの講演を稼ぎにしている言論貴族も増えている。
それは、国家の外敵危機を煽り、経済予想で懐銭の多寡を憂慮させ、さも容易な解決策を無責任、かつ詐欺的話法で食い扶持稼ぎ場として浮俗に漂っている。
ある週刊誌の記者だが退職して物書きになった。ネタは戦記物の逸話や事件物だが、情感が薄いせいか物語小説は書かない。小説と言っても明治のころは、今でいう漫画の類で、格落ちの売文屋と蔑まれていた徒の部類だった。
商業として成り立つようになると部数を競い、勝手に大衆文学と称するようになると、流行りのカルチャー(文化)に乗じ、新聞連載やテレビの出現などで、いつの間にかオピニオンリーターや文化人などとして持て囃されるようになった。
その記者あがりの物書きだが、近ごろは本も売れない。昔は何十万部あったヒット本も最近では数万ないし数千にもならない部数もあるという。よって講演で稼ぐようになる。
義を講ずる講義ならぬ、講演と称して「大衆漫談」と洒脱に語ったのは安岡正篤氏だが、高学歴無教養といわれる最高学府でも義を講ずる人物は乏しくなっている。
その物書きに講演を頼んだことがある。相場は20万。それも一コマ90分の大学より少ない60分くらいだ。あのS女史は80万だ、と相場を比較して教えてくれた。
スポーツ選手の誰それは一時間何百万、北野たけし氏はも顔出しで何百万、政治家だって車代がある世情だ。
10年位前の話だが、東北の某県では知事の誕生日を各支部で催して一か所2百万、結婚式の顔出しで同額と聞く。物書きのそれはアゴ足付き。ホテルと交通費と宴会付きだが、新幹線はグランパスクラスだ。主催者経費は会場と動員を含めて50万はかかる。
その動員と言っても、軽カルチャーに浸っているご婦人が多いせいか、香水が漂っている会場だ。参加者は50人くらいでも、それでも東京の、たまにテレビでコメントを語っている物書きの話しを聴きに来る、いや、その物書きを見に来ている。
内容はともかく、「観てきたよ」が感想だ。

台湾緋桜 東御苑
以前、司馬遼太郎が産経のコラムに講演のことを書いていた。
苦てな講演を頼まれたとき、前の方で私語を交わしていた。それが気になって「負けてしまった」と記していた。
亡くなった直後、著作の権利をもっている出版会や産経が祭上げ、ひと稼ぎを企てた時だった。
その世界で食っていく人間には邪魔な一言だったが、拙文を備忘として残したことがある。
以下、「不学無術の伸吟」より抜粋
◇ 「空しくなった、負けてしまった」 ◇
物書きはその講演の最中に聴衆が好き勝手に昼食の話や世間話をする「私語」に負けた、空しくなったと散々おもいで感想を書いています。
しかも、「私語」に苦労している教授の話を同様な煩いとして、さも自らの体験をなぞるように 引用しています。
ある日の稿では、小便がちかいため、陛下の御進講の際に中座して厠の案内を皇太子に尋ねた状況を書いています。
「空しくなった」「負けてしまった」という「私感」はともかく、聴衆の分(ぶん)が合わなかったというのか 、それとも員数合わせの善男善女なのか、読書でいえば「読めないのか」「読まれないのか」あるいは聴衆が庶世の哲人であるためか、どうも講演者の側に妙な錯覚があるようです。
世に言論貴族、売文の輩と軽称されている部類によく見かける煩いでもあります。
知識人の幼児性は大衆の内なる嘲笑を感ずる事なく、単に「文壇」や「言論界」の中でしか通じない隔離された兵隊ごっこがまかり通っていることに気が付かないようです。
無いよりは有ったほうが幾分マシだが、何ら人格を代表することのない付属価値である、地位、名誉、学歴、財力を唯一の糧として倭人特有の群行群止を促すような、いとも高邁な珍説、奇説、はたまたは覗き、脅し、予想を虚飾する輩にゆめゆめ惑わされてはなるまい。
隣国では知識人を「臭九老」と称して淫売婦の上、上から数えて九番目に卑しんでいます。
宋代では皇帝が学問を奨励するために「勧学文」を掲げ“書中、自(おの)ずから黄金の部屋あり”“書中、自ずから女あり”と、食色財の欲望に直接勧誘することにより、それなりの学問が盛んになったといいます。
「利は智を昏(くら)からしむ」というべきか、明の攻略にひとたまりもなく滅んだ状況が目に浮かぶようです。 何のために学び、何に問うのか、「本」(もと)を問いたくもなります。

佐藤慎一郎先生
◇ 「座して尿せよ」 ◇
空しくなった物書きは明治の言論人、陸羯南を書き遺そうとしたという。
ある章に「陸羯南がいなければ俳句など電池の切れた懐中電灯の殻のようなものだった…」
 陸 羯南
陸 羯南  山田 孫文
山田 孫文
「今の入社試験では採れないような正岡子規、長谷川如是閑など…」と敬意を込めて記述している。
陸羯南といえば青森県弘前市在府町、真向かいは辛亥革命に挺身し、日本人で最初に犠牲となった山田良政。孫文の臨終に唯一日本人として立ち会った純三郎兄弟の生家である。
良政は幼少より羯南に可愛がられ、異国の革命を我ことのように奮闘にするような、時代に先駆けた教育の基が養われのです・・・・
・・・・山田兄弟の「不言の教え」で育てられた佐藤慎一郎氏は昭和初頭に旅順水師営の中国人小学校の教師として赴任、北京留学を経て満州国崩壊を期に帰国しています。
その風貌は「王道は人情に基づく」といった大らかで暖かい雰囲気を醸し出し、「他」に対する勇気と熱情は異民族の心底さえもを揺り動かし、民情に基づく透徹した推眼は国策遂行にも欠くことのできない助言者でもあります。
その佐藤さんが講演依頼されたときのこと、寒かったせいか便所に立つものも多く、物書きの言う「私語」と同様な状態でした。
「座して尿せよ」(座ったままで小便をたれろ)
九十を越えた今でも、五十人ぐらいの聴衆ならマイクなしで立ったまま講義する佐藤さんが「座して尿せよ」と、大声で叱責したので一同金縛りにあったように時が止まった。
「私は真剣だ。明日再び会えないかもしれない。いや明日死ぬかもしれない。今日という一日を皆さんと一緒に過ごしている。今日という一日は二度とない。君たちとの大切な時間ではないか。」
そこには「空しくなった」「負けてしまった」といった敗北感はない。 物書きが追い求めた明治の実直さと勇気、そして慈愛に裏打ちされた熱情があるだけだ。
なかにはこんな明治もある。
講演を依頼されると員数は、どんなレベルか、会場は、謝礼はと、言論貴族の権化みたいな放談で著名な老評論家だが、伝を頼って陛下に拝謁した折り、侍従のワイシャツのメーカーを話題に供し不興をかったり、実直な民族思想家に「死んだら銅像が建ちますよ」と述べた途端、「口先で迎合したようなことを言わずに自分の番組で僕の考えを伝えたらどうだ」と一喝されたような人間もいる。
佐藤先生が引用した 「座して尿せよ」とは、戦国武将の軍議の場で子供が小用に立ち上がった際、「明日の決戦で生きるか死ぬかの大切な会議をしているのに小便ぐらい我慢できないか。一言でも聞き漏らさず その場で座ったまま小便をしろ」と、叱責した情景を模してのことである。
同様な場面だが、物書きの一文にも明石元三郎と山縣有朋の真剣な会話の情景が書かれている。
簡略に著せば、厳冬の季節に明石が山縣に情勢報告を行っているさなか、真剣さのあまり尿意を忘失、小便を垂れ流し、それが山縣の外套に染み上っても、そのまま続けたという姿である。
上下関係や現場の状況より、「公」にもとづいた談義はときとして肉体的生理を超越した「狂」の位置にある。
あの長州閥を率いて権勢を布いた山縣だがこんなこともある。
(参考抜粋終わり)


佐藤先生は、まず対価は受け取らない。対価は講義後の懇親会と交通費の実費くらいだ。
しかも、講義の前段は、短いもので一週間余を掛けた教授案の作成だ。
それを取りまとめれば、そのまま書籍になる精密な文章だが、資料として一部は朗読するが、多くは一期一会の出会いと自身が考えている、緊張した脳内整理というものだ。
住まいは荻窪団地の3階の年金暮らし、90歳になっても研究は欠かさず、病弱の妻と二人暮らしだ。

しばしば酔譚を・・・
その状況を筆者の備忘録から抜粋する。
師弟酔譚「荻窪酔譚余話」より
杉並区の荻窪住宅23楼301号の住人、佐藤慎一郎宅には多くの客人が訪れる。
さて、幾人が荻窪南口から経由する団地行きのバスに思い出を乗せたことだろう
文章定かではないが梅里先生(徳川光圀)の碑文にこんな刻文がある
「第宅器物その奇を用せず、有れば有るに随い、無ければなきに任せてまた安如たり」
書棚に囲まれた部屋に、まるで帰宅するような厚かましさで拝聴する無恥と無学の懇請は、まさに附属性価値を排して、無名で有力であれと諭す佐藤先生と懇意な碩学の言に沿ったものでもあろう。
はじめは異質、異文化の世界かと伺っていると、浮俗にまみれていた自分に気付く。
驚くほどに透明感のある率直な欲望を鳥瞰して、そのコントロールの術を自得する人間
学の存在を認識する。いわゆる「自ずから然り(自然)」と人間の同化と循環、そして離反に表われる歴史の栄枯盛衰を自らが解き明かす(自明)という吾の存在の明確化という真の学問の探求に他ならない。
不自由な身体を運び、3楼から道路まで見送りに降りる姿は、多くの明治人が醸しだす、
いとも自然な実直さを漂わせ、乗車、発車から車影が微かになるまで手を振る姿に車窓が涙
でおぼろげになることも屡だった
交談は、「話」という舌の上下ではなく、体験に観た吾そのものを伝える「語り」であり、知識や物珍しさの収穫ではなく、感動と感激の継承という人間を探求して「学んだら行う」学問の姿であった。
もちろん、巷間の学者、研究者の類にその薫りを観ることはない。
(抜粋おわり)
有名を追わず、淡々とした学究は人に囚われたり拘らない、もちろん財貨の欲求もない。
「金や地位の関係は作為を生む。無条件の愛情は真の信頼を生む。あの中国の庶民はその細やかな人情を感知できる。人情は国の法律より上だ」

碩学と謳われた安岡正篤氏も古典の深淵さと躍動感を佐藤氏に訊いている。
交誼は水魚の如くだが、謙譲の精神で「間(マ)」を大切にして語り合っている。
安岡氏が病に陥ると代講を懇嘱され度々受任している。
以下、ふたたび拙章「不学無術」より
いずれ放心から醒めた庶世の哲人は「分」を錯覚した物書きをしたたかに嘲笑し、時流の余興にしてしまうでしょう。
それは政治家、教育者の唱えまでも漫談や娯楽の類いにしてしまうことにもなります。
その結果は、何れ到来するであろう指導者の哀願や、訴えといった状況が空虚に陥る過程でもあります。
人が公私をわきまえた他の存在を信じられないとき、あの大観園の親分の言っていた泥水同化の招来をくい止めることが不可避となります。
明治の賢人は「明治」を語ることに虚飾はない。
舌の上下である「話術」の講演でもない。吾を語る「講義」があるのみです。
極論すれば肉体的衝撃から我が身を保身するため、媚文芸言を駆使していざとなったら逃避する有名無力の穢利偉人(エリート)特有の術などはそこにはない。
耳から入って直ぐに口から出るような「口耳四寸の学」や、その場、その時で演技をする「逢場作戯」のような講演者では、内容より事の大小、多少、巧拙に囚われた文章や話になって当然であるといえるでしょう。
「空しくなる」のは聴衆の側です
筆者の独り言だが、孔子さまも一語忘れているようだ。
「巧言令色、仁すくなし」と仰せになったが、当世では「巧言麗文、義すくなし」だろう。
佐藤さんは、時運に迎合した組織の運営が本来の目的を忘れ、参加者の多少のみを憂うる主催者に対して、
「本(もと)立って道、生まれる。一人でも小なしといえず、千人でも多しといえず」と、その多勢の衆を恃む目的の錯覚を諭しています。
なぜなら、聴衆のなかで真剣に聞くものがあればが一人でもいい。「国は一人によって亡び、独によって興きる」ということを土壇場の実感として分かっているからです。
二時間の講義に一週間前から草稿作成に取り掛かり、自らのものとして真剣に臨む姿は、物書きのいう明治の実直さを体感できる講義でもあります。
「教育は魂の継承にこそ本当の意味がある。それが今を真剣に生きるものの歴史に対するささやかな責任であろう。そして邪魔にならないうちに消えさることです」と、常々、語っています。
「 亡国は亡国の後、その亡国を知る」といいますが、記誦の学の餌食になって昇位発財した知識人の幼児性は、その錯覚した現象とともに亡国の徴であるかのようにおもえてならない。




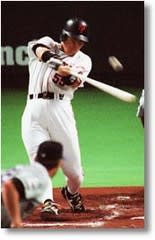






















 も組 竹本
も組 竹本




 陸 羯南
陸 羯南  山田 孫文
山田 孫文






























