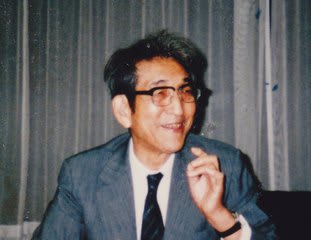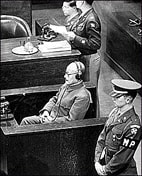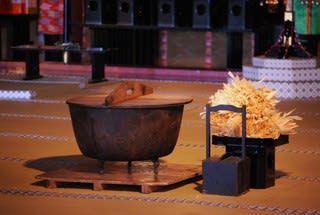管理人の棲家は欧州から米国、そして連衡へ 国家を超え、自由を求めて
グローバルゼーションの喧伝が定着すると、次の手順として収れんが始り、独裁という従来の概念に似て非なる目に見えない収束が起こってくる。
しかし、為政者あるいは管理人が、人間なるものの厄介な存在を欲望喚起を用として群盲のように仕立てても、一方では異なるものへの埒外な欲望への欲求は、従前の疲弊再興、不便から便利、貧困から富裕をスパイラルのように転回させる従前の管理方法では収まらない状況が発生している。
それは思想を看板にしては経国できない状態が数多の国なるものに起きている。宗教も然り、経済も然り、大衆が偶像化した財貨への欲望は管理人によって固有の財貨発行権すら無効とし、為政者の執る政治なるものは、管理人のルールに収斂された厄介な国民なる大衆の欲望の交差点でウロウロするようになってきた。
まさにキャッシレス化の功罪ではあるが、一過性の利便性によって進化の罪は覆い隠されている。
むかしは管理人を羊飼いとも云った。群盲となった羊を追い立てる犬は、吠え、誘導した。羊は管理人を独裁とは思わない。与えられることに慣れ、行く末を想像することもなく、目先の餌を競い、押しのけ、それが羊の労働だった。そして自由に走る放埓から、埒(囲い)内での眠りについた。それが自由で安全な環境であり、犬は満腹に誘う先導者と理解していた。
 北京の友人作
北京の友人作
以下、旧稿ですが・・・
自由は国家や分別された機関のカテゴリーにある自由感覚と、それから解き放たれようとする自我自由がある。とくに古代文献に記されている土地、つまり固定資産を財として持つものと、その圧政や宗教的抑圧からの逃避が、移動性を生み、つねに流動したものの蓄財法を民族の陋習まで結びつけた民族は、よりその蓄財のグランドを、゛己の自由゛に適したグランドとして、財に似て非なる価値を抱くアジアの一隅に捜し求めた。
とくに、国家の管理するシステムが硬直し、あるいは国家として存在するに前提となる税務執行の恣意的な国柄には、その自由と民主というプロパガンダによって大衆の欲望に順じて弛緩したシステムを要求(例 対日年次要望書)、達成しつつ、自らの自由グランドを構築している。
また大衆はより自由という結果に到来する固体分離された孤独の恐怖から、より無定見な放埓に流れ、終には弛緩した社会を構成して、逆に管理された安住を捜し求めるようになる。
砂民ともいわれるものが、曲りなりに国家の態を成す凝固の触媒となった人情と財の感性を権力維持の手法とした恐怖と監視の緩みから、独裁専制からの開放、いや民癖を知り尽くした権力によって、放逐に近い策で解き放たれた。それは無策の策といったものでもある。そこには歴史的には法治では立ち行かないしたたかな民情に加え、民生の安定制御を司った習慣、掟といった陋規の崩壊が、よりその進行を早めている。
しかし、その触媒となる財貨、人情には変わりなく、返ってより自由な海外逃避に保全の途を抱くことが多いようだ。とくに権力に近いものたちの子弟、親族にその傾向が強く、国家に責任を持つ、つまり愛着の前提にある国家、社会の連帯意識の欠如は、外的進入によって易織が変ることの無常観、諦観が染み付いている民族の悲哀でもあるが、昨今騒がれているグローバル経済には取ってつけたようにピッタリと呼応する民族でもある。
つまり、翻ってみるに、我国に観られるおんぶに抱っこの限定的自由獲得は、もらい扶持、食い扶持の政治家、官僚の公徳心欠如によって、より増長した社会を作りだし、外部から見れば民主と自由の大義を吠えられれば、牧羊犬に追われ群行群止する家畜のように見えるだろう。
実利として役に立たない官制学歴、軽薄な金銭価値、狭い範囲の兵隊遊戯のような官位褒章の執着など、人間の作為として行う経国の要諦を見失った似比独立国家のように時代に滞留している。
 弘前城公園
弘前城公園
上海におけるサッスン財閥の繁栄は、大陸における財と情報の浸透性が共通価値の中で容易に行われたことを実証している。それは色、食、財の欲望に正面から向き合える民族と、タルムードに裏打ちされた財貨への欲望価値と偏在する世界観の普遍化への欲求が、あまりにも似ていることに由縁する民族の悲哀にも似た類似性でもある。
宗教的にも、あるいは権力の固定維持から統治仕法となった冠位を忌諱し、却って身分の棲み分けを強靭なシンジケートに変え、宗教的賎業であった金融を、貴族の資産運用や戦費調達にかかわる金融為替を生業にした人々は、地域間の国力差異、紛争時の軍費としてその使用料、つまり金利によって権力者の喉もとさえ押さえつけるようになった。
その意味で戦争は破壊ではなく、絶好の生産機会であり、促したり誘発させることによって生ずる虚利の対象として、その情報の虚実を操作して国家間の軋轢さえ企てるようになった。
それは、当時の国民政府、共産党の政治勢力状況や諸外国の干渉を超越した部分の民癖、あるいは欲望の志向性とも思える素直な共鳴感がみてとれる。もちろん国民党の孔財政部長による米国の援助資金確保や、中華人民共和国成立時のソ連から莫大な援助なと、双方混乱時の資金流動もあるが、それにも増して権力当事者の財貨、権力の欲望は、その看板とする思想さえ、単なる意味の薄い「話(ハナシ)」として権力奪取の具にされている。
表層の柔和さと表裏を成すように、その内に秘めた別の心で読み取る財と人の関係と、わが身に及ぼす禍福の影響を感じ取るための透徹した感性に裏づけされたある種独特の価値観があり、かつ両民族の似て非なる様相は民俗学、人間学、比較理財の利学としても興味のある問題でもある。
ともに数千年の歴史を経た民族でありながら、一方は地球上のグランドを選択し、一方は亡羊とした環境のなか選択不可欠かつ刺激的なグランドで諦めにも似た悲哀を抱えながら栄枯盛衰に身を任せている。各地域で掲げる自由、平等、博愛は人類普遍なスローガンのようにみえるが、己の意思の自由獲得、少数ゆえの平等、同胞愛に根ざした友愛であることは歴史の事実として明確に語られるところでもある。
一方、片手に孔孟の謂う規範像を装いながら、老荘の謂う天下思想に実利ある生き方を方便として、天と地の間に国家帰属意識もなく、砂民のごとく地球上至る所に生息して、その特異なる金銭感覚と陰陽対比と調和に基づいて滅ぶことのない復元力によって旺盛な生活を戯れのように演じている。それは「逢場作戯」という臨機に柔軟さを増し、「小富在勤、大富在天」にあるように、勤労によって生ずる富は小さく、天に沿った富は大きい、と小欲、大欲の価値感性を規範的な孔孟にも考えられ、かつ危機や厄災を達観できる老荘の柔軟性を使い分け、ことのほか楽観的(positive)に人生を活かす術も心得ている。
また双方は、究極の統治形態である専制独裁にその有効さを認めている民族であり、20世紀にはその試行も経験している。それは人間を管理し有効に利するには、耳障りのよい自由と民主が大衆の意思を群行群止させる一番の方法であり、意思なき分裂に導くことによって国家を融解させ、財貨の欲望と管理によって情報の指向性をコントロールすることをいち早く発見した人々でもある。
 岩木山
岩木山
全体主義のドイツ、共産主義のソ連、中華人民共和国、民主と自由を掲げた資本主義に代表される西欧やアメリカ、日本。フランスのブルボン王朝は自由、平等、博愛の名のもとに断頭台に終焉し、社会大衆革命の名の下にロシアロマネフ王朝は滅亡した。また純化のために階級闘争のために粛清と称してヒットラー、スターリン、毛沢東、カンボジアはポルポドの政策によって短期間に合計一億人以上の民衆が抹殺されている。
また、驚愕するにそれらの専制独裁を間接的支えたのは、国際金融資本であり軍備費、戦禍復興いずれにも色の付いていない金が使われている。
権力維持や反対者の抹殺のために資金が使われ、その使用料としての金利によって権力そのものが管理される滑稽な状況結果がある。
ちなみに、日露戦争にも外国債が使われたがその担保は関税権であり、年6分である。
しかもロシアにも同様に貸付られている。幕末の薩長にはイギリス、幕府にはフランスが援助干渉しているが、その意図はアジアの状況によって察知されている。
金貸しが為替差異や金利を稼ぐことから、国家の関税権や統治システムまで収奪することが、当時の植民地政策のあらたな管理方法として定着してきた。
一番効果的な管理方法は人間そのものの欲望によって、自らを自動的に衰亡に導ける自由と民主による孤独と自己責任という、言うに云われぬ連帯希薄な環境に追い込んでいる。 資本主義のダイレクトな効果利潤として金融支配は、とくに使用料としての金利という虚の循環生産を駆使して、促成された欲望の収斂を図り、つまり消費管理資本主義という力の強いものの一方的な管理社会を構成するという、国家さえ超越した大衆管理を成し遂げている。
それは一国の通貨管理や生活システムの馴化につれて情緒の融解さえ巻き起こしている。
処世の一方は旧約聖書にある名門でありタルムードという経世訓を保持し、一方は厚黒学という、歴史の看板である老荘孔孟を包み込む利学を有している。
それが彼らの生産のための術であった人為的冷戦を経て、看板はいまだ塗り替えられない共産主義の苦衷にある政体の支配地域に、彼らの自由という安住を認めて再び舞い戻り、賞味期限が過ぎた米国という仮の住処を離れつつある状況がある。しかも用心棒の指令アジトを米国のトランスフォーメィションという構想を掲げ、順応国家である近隣に配備しての慎重な進出準備がある。
駐中国大使であったブッシュパパと真の権力者◇氏との関係は、クリントンの親中スタンスと共通する底流であり、その時代のクリントン宮沢合意にある、その後の「対日年次要望書」によるアメリカ化、あるいは金融権力のベースの移設環境整備として、よりその有効性を顕著にしている。本丸は大陸中国であり、太平洋の島礁に位置するフィリッピン台湾、日本はもはやその役割を終えようとしている。

欲望の構図に話を戻そう。
男女の性欲に関する欲、食欲という生命保持と止め処もない飽食、有れば有るに越したことのない財貨の集積欲、これら三欲は人間の同化を促す術として有効な手立てでもある。
満州国、新京の魔窟といわれた大観園の親分は一方で道徳会の会長でもあった。
親分は実直な日本人にこう話した。「日本は早く負けて日本に帰ったほうがよい、さもなければ日本そのものが亡くなってしまう。なぜなら我々は濁水の中で生きている、清水にも生きられる。しかし日本人は濁水の中では生きられない。欲望は一緒でもこの国では日本人そのものが亡くなってしまう。日本人は遺さなくてはならない・・」と。
また、副総理張景恵は「日本人は四角四面だ。あと二、三回戦争に負けたら柔らかくなるだろう」と、大陸での実直すぎる日本人観を述べている。
善悪の可否を超越して、力こそ正義だというだという大陸の感覚を、アジアにおいて似て非なる人間の生き方として学ぶときが訪れることを示唆している。
脱亜入欧といわれた文明開化において、入亜をスキップして入欧したツケは未だ尾を引いているようだ。政治家、否、日本人は異民族との交流に致命的に欠陥を露呈する。とくに土壇場の状況はより鮮明な姿を表している。
だが、唯一のセキュリティーであり、実直さのあまり異質にもみえる日本人の陋習にある生活規範は、曲がりなりにも醸成された、勤勉、正直、礼儀、忍耐という集積された特性を備え、欲望同化の誘引に対応する唯一無二の資質として、国柄という範疇を超越して人間の尊厳を祈護した古代の賢者の祈りに沿うものでもあり、栄枯盛衰の導かれた智の結晶でもある。だが、その徳性の劣化も指摘され始めて久しい状況でもある。
またそのことは維持し、祈護することによって、いずれ訪れる民族や人間が混迷するであろう社会において、その復元力を宗教や環境を超えた人間そのものの存在意義に普遍な価値を探すとき、人と禽獣の異なりを理性と習慣によって抱合した恒常的意義が映す行為を、勤勉、正直、礼儀、忍耐の姿に光明を求めることを自明の理と考えるからである。
いずれ中猶連衡は必然である。それは繁栄のサイクルと地球上の移動が、時を同じくして歴史の循環と共動し始めているからである。