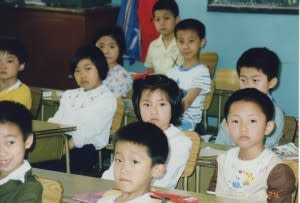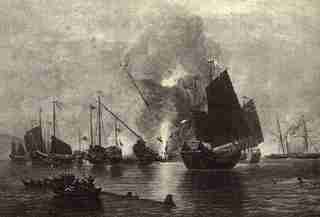青森県弘前市 子供議会(中学生)
猫も杓子も「世の中は民主主義だから・・」とうそぶく。
それを有効成さしめるのは議会制民主主義の要員を選ぶ選挙だという。
近ごろは国民も選挙にはお付き合い程度の感覚しかなくなっている。
それに連れて議院内閣制である行政府と立法を専らとする議員の関係が混在し、その整理なのか,専制への導きなのか、内閣官房の力が増大している。
つまり、官吏の集合体と化し、形式的になった政府の発する規制、扶養、が、これまた委任事務を扱う出先の自治体の作業を通じて、政府と国民の関係が密になり、その選挙を通じて選ばれた議員の権能が、とみに衰えているようになった。
それは連帯を希薄にして個別化の進んだ国民個々と内閣が直結して,慣らされた群行選挙によって選任した中間監視組織でもある議会の衰退でもある。
むかしは陸軍、いまは官僚と揶揄されるような現在の実態政府の形態は、゛選挙は民主の根幹 ゛と、ときに無知蒙昧にも言葉だけの人権、平等、民主、自由を大言する大衆をいまだに混迷の囲いに閉じ込めている。
もとより、専制によって人々を収斂(恣意的に集合)するには、美辞麗句がある。選挙で謳うあの大義であり名分である。住みやすい、安心、豊かさ、行政官吏も利便と効率で追従する。現実に手玉に取られポチになった食い扶持議員は、無責任な官吏の失態や細々としたミスや恣意的作為などの議会の質問追求に、まるで隠し屏風にようになって行政官吏の擁護に窮している。まるで寄席の福話術か二人羽織のように巧みな演技をする。 答弁の脚本だけではなく、質問まで役人任せだ。
めでたく政府側に位置すると言語障害、思考狭窄になったかのように、選挙の票の騙取につかった大義は消えうせる。とくに行政改革、無駄のない政治、などは無かったかのような態度だ。これも内閣を司り官吏の住処である省庁の代弁者となった官房の管理と監視である。
つまり内閣官房と国民の直結関係であり、民主平等を掲げ遊惰に生活を営む国民との変質した民主の姿であろう。どうだろうか、この直結した関係は専制を通り越して独裁主義になりつつある前兆ではないだろうか。
上からの下ろす道はあっても、間接要員(議員)を通じた下からの道は理屈形式では整っているようで道はことのほか狭い。
とくにその風潮は、小泉氏が国民に直接唱えた郵政選挙のワンフレーズに、嬉々として投票所に足を運んだ国民大衆の群行と、その群集心理を効果的に利用した為政者の狡知なのではないだろうか。よく陣笠いわれる議員だが、国民の選任するのは腹話術のように大義を連呼し、闇雲に突撃する陣笠の就職運動にも観えなくもない。
つまり、これが民主主義のシステムに組み込まれた伝統的な間接選挙の要員の姿なのだ。これが、いまは用を成していないのだ。
瓦版屋(マスコミ)も政治記者の総理との会食が頻繁に催されている。
総じて為政者のポチに成り下がり、なかには博打場の開設や世界運動会の便宜を請う瓦版屋もいる。ここでも第四権力の有効性を衰亡させている。
いくら平等主義でもこの関係は無くてはならない相互関係だ
独裁者は思い込みと過度の恐怖心が逆な効用を誘引する。
かといって、独裁者自身も過去の歴史が示すように機関の構成員であり、一員でしかない。
民主の前提は人間の尊厳を継続することにある。尊厳とは真の自由の発見と自他の厳存を認め合う連帯を己の任務とすることから始まるが、その秤の均衡はいかに熱狂と偏見による欲望をコントロールができるかどうか、それが民主の成立前提である。
その個々の民が思索と観照を衰えさせ、種の継続要因である神と精霊の思想を無用なものとして、財貨の欲望に突き進み、善なる欲望すら退化させて他と競い争う姿は、より前記した政府との直接関係をより依頼性の強いものとして、政府は平等観念を無謬性にまで高め、より人々の制御膜を希薄にさせて刺激過敏な条件反射に応ずる享楽なり遊惰を注入している。
人々は高邁な政治には無関心となり、ひたすら群行群止を繰り返して、しまいに疲弊する。
享楽は無駄と簡易利便であり、遊惰は清規(成文法)に拘泥して易きに流れる国の方向だ。
民主は人心が微かになり、政治が易きに流れると自ずと全体主義独裁に陥る。選良の有効性を無くし中間的制御がなくなると政府と国民の直接関係が深くなり、我が国の場合は特に内閣官房を支える姿なき官吏の自浄なり改正がない限り、容易に独裁に進む傾向がある。
軍、軍官吏の暴走も議会の形骸化にあった。
他国だが、韓国の経済は財閥主導で中小企業は弱小だ。中国は官製公司が幅を利かせ、民は国家への帰属もなく財貨の欲望に邁進している。だだ、濁水に生きることを習性としている民族は滅びることもなく、他の清水に交じっても躍動はさらに増している。
韓国は財閥でさえ国際金融資本のコントロール下におかれて逼塞している。
彼らには伝統的に中間的緩衝が乏しい。民族の性癖なのだろう中央政府の直接関係、つまり専制に慣れた人々である。だから解放したりすると混乱する。ゆえに民主の価値観や欲望はなく一党独裁でなければ収斂しないのだ。
国家より天と地の間に棲むという天下思想のもと、守ってくれなくても邪魔さえしなければと考える為政者との関係がある。
ここではどのような主義が全世界の異なる文化を持った人々に普遍性を持つものだとは限定しない。宗教や独特な規範、独裁、自由、民主、社会、共和、いろいろ呼称はあるがそれが混沌を維持する妙なのだからだ。
だだ我が国をみれば、民情と制度、生業、つまり業となっている教師、官吏、宗教家の歴史的変遷をみると、政治家、官吏の突き詰めた選択肢が標準や管理を、普遍性、無謬性に置き換えられたとき、国民との中央政府の関係において独裁的方向に進みやすい前提があることに気が付かなくてはならない。
それは大権を持った当時の天皇でさえ煩悶した状況であり、いつの間にか、どうして、との疑問が熱狂した群行に遮られた、つまり大人しく、涵養で、連帯心と調和する習性なり掟を涵養した民族でもそうなった不思議さでもある。
そうなると頭を当てるか、冷水を掛けられなければ分からなかった民族である。なかには敵の力を利用してその暗雲の根である陸軍に鉄槌を下してもらおうとする企図もあったのだろう。しかし、ことは国賊的企図である。
歴史は隠蔽されるべきことも存在する証左だ。
他民族の混在は強制的収斂、統一的専制しかない 国家の弱体は他国の侵入を招く
一方は同志友愛と金融による統治だ
最近は前記した小泉選挙だ。田中真紀子議員の漫談アジ演説、小泉の政策ならぬ米国からの年次要望書にある郵便業務の透明化と解放を「開放」と「改革」にしたワンフレーズ「良いか、悪いか」がある。
慎重もしくは反対する候補者をうむも云わせず国民の熱狂と偏見を煽り抹殺する。この手法こそ独善的手法なのだ。また、それが可能になった民情なのだ。
多くの国民は喝采し、中間的緩衝層である国会の議員諸氏まで黙らせた。食い扶持安定職の就職担保なのだ。ここにも独裁の要因土壌がある
我が国は独裁が容易なのだという証左だ。また、遊惰、放埓、平等に飼い慣らされた国民を扇動し、勤勉、正直、礼儀、忍耐が国民の徳性だった頃の実直精勤した官吏や疑似権力者である、宗教家、知識人、教育者、経済人を覚醒するには、ときに善なる独裁の誘引を願う国民の心に残置されている。
もちろん第四権力や他国の、似て非なる思想主義を借用する政党は反対するだろうが、陛下の被災地巡察慰問に感動する国民の存在するうちに、一時の善なる権力行使も多くの国民の歓迎することでもあろう。
つまるところ、為政者の信頼にかかっている。多くの独裁者は国民から熱狂で迎えられた。
畏敬とか偉大は文章上の装飾文字だ。国民は簡便な善悪の区別と憧れが人を歓迎する。ときに連帯からの疎外や排除の恐怖もあるが、自由と裏腹の孤独感は新たな収斂と帰属意識を生ずる。
本来は宗教家や瓦版屋が助力するものだが、効を成さない現在は中央政府の扶養にすがるしかない。ただ、欲望の際限が亡くなった大衆は、その裏腹に苦しみの共有には従順とする習性もある。とくに迎合心と好奇心が豊富な国民性は多くの為政者にその妙手を提供してきた。
上記は、独裁は近いし、人々はすぐ慣らされると考える。
誰が言い始めたのか、独裁は悪で民主主義は善だと。
大衆が選んだ総理は震災地では罵倒されたが、陛下が膝を折れば感涙する。総理が企業から五億円を受領し、瓦版屋と談合しようが、議員や官吏が放埓になって国政は荒れても、騒ぐのは第四権力と揶揄されるマスコミの売文の輩や言論貴族だが、直ぐに一過性の好奇となる。とこかで、安逸な生活を自覚しているか、国がなくなることなど心配していない。
あの時は王政復古だった。権力が糜爛して有効性を無くした時、倒したのは利害得失に敏感な無頼の武士だが、だから西郷は「こんな国にするつもりはなかった」と嘆いたが、復古した威の存在の変わらぬ座標に望みを懸けた。
考えは西洋の直線的滅亡のハルマゲドンではなく、東洋はスパイラルに時空を循環する輪廻感覚が政治観にあった。西郷のみならず無学な民衆とて当然の如く熟知している。
「もうそろそろ終わりだ」「このままで済むはずはない」「そんなものだ」渦中に飛び込むオッチョコチョイもいるか、世の中はそのように移っていくことを言葉に出さなくても知っている。
そんなつもりの諦観じみた考察だが、いつの間にかそのような政体になることは分る。
論拠や論証、合理的説明や体系化した組立と数値選別の徒は騒ぐが、そんな庶民の直観が堆積している下座の観察は、深層の国力として君たちの立つ処を支えていることも忘れないでほしいものだ。
数多の主義も人心が微かになり、堕落、弛緩したら別の統治方法を選択するものだ
だだ、旧来の既得権、つまり欲得の放棄がなければ消滅を待つしかない
「亡国は、亡国の後にその亡国を知る」たしかに歴史は鑑のようなものだ。