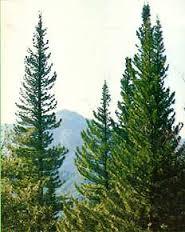公務員のお手盛り視察は予算残余の帳じり合わせと聞くが、議員のそれは与野党そろってアゴアシ(交通費、食事)付、土産に報告書の代書までついてくる。それほどタダの毒饅頭は恥いる暇のないくらい美味しいものらしい。中味は、さもしさ、卑しさの詰まった効き目のある毒饅頭、競って手を出す習慣性もあるらしい。
ゴマメの言いがかりだが・・・・
「視て察する」、これは相当熟達した教養がなければ難しい。
「見て学ぶ」は、知った。覚えた、そのくらいのことだろう。
文部省の官製学校歴を幾ら積もうと、いや、積めばつむほど判らなくなる。
ただ察するのではない。「明察」に達しなければ単なる暗愚のそぞろ歩きである。
あのとき菅総理が災害被災地に視察に行った。遅いも早いも問題にする方もおかしいが、察することができるなら音声や映像視覚でも用が足りることだ。現地の実態視察によって用が足りるのは別の意味からだろう。流行りのパフォーマンスもあろう。
ちなみに菅総理が行ったときヤジや罵声が飛んだ。あくまで国民の感覚的印象の一声が飛んだが、仮にも選挙で選んだ総理である。逆に小泉議員が行くと黄色い嬌声が巻き起こるが、これとて政治なるものでない。
両者の好き嫌いはともあれ、陛下が膝を折ると鎮まりの中でその忠恕心に涙する。権力はともかく威力がある。それはとてつもなく大きい。
しかも過不足を哀願したり、批判することはないが、被災者のあてどころもなくも、やりきれない心を慰めとともに自省や自立を抱かせる威力だ。それを癒しというのだろう。
つまり国の政治とは、金や資材の提供だけではなく、自立心と努力に相応した成果なり価値観をつくるための自由を担保・護持するものであり、人の善性の喚起を援け、それによって人々は「分」を得心し、親和力を促す作用なのだろう。
「分」とは自然界に生息する人間種としての弁えと、調和によって役割を知ることだとおもう。
PKO自衛隊員
事件の証拠集めではないが現場を見なければならないことも多々ある。
匂い、感触、感動、など言葉や文章で説明しきれないものがある。たしかに高給取りが持ってくる多種多様な情報が錯綜し、四角四面な成文法に縛られていては用が足りないことも斟酌できるが、先ずは総理がしたことは「見学」が適当である。
目で見て学び、その後、推察、洞察することである。
なにか文字にすると軽薄に感ずるような「見学」だが、いい加減に言葉の意味を解釈すると解釈がスキップして妙なところに着地することになる。やたら、゛文句付け゛を食い扶持の種にしている輩に気をとられていると沈着冷静な判断ができなくなる。
もともと荷が重いことも知らずに背負った立場だが、せめて松戸市の「すぐやる課」なみのフットワークで現場を見学して欲しい。
総理の政治経歴もそうだが、政権内外には、゛いまさら゛という気分が立ちこめている。
内には自衛隊違憲、大企業の横暴、米軍への感情的嫌悪を党是としていた群れがあり、一種の逡巡と衒いがある。
外には卑小な阿諛迎合と現世利益を当て込んでいた民情の流れがあった。その圏外には儘っ子扱いされた自衛隊や現業職員が被災地の前線で辛労している。その解けない気分の方が辛い。
民情の流れの中には真摯に可能性を探りながら自活と自制を心がけるものがいる。陛下のお暮らしとメッセージはそれを後押しした。一方、鬼気せまる形相で買占めに走る、多くは戦後生まれの婦女子の大群がいる。落ち着いたが、それも反省ではなく飽きたのである。
まともな人間はそれを見学した。愚かさの反面教師である。そして彼女達は社会熱となった義捐募金に乗り遅れまいと参加し溜飲を下げて、その貢献の大小なりを語り合っている。
今こそ己の内と外を学ぶ良機だ。その点、家庭も学ぶべき場だろう。先ずは童に傾聴することだ。学校は何を学び、社会は何を教えてくれたのか。そして言志をなくした雄の子はどう学び、覚醒するのか。
そして「察する」こと、つまり他への忖度から忠恕に高めることが促がされるだろう。
文献や考証学、はたまた他に説明できるものに意味をおく知学の土壇場の無力を、人の倣いとして察することだ。それは潜在する能力や情緒の確認であり、己の再発見となるだろう。
徒な批判、右往左往する行動、それは先ず「見学」、そして「観察」が大切なことだ。
「目で視る」から「観る」、そして察する。この順序が狂うと結論が逆になる。
「陛下、今年は涼しくて何よりで・・・」
『東北は冷害で大変だろう』
「陛下、雑草を刈り取りました・・」
『名もない草木でもそこで生きている。やたら刈り取らないように』

どうも世俗の学徒とは観点が異なる。それは幼少期の乃木学習院院長や青年期の杉浦重剛の倫理御進講の由縁なのだろが、戦後は一時期を除いてその人間学(帝王学)に沿う宰相には遇うこと難しだった。(経師、遭いやすく、人師、偶いがたし)
かといって四角四面の固陋な気質ではない。
「入江は食べ過ぎだっのか?」
入江侍従長がなくなった折に卜部侍従に下問した言葉だったが、健啖家の入江侍従長の死因に関する素直な疑問ではあるが、洒脱とも思える述べ方は筆者と卜部氏が理解した阿吽の双意だった。
察する、思いを寄せる、倣うべきは学び舎の数値ではなく人物から倣う。
それは、縁あって棲み分けられ、日本人として呼称されている人々の情緒は、その倣いを許容し理解する器量が矜持でもあったはずだ。。