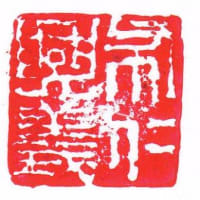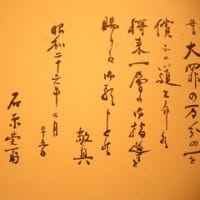一つは中東に棲むユダヤ民族に伝承されている処世の知恵として、他方は永い歴史を刻むなかで百家が説いた「論」を集積しつつも、「論」を噺の類にして、無尽なる欲望へのエネルギーをあからさまに人間関係の術としてリアルに「学」としたものである。
棲み別けられた自然や、政治環境の異なりはあるが、人と人が相対する接点における独特の術は歴史の時を違えて応答行動の姿として醸し出されている。わが国の「ことわざ」も対比させると面白い。
堅物の合間に手にとるロシュフーコや各種小話にも似たようなものがあるが、こと世界観、人間観ともなると、いま時を考察するのには面白い内容だ。

インターネットは世界を駆け巡るが、新旧取り混ぜた情報と称す真実、虚偽は時として民族性癖と交じり合って人々を群行群止させる。とくに覗き、脅しの類は、いたずらな恐怖心を添えてシャワーのように降りそそいでいる。
金融不安、疫病など、あたかも面前の恐怖のように映像と音声によって襲ってくる。商業マスコミに乗じた際限の無い欲望への喚起は生活最小限の利便性を多岐に重層して、夫々の資質にあった選別を難しくさせ、かつ情報資本の獲得比較の優劣を競う余りに無用な怨嗟や嫉妬を起こしている。
つまり人を信用の置けないものと仮定し、かつ複雑な要因で構成される国家というものさえ個々の利便性のなかに置くという、独特な民族性を持つものが動きやすい世界に入り込んできた。
たしかに切り口を変えれば国家に縛られない自由、人類平等と謳えばその意識もわからない訳ではないが、残念ながら曲がりなりにも国域(カテゴリー)に養った制度、慣習に庇護された多くの人々にとっては、まだまだ理解の淵には遠く、また彼等のしたたかにも見える世界観を認知すら出来ない戸惑いが昨今広がっている。
「平和だが何かおかしい」「幸せへの不安」と、吾が身を覆った一定の成功価値に問題意識をもつのは序の口で、抗する術(すべ)を見失いかけた国家の為政者に向かう人々の群は、羊飼いの犬に追われたように右往左往している。

タルムードと厚黒学を同質にとらえるものではないが、従前の国家が重積した歴史の残像にある共通的情緒と連帯意識では解くことが難しい点では共通した深層意識でもある。表層では交じり合い、財利の欲望もことさら異質性は認められないが、深層の企てなり謀はその発生と歴史的経過を客観的解明しようとしても、なかなか解りづらいものである。
民俗学、比較文化、地理学、歴史学など多岐に分派した学び方があるが、今は無き人間学、統合観察(プロデュース的)など、面前の応答辞令なり、オーラルヒストリーなどから感受する直感性や死生観などから読み解くことがなければ理解できないことであり、しかも実利に直結する緊張感と集中力がその実感を顕にする唯一の方法となる。
はたして組織の一員として、学域の範疇として、あるいはカルチャー知識など、多くのステータスを冠した情報によって、果たして彼等の言う智恵、はたまた利に向かって狡知にも転ずる美句、虚像に抗することができるのか、あるいは良知にも応用可能なのか疑問とするところである。
人が向かうところ、人の弱さと強さ、陥りやすい状況、表裏の柔軟な活用と正邪の転用などを熟知、いや刻み付けた彼等にとって、今どきの流行ブランドに志向したり、面前の利や動向に一喜一憂する意思亡き民は、最も好都合な群れでもあるだろう。
また彼等は自然界の循環に対する諦観と精霊の思想を秘奥に認めている。
単なる現世宗教やエコロジーではない。現世宗教は争いの具として、自然界は架空恐怖の具として利用されるべく茫洋且つ遠大な理想を対極に対峙させ、つねに調和と連帯なきカオスを温存しつつ、自らの座標の軸を中心に群れを回転せしめている。
ならば表層に現れた彼等の力である情報力 財利、あるいは財利に傀儡となった国家のフォーマルな軍事力と外交力に汲々としている地球の国群の民にとって「どうしたら・・」という同類に抗すべき問題を比較して考えるより、失くしてしまった直観力を甦えさせることが必要だ。

では「何が亡くなったか」「どうして衰えたか」
彼等に問わずとも彼等はそれを示している。
・ ・・自然界の循環に対する諦観と精霊の思想を秘奥に認めている・・・
彼等の智の発生と活用の妙は民族性や巧みな口舌や謀だけではない。
地表に蠢く数多の生物のなかでの微小な人間を認め、しかも群れの一粒としての魂を養い、血を継続するために自然界の循環への諦観と精霊の存在を認めている。
同じ群れでも似て非なる群れなのだ。選民思想とはいうが含まれる意味は重く深い。
「そうあるべきだ」と学ぶことが必要だと問いかける。
血は知を集めることを経て智に転じ、血が継承される。
グローバルな世界国家は仕組みや方法の争論はあっても帰結する先は血の保守であることを思考するかのように導かせる。
血は「医学的に・・」「遺伝子が・・」と雑論は別にしてだが・・・