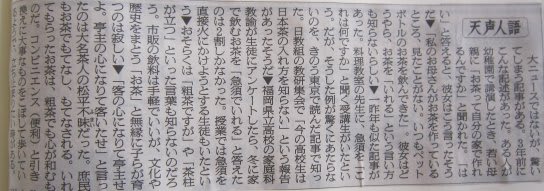朝日新聞の生活面に「ひととき」という女性専用の投稿欄がある。
どのくらい前だったか定かに覚えていないが、ここを男性にも開放し、土曜日だけ「男のひといき」として、男性の投稿が載るようになった。
「ひととき」も目を通しているが、この「男のひといき」も、なかなか興味深く、いつも楽しみに読んでいる。
前回(2月2日)の「男のひといき」は、「さて、自分ならどうするだろうか」と色々と考えさせられた内容だった。
投稿者は76歳の愛知県の男性。
正月休みに帰省していたお嬢さんと小学3年のお孫さんにまつわる話である。
散歩中に落ちていた1円玉を見つたお孫さんが、交番に届けたいと言い、2人で近くの交番に届けた。
申し出を受けたお巡りさんは、すぐ拾得物届けの書類を作成し、預かってくれた。
そして、
1円玉を届けた孫はもちろん、一緒になって交番まで連れていった娘、いやな顔ひとつせずに真面目に対応してくれたお巡りさん、それぞれにいいことをしてくれたと思う。「本当にいいことをしたね」と娘と孫を褒めた、
と書いている。
投稿者は、そのような娘と孫を褒め、誇りに思いつつ、こう続けている。
もし、娘ではなく私だったら、孫に対してどのような対応をとっただろうか、と。
そして、「私はおそらく、たったの1円を届けるのは恥ずかしいし、お巡りさんも困ってしまうと勝手な判断をして、孫に届けることをやめさせたのではなかろうか」と。
小生も孫がいるので、このような場面に遭遇する機会がないとも限らない。
その際、どう対応すべきか、大事なのは、(拾ったものを届け出ようと思う)子どもの「純な心」であり、その心を大人の打算で汚してしまってはならないと思う。
その伝で言えば、子どもの純な心にそって、いやな顔ひとつせず真面目に届け出に対応したお巡りさんの態度は、何よりも「立派だった」と、誉めても、誉めすぎることにはならない、そう思った次第である。
どのくらい前だったか定かに覚えていないが、ここを男性にも開放し、土曜日だけ「男のひといき」として、男性の投稿が載るようになった。
「ひととき」も目を通しているが、この「男のひといき」も、なかなか興味深く、いつも楽しみに読んでいる。
前回(2月2日)の「男のひといき」は、「さて、自分ならどうするだろうか」と色々と考えさせられた内容だった。
投稿者は76歳の愛知県の男性。
正月休みに帰省していたお嬢さんと小学3年のお孫さんにまつわる話である。
散歩中に落ちていた1円玉を見つたお孫さんが、交番に届けたいと言い、2人で近くの交番に届けた。
申し出を受けたお巡りさんは、すぐ拾得物届けの書類を作成し、預かってくれた。
そして、
1円玉を届けた孫はもちろん、一緒になって交番まで連れていった娘、いやな顔ひとつせずに真面目に対応してくれたお巡りさん、それぞれにいいことをしてくれたと思う。「本当にいいことをしたね」と娘と孫を褒めた、
と書いている。
投稿者は、そのような娘と孫を褒め、誇りに思いつつ、こう続けている。
もし、娘ではなく私だったら、孫に対してどのような対応をとっただろうか、と。
そして、「私はおそらく、たったの1円を届けるのは恥ずかしいし、お巡りさんも困ってしまうと勝手な判断をして、孫に届けることをやめさせたのではなかろうか」と。
小生も孫がいるので、このような場面に遭遇する機会がないとも限らない。
その際、どう対応すべきか、大事なのは、(拾ったものを届け出ようと思う)子どもの「純な心」であり、その心を大人の打算で汚してしまってはならないと思う。
その伝で言えば、子どもの純な心にそって、いやな顔ひとつせず真面目に届け出に対応したお巡りさんの態度は、何よりも「立派だった」と、誉めても、誉めすぎることにはならない、そう思った次第である。