
『卒業論文マニュアル 日本近現代文学編』斎藤理生・松本和也・水川敬章・山田夏樹 編(ひつじ書房2022年 図書館本)
■ ぼくは工学部を出たけれど、文学部は工学部から一番離れたところにある学部だろう。その文学部ではどんな卒業論文(卒論)を書くのだろう・・・。このような興味から、この本を借りて読んだ。
書名の通り、本書は近現代文学を対象とした卒論に特化して、候補作品選びからテーマの設定、論文の書き方について、段階ごとに具体例を示しながら記述されている。
実証的に、つまり証拠を示しながら論理的に記述する。工学部であれ、 文学部であれ、これは論文執筆の基本であろう。本書でも卒論について、何がどのようにクリアできれば達成といえるのか、その目安として、次の3点示されている。
**①先行研究の調査・位置づけを踏まえた、有効なテーマ設定ができたか。
②テーマに即した適切な方法を用いて、明快に論旨を示すことができたか。
③参考文献・注を整え、論理的・説得的な表現で論述することができたか。**(14頁)文中の下線は引用した私による。
巻末に執筆者の卒論が掲載されている。新井真理亜さんの卒論「安部公房『砂の女』試論」は読んでみたい。ただ、試論とは字義通りだと、試みの論考ということだが、これには真っ向勝負でなく逃げ腰というか、言い訳的なニュアンスをぼくは感じてしまうが・・・。
しばらく前に読んだ『金閣を焼かなければならぬ 林 養賢と三島由紀夫』内海 健(河出文庫2024年)は、精神科医の著者が専門の精神病理学的知見によって、金閣寺に火を放った学僧・林 養賢と、金閣寺焼失を題材にした小説『金閣寺』を著した三島由紀夫の精神分析をした論考だが、大学4年生がこんな論文を書くことができたら、すごいだろうな、と『卒業論文マニュアル』を読み終えて思った。















 360
360
 320
320 480
480

 320
320

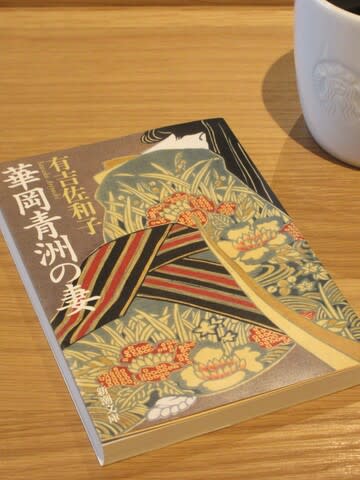 320
320

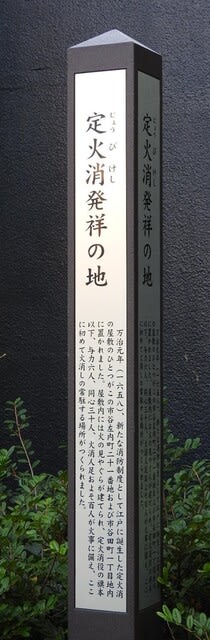




 540
540










