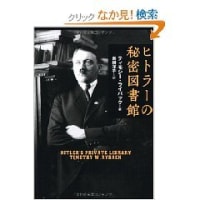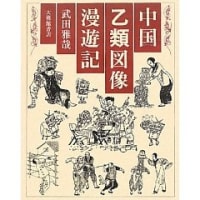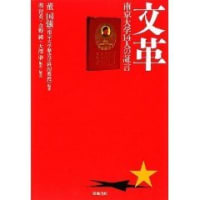村田氏は女流小説家では随一の人だと私は考えている。その最新作がこれだ。「文学界」中心に連載された、八つの短編を集めたもの。テーマは自身の放射線によるガン治療と2011年の東北大震災(福島原発事故)を関連させたものが四つ。土地の力、地の霊力について書かれたものが四つという構成である。前の四つが自身のガン体験を踏まえているだけに、より切実さがある。
著者が火山灰の舞う鹿児島へ放射線治療に出かけ、そこで日々めぐらせた思いは、3・11に続く体験とも言える。原発への恐怖と、放射線治療の恩恵と、太陽を燃やし地球を鳴動させる巨きな世界への驚異である。
自然界の厄災とガンという個人の厄災、その中で生き残ることと死ぬこと、これを「運命」という言葉で片付けるのは簡単だが、実際はもう少しデリケートだ。3つ目の『原子海岸』の中でそれが的確に語られる。鹿児島に放射線治療に来ていた患者たちがガン克服後、日南海岸で交流会を開き、そこで主人公の秋山の妻が、もと患者たちと交わす会話を以下に引用する。
駐車場に戻りながら秋山の妻は波江に言う。「この先原発がなくなったら、放射線治療もできなくなるんじゃないかって、私、そんな自分の利害のことを心配したんじゃなかったのよ」
「ええ、ええ。わかります」と波江もうなずきながら歩く。
「私のガンが見つかったのは3,11の明くる日でした。もう日本中がどんどん放射能に震え上がっていた頃です。大きな鬼が暴れまくっているときに、日本中がその鬼を憎んで罵って石投げているときに、車一台買えるくらいのお金を持って、その鬼の毒を貰いに行ったようで、何とも言えない気分だったの」
「そうですねえ。その後ろめたさっていうか。そういうことですよねえ」
「東日本では沢山亡くなったじゃないですか。その元気な人たちが、一瞬に。病気もないのに」
「ええ、ええ。ガンでもないのにね」
「だから私たちガンが消えても、あんまり大きな声でバンザイって叫べませんものね」
「ええ、ええ、叫べないですよね」と下向い歩く波江郁美。だが人にはそれぞれ運命があるかもしれない、と秋山は思いながら後ろからついていく。一つ寝床に入る夫婦でも片方はガンになり片方はピンピンしている。石が飛んできてもその場の全員にあたるわけじゃない。あれだけの津波でも同じところにいて生死を分けた人もいる。バンザイと小さな声なら言ってもいいんじゃないか。いや、しかし、放射能は同じところにいるならば生死を分けることはない。一緒に平等に被曝しる。まんべんなく浴びる。石が飛んでくるのではない。放射能はでかい大岩だ。生死を分けるには巨大すぎる。地震や津波や戦争には個別の死がある。放射能に個別はない。降ったら浴びる。いや、それでも原発だって広域でなら場所を分ける。東日本と西日本を分けた。ヒロシマ・ナガサキとそれ以外を分けた。運命という言い方が嫌なら、大岩の飛来を免れたというべきか。別に妻は原発の悪鬼に命乞いに行ったのではない。(以下略)
放射能被害が深刻に伝えられる中で、放射線治療で命を助けてもらおうとする行為の後ろめたさと放射能の巨大な恐怖、災害で生き残ることの運不運が委細漏らさず描かれていて見事だ。個人のガンとの闘いがこれほどの社会的な広がりの中で描かれた例を知らない。私が当代随一と評価する所以である。
著者が火山灰の舞う鹿児島へ放射線治療に出かけ、そこで日々めぐらせた思いは、3・11に続く体験とも言える。原発への恐怖と、放射線治療の恩恵と、太陽を燃やし地球を鳴動させる巨きな世界への驚異である。
自然界の厄災とガンという個人の厄災、その中で生き残ることと死ぬこと、これを「運命」という言葉で片付けるのは簡単だが、実際はもう少しデリケートだ。3つ目の『原子海岸』の中でそれが的確に語られる。鹿児島に放射線治療に来ていた患者たちがガン克服後、日南海岸で交流会を開き、そこで主人公の秋山の妻が、もと患者たちと交わす会話を以下に引用する。
駐車場に戻りながら秋山の妻は波江に言う。「この先原発がなくなったら、放射線治療もできなくなるんじゃないかって、私、そんな自分の利害のことを心配したんじゃなかったのよ」
「ええ、ええ。わかります」と波江もうなずきながら歩く。
「私のガンが見つかったのは3,11の明くる日でした。もう日本中がどんどん放射能に震え上がっていた頃です。大きな鬼が暴れまくっているときに、日本中がその鬼を憎んで罵って石投げているときに、車一台買えるくらいのお金を持って、その鬼の毒を貰いに行ったようで、何とも言えない気分だったの」
「そうですねえ。その後ろめたさっていうか。そういうことですよねえ」
「東日本では沢山亡くなったじゃないですか。その元気な人たちが、一瞬に。病気もないのに」
「ええ、ええ。ガンでもないのにね」
「だから私たちガンが消えても、あんまり大きな声でバンザイって叫べませんものね」
「ええ、ええ、叫べないですよね」と下向い歩く波江郁美。だが人にはそれぞれ運命があるかもしれない、と秋山は思いながら後ろからついていく。一つ寝床に入る夫婦でも片方はガンになり片方はピンピンしている。石が飛んできてもその場の全員にあたるわけじゃない。あれだけの津波でも同じところにいて生死を分けた人もいる。バンザイと小さな声なら言ってもいいんじゃないか。いや、しかし、放射能は同じところにいるならば生死を分けることはない。一緒に平等に被曝しる。まんべんなく浴びる。石が飛んでくるのではない。放射能はでかい大岩だ。生死を分けるには巨大すぎる。地震や津波や戦争には個別の死がある。放射能に個別はない。降ったら浴びる。いや、それでも原発だって広域でなら場所を分ける。東日本と西日本を分けた。ヒロシマ・ナガサキとそれ以外を分けた。運命という言い方が嫌なら、大岩の飛来を免れたというべきか。別に妻は原発の悪鬼に命乞いに行ったのではない。(以下略)
放射能被害が深刻に伝えられる中で、放射線治療で命を助けてもらおうとする行為の後ろめたさと放射能の巨大な恐怖、災害で生き残ることの運不運が委細漏らさず描かれていて見事だ。個人のガンとの闘いがこれほどの社会的な広がりの中で描かれた例を知らない。私が当代随一と評価する所以である。