今日、社会人のメンバーで構成されるマンドリンアンサンブルの団体、ポルタビアンカマンドリーノの第12回演奏会を聴きに行ってきた。
社会人の団体の生演奏を聴くのは初めて。
今まで学生団体ばかり聴いてきたが、社会人の団体というと音楽は二の次、交流を楽しむことがメインで演奏レベルも曲目も今一つというイメージがあったため、一度も聴きにいく機会は無かった。
私もマンドリンアンサンブルではないが、20代の頃、ギターアンサンブルの社会人団体に参加していたことがあった。
しかし曲目がポピュラー音楽ばかりでつまらなくなり、半年ほどでやめてしまった。
今日、ポルタビアンカマンドリーノの演奏を聴きたいと思ったのは、プログラムに藤掛廣幸の「スタバート・マーテル」があったからだ。
藤掛廣幸の「スタバート・マーテル」は、鈴木静一の交響譚詩「火の山」とともに私の最も好きなマンドリンオーケストラ曲であり、学生時代に演奏した思い出の曲だ。
今日は東京に出るまで会社で仕事の残りを片付け、飯田橋のトッパンホールへ向かった。
トッパンホールは初めて行ったが、飯田橋駅から歩いて15分くらいの距離にあり、トッパンの高層ビルの1階にある。
客席数は少ないが音響のいい、立派なホールだ。
驚いたのは殆ど満席になるくらい客が来ていたこと。
先に述べたように社会人団体は下手というイメージがあったので、こんなに客が来ているとは思わなかったのである。
さて今日のプログラムは下記のとおり。
ステージⅠ
・セントポール組曲 ホルスト作曲、小穴雄一編曲
・リュートのための古風な舞曲とアリア第3組曲 レスピーギ作曲
ステージ2
・主題と変奏 ミラネージ作曲
・夏の庭 -黄昏- シルヴェストリ作曲
・スタバート・マーテル 藤掛廣幸作曲
前半がオーケストラ曲の編曲もの、後半がマンドリンオリジナル曲という構成。
団員数は40名ほど。
いよいよ演奏が始まったが、驚いた。
音に凄いパワーがあり、エネルギーの力に圧倒された。
そして上手い。テクニックも相当なものだ。
演奏が進むにつれてだんだんと分かってきたが、このメンバーたちは、学生時代にマンドリンオーケストラでの演奏を経験しており、そしてその魅力にとりつかれて社会人になっても続けてきた方たちなのだ。
だからマンドリン音楽に対する気持ちの強さ、演奏技巧の高さ、確実さが長年の積み重ねにより更に築き上げられ、それらが集約され大きなエネルギーとなって聴く者に伝わってくるのである。そこに学生オーケストラとの決定的な違いを感じた。
セントポール組曲はホルストの弦楽合奏のための曲であるが、変化に富む難曲である。
ステージⅠのコンサートマスターを務めたのは、昨年、一昨年に中央大学マンドリン倶楽部でコンサートマスターだった方だった。卒業後も、先日の中央大学の111回定期演奏会でも賛助として出演されていた。
難しいソロも高い技巧で弾き切り、演奏に爽快さを感じた。
またコントラバスの音が半端でない。3人だけだったが凄い迫力だ。
2曲目の リュートのための古風な舞曲とアリア第3組曲は、有名なレスピーギの管弦楽曲からの編曲。
この曲は、私の大学時代の2つ上の先輩が大絶賛していた曲だ。
この先輩(ギターパート)から何度もこの曲の素晴らしさを聴いた。
丁度その頃、現代ギター誌の付録の曲集に、このリュートのための古風な舞曲とアリア第3組曲のギター編曲版が掲載された。
しかしその頃の私は古楽に関心が無く、ギターで弾いてこの曲を味わうことはしなかった。
しばらくしてこの曲集をギターパートの誰かに貸したらついに戻ってこなかった。
卒業して20年以上経って、上野の音楽資料室でこのギター編曲版をコピーした。

この先輩とは、後輩の3人で、卒業演奏会で、ファリャの粉屋の踊りとグラナドスのスペイン舞曲第2番「オリエンタル」のギター3重奏版を編曲、演奏した思い出がある。

今日のポルタビアンカマンドリーノの演奏では、第3曲「シチリアーナ」と第4曲「パッサカリア」が素晴らしかった。
最後の方のドラの超絶技巧には驚いたが、それにしても物凄い精神的エネルギーが表出される演奏。
古楽のたたずまいを超えた、この曲を作った古代の人の強い思いが十分に伝わってくる演奏であった。
休憩を挟み、第2ステージが始まる。
1曲目と2曲目はイタリア人によるマンドリンオリジナル曲であるが初めて聴く作曲だ。
コンサートマスターとドラトップがステージⅠと入れ替わる。
良かったのは2曲目の「夏の庭 -黄昏-」マンドリンのハーモニーが美しく、また説得力のある音。
曲が終るとひと際強い拍手が起きる。この曲はもう一度聴いてみたい。
終曲は藤掛廣幸の「スタバート・マーテル」。
この曲は以前記事で紹介したが、私の最も好きなマンドリンオーケストラ曲。
藤掛廣幸氏の人気曲には「パストラル・ファンタジー」や「グランドシャコンヌ」が挙げられるが、私はこの「スタバート・マーテル」が最高傑作だと思っている。
曲の構成力、旋律の美しさ、構成の多様性、精神性の高さなど、前2作よりはるかに優れていると感じる。
音楽監督が曲の演奏の前に、このスタバート・マーテルの意味や解釈などを解説してくれた。
後半から合唱が加わり、宗教的な精神的性格性が曲に現れるが、前半はあまりそのような感じはしない。
むしろ私は藤掛氏が、青少年時代を過ごした頃に体験した、1960年代から1970年代の高度成長時代の日本の情緒性が知らず知らずに曲想の根底に滲み出ているように感じる。
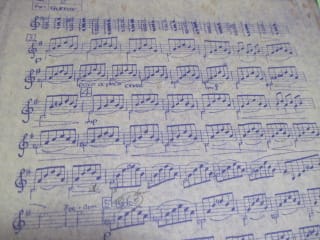
例えば、寂しい夕暮れ時の哀愁を感じるような部分、コントラバスの音が少しずつ下がっていく部分、このフレーズがこの曲で最も好きなのであるが、ここの部分を聴くとすごく頭が覚醒してきて少年時代から思春期にかけて体験した情景が次々と蘇ってくるのである。その時代は日本全体が希望に燃えていた時代といってよい。



そしてその後に、非常に美しいマンドリンソロが奏でられる。この部分も好きであるが、とても美しい旋律だ。幸福感の絶頂を思わせるような旋律。今日のコンサートマスターのソロもとても上手くいっていた。

この後にギターのアルペジオとともに速度がだんだんと落ちていき、合唱が挿入される。
学生時代はオーケストラのメンバー自身が歌を歌ったし、原曲の指示もそうであるが、今日の演奏は音楽大学の方の賛助の演奏であり、本格的なものであった。

この「スタバート・マーテル」は卒業してからも度々、いくつかの印象に残るフレーズを折にふれて弾いた。
この曲が好きだったからだろう。
今日のポルタビアンカマンドリーノの演奏を聴いて感じたのは、団員それぞれがマンドリンオーケストラがこのうえなく好きで、演奏することに強い喜びを感じていることが伝わってきたことである。
まず何よりもこのことに心打たれた。
次に、楽器から最大限に音を引き出そうとしていたこと。とても強い音を引き出していたが、それが物理的な力によるものではなく、精神的、感情的な力によるものであり、その音が強いエネルギーに満ちていたことである。
だから音は強くても美しいのである。感情的美しさと言っていい。
指揮者と団員のコミュニケーションも素晴らしかった。
指揮者のエネルギーが団員に伝わり、それが楽器をとおして聴き手に伝わってくる。
音楽の力というものがこれほど大きなものであるかが実感される。正直、日常の仕事上、生活面でのささいな苦しみがちっぽけなものに思われる。
1年に1、2回、2時間というわずかな時間であっても、演奏者と聴き手との交流は互いに面識が無くてもしっかりとなされている。
まさにこのことを改めて感じさせてくれたのが今日の演奏会であり、そのような演奏をしてくれたポルタビアンカマンドリーノに感謝したい。

社会人の団体の生演奏を聴くのは初めて。
今まで学生団体ばかり聴いてきたが、社会人の団体というと音楽は二の次、交流を楽しむことがメインで演奏レベルも曲目も今一つというイメージがあったため、一度も聴きにいく機会は無かった。
私もマンドリンアンサンブルではないが、20代の頃、ギターアンサンブルの社会人団体に参加していたことがあった。
しかし曲目がポピュラー音楽ばかりでつまらなくなり、半年ほどでやめてしまった。
今日、ポルタビアンカマンドリーノの演奏を聴きたいと思ったのは、プログラムに藤掛廣幸の「スタバート・マーテル」があったからだ。
藤掛廣幸の「スタバート・マーテル」は、鈴木静一の交響譚詩「火の山」とともに私の最も好きなマンドリンオーケストラ曲であり、学生時代に演奏した思い出の曲だ。
今日は東京に出るまで会社で仕事の残りを片付け、飯田橋のトッパンホールへ向かった。
トッパンホールは初めて行ったが、飯田橋駅から歩いて15分くらいの距離にあり、トッパンの高層ビルの1階にある。
客席数は少ないが音響のいい、立派なホールだ。
驚いたのは殆ど満席になるくらい客が来ていたこと。
先に述べたように社会人団体は下手というイメージがあったので、こんなに客が来ているとは思わなかったのである。
さて今日のプログラムは下記のとおり。
ステージⅠ
・セントポール組曲 ホルスト作曲、小穴雄一編曲
・リュートのための古風な舞曲とアリア第3組曲 レスピーギ作曲
ステージ2
・主題と変奏 ミラネージ作曲
・夏の庭 -黄昏- シルヴェストリ作曲
・スタバート・マーテル 藤掛廣幸作曲
前半がオーケストラ曲の編曲もの、後半がマンドリンオリジナル曲という構成。
団員数は40名ほど。
いよいよ演奏が始まったが、驚いた。
音に凄いパワーがあり、エネルギーの力に圧倒された。
そして上手い。テクニックも相当なものだ。
演奏が進むにつれてだんだんと分かってきたが、このメンバーたちは、学生時代にマンドリンオーケストラでの演奏を経験しており、そしてその魅力にとりつかれて社会人になっても続けてきた方たちなのだ。
だからマンドリン音楽に対する気持ちの強さ、演奏技巧の高さ、確実さが長年の積み重ねにより更に築き上げられ、それらが集約され大きなエネルギーとなって聴く者に伝わってくるのである。そこに学生オーケストラとの決定的な違いを感じた。
セントポール組曲はホルストの弦楽合奏のための曲であるが、変化に富む難曲である。
ステージⅠのコンサートマスターを務めたのは、昨年、一昨年に中央大学マンドリン倶楽部でコンサートマスターだった方だった。卒業後も、先日の中央大学の111回定期演奏会でも賛助として出演されていた。
難しいソロも高い技巧で弾き切り、演奏に爽快さを感じた。
またコントラバスの音が半端でない。3人だけだったが凄い迫力だ。
2曲目の リュートのための古風な舞曲とアリア第3組曲は、有名なレスピーギの管弦楽曲からの編曲。
この曲は、私の大学時代の2つ上の先輩が大絶賛していた曲だ。
この先輩(ギターパート)から何度もこの曲の素晴らしさを聴いた。
丁度その頃、現代ギター誌の付録の曲集に、このリュートのための古風な舞曲とアリア第3組曲のギター編曲版が掲載された。
しかしその頃の私は古楽に関心が無く、ギターで弾いてこの曲を味わうことはしなかった。
しばらくしてこの曲集をギターパートの誰かに貸したらついに戻ってこなかった。
卒業して20年以上経って、上野の音楽資料室でこのギター編曲版をコピーした。

この先輩とは、後輩の3人で、卒業演奏会で、ファリャの粉屋の踊りとグラナドスのスペイン舞曲第2番「オリエンタル」のギター3重奏版を編曲、演奏した思い出がある。

今日のポルタビアンカマンドリーノの演奏では、第3曲「シチリアーナ」と第4曲「パッサカリア」が素晴らしかった。
最後の方のドラの超絶技巧には驚いたが、それにしても物凄い精神的エネルギーが表出される演奏。
古楽のたたずまいを超えた、この曲を作った古代の人の強い思いが十分に伝わってくる演奏であった。
休憩を挟み、第2ステージが始まる。
1曲目と2曲目はイタリア人によるマンドリンオリジナル曲であるが初めて聴く作曲だ。
コンサートマスターとドラトップがステージⅠと入れ替わる。
良かったのは2曲目の「夏の庭 -黄昏-」マンドリンのハーモニーが美しく、また説得力のある音。
曲が終るとひと際強い拍手が起きる。この曲はもう一度聴いてみたい。
終曲は藤掛廣幸の「スタバート・マーテル」。
この曲は以前記事で紹介したが、私の最も好きなマンドリンオーケストラ曲。
藤掛廣幸氏の人気曲には「パストラル・ファンタジー」や「グランドシャコンヌ」が挙げられるが、私はこの「スタバート・マーテル」が最高傑作だと思っている。
曲の構成力、旋律の美しさ、構成の多様性、精神性の高さなど、前2作よりはるかに優れていると感じる。
音楽監督が曲の演奏の前に、このスタバート・マーテルの意味や解釈などを解説してくれた。
後半から合唱が加わり、宗教的な精神的性格性が曲に現れるが、前半はあまりそのような感じはしない。
むしろ私は藤掛氏が、青少年時代を過ごした頃に体験した、1960年代から1970年代の高度成長時代の日本の情緒性が知らず知らずに曲想の根底に滲み出ているように感じる。
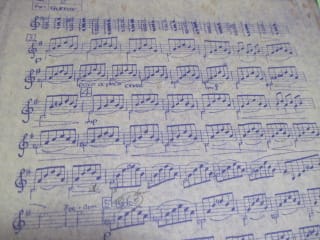
例えば、寂しい夕暮れ時の哀愁を感じるような部分、コントラバスの音が少しずつ下がっていく部分、このフレーズがこの曲で最も好きなのであるが、ここの部分を聴くとすごく頭が覚醒してきて少年時代から思春期にかけて体験した情景が次々と蘇ってくるのである。その時代は日本全体が希望に燃えていた時代といってよい。



そしてその後に、非常に美しいマンドリンソロが奏でられる。この部分も好きであるが、とても美しい旋律だ。幸福感の絶頂を思わせるような旋律。今日のコンサートマスターのソロもとても上手くいっていた。

この後にギターのアルペジオとともに速度がだんだんと落ちていき、合唱が挿入される。
学生時代はオーケストラのメンバー自身が歌を歌ったし、原曲の指示もそうであるが、今日の演奏は音楽大学の方の賛助の演奏であり、本格的なものであった。

この「スタバート・マーテル」は卒業してからも度々、いくつかの印象に残るフレーズを折にふれて弾いた。
この曲が好きだったからだろう。
今日のポルタビアンカマンドリーノの演奏を聴いて感じたのは、団員それぞれがマンドリンオーケストラがこのうえなく好きで、演奏することに強い喜びを感じていることが伝わってきたことである。
まず何よりもこのことに心打たれた。
次に、楽器から最大限に音を引き出そうとしていたこと。とても強い音を引き出していたが、それが物理的な力によるものではなく、精神的、感情的な力によるものであり、その音が強いエネルギーに満ちていたことである。
だから音は強くても美しいのである。感情的美しさと言っていい。
指揮者と団員のコミュニケーションも素晴らしかった。
指揮者のエネルギーが団員に伝わり、それが楽器をとおして聴き手に伝わってくる。
音楽の力というものがこれほど大きなものであるかが実感される。正直、日常の仕事上、生活面でのささいな苦しみがちっぽけなものに思われる。
1年に1、2回、2時間というわずかな時間であっても、演奏者と聴き手との交流は互いに面識が無くてもしっかりとなされている。
まさにこのことを改めて感じさせてくれたのが今日の演奏会であり、そのような演奏をしてくれたポルタビアンカマンドリーノに感謝したい。
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます