

完璧なカップリングの7インチというものがある。
ビートルズの『STRAWBERRY FIELDS FOREVER c/w PENNY LANE』、キンクスの
『SITING IN THE MIDDAY SUN c/w SWEET LADY GENEVIEVE』、C.C.R.の
『TRAVELLIN BAND c/w WHO'LL STOP THE RAIN』、テレビションの『VENUS c/w
FRICTION』etc, etc . . . 。
ジョニー・サンダース&ザ・ハートブレイカーズの『CHINESE ROCK c/w BORN TO
LOSE』もそんな1枚じゃないだろうか。
『BORN TO LOSE』という曲を初めて聴いたのは19歳の時で、それはラジオでもレコード
でもなく、アマチュア・バンドが演奏するバージョンであった。私が通った大学では当時6月頃に
「音楽祭典」というのがあって、それは確か2日間くらいを費やして様々なバンドがエントリーして
演奏を披露するというものであった。
午後の授業もなく(サボったのかもしれない)何の予定もなかった、とある日に私は会場を
のぞき、次々と登場するバンドの演奏を聴いていた。もちろん、格好いいバンドを探すためなんかでは
ない。自分たちのバンドが一番格好いいことを再確認するため(笑)と、くだらない軽音とかに
所属するバンドを嗤うためであった。いくら若いとは言え、何と傲慢で間抜けなのだろう。
こういう考え方が、私の日常に反映されてしまって不愉快な思いをしたであろう友人たちには
今思えば「悪かった」としか言いようがないが。
で、登場したバンドの一つが、件の曲を演奏し始めた。実のところ当時の私はジョニー・サンダースには
全く興味が無かったのだが、曲調と歌詞から「何かジョニー・サンダースっぽいな。」なんて
的外れでないにしろ、阿呆なことを考えながら演奏を聴いていた。この曲をレコードで聴いたのは
その2年後くらいで、後輩がアルバム1枚ではなく、この1曲だけを聴かせてくれたように記憶する。
よく見るとドラマーは同じアパートの同じ階に住むヤツじゃないか。お互い愛想なく
4年間同じ処に住んでいながら、挨拶の一つも交わさなかったのだが、妙なライバル心が湧いてきて
「けっ、つまんねえ曲を演奏してらぁ。」なんて思いが増幅し、ますますジョニー・サンダースとは
縁遠くなってしまった。
デヴィッド・ヨハンセンのアルバムは、ほとんど全て所持しているが、何故ジョニー・サンダースを
遠ざけていたのか、これまた間抜けな話だが、その全うな理由が思い出せない。
やたらと出されるライブ盤の山を前にして、「どれから聴けばいいのか。」と思ったのは事実だが。
ある日ジャケットの格好良さに釣られて(笑)手にした「L.A.M.F.」を聴いて、全てのモヤモヤが
吹き飛んだ。こんな格好イイ盤はそうは無いだろうと思ったものだ。事実、他のジョニーの盤で
コレに匹敵する盤は無いと思う。
「L.A.M.F.」35周年の4枚組ボックスは当然、入手した。35周年の祭りはまだ続いていて
掲載写真の7インチがリリースされた。300枚限定のホワイト・ビニール。
どっちの曲がA面であってもおかしくない、最強の7インチ。


同時発売された2枚もカラー・ヴィニールで左は赤盤、右は青盤。右の盤は発売中止スリーブだったと
何かで見た記憶があるが、果て何だったっけ。
話戻って、先の「音楽祭典」。クリムズンの曲を演奏するバンドがあって「おおっ」と思ったが
その次に演奏したのがM.○.G.の曲だったので、いきなり萎えたのを思い出した。
私が見た中で一番凄かったのは、つまり私達のバンドが太刀打ち出来ないと思った唯一の
出演者は・・・。
ラジカセでカラオケテープを流しながら、一人で浜○省吾を2曲熱唱したあいつ、
あいつには勝てない。本気のあいつには敵わない。恐ろしく場違いながらも、恐ろしく自己憐憫に
満ちた歌唱を耳にしながら私はその場を去ったのであった。















 この曲のカバーは多くあるが、おそらく最も有名なのがC.C.R.の
この曲のカバーは多くあるが、おそらく最も有名なのがC.C.R.の ジェイは人を驚かせ楽しませることを、何より自身が楽しんで
ジェイは人を驚かせ楽しませることを、何より自身が楽しんで






 『MONA』のカバーと言えば、即座に浮かぶのがこのアルバム。
『MONA』のカバーと言えば、即座に浮かぶのがこのアルバム。 2004年にミック・ファレンが来日した時、某氏から「東京公演に招待で入れてやるから
2004年にミック・ファレンが来日した時、某氏から「東京公演に招待で入れてやるから
 その後も様々な歌手にカバーされ、最早スタンダードと言っても
その後も様々な歌手にカバーされ、最早スタンダードと言っても バッドフィンガーのアルバム「NO DICE」収録曲『MIDNIGHT
バッドフィンガーのアルバム「NO DICE」収録曲『MIDNIGHT 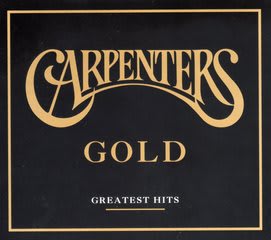
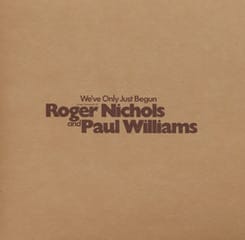

 とどめが、コレだ。94年に出たトリビュート・アルバム「IF I WERE A
とどめが、コレだ。94年に出たトリビュート・アルバム「IF I WERE A
 ダン・ベアード率いる、ヤイフーズの01年のアルバム
ダン・ベアード率いる、ヤイフーズの01年のアルバム





 で、私がアロウズに到達するのはそれから約10年後くらい(笑)
で、私がアロウズに到達するのはそれから約10年後くらい(笑) ウォッカ・コリンズが演奏する『I LOVE ROCK AND ROLL』は
ウォッカ・コリンズが演奏する『I LOVE ROCK AND ROLL』は






 ハンク・ウイリアムズのアルバムは未だに我が家には
ハンク・ウイリアムズのアルバムは未だに我が家には



