

彩の国さいたま芸術劇場の高齢者演劇集団「さいたまゴールドシアター」を「アンドゥ家の一夜」で初めて観て感心(感想は未アップ)。2008年の「ガラスの仮面」をきっかけにつくられた若手演劇集団「さいたまネクストシアター」にも注目。劇場の中にある「舞台芸術資料室」でハヤカワ演劇文庫の「真田風雲録」が置いてあったのを見つけて最初の方だけ読んだだけでも面白かったので、この舞台は絶対観るぞと決めていた。文庫もしっかりと買って前日までに読み終える。

【真田風雲録】
作=福田善之 演出=蜷川幸雄 音楽=朝比奈尚行
出演=さいたまネクスト・シアター、横田栄司、原康義、山本道子、妹尾正文、沢 竜二
あらすじは公式サイトより、以下引用。
「慶長5年(1600年)関ヶ原。天下分け目の死闘の傍ら、姿を現す浮浪児たち。男とも女ともつかない汚い姿で、屍体から金品を奪って生活する彼らこそがのちの真田十勇士である。時は経て、関ヶ原後、長期的安定政権をめざす徳川家だが、周辺では大坂の豊臣家をはじめ、行きどころない浮浪人たちが絶えず反旗を翻す機会を狙っていた。大仏鐘銘事件をきっかけに、徳川打倒を決めた豊臣方に加勢すべく、半ば浪人と化していた真田幸村を中心とする真田十勇士は、「カッコよく死ぬ」を合言葉に、奇襲戦法で出撃する。奇襲は成功するも、味方からは独断専行を咎められ、豊臣家を守るという大義名分のもと、戦いらしい戦いのないまま、穏便に和議が結ばれる。しかし、情勢は次第に不穏さを増し、遂に徳川家対豊臣家の最後の決戦へと突入していく――。 」

自宅から自転車をかっとばして必死にかけつけ、劇場スタッフの案内で大ホールの舞台の裏側に特設された客席へ。300席の仮設小劇場がつくられていて正面の2列目に着席。すぐにスタッフのナマ声で観劇上の注意。席に配られている黒いビニール袋をシート状にしたものを「舞台には1.7トンの泥土を敷き詰めてあり、その泥が客席に飛んできたらシートを使って防いでください」とのこと。舞台上に土が敷き詰められてマスク着用で観た「リア王」からさらに型破りの舞台装置に期待が高まる。

奥に戦絵巻を描いたような板壁のパネル。三方を囲むすり鉢の底のどろんこの舞台は即、関ヶ原の合戦場になり、いきなり大勢が出てきて東軍西軍入り乱れての戦闘場面で泥がはねあがる。この効果絶大!
勝敗は決しても下級武士どうしの恩賞の首狙いの死闘は続き、それを助けて武具をねらう浮浪児集団があらわれる。その中の紅一点むささびのお霧が後の霧隠れ才蔵になりというように、真田幸村の家来になりというように破天荒のドラマは展開していく。

彼らの子ども時代は離れ猿の佐助をのぞいて女優たちが扮し、一瞬にして一斉に黒布で隠れていた大人役に入れ替わる。コクーン歌舞伎「桜姫」のように小さい箱状のものに役者が乗って泥の舞台へ黒衣が押してくる演出も含めて、歌舞伎を真似する手法を遠慮なく使うのが実に好ましい。
泥の舞台で衣裳も汚れて足もとられて役者たちもスタッフも大変だと思うが、そのような負荷をかけても余りある面白さがある。蜷川組に多くの人間が集まるのは無理もないなぁと思う。ネクストシアターのメンバーは公演ごとに配役が変わるらしく当日の配役表がプログラムの小冊子と一緒に配られている。

横田栄司以下の客演陣が舞台を引き締めながら若手の伸び盛りの熱気があふれ出て、1960年安保闘争の頃の熱い青春群像が透かし見えるドラマが展開する。
真田の軍議は当時の学生集会のようなやりとり。横田栄司もその大将として堂々の存在感。紅一点のお霧に幸村以下全ての勇士が思いを寄せる中で、人の心が見えてしまう佐助の屈折とお霧の思いが交錯するというロマンスを含むことが一層ドラマを熱くする。その一方で秀頼・千姫の政略結婚を超えた愛情関係が対置されるのがいい。千姫のほのぼのとしたキャラ設定がよく、共に落城したお霧が生きていくことへの曙光への希望が感じられる。

大坂夏の陣で「カッコよく死ぬ」ことをめざした男たちが幸村のカッコ悪い最後同様に死に向かっていったこととくっきりとした対照をみせる。
理想を追い求めるあまりカッコよく刹那的に生きることは実はカッコよくないのだと思う。人間関係のあれやこれやに傷つきながらも尚生きていくという姿をヒロインに体現させているように受け取った。

蜷川幸雄はこのところ自らの演劇人生の原点の時代の1960年代の戯曲に取り組み、現代の社会に突きつけてくる。井上ひさしの初期の作品しかり清水邦夫作品しかりだ。
福田善之の作品は今回が初見だが実に面白いと思った。

奥の板絵のパネルが開いて奥に朝比奈尚行の音楽を演奏するバンドがいる。その奥がいつも私たちが座っている赤い客席が見え、死んでいった人物たちがあちこちの席にいるのをライトの向こうに透かし見せる演出が憎いねぇと思わせる。
「小劇場演劇」という概念を野田秀樹たちの1980年代のものと区別するために1960年代演劇という言葉が生まれたらしい。1960年代の小劇場演劇を特設の空間を使っても再現しようという蜷川幸雄の思いと力を見せつけられた。

千穐楽のカーテンコールらしく、蜷川幸雄が客席から作者の福田善之を呼び寄せた。頭の薄くなった蜷川さんと真っ白な頭の福田さんが若者たちの真ん中で拍手に応えて照れくさそうにしている姿が可愛かった。シルバーパワーと若者のパワーが融けあって新しいものが生み出されていることを実感。人間死ぬまで成長していくことをめざせるですよね、蜷川さん!!

写真は「Web埼玉」の10/15付けニュースより公開稽古の様子の写真。













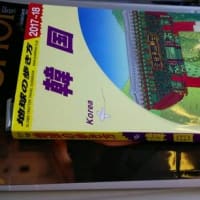
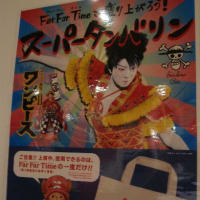

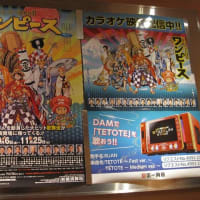
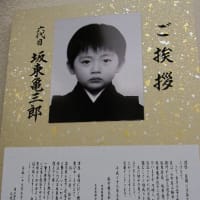
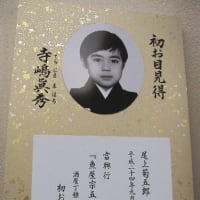

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます