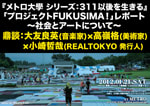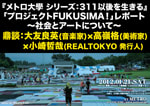また悪いクセだ。
もう二週間も経ってから感想を書こうとしている。
#細かい事はもうじぇんじぇん覚えていないよ~、メトロの後,、知り合いとの新年会だったしな~
でも書く。書かなくては。
一応、先に備忘録代わりにツイッターで
>福島出身の大友さんの立ち位置での話を聞けたことはとても重要。キーワード「一つ上の民主主義」・「意識されない差別のきつさ」・「『福島は元気』じゃない」・「いくつもの分断」。
なんてつぶやいておいたけれども、ツイッターじゃ結局流れて行っちゃうからなぁ。
ちゃんと書きとめておかないとバカだから結局忘れちゃいそうで怖いのだ。
今回のメトロ大學は去年の8月15日に福島で行われた、世界同時多発フェスティバルFUKUSHIMA!の仕掛け人である大友良英さんを迎え、高嶺格さんと小崎哲哉さんの3人による鼎談という事になっている。
因みに、高嶺さんと小崎さんという方は存じ上げませんでした。ごめんなさい。(言わなくていい?)
小雨そぼ降る21日。
ちょと遅れて入ったメトロですが「前の方空いてますよ~」との声に唆され、最前列のいすに座っちゃう。
既にステージ上では
オーケストラFUKUSHIMA! - LIVE @ 世界同時多発フェスティバルFUKUSHIMA!の映像をみせながら、大友良英さんがちょこちょこと解説を加えているところ。
この8月15日のライブの事は、儂全然知らなかった。当日もツイッターのTLで見かけてで最後の渋さ知らズだけリアルタイムで見たのだ。
その後、だいぶ暫くしてから、YOUTUBEでなんかの映像を探してて、このオーケストラFUKUSHIMAに辿り着いた。その時のショックといったら!
合奏、と言っても全員できちんとした旋律を奏でるというものじゃない。多少はあったのかもしれないけれど、全体としてはリズムと自由な音の重なりの大洪水。それを大友良英さんが指揮(というより合図)で操るのだ。え゛、いったい何人いるの?プロからおそらくアマチュアであろう無名の人たちまで。小学生くらいと思しき子どもから、かなりのお年嵩まで。ギターもいればホーンもいる、けどピアニカ?リコーダーか?なんですか?その弓みたいない奴は?えと・・・風鈴!?(爆)。 そしておびただしいパーカッション群!!!
渋さ知らズが好きで(渋さメンバーも参加)儂自身もお遊び程度に楽器をしている身でもある、何よりも羨ましかったのだ、その一体化した昂揚感が。
一体、なんなんだ?これだけの人を集めて。福島だぞ、原発の事故で放射能汚染が問題視されている場所やぞ。そこでなんでこんなイベントが?
後で調べたら、放射能対策もしてる、NHKの放射能汚染地図で一躍有名になった木村真三さんを迎えて。なんともなんともでかい風呂敷(縫い合わせたもの)を用意したりしている。それもただ単にライブイベントをするっていうだけじゃなくて、こんな風に地域を巻き込んだ形でのイベントだ。それが通り一遍のイベントじゃない事は参加してる人たちの顔をみれば分かるような気がする。
いや、これはホントにただの音楽フェスじゃぁない。
それだけはYOUTUBEの映像でも十分に分かった。
それはわかったが、その理由については謎のままだった。
結論めいているけど、仕掛け人である大友さんがちゃんと福島の地に足の着いている方であり、臨機応変にきちんとコーディネートできてるからなのだな。
あ、ダメだ。言葉にしたら陳腐だ(^^ゞ
さて、
メトロ大學の進行としては大友さんが3月11日以降、どのように考え行動し、このイベントに結び付け、そしてその後どうしていこうとしているか(どうする予定か)という時系列の話を中心に高嶺さんと小崎さんが質問したり、話を展開したりという感じ。
詳しい事は書かないけど(忘れてるけど)、大事なことは、福島出身である大友さん自身が直接福島に戻り、人と会って話をして、その先にこのイベントがあったという事。そう聞くと、このイベント自体が必然のようにも思えてくる。
大友さんが福島に初期に入り、「話を聞くとみんな疲れ果ててる、ほとんど鬱だ」みたいに言う、そのリアル。儂らがマスコミの報道だけ見聞きしているだけでは、決して伝わってこない現地の人たちの顔がきちんとそこにある。
「福島、全然元気じゃないよ!」
(福島県が進めようとしている、福島は元気だ、と喧伝しようとしているキャンペーンに対しての発言)
耳触りのいいキャッチコピーなんかてんで役に立ちはしない。風評被害を煽るだけだ。
本当のありのままの姿がみられない事には、儂らが福島をイメージして支援する事なんか出来っこない。
例えば
岩上安身さんのIWJがやっている百人百話のように、直接福島にいる人に聞かないとわからないリアルを意識するというのは本当に大事な事なのだ。
っつーか、みんな何故か忘れているような気がするけれどそれこそ当たり前の事なのだ。
あと、キーワードに上げた一つ、「一つ上の民主主義」
311の後、明らかに一部では政治に対して主体的な動きが大きくなった。
でもモノ足りない。
なんだかもう一つスコーンと突き抜ける何かが欲しい、そう感じていた。
が、それをどう表現したものか?わからないままもやもやしたものを抱えていた。
それを大友さんがこう表現してくれたと感じたのだ。
なんていったらいいのかな。
今はまだ、みんな表面的な事に対して文句を言ったり意見を言ったりする段階だと思う。でも、それだけでこの国が、社会が変化するとは到底思えないのね。
一つには、物事はいろいろつながりが合って、その表面的な物事になるのであって、儂らはもっともっと個人個人が繋がってそのうえで大きな繋がりの中で問題も考えて行かなくてはいけないという事。
一つには、大きな時間軸で考えないと物事は最終的に解決につながらないという事。もちろん短いスパンも大切なんだけど、中期的、長期的な視点が同等に扱われないと絶対ダメよね。
一つには、その変化を起こすためには事象の裏に隠れている(?)システム(というか、利権とか人脈とか構造とか力関係とか)があって、それを変える為の効率的な部分にみんなの目が行くという事。
一つには、個人のパラダイムが変化する事。利己主義にもいろいろあるんだけど、その利己主義が全体とつながった時に現れるパラダイムがあると思っている。
ちょっと、自分の中でまだ整理しきれていないから、ぱっと思い浮かんだままで書いていて恐縮だけど、大友さんがもっとウマい感じで表現してたんだけどなぁ、なんだっけなぁ(をい!)
#だから、すぐに書けって(心の中で自分に)言っているんだ!あかん、
クロニクルFUKUSHIMA 読もう
大友さんの去年のプロジェクトはそういったものが有機的に繋がった好例だというのが話を聞いててもひしひしと伝わってきたし、だからこそ大友さん自身も「一つ上の民主主義」って言葉が出てきたんじゃないのかな。
#「民主主義」って言葉は多分に政治的だけど、儂らが社会の中で何かをなそうとする事それ自体が政治的行為だと言えますよね。堅い言葉でちょっと敷居高く感じるかもしれないけれど、本当はそんなフツーの事だと思うんですね。
大事なのはイメージする事と気付く事かな、と。
「意識されない差別のきつさ」・「いくつもの分断」と書きましたが、善意で言ってるつもりのセリフが逆に差別する(差別されてるという意識に繋がってしまうという)事があったり、本来責任を取らなくてはいけない東電や政府に向けられるべき怒りが、人々を分断してしまうという事例にイヤといういうほどぶち当たりましたよ、この一年間。
これを乗り越える為に確かに必要な事の一つなんじゃないのかな、イメージする事と気付く事(若しくは気付いてない事があるかもしれないという感覚を常に持って意識する事)。
間違いなく言えることは、
・去年の3月11日を踏まえ、儂らは絶対に今までの通りではいられないという事。
・そこから目を背け、まるで今までと何も変わらないかのようにふるまって生活するという選択肢は基本的にあり得ないという事。
・新しい時代に適応する為には、どうやら大きな意識の転換が必要であるという事。
これくらいの事はもう疑いがないと思うのだけど、如何ですか?