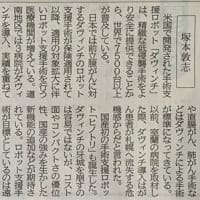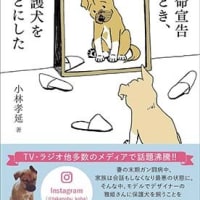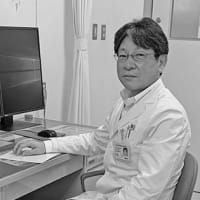24日は川汲(かっくみ)峠の北側に位置する台場山を登った。
出発点は道道83号(函館南茅部線)の新川汲トンネル手前(函館側)にあるNTTの管理道路。
ゲート前には3台ほどの駐車スペースがあるが、いろいろな物が捨てられているのを見ながら登山の準備をするのは気が重い。


熊出没看板 ゲート横が登山口
舗装した道をのんびりと歩いていく。
ゲート前には車が1台停まっていたが、山菜採りの人の車だった。
道は上冷水川沿いに北上するが、少し歩くと川を渡って南へUターン。
その後は道道に沿って北へ進み、やがて峠へと向かっていく。
途中からは左側がコンクリートで覆われている法面(のりめん:人工的な斜面のこと)の道が続く。
右眼がゴロゴロするようになった。
毎年この季節になると鼻水・くしゃみが数日続くが、眼に花粉症の症状がおきたのは初めてだ。


舗装道路 NTT無線中継所が見えてきたら頂上は近い
登り始めてから1時間ほどで分岐に達する。
NTT無線中継所とは反対の「台場山砲台跡」標識のある左の林道を進む。


林道から頂上への入口に標識がある 頂上への道
台場山の山名の由来は、明治元年の箱館戦争の際に榎本武揚が率いる旧幕府軍の土方歳三が砲台場を築いたことによる。


台場山頂上 正面奥の函館山は霞んでほとんど見えない。
風は少し強いが天気もよくて心地よい。
しばらく頂上でぼんやりと景色を眺めていた。
頂上の右奥にはっきりとした道がある。川汲温泉からの尾根道のコースだ。
函館の山岳会やSさんなどの記録を見た覚えがあるが、まったく予定はしていなかったので迷った。
恵山をホテル恵風から登り、八幡川コースを下ったときは、車のある登山口までは約1時間かかった。
川汲温泉コースを下山後は、それ以上の時間がかかるはずだが、初めての道を歩きたい気持ちが強くなった。
登山道はよく整備されている。頂上へ戻ることはせずに進むことにした。
ブナの林もある。ブナの巨木も出迎えてくれた。


大きなブナの木 キツツキが開けた穴
北海道で見ることのできるキツツキの仲間はアカゲラ、アリスイ、ヤマゲラ、コゲラ、オオアカゲラ、コアカゲラ、クマゲラの7種類。アリスイだけは夏に南から渡ってくる。
予想以上に快適な道だが、ヒグマの落とし物(糞)もあるので、何度も笛を吹いた。
右側の急斜面の下には見えないが、道道83号が走っている。救急車のサイレンが聞こえてきた。
このコースは途中で何度か小さな起伏を越える。
尾根の終わりに近づくと峠を走る車の音がよく聞こえるようになった。
ジグザグの斜面を下っていくと川汲温泉旅館の屋根が見えてくる。
川汲川のほとりに立った。登山靴のまま川を渡る。
道がわからないのでそのまま笹薮を進むと、川汲温泉旅館の入口正面だった。

川汲川
川汲温泉旅館は、18世紀中頃の寛保年間にはすでに開湯していたと南茅部町史(昭和62年刊行)に記されているほど歴史は古い。
川汲山中で傷ついた鶴が湯浴み(ゆあみ)して癒していたという伝説から、昔は「鶴の湯」と称されていたが、まだ行路が開かれていなかった200年も前から函館から湯治にくる者が多かったという。
鶴の舞いおりる霊泉の名は、鶴の湯伝説となって名湯の名を一層高くしていた。
湯治場となったのは文政12年(1829年)。函館の能登谷治兵衛が湯守としていた弁吉より、温泉地および権利を譲り受けた。
さらに幕末期には旧幕府軍の土方歳三隊がここに逗留したという記録もある。旅館の駐車場には「箱館戦争川汲戦戦死者の慰霊碑」があり、土方歳三はじめ旧幕府軍の幹部らは当時「山中旅館」と言われたこの旅館に泊り、野営の兵たちも交代で入浴、行軍の疲れをいやした後、翌朝早く五稜郭へ向けて出発した。
昭和45年には大幅な改築が行われて、現在の川汲温泉旅館となった。


川汲温泉旅館

旅館の敷地内にある「函館維新の会」の案内版と慰霊碑。
下着の着替えとタオルでも持っていたら、川汲温泉で汗を流し、タクシーを呼んでもらいたかった。
温泉でタクシーだけを呼んでもらうのは諦めることにして歩き出す。
この峠の道は飛ばす車がほとんどだ。
40分ほど歩くと新川汲トンネルで、全長は2,056㍍と記されている。
左側に旧道があるが、そこには川汲隧道(トンネル)があるはずだ。
どちらを進むか迷ったが、新川汲トンネルにした。
トンネル内で大型トラックが通ったときは風圧で身体が道路側に押されそうになる。
後で調べてわかったが、川汲隧道は塞がれていた。
理由は「重金属を含む土砂を適正に管理するため」で、新川汲トンネルのずり(掘った土砂)かはら基準をオーバーするヒ素や鉛などが検出されたために、川汲隧道に保管されているようだ。

新川汲トンネル。左は旧道。
ゲートを出発して、車に戻ってくるまで4時間近くかかった。
帰宅後も右眼のゴロゴロは治らず、さらに右瞼は虫に刺されて赤く腫れていた。
まさに「泣きっ面に蜂」となってしまった。
出発点は道道83号(函館南茅部線)の新川汲トンネル手前(函館側)にあるNTTの管理道路。
ゲート前には3台ほどの駐車スペースがあるが、いろいろな物が捨てられているのを見ながら登山の準備をするのは気が重い。


熊出没看板 ゲート横が登山口
舗装した道をのんびりと歩いていく。
ゲート前には車が1台停まっていたが、山菜採りの人の車だった。
道は上冷水川沿いに北上するが、少し歩くと川を渡って南へUターン。
その後は道道に沿って北へ進み、やがて峠へと向かっていく。
途中からは左側がコンクリートで覆われている法面(のりめん:人工的な斜面のこと)の道が続く。
右眼がゴロゴロするようになった。
毎年この季節になると鼻水・くしゃみが数日続くが、眼に花粉症の症状がおきたのは初めてだ。


舗装道路 NTT無線中継所が見えてきたら頂上は近い
登り始めてから1時間ほどで分岐に達する。
NTT無線中継所とは反対の「台場山砲台跡」標識のある左の林道を進む。


林道から頂上への入口に標識がある 頂上への道
台場山の山名の由来は、明治元年の箱館戦争の際に榎本武揚が率いる旧幕府軍の土方歳三が砲台場を築いたことによる。


台場山頂上 正面奥の函館山は霞んでほとんど見えない。
風は少し強いが天気もよくて心地よい。
しばらく頂上でぼんやりと景色を眺めていた。
頂上の右奥にはっきりとした道がある。川汲温泉からの尾根道のコースだ。
函館の山岳会やSさんなどの記録を見た覚えがあるが、まったく予定はしていなかったので迷った。
恵山をホテル恵風から登り、八幡川コースを下ったときは、車のある登山口までは約1時間かかった。
川汲温泉コースを下山後は、それ以上の時間がかかるはずだが、初めての道を歩きたい気持ちが強くなった。
登山道はよく整備されている。頂上へ戻ることはせずに進むことにした。
ブナの林もある。ブナの巨木も出迎えてくれた。


大きなブナの木 キツツキが開けた穴
北海道で見ることのできるキツツキの仲間はアカゲラ、アリスイ、ヤマゲラ、コゲラ、オオアカゲラ、コアカゲラ、クマゲラの7種類。アリスイだけは夏に南から渡ってくる。
予想以上に快適な道だが、ヒグマの落とし物(糞)もあるので、何度も笛を吹いた。
右側の急斜面の下には見えないが、道道83号が走っている。救急車のサイレンが聞こえてきた。
このコースは途中で何度か小さな起伏を越える。
尾根の終わりに近づくと峠を走る車の音がよく聞こえるようになった。
ジグザグの斜面を下っていくと川汲温泉旅館の屋根が見えてくる。
川汲川のほとりに立った。登山靴のまま川を渡る。
道がわからないのでそのまま笹薮を進むと、川汲温泉旅館の入口正面だった。

川汲川
川汲温泉旅館は、18世紀中頃の寛保年間にはすでに開湯していたと南茅部町史(昭和62年刊行)に記されているほど歴史は古い。
川汲山中で傷ついた鶴が湯浴み(ゆあみ)して癒していたという伝説から、昔は「鶴の湯」と称されていたが、まだ行路が開かれていなかった200年も前から函館から湯治にくる者が多かったという。
鶴の舞いおりる霊泉の名は、鶴の湯伝説となって名湯の名を一層高くしていた。
湯治場となったのは文政12年(1829年)。函館の能登谷治兵衛が湯守としていた弁吉より、温泉地および権利を譲り受けた。
さらに幕末期には旧幕府軍の土方歳三隊がここに逗留したという記録もある。旅館の駐車場には「箱館戦争川汲戦戦死者の慰霊碑」があり、土方歳三はじめ旧幕府軍の幹部らは当時「山中旅館」と言われたこの旅館に泊り、野営の兵たちも交代で入浴、行軍の疲れをいやした後、翌朝早く五稜郭へ向けて出発した。
昭和45年には大幅な改築が行われて、現在の川汲温泉旅館となった。


川汲温泉旅館

旅館の敷地内にある「函館維新の会」の案内版と慰霊碑。
下着の着替えとタオルでも持っていたら、川汲温泉で汗を流し、タクシーを呼んでもらいたかった。
温泉でタクシーだけを呼んでもらうのは諦めることにして歩き出す。
この峠の道は飛ばす車がほとんどだ。
40分ほど歩くと新川汲トンネルで、全長は2,056㍍と記されている。
左側に旧道があるが、そこには川汲隧道(トンネル)があるはずだ。
どちらを進むか迷ったが、新川汲トンネルにした。
トンネル内で大型トラックが通ったときは風圧で身体が道路側に押されそうになる。
後で調べてわかったが、川汲隧道は塞がれていた。
理由は「重金属を含む土砂を適正に管理するため」で、新川汲トンネルのずり(掘った土砂)かはら基準をオーバーするヒ素や鉛などが検出されたために、川汲隧道に保管されているようだ。

新川汲トンネル。左は旧道。
ゲートを出発して、車に戻ってくるまで4時間近くかかった。
帰宅後も右眼のゴロゴロは治らず、さらに右瞼は虫に刺されて赤く腫れていた。
まさに「泣きっ面に蜂」となってしまった。