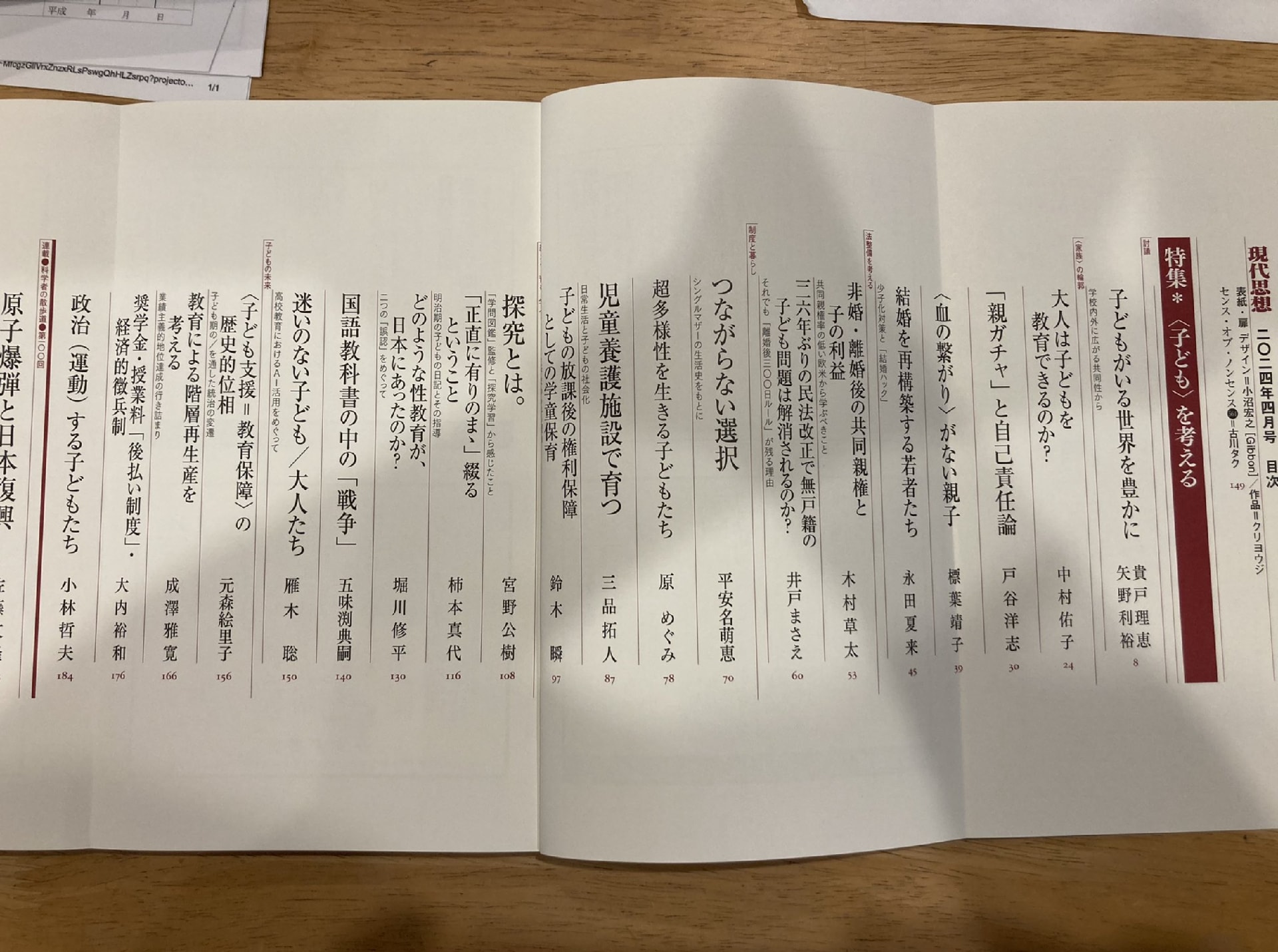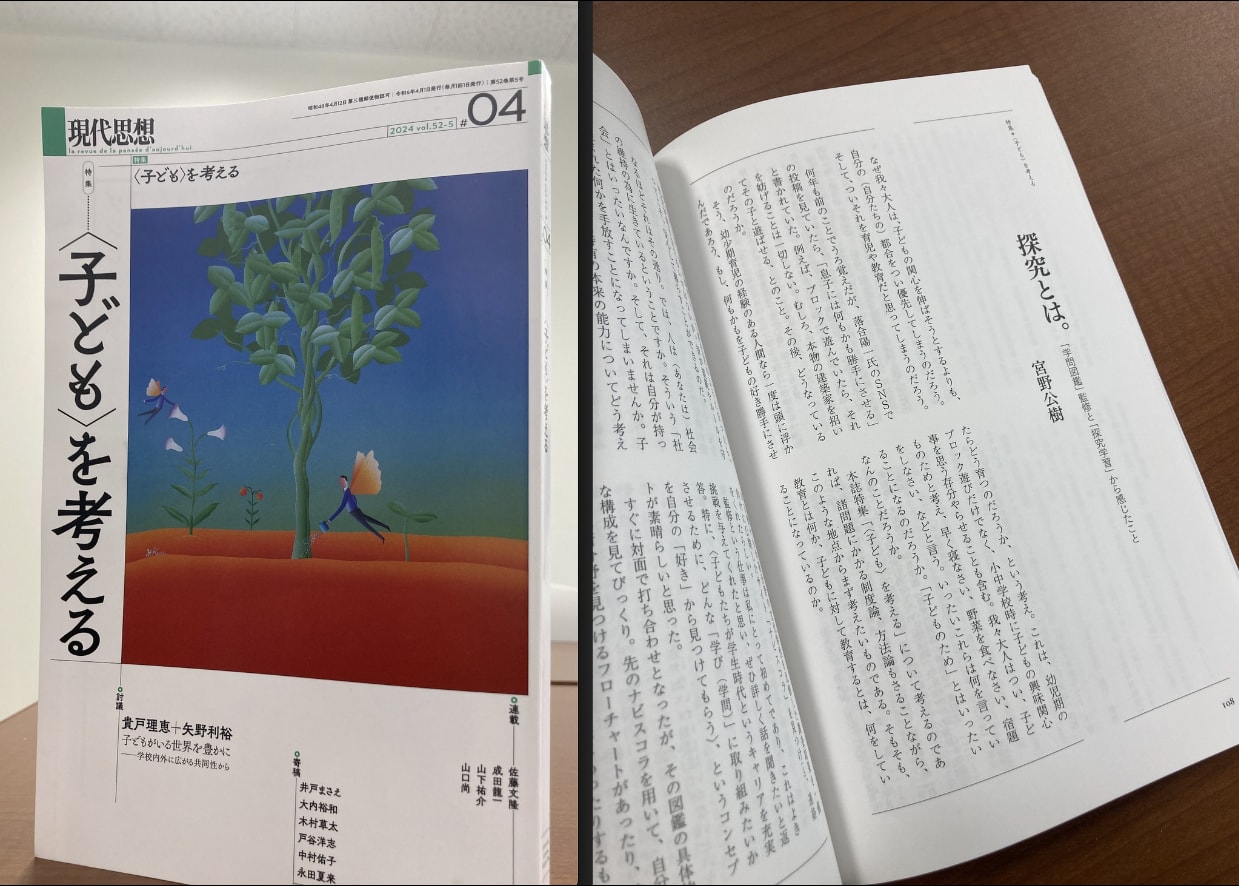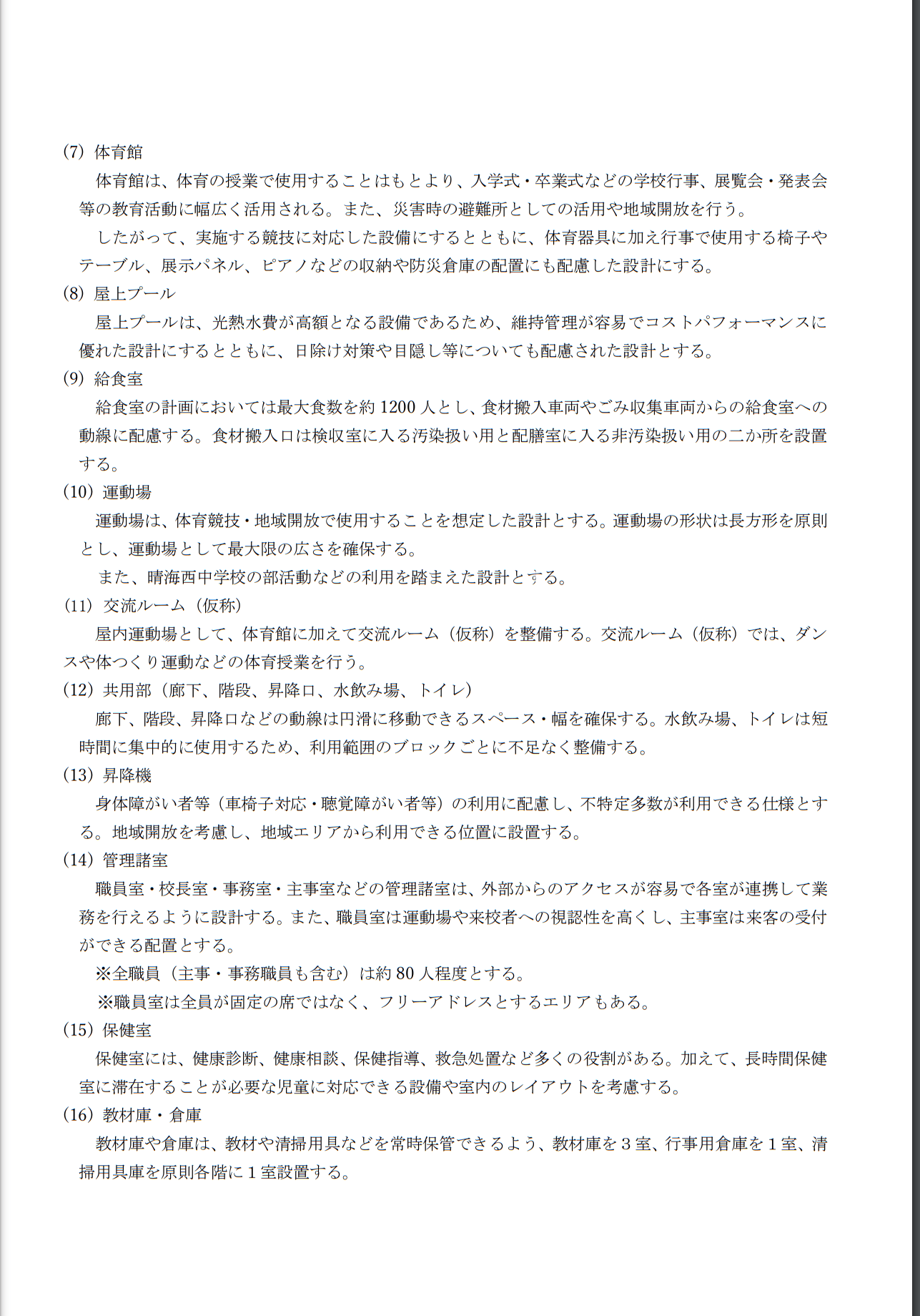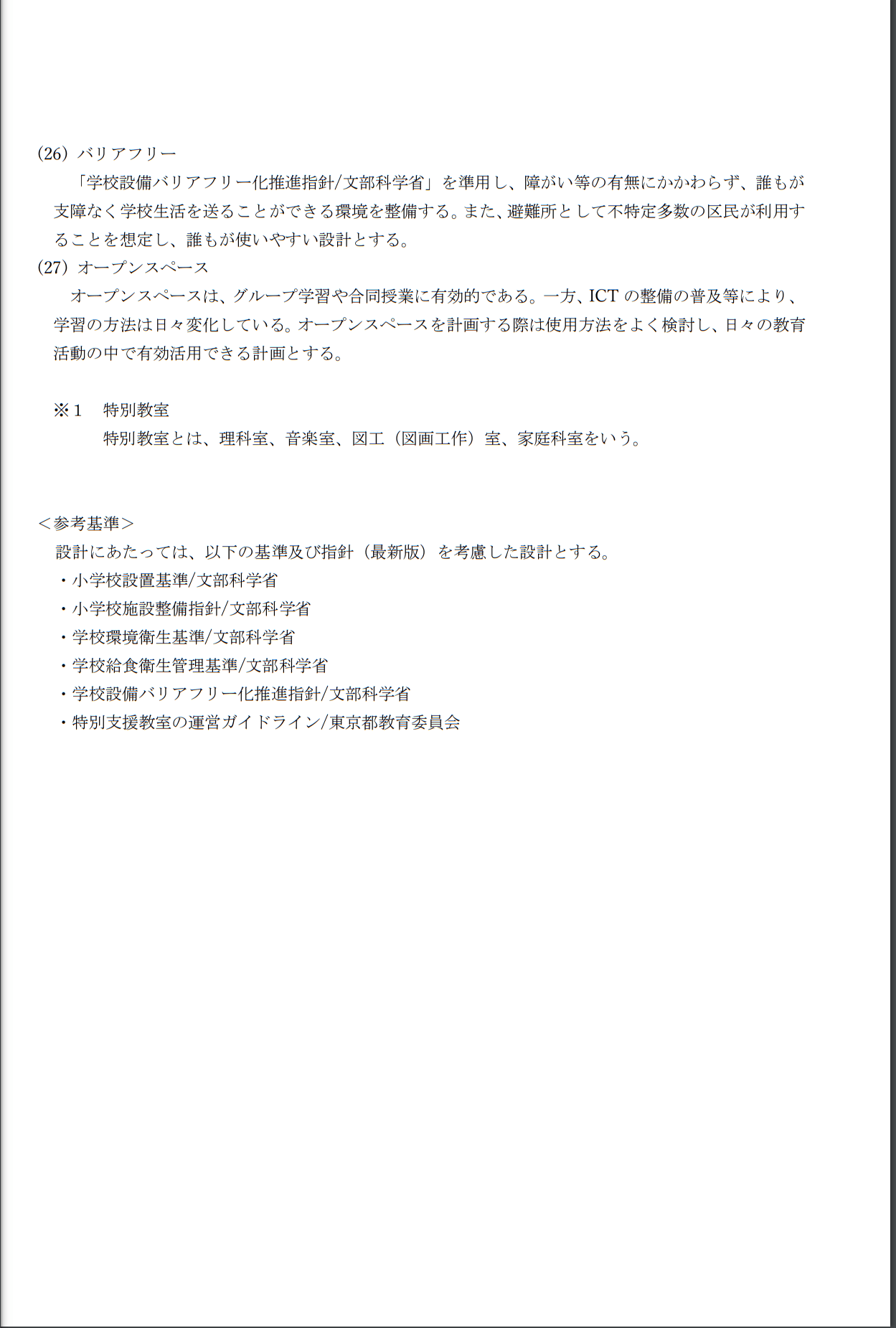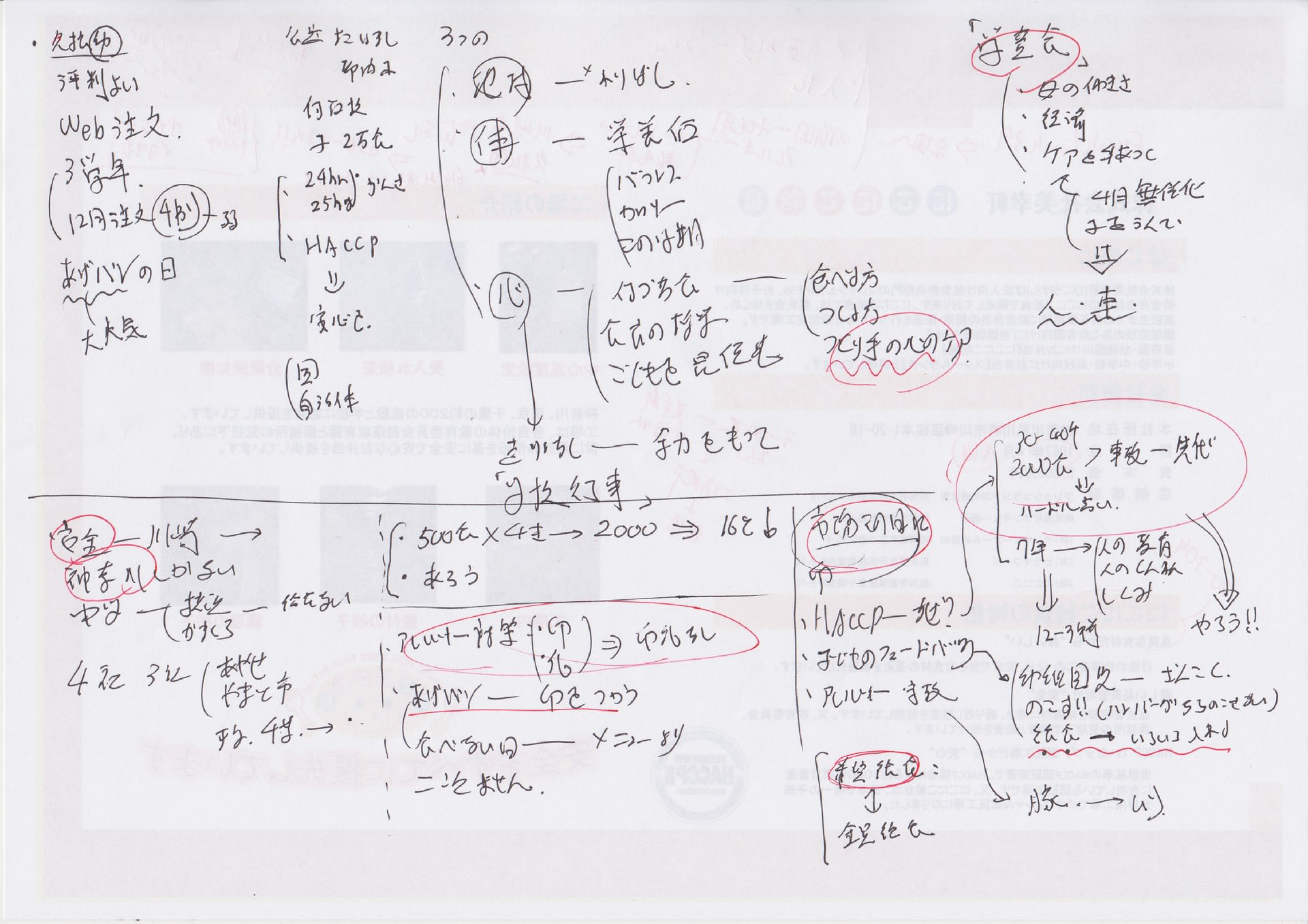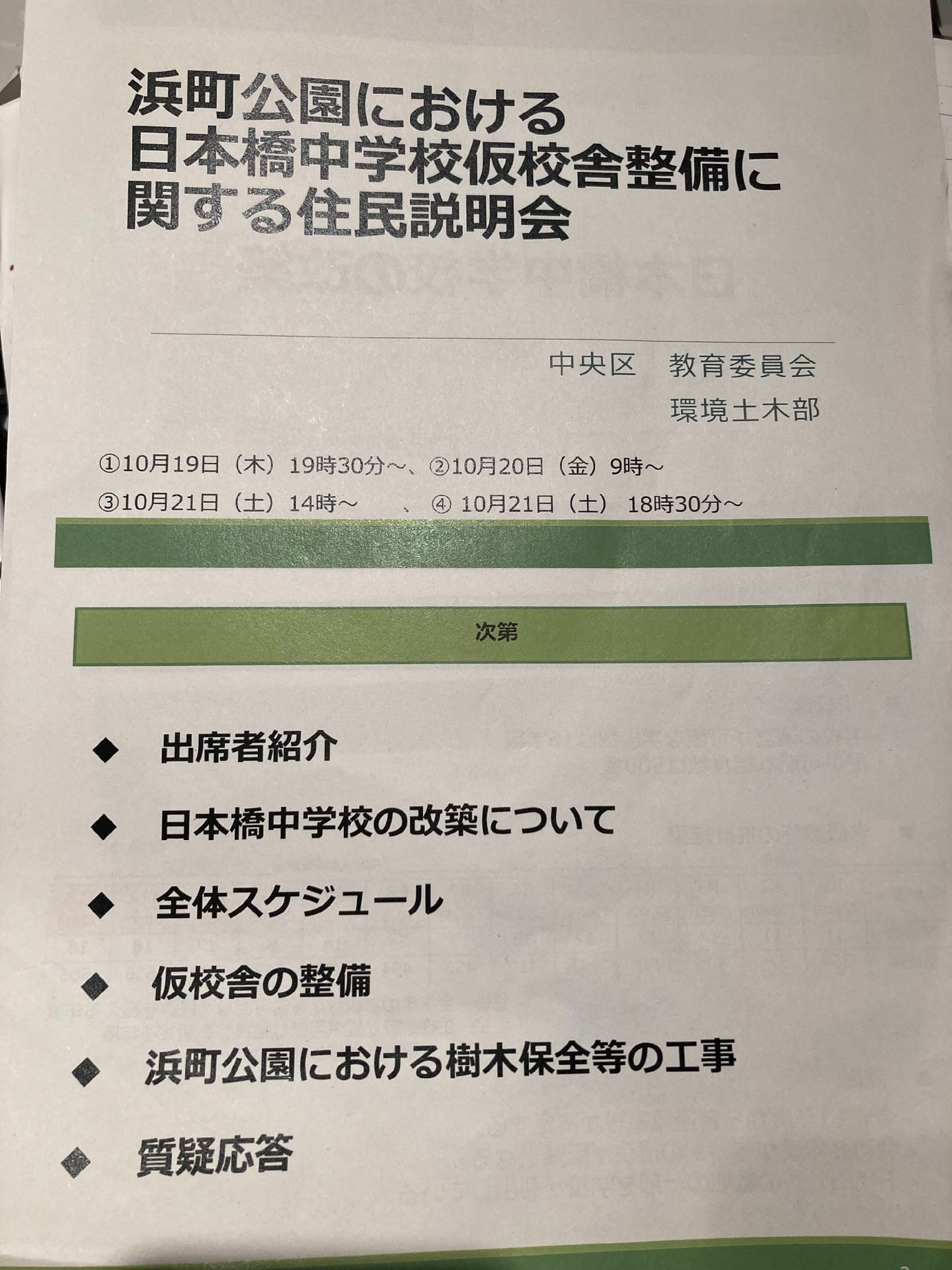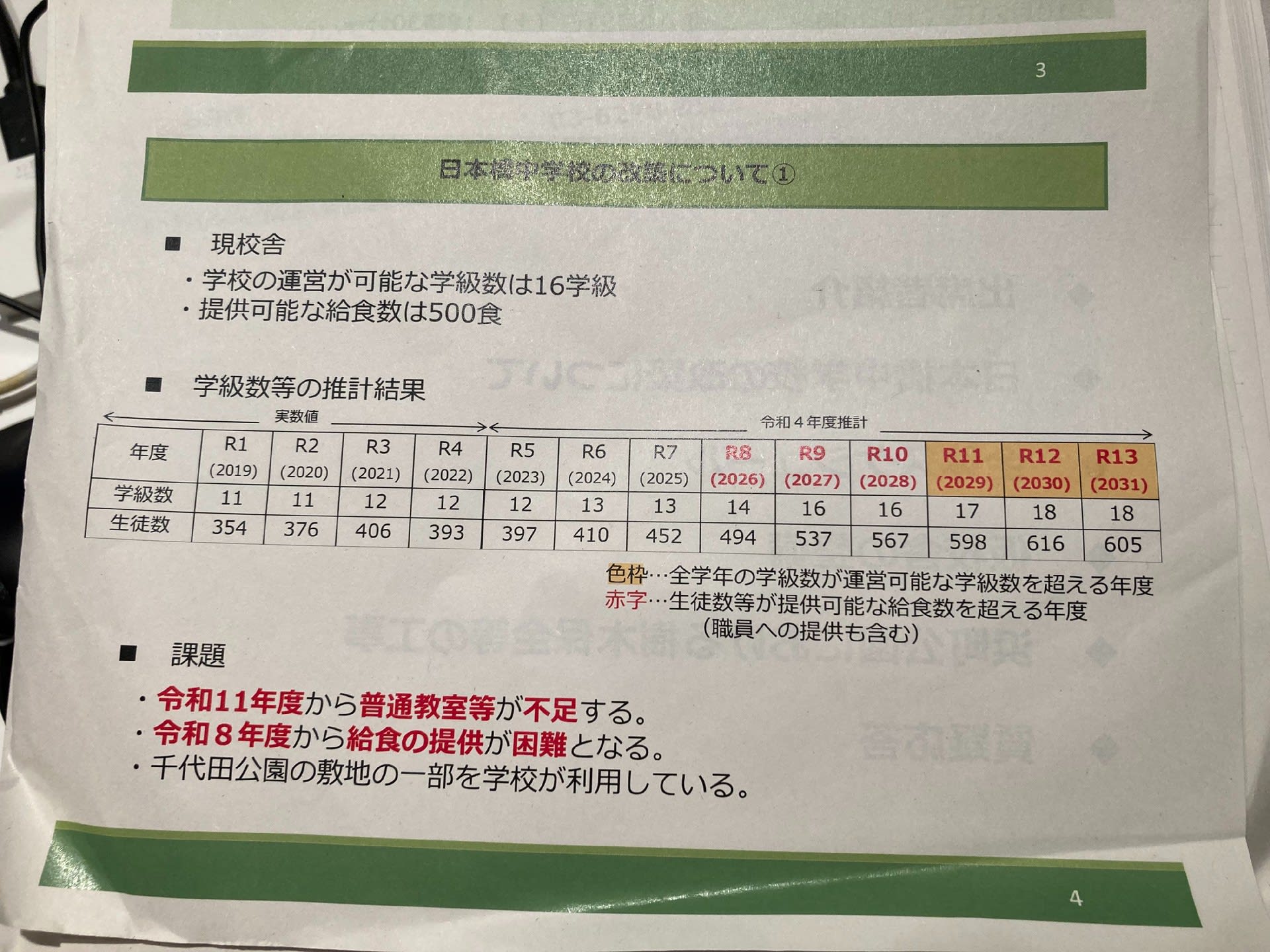先日の予算審議でも議論してきましたが、中央区(だけではなく全国ではあるが)の最大の課題のひとつは、学校の先生方の多忙を解消すること。
本日の東京新聞に、先生方の疲弊の声がアンケート結果として掲載されています。
中央区は、昨日の教育委員会で教育長からご報告がありましたが、「欠員なし」でスタートすることができています。
これも当然といえば当然だけど、「欠員」のある自治体もあるようです。
先生がたの多忙が解消できるように考えていければと思います。
いろいろなアイデアを、よろしくお願いいたします。
現場の先生からも、こうしてほしいなどの声もお願いします。
●専門家(日本大文理学部の末冨芳教授(教育政策学))が提言する解決策:
1,教員志願者の奨学金返済免除
2,定年後再任用教員の待遇改善
根本治療
3,基礎定数の改善、
4,教員養成課程におけるカリキュラム負荷の軽減
********東京新聞2024.4.11*********
https://www.tokyo-np.co.jp/article/320477
先生の6割が「3年以内の離職・転職」を考えている…教員不足で現場に起きているひずみの数々
2024年4月10日 20時39分
大学教授らでつくるグループが、教員不足について公立学校の現職教員にアンケートしたところ、昨年12月時点で「勤務校の教員不足が起きている」と答えた小学校教員が64%いたことが分かった。「4月の年度初めから不足していた」と答えた教員は37%、「夏休み明けの9月から」と回答した教員は57%で、年度内でも徐々に悪化していく状況が浮かび上がった。(榎本哲也)
◆公立学校教員1231人の回答を分析すると…
中学校教員の回答では、不足が起きた時期が4月が37%、9月55%、12月56%。特別支援学校ではさらに深刻で、4月に欠員があったと答えた教員が63%、12月は77%にまで増えていた。調査結果やアンケートの自由回答からは、産育休や病気の欠員を補充できず、教員の健康や子どもたちの学びに悪影響が出ている実態が見て取れる。
調査したのは、NPO法人スクール・ボイス・プロジェクトなどでつくる「#教員不足をなくそう!緊急アクション」。昨年12月~今年2月、SNSを通じてウェブアンケートを実施。寄せられた回答のうち公立学校教員の1231人分を分析し、今月9日に発表した。
小学校教員のうち「3人以上の教員不足」が生じたと答えた教員は4月時点が2%だったが、12月では10%に上った。また、1年以内に離職や転職を考えていると答えた小学校教員は13%で、「3年以内」も含めると62%。中学校教員もほぼ同じ割合だった。
調査を分析した日本大文理学部の末冨芳教授(教育政策学)は「まず、教員志願者の奨学金返済免除や、定年後再任用教員の待遇改善などに取り組んだ上で、根本治療として基礎定数の改善、教員養成課程におけるカリキュラム負荷の軽減などを進めてほしい」と提言している。
********国会図書館*************
https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10311174_po_0945.pdf?contentNo=1#:~:text=%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E5%AE%9A%E6%95%B0%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E6%95%99%E8%81%B7%E5%93%A1,%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82&text=%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E5%AE%9A%E6%95%B0%E3%81%AE%E5%A4%A7%E9%83%A8%E5%88%86,%E5%BF%9C%E3%81%98%E3%81%A6%E7%AE%97%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%80%82