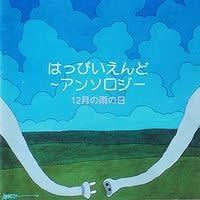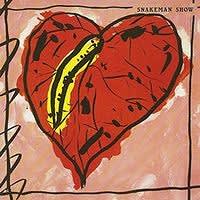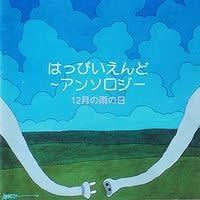
はっぴいえんど~アンソロジー 12月の雨の日 / はっぴいえんど (1998)
はっぴいえんどのベスト盤。といってもこちらは一般的に発売されたものでなく”The CD Club”という通販企画で通販のみで頒布発売された商品のよう。この”The CD Club”というのは洋邦他ジャンルの音楽を特集して発売している息の長いシリーズだが(今もあるのかな?)、市販品の丸写しでなく独自選曲で、しかもしっかり的を射た選曲だったりするし、易々とレーベルの壁を越えたり、解説が詳しかったりするのでなかなか侮れない。
自分が初めてはっぴいえんどを聴いたのは中学生ぐらいの頃だったか。YMOのファンだったので細野晴臣経由だったか、それとも日本の伝説のロックバンドという括りで聴いたのか忘れてしまったが、ギターの音には痺れたけれどさしたる感銘を受けた訳ではなく、「~です、~ます」調の歌詞をよくロックにのせるなァなんて思ったぐらいだった。かなりフォーク的に感じて、それが違和感でもあった。なのでオリジナル・アルバムも1枚も持っておらず、その後何年も経ってからレンタルCDで借りた編集盤をカセット・テープに録音したものぐらいしか持っていなかった(※調べてみたら92年発売の「Let The 70's Die」<ジャケ写真下>という渋谷陽一監修の日本語ロックの編集盤だったようだ)。

ちなみにその盤の選曲はこれ。
01. 銀色のグラス (ザ・ゴールデン・カップス)
02. 本牧ブルース (ザ・ゴールデン・カップス)
03. 朝まで待てない (モップス)
04. 御意見無用~いじゃないか (モップス)
05. からっぽの世界 (ジャックス)
06. ラヴ・ジェネレーション (ジャックス)
07. 塀の上で (はちみつぱい)
08. センチメンタル通り (はちみつぱい)
09. はいからはくち (はっぴいえんど)
10. 春よ来い (はっぴいえんど)
11. 塀までひとっとび (サディスティック・ミカ・バンド)
12. タイムマシンにおねがい (サディスティック・ミカ・バンド)
13. おそうじオバチャン (憂歌団)
14. 嫌んなった (憂歌団)
15. 春のからっ風 (泉谷しげる)
16. 翼なき野郎ども (泉谷しげる)
17. 雨あがりの夜空に (RCサクセション)
18. スローバラード (RCサクセション)
なかなか凄い。このCD改めて欲しくなった(笑)。
それはさておき、繰り返し特集されたりする彼らの偉大さにはちっともピンとこなかったのだが、最近バッファロー・スプリングフィールド(Buffalo Springfield)、CSN&Y(Crosby, Stills, Nash & Young)、ニール・ヤング(Neil Young)、ザ・バンド(The Band)やなんかを聴き直しているうちに、やっとそれらの音楽とはっぴいえんどの音楽との繋がりを意識するようになり(遅い)、ちょっと聴いてみたくなったのだ。その辺のことはもう既に語り尽くされていることばかりで書き加えることは無いが、あの時代の日本のロック人達の早熟な事には毎度の事ながら恐れ入る。今と違って情報量が圧倒的に少ない時代。ましてや映像なんてほとんど無いから耳コピでマスターしていったり、直接海外まで行って体得したのだろうが、遜色ないどころかすでに個性も生まれていて、それに日本語歌詞をのせる試みが行われているのだから驚く。
オークションにて購入(¥780)