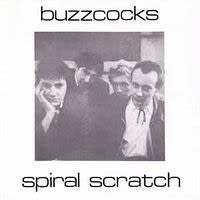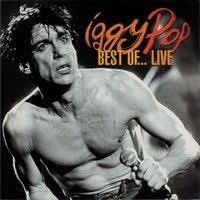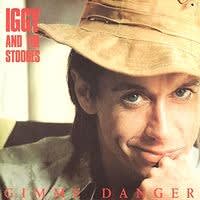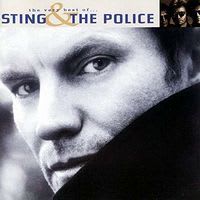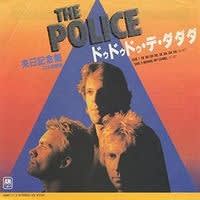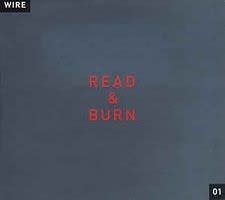

Read & Burn 01 / Wire (2002)
Read & Burn 03 / Wire (2007)
ワイヤー(Wire)のデジパックのEP2種を購入。ワイヤーは現在でも活躍する数少ないオリジナル・ロンドン・パンク~ポスト・パンク・バンドのひとつ。自分も彼らを聴き始めてはや30年以上が経つが、ここまで存続するとは思っていなかった(※途中活動停止時期や別活動あり)。現在はオリジナル・メンバーのブルース・ギルバート(Bruce Gilbert)は抜け、若いMatthew Simmsがギターを担当している(←ストレートの長髪がイヤ・笑)。中心はもちろんコリン・ニューマン(Colin Newman)だが、彼の創作意欲は衰えないようで、オリジナル・アルバムもしっかりと発表し続けている。それぞれ02年と07年に発売されていて、「02」ももちろん存在しているが持っていないはず、と思ってCDの棚を確認しに行くと…無情にも「01」があった…。またやってしまった(涙)。
「01」の方は初期を彷彿とさせるようなスピード感のある曲が並ぶ。”原点回帰”なんていうテーマでもあったろうか。先に2003年に発売されたアルバム「Send」に収録されている曲もある。アルバムに先行して発売されていたのだろう。それもあって聴いたことある曲もあるな…と思ったが、先述の通り「01」は持っていたので聴いたことがあるのは当たり前だ(←把握していないのが情けない…)。コリン・ニューマンのクールなのに熱いヴォーカルが、高速で弾かれる硬質な音色のギターと独特の世界を作りだす。これだけ音が溢れている時代に、聴いてすぐそれと分かるバンドっていうのも凄いことだ。相変わらずカッコイイ。03の方はもっと内向的な曲が並ぶ。これもワイヤーの重要な側面。発表年が離れているのにシリーズとしたのは何か意味があったのだろうか。
ネットにて購入(各¥500)
- Label : Pink Flag
- ASIN : B000065CU9
- Disc : 1
- Label : Pink Flag
- ASIN : B000WW27MU
- Disc : 1