
仙波太郎、陸軍中将正三位勲一等功三級
画像は、昭和46年4月1日、私が福音寺公民館に掲示してあった写真を複写し、パネルに仕上げて、陸上自衛隊松山駐屯地に寄贈、駐屯地の資料館に展示してある。
仙波太郎は安政2年(1855)4月21日に、久米郡福音寺(現・愛媛県松山市福音寺町)に生まれ、幼名を惣太郎といった。
父は、旧和気郡馬木村の庄屋田所与惣右衛門の弟で、仙波家の養子となった。
その資性は、世俗のわずらわしさを気にしないのびのびしており、まじめでおごそかで、 どっしりしており、また書が達者であった。
仙波家は、福音寺村の庄屋であったが、太郎の幼少時に家計の不如意から、家産は次第に減少したようである。(私の曽祖父、仙波友十郎と幼友達で、沢山の書簡が届いていた。それを大切に保存し、屏風にしていた。)
少年時代から三津浜で魚類を買って、松山に行商したり、小野村の山奥の駄馬に行って入会林で切り取った木の枝を刈り、これを町へ売り歩いたりしながら、僅かな賃金を得て家計を助けた。
父が病床に臥せってから、母と二人で苦労を重ねたが、この間に処しては母は貧しいなかにも太郎を激励し、その薫陶に全力を傾け激しい労働のかたわら、僅かな時間を惜しんでで南久米の三輪田塾に学び、直接米山の教えを受け明治7年の秋(20歳)の時陸軍教導団に合格、病床にあった父は彼を激励、意を決し上京、叔父の松田通博の学友河東坤(碧梧桐の父)の援助を受けた。
その後陸軍士官学校に入学、明治11年12月卒業、同12年2月歩兵少尉、同16年に中尉となった彼は、故郷星ノ岡に土居通増・得能通綱らの奮闘の生涯を永遠に伝えるために松田通博・吉田格堂・鈴木安職らの有志と謀って土居・得能氏の古戦場に「星岡表忠之碑」を建設した。
同16年4月創設された陸軍大学第1期生として入学同期生に秋山好古がいた。
その後陸軍大学教官、ドイツ留学その時射撃術を習得帰国後射撃術の優秀な部隊に名誉旗を授与するようになったのは彼がドイツで行なわれていた制度をわが国に採用させた結果である・・中略・・陸軍士官学校教官を経て大佐に昇進第三師団(名古屋)の参謀長、このころ、陸軍の三太郎「宇都宮太郎・桂太郎、後の内閣総理大臣・仙波太郎」のひとりと呼ばれた福岡歩兵第24連隊長となりその後第二旅団長を経て明治43年11月30日陸軍中将・・中略・・かねてから永住の地を岐阜県加納町に決定していた。
退役後夫人、矢野タマの出身地である加納町に居住した。
大正9年5月衆議院議員に当選、わが国の社会教育に貢献、彼は質実剛健で正義の士あって真に軍人の典型的であり、しかも単なる軍人に終わった人でなく常に豊富な学識と社会的常識とを保持し、正確な判断と処理となし得た立派な社会人でもあった。・・秋山好古は、仙波太郎中将は良く働いたとの談話がある。
仙波太郎と久米村との関係は、大正7年に御下賜金を受けた時、これを直ちに岐阜県教育委員会と久米村青年団とに匿名で寄贈した。
また昭和2年(1927年)に生誕地福音寺の屋敷跡に村民のために「公正会堂」を建てて寄付し、村の社会教育のために努力した。その跡地は現在集合住宅となっている。
昭和4年2月19日、逝去 75歳。(久米村誌より)
参考1:陸軍大学校は明治16年参謀将校の育成と軍事研究等を主任務として創設され、第1期生は、選抜された19名が入学、その中に伊予松山から秋山好古と仙波太郎がいた。卒業できたのは10名で、主席で卒業したのは、東条英教(東条英機の父)で秋山好古は9番目、仙波太郎は3番目の成績で二人とも卒業出来た。
教育期間は、歩兵・騎兵が3年、砲兵・工兵は2年であった。
参考2:陸軍士官学校の教育期間は、歩兵・騎兵が3年、砲兵・工兵は4年であった。
参考3:旧伊予松山藩主、久松定謨がフランス留学の時、同伴役として依頼を受けたが「私は、藩主久松定謨様には世話になってない、庄屋として多くの年貢を献上してお世話をした方である。よって断わる。」と言った。それで好古が行くことになった。
参考4:仙波太郎は、退役後、岐阜市から慕われて衆議議員に選ばれ社会教育の振興に寄与した。

画像は、左から、秋山好古(近衛師団長)・久松定謨(近衛第1連隊長)・仙波太郎(歩兵第1師団長)
この3人が、大正3年衛戍地である東京を、朝敵とされた旧伊予松山藩出身者の、秋山好古・久松定謨・仙波太郎の3名が守護した。軍人であったが、晩年は「世の為、人の為、故郷の為」教育に尽くした偉い人達であったと思う。・・一時期朝敵とされ苦労したが!!

大佐時代の仙波太郎(45歳)右は、少佐時代の仙波太郎(38歳)
写真は、田所氏所蔵。
本原さんが書かれた仙波太郎の手記の一部
松山の宿は木屋町一丁目の私の家、松山に帰って時は大抵1ヶ月は滞在し家族同様にして過ごした・・・中略・・軍を離れたはじめの頃は満州や支那にもよく行っていた。帰りに松山で疲れを休めていた。そして揮毫をよくするので父はその墨をするのに汗だくであった。鍾馗と達磨が得意で5分間くらいで書き上げるので驚きの目で見ていた。中略・・秋山好古が松山に帰れてからはよく訪ねて来られ「ワシ」「オマエ」の仲で昔話を楽しんでおられた。松山高等学校のストライキが起こりかけた時も丁度仙波が来ていて、北豫中学校長であった秋山好古と香坂県知事の三人で木屋町の家で密談をしておられ、ストライキは不発に終わった。
「これが仙波の帰松最後の事件であったかもしれない」
昭和3年か4年頃、仙波から今年も又そのうちに帰るからその前に福音寺に持ってゆくお地蔵さんを送るから受け取っておいてくれと連絡があり、着いたのは一米位のお地蔵さんであったが首が落ちていたので母が何か悪い予感がすると心配したが、予感通リそれが最後の帰郷計画になってしまった。お地蔵さんは久米に送ったが今は何処にあるのか時々考えることがある。尚どうしたわけか知りませんが千舟町の白石写真館で撮った仙波太郎の写真が手元にありますので司馬遼太郎の記事を機に写真と共に古いとりとめのない思い出をまとめた次第です。しかし何分にも古い事ですので思い違いがありましたらお許し下さい。・・こんな記事があります。

仙波太郎の得意であった鍾馗の絵。
写真は、田所氏所蔵。

松山平野で、此れから出て来る星岡山と土亀山の位地を確認のため掲載した。
土居・得能氏の古戦場の「星岡表忠之碑」があるのは、星岡山で、仙波太郎の墓所は、土亀山にある。

この画像は、松山市畑寺町の淡路ヶ峠から撮影。

「星岡表忠之碑」
揮毫は、二品伏見宮貞愛親王
石碑は、明治16年に中尉となった仙波太郎は、故郷の星岡山に土居通増・得能通綱らの奮闘の生涯を永遠に伝えるために松田通博・吉田格堂・鈴木安職らの有志と謀って土居・得能氏の古戦場に「星岡表忠之碑」を建設した。
参考:二品伏見宮貞愛親王・安政5年4月28日~大正12年2月4日は、日本の皇族、陸軍軍人。官位は元帥陸軍大将大勲位功二級内大臣。

「星岡表忠之碑」右側に、建立発起人 陸軍中尉 仙波太郎・松田通博・吉田格堂・鈴木安職、鴻田佐太郎の各位の氏名が刻まれている。

「星岡表忠之碑」裏面碑文
建武中興之功臣楠氏新田氏北畠氏固卓々牟亜之者莫西海菊池氏南海土居氏得能氏若也得能氏名通綱土居氏名通増並河野之族為伊予著五世祖河野通信為国守護承久之役属官軍軍敗・・中略・・仙波太郎等慨此謀建碑表之同志者・・明治十七年甲申五月
史館編修 従五位 藤野正啓撰・・と揮毫してある。

松山市教育委員会設置の「星岡古戦場」説明板。

松山市星岡町薬師山(75m)山頂に建立されている、星岡表忠之碑と説明板。休憩用のベンチも設置されている。

古戦場に「星岡表忠之碑」の横に、三等三角点がある。
点名:星岡(ほしおか)
種別等級:三等三角点
所在地:松山市星岡町薬師山乙240番地
緯度:33°49′00.1958
経度:132°47′14.4014
標高:74.97 m

星岡山登り口に設置されている案内板。

星岡山(薬師山)山頂にある「薬師堂」で、1200年前聖武天皇詔を国司散位太夫平智宿彌に降りし給し天平13年3月に建立せられる。尊像は行基菩薩の作と伝えられる。別に脇仏として日光菩薩月光菩薩十二神将の尊像を安置す。また薬師堂の西側には、南朝の忠臣土居・得能両氏の勤王についての表忠碑あり星の岡古戦場として史跡を保存す。・・と雲門寺所蔵古文書に記述がある。(石井村誌)

星岡山、山頂から見た伊予郡砥部町方向の風景。

山麓にある「雲門寺」、曹洞宗五岳山雲門寺、伊予十二薬師八番霊場である。

松山市福音寺町「土亀山」にある仙波太郎中将のお墓。
仙波太郎は、奥さんの郷、岐阜市加納町で死去した。福音寺の墓は分骨である。
墓石の左側に先妻の「妻ケイ」の名前が揮毫されている。
正岡子規の「凩にはひつくばるや土亀山」明治25年 終わりの冬、に詠んだ句がある。
生前墓は、大きな墓石にするなと言われたのではないか? 先祖の墓石とほぼ同じ大きさである。
軍人の墓石は、肩書入りの大きな墓石であるが、秋山好古も墓石は家族と一緒「秋山家」の墓で眠っている。
仙波も、秋山もよく似たものだ。
参考までに:秋山好古の墓は東京青山霊園に在るが「秋山家」の墓に家族と一緒に眠っている。軍人時代の肩書は一切揮毫していない。また松山道後鷺谷墓地に在る墓は、東京青山霊園からの分骨である。

昭和49年、仙波太郎の長男、仙波正、孫の仙波昭が建立した「仙波家墓所」の石碑。

仙波太郎中将の先祖代々のお墓。
仙波太郎の一族は松山には居なく時より岐阜市から墓参りに来ておる。
時々秋山兄弟生誕地で研究員として活動している、「仙波女史」が墓掃除をしている。・・親族ではないが。










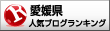

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます