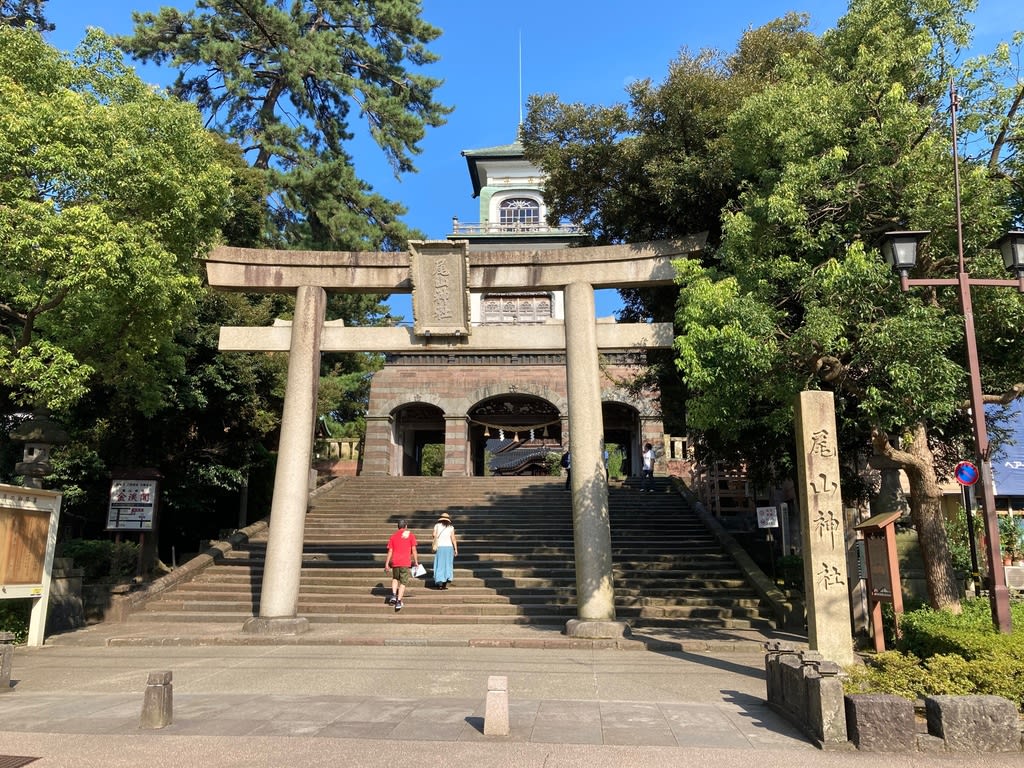2019年辺りから南北朝時代が注目を浴びているらしい。それに合せるように2020年の日曜日の朝には約30年前の大河ドラマ『太平記』が再放送されていた。このドラマは、それまで日本史の三大悪人の一人(諸説あり)とされていた足利尊氏の再評価が行われたことでも特筆すべき内容だったが、鎌倉幕府が滅びるまでの経緯を丁寧に描いた作品としても大きく評価されている。
彦根藩を調べていても南北朝時代は避けて通れないほど井伊家に大きく関わっていて、彦根藩の行動理念の基になる理由付けになっているため、私も「井伊家千年の歴史」を連載しているときは『井伊家傳記』と『太平記』を読み込み矛盾のない繋がりを探し続けた。
また近江は、南北朝時代も当然のように重要拠点となり幾つもの関連地が伝承されている。この連載でも長浜市安楽寺の紹介で足利尊氏との関わりを紹介している。
さて、そんな近江と『太平記』の関わりで特に有名な史跡は米原市番場の蓮華寺ではないだろうか?
足利高氏(鎌倉幕府滅亡後に尊氏に改名)は幕府の命で京に上洛し亀岡市の篠村八幡宮で討幕を宣言して一気に鎌倉幕府京都守護の拠点である六波羅探題を攻め落とす。六波羅探題の責任者は北条時益と北条仲時の二人だったが、足利軍の急襲に驚いて対応ができないまま光厳天皇・花園上皇を連れて鎌倉に向かって落ち延びることとなる。
時益は京から出る前に討死、仲時は東山道を進んで行った。この道中を見る限り仲時に隠れる様子はなく、観音正寺に宿泊したとの言伝えもあることから悲壮感は感じられない。しかし不破の関の直前で佐々木高氏(道誉)が陣を構えていると知った時点で近江を抜けることができないと悟り、天皇・上皇の安全を見定めた後に蓮華寺本堂前において家臣らを含めた432人が自害して果てたと言われている。こうして仲時らの墓所は蓮華寺内に建立されているが、仲時の最も古い墓石はここにはない。
江戸時代、井伊家当主が馬上のまま蓮華寺の墓に参った夜、仲時が夢枕に立ち「我を馬上から見下ろすとは何事ぞ」と怒ったため、墓石が向かいの山に移されたとの伝承があるのだ。墓石の移転は享保年間と言われているため藩主は井伊直定ではないかと推測される。歴代彦根藩主を考証すると個人的に「直定公ならやりそう」と思っているが、史料から直定が移転させたかを確定することはできない。しかし、どの藩主が命じたにしても仲時の墓は蓮華寺と向かい合うように建立されていて悪意を持った移転ではないと信じたい。
仲時の墓を移転させた山は、現在「六はら山」と呼ばれている。仲時の墓石直下の山裾には稜威直孝彦命(井伊直孝)を祀った溝尻神社(昭和49年に直孝神社と改称)が建立されている。実質的な彦根藩祖とも言える直孝の上に仲時が供養されていることに根拠のない妄想を膨らませてしまう。
六はら山山頂付近の北条仲時の墓