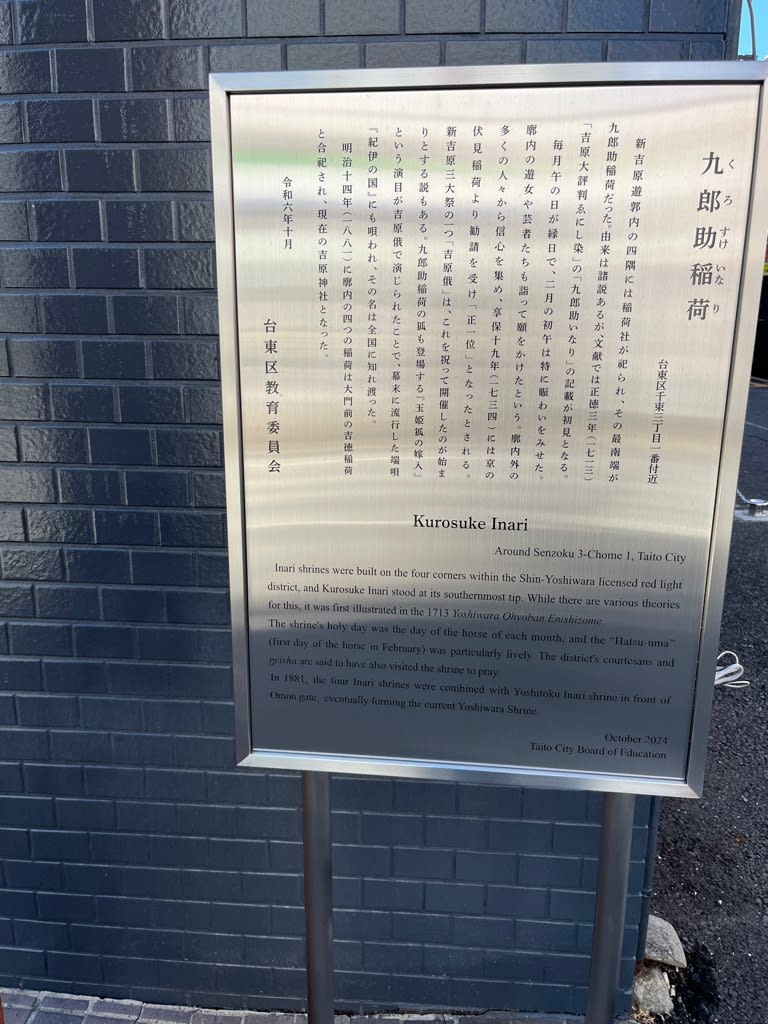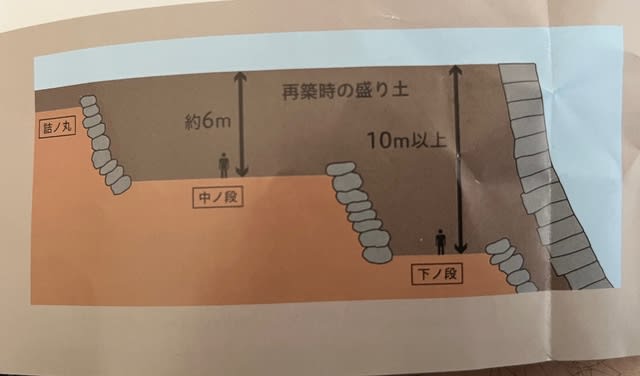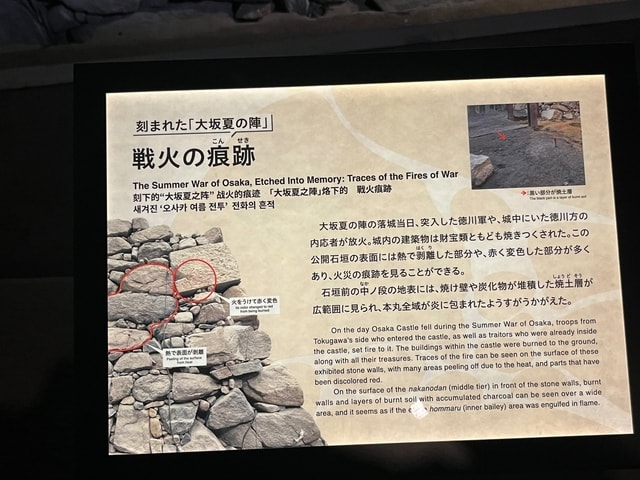鱗形屋は、田沼時代には三代目を数える江戸の地本問屋でした。
もともとは京都の八文字屋の江戸店を引き継いで開いた店であるために上方の版元との繋がりが強く、出版後進地域であった江戸において出版を牽引した版元でもあったのです。
また、地本問屋であり書物問屋でもある大店でした。
しかし、安永4年(1775) 、『新増説用集』という本が『早引説用集』(上方の柏原屋与左衛門・村上伊兵衛が版権を持っている)を盗作したものであるとの訴えがあり、鱗形屋の板木などは没収されました。
そして同年末には『新増説用集』の責任を追っていた手代である徳兵衛が家財欠所及び江戸から十里四方追放、主人の孫兵衛が急度叱及び過料鳥目廿貫文などの処罰が下されたのです。
ちなみに『説用集』とは、単語の最初の読み方で「いろは」順に分類し、それを部門毎に分けて漢字や読み方を紹介した今の国語辞典の元祖になるような物です。
また上方では半世紀以上前から盗作については問題視されていて、書物問屋たちが京都や大坂の町奉行に禁令を依頼して何度も禁令が発布されていますが、守られていないのが実情でした。
このことからも、わざわざ江戸の鱗形屋を上方の版元が訴えることについての疑問も感じざるを得ません。
しかし、同年に鱗形屋から恋川春町の『金々先生栄華夢』も刊行され、黄表紙という新ジャンルの開拓(ただし当時の人々は黄表紙との認識はなく青本の一種としている)した鱗形屋は家業を保たせていました。
そんな中、旗本某家の用人が遊ぶ金欲しさに主の物を盗んで売るという事件が起こり、この用人と盗品購入業者の仲介を行った罪で孫兵衛は江戸所払いの罰を受けました。
安永10年には江戸に戻り、寛政年間まで家業は続けたようですが、再び登り目になることはなく廃業し、その後の記録は残っていません。
ただ、孫兵衛の次男は西村屋与八の養子となり、二代目西村屋与八として活躍、戯作者としての名も残していますし、二代目の跡を継いだ三代目西村屋与八は葛飾北斎『富嶽三十六景』の版元にもなっています。