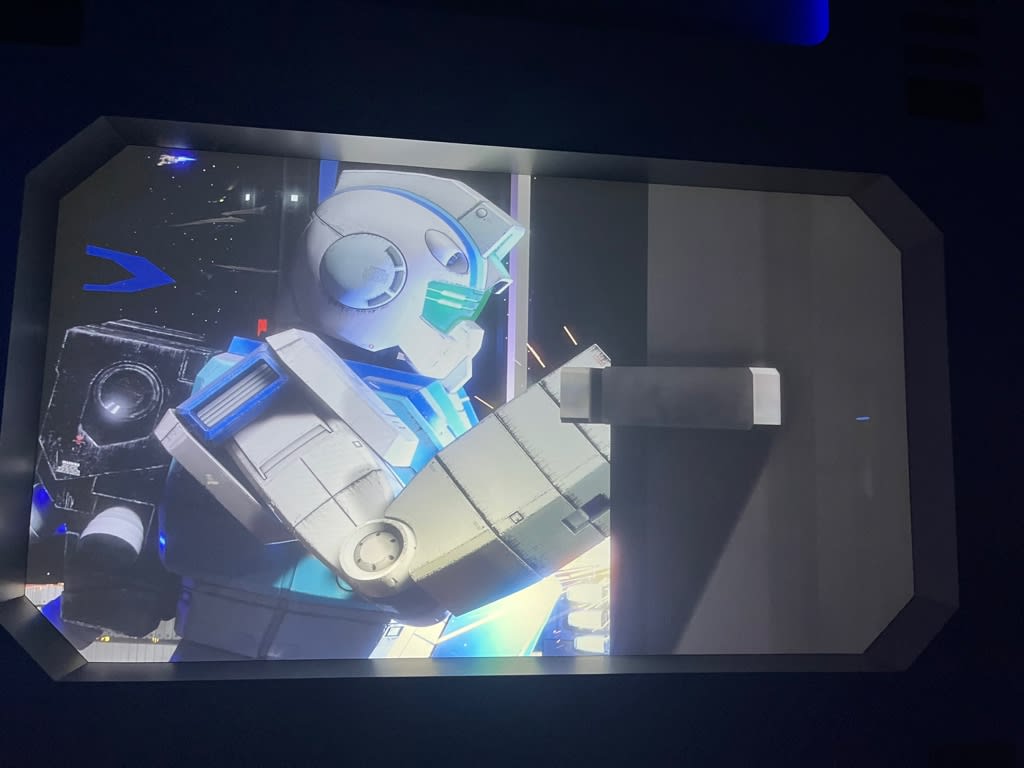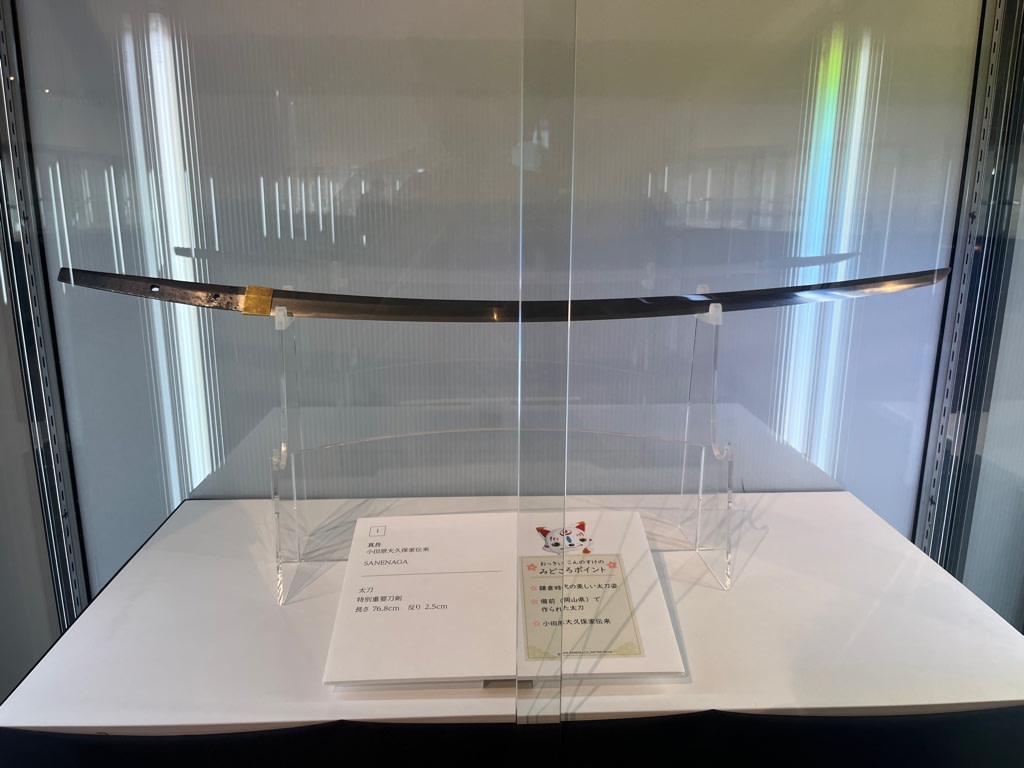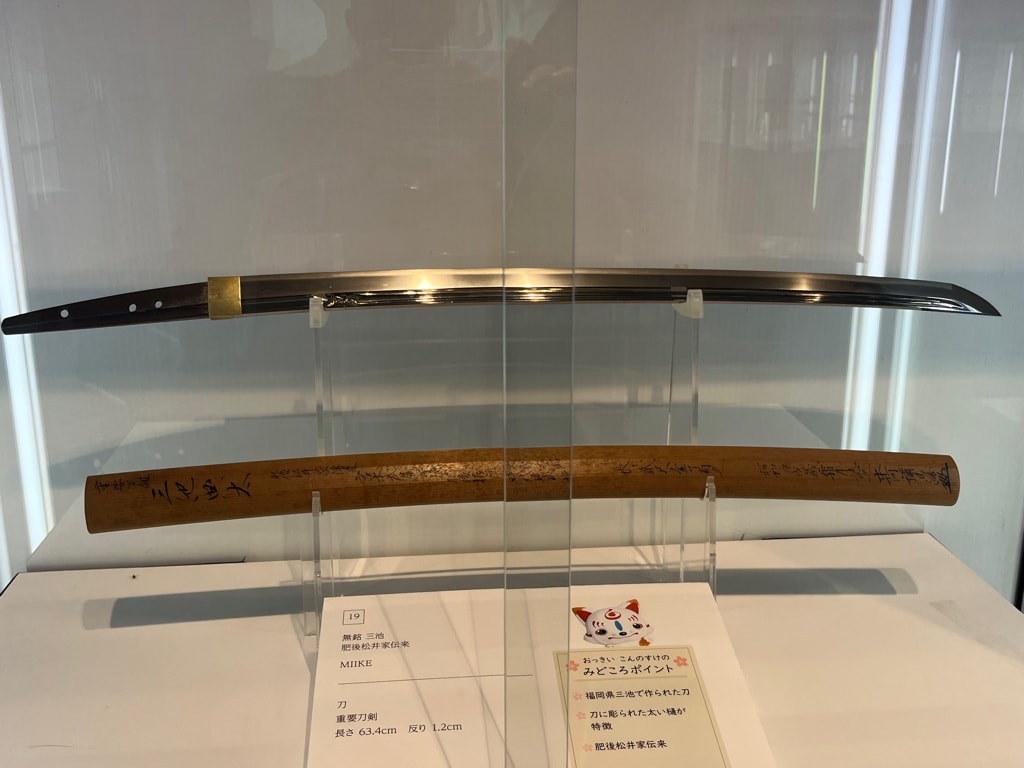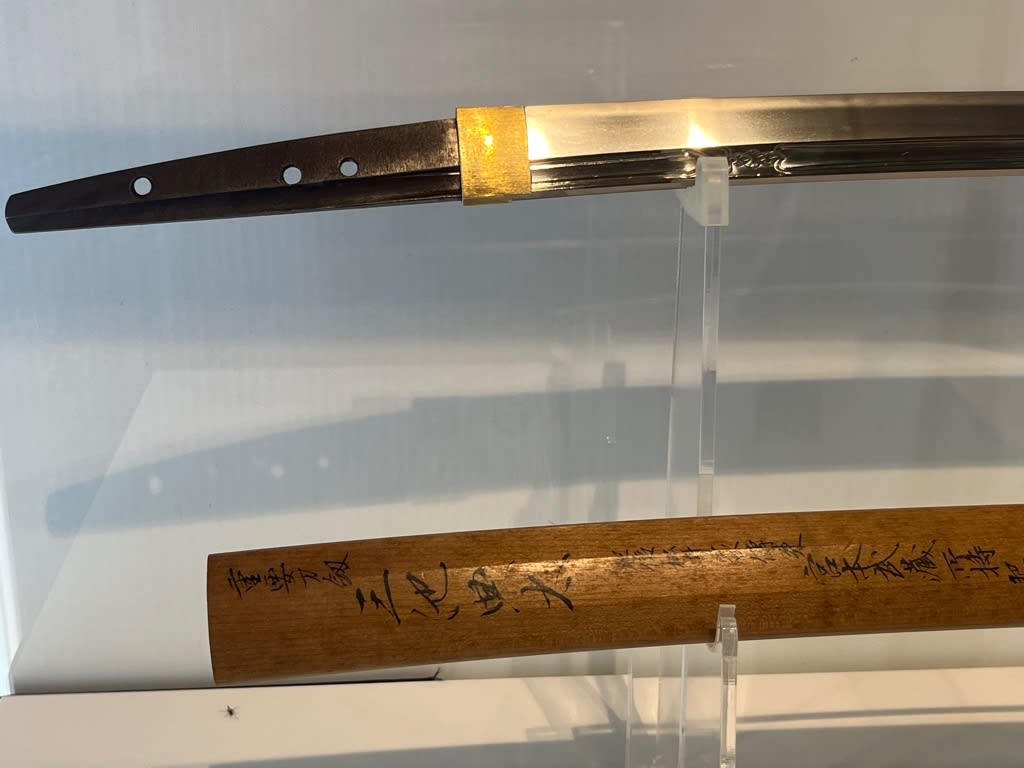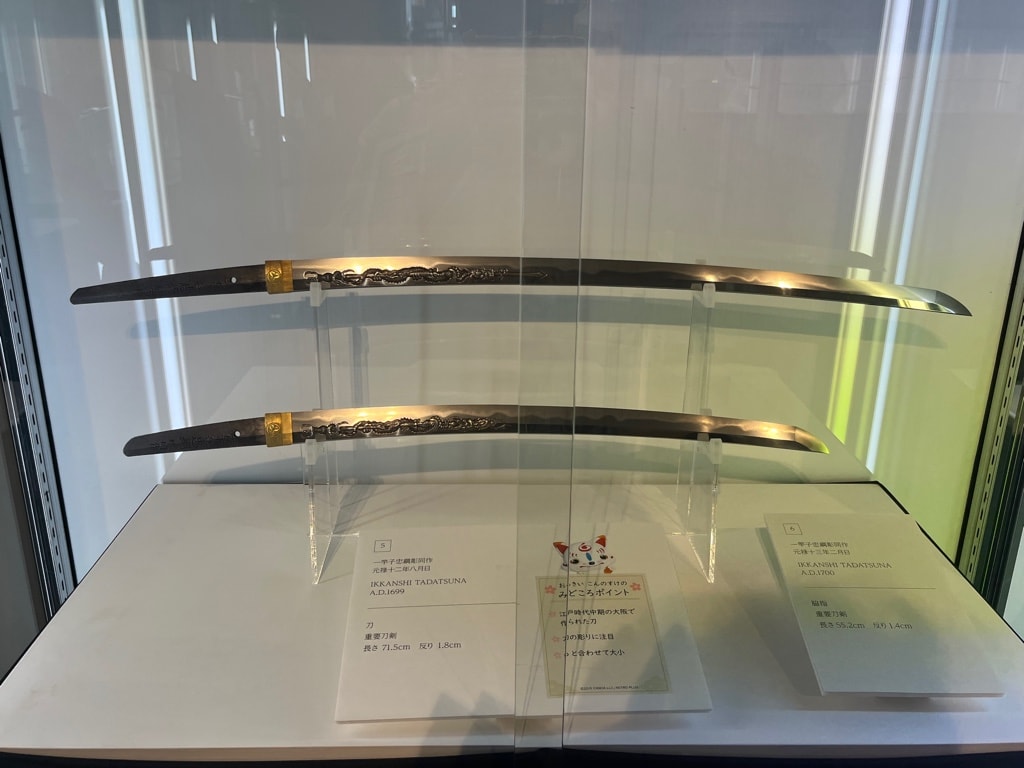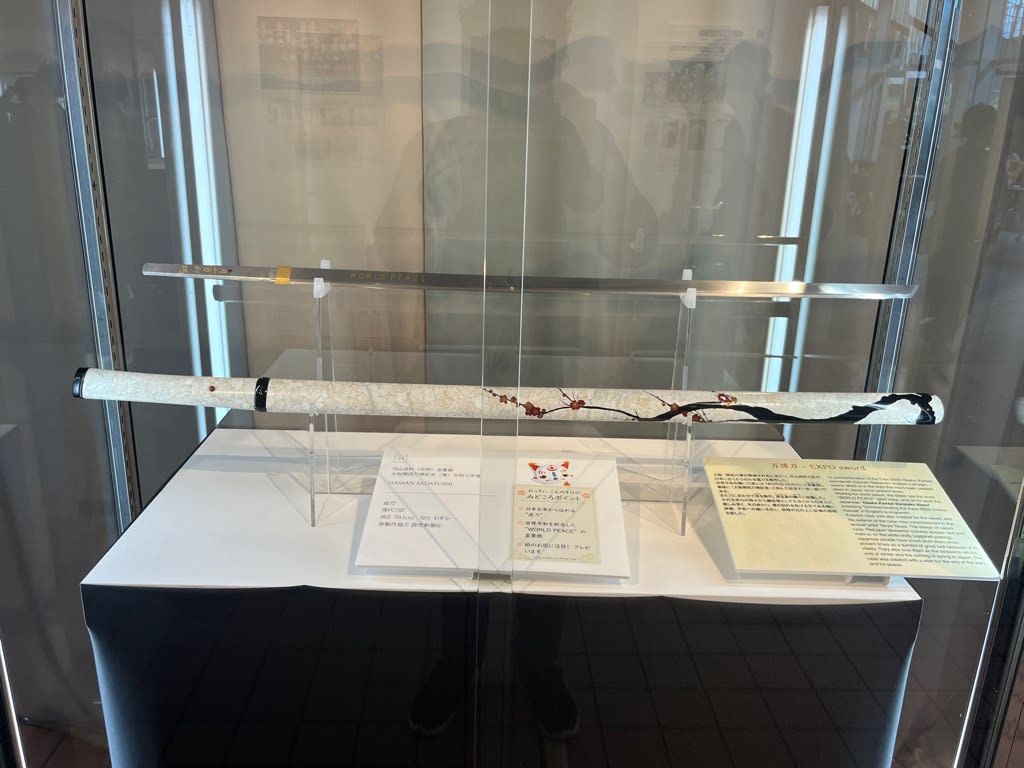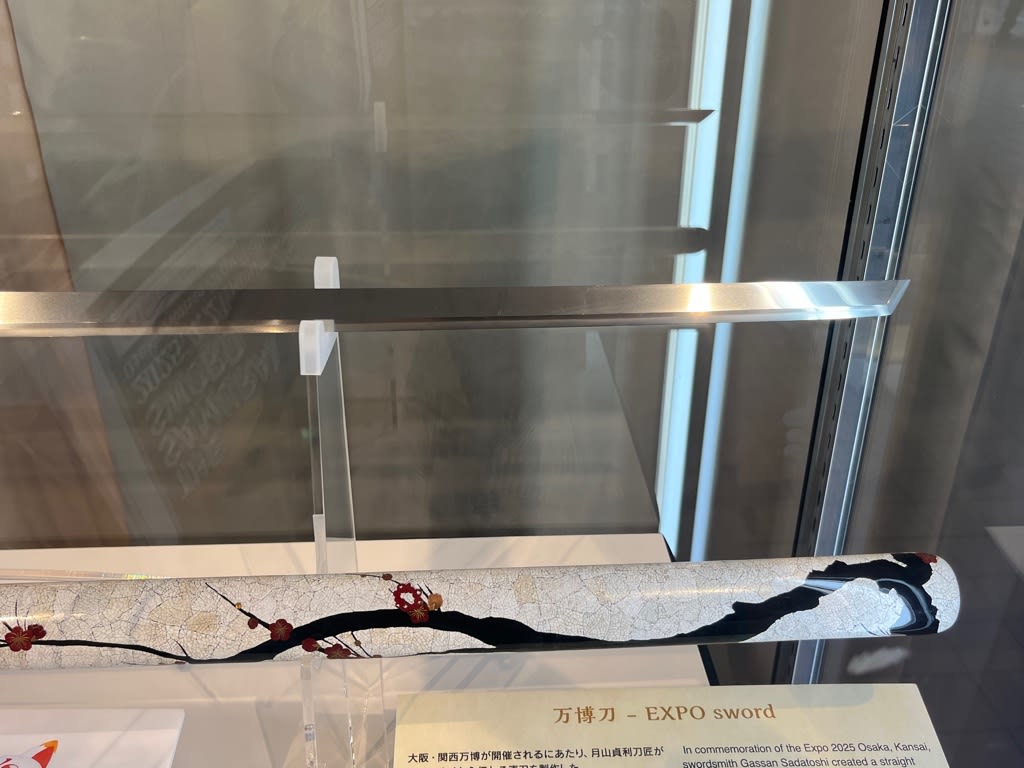天明7年(1787)10月、田沼意次が老中職を辞しながらもまだ権力を握っていた田沼派の幕閣たちも次々と失脚し、松平定信政権は田沼意次個人に対して苛烈な処分を行います。
・意次の蟄居
・家督は孫意明が相続
・相良藩の旧領没収のうえ、奥州下村藩一万石立藩
でした。
目立った罪がない元老中に対して最大で五万七千石(実益はもっと多い)から一万石(実益は半分くらい)に減封というだけでも相当の怨みを感じます。
10月12日、幕府は相良に40名強の役人を派遣
16日、収城使を命じられた岸和田藩主岡部長備が藩士ら2600名を率いて江戸より相良にはいり、平田寺に本陣を置く。
11月25日夜明けとともに、岡部長備が相良城に入城。
相良藩士たちの抵抗に備えて、佐賀藩鍋島治茂、丹波篠山藩青山忠講の家臣が掛川宿にはいります。
また、城の四方を、横須賀藩西尾忠移、田中藩本多正徳、三河吉田藩松平信明、掛川藩太田資愛、浜松藩井上正甫が固めていました。
『忠臣蔵』の赤穂城明け渡しでも、収城使が緊張している場面がありますが、相良城でも多くの大名や幕臣を備えたのでした。
これに対し、相良城には城代倉見金太夫、家老各務久左衛門、中老潮田由膳らが岡部長備を作法通りに迎えたのです。
田沼家家臣たちのほとんどは浪人することになるのです。
本来ならば、収城使が無事に入城した段階で相良城は幕府の公的資産になるのですが、松平定信は相良城の破城を命じます。
現代で言うならば、個人的感情で公費を使って省庁の建物を勝手に壊す愚行です(定信に関して、個人的に悪い感情を持ってますが、これは事実なので…)
相良城接収から年を越して、天明8年1月16日、相良城破城が始まります。
相良城は、天守は築かれませんでしたが天守に替わる三重櫓が建っていました。この櫓はとても堅固で解体に苦労したようです。
同月25日本丸御殿破却、29日城内の建物は撤去、2月5日には全ての作業が終わったのです。
そして、2月22日に資材などが競売にかけられました。
これらの資材は今も見ることができます。
◯牧之原市内
・大澤寺
本堂が転用資材



礎石





田沼街道沿いの石垣が転用資材


杉戸

陣太鼓




他にも相良城の資材は転用されているとも聞いています。
相良城だった場所は田畑として開墾されることになりましたが、破城の4年後に城址を訪れた小林一茶が
石運び なげき照りつむ しめし野の
人のあぶらに 光る城かな
と詠んでいるため、この段階でまだ石垣の石が運ばれていることもわかるのですが、小林一茶が俳句ではなく和歌なの?と少し気にはなっている逸話でもあります。