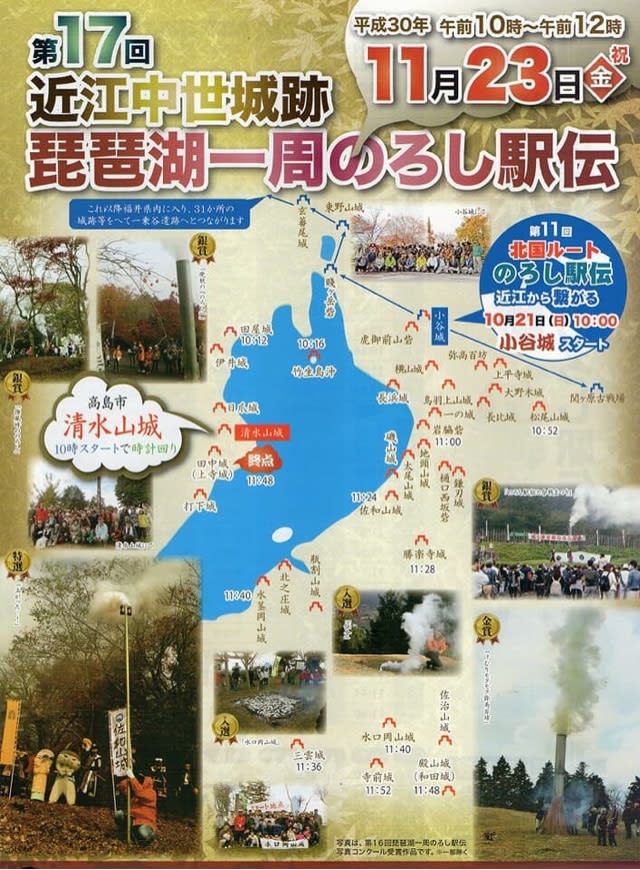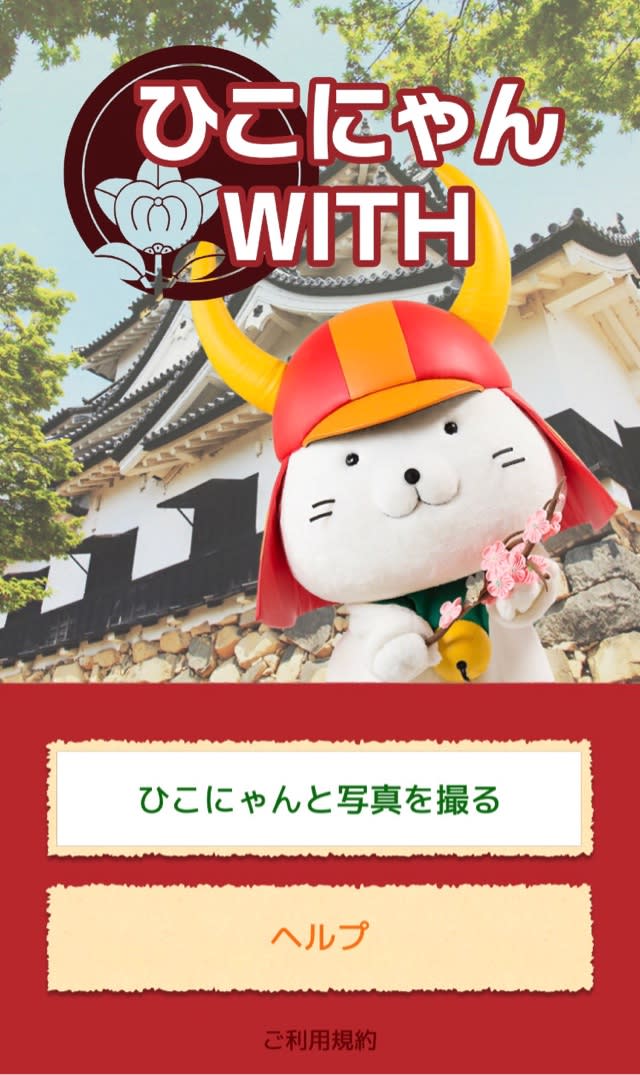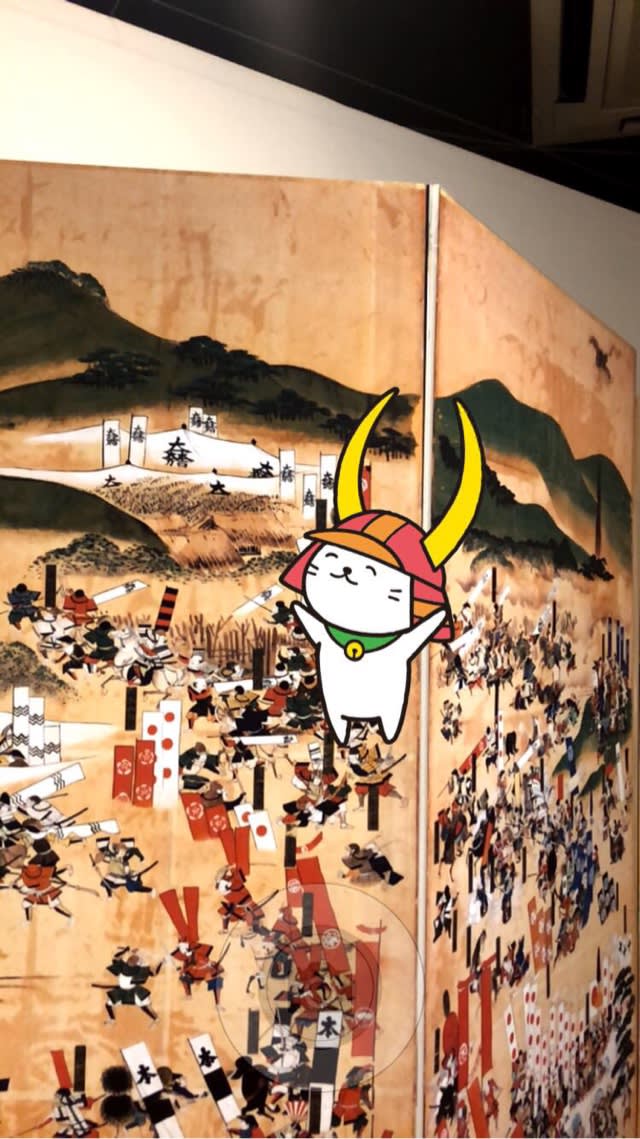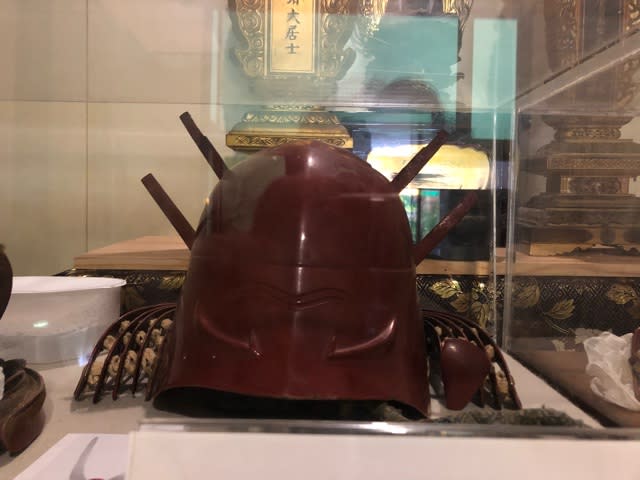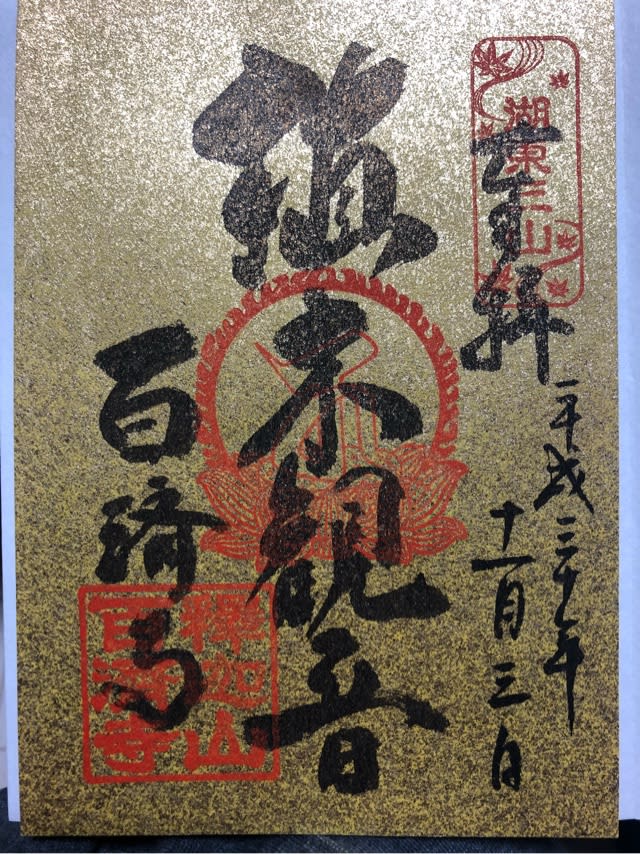もう何年も前の話。
安土の沙沙貴神社に参拝に行き、本殿に向かって左にある少名彦社に願かけ石という物がありました。
周りからもせっつかれ、婚活などというものをやるような宣言もしていたこともあり、出逢いの願かけをして石を持ち帰りました。

この願かけ石は満願成就の時に返しにこないといけないため、わかる所に置いていたはずですが意識の片隅にありながらも返すチャンスもなくそのままになって、何年も過ぎました。
昨日、偶然沙沙貴神社が話題になり、その後の出来事からこのまま持っていて願いがまだあると神様に誤解されたら困るので、返しに行きました。


本殿にお参りし、少名彦社の奥の大きな石の前に持っていた石をお返ししました。


「ここからは、自分の努力次第」
そんな想いも新たに湧く、自分だけの神事となりました。
沙沙貴神社さん、少名彦社さん、長い間大切な石をお借りしてありがとうございます。
安土の沙沙貴神社に参拝に行き、本殿に向かって左にある少名彦社に願かけ石という物がありました。
周りからもせっつかれ、婚活などというものをやるような宣言もしていたこともあり、出逢いの願かけをして石を持ち帰りました。

この願かけ石は満願成就の時に返しにこないといけないため、わかる所に置いていたはずですが意識の片隅にありながらも返すチャンスもなくそのままになって、何年も過ぎました。
昨日、偶然沙沙貴神社が話題になり、その後の出来事からこのまま持っていて願いがまだあると神様に誤解されたら困るので、返しに行きました。


本殿にお参りし、少名彦社の奥の大きな石の前に持っていた石をお返ししました。


「ここからは、自分の努力次第」
そんな想いも新たに湧く、自分だけの神事となりました。
沙沙貴神社さん、少名彦社さん、長い間大切な石をお借りしてありがとうございます。