
蔦屋重三郎の人生において特に明るい時期とも言えるのが田沼時代であり、この後の寛政の改革では幕府と反発することとなる。江戸の町人である蔦重ですら人生が大きく変わってしまうほど歴史的転換期とも言える出来事が田沼意次の失脚である。今稿ではその流れを紹介したい。
天明4年(1784)意次の嫡男で若年寄を務めいていた田沼意知が江戸城内で刃傷され亡くなる。すでに66歳という年齢で世代交代も念頭においていた意次にとっては優秀な補佐でもあった意知の死で受けたショックはどれ程のものであっただろうか? しかし政治を停滞させる訳には行かず意知横死から約半年後に井伊直幸を大老とする。大老は幕府に重大な問題が起こったときに一時的に設置される幕閣の最高職であり直幸の祖父・直該(直興)以来約70年ぶりの就任であったが、この時期には幕政に目立った重要案件は認められず、井伊家が意次の閨閥に含まれていたこと、そして井伊直幸自身が大老職就任を望んでいて大老就任後に、九尺(訳2.27m)四方の島台に一棟の小屋を作り屋根は金で吹き、壁や戸も金銀で飾る、庭は豆銀を巻き、小動物も金銀で作った秋の山家の情景を模した物を贈っている(『徳川太平記』)。これにより井伊直幸は大老能力もないのに賄賂で身分を買った田沼意次に利用された大老とも評価されている。
これらの悪評を受けながらも、蝦夷地探索や、幕府が固定資産税を徴収してその資金から低金利の公的ローンを運営する『貸金会所令』などを進めて行く。この頃の田沼政策は着想が早すぎて技術的にも周囲の理解も追い付かなかった。また浅間山噴火による自然災害の積み重ねから印旛沼での開拓事業の失敗が追い打ちをかけた、これに対し意次が鋳造した寛永通宝の裏が波模様であったことが悪いとの言いがかりまで流布された。また、井伊直幸が大老に就任した一年後に反田沼派の急先鋒である松平定信が老中の諮問機関である溜間詰に任ぜられ幕府内に歪ができる。
天明6年は丙午の年で元日も丙午から始まったため不吉な年との噂が広まっていたが8月になり将軍徳川家治が発病。25日に家治が亡くなるがその死は隠蔽され二日後に公文書偽造が行われ意次は老中を罷免され雁間詰め(閑職)を命ぜられる。しかし幕閣には直幸ら田沼派の実力者が残っていたために一気に反田沼派が政権を握ることはなかった。これは政権を巡る政治家同士の戦いであり政治の空白期間が起こる要因となった。天明の大飢饉による市場不安が落ち着かないままで政治的空白期間が生まれるとしわ寄せは民衆に向かい、米を始めとする物価の急上昇が起こり大坂で豪商や米問屋を狙った打ちこわしが勃発。東海道を伝播して江戸でも打ちこわしが起こり田沼派の重鎮たちが責任を負わされ失脚。その後、意次・直幸や田沼派の関係者たちが相次いで急死し田沼時代は多くの史料と共に歴史の闇に堕とされたのだ。
田沼時代に鋳造された寛永通宝(波銭)著者蔵

















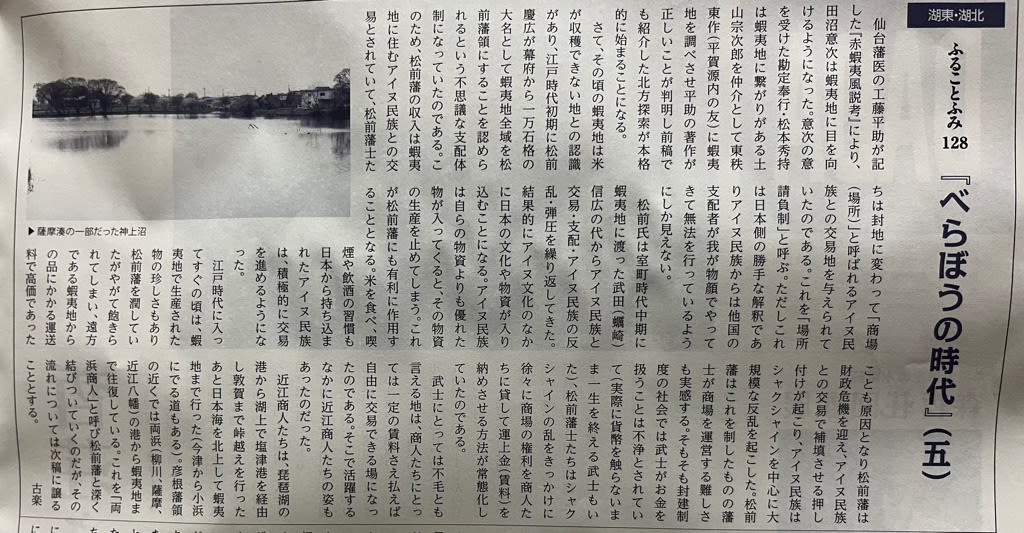





 2025年大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』の主人公は蔦屋重三郎である。この名前を聞いてどんな人物であるのかをすぐに答えられる方は少ないのではないだろうか? しかし名前は知らなくても彼が日本史に残したものは私たちの記憶に刻みつけられている。それは私たちが想像する江戸文化にぴったり符号するからである。
蔦屋重三郎をひと言で表すならば版元。江戸時代の出版社であるが、当時の版元は文化人の発掘からプロデュース、印刷、販売の全てを行なっていた。重三郎も「耕書堂」という屋号でこの全てを行なっており、重三郎が育てた文化人は浮世絵師では喜多川歌麿・東洲斎写楽・葛飾北斎など、作家では山東京伝・十返舎一九・曲亭馬琴などが挙げられる。この名前を見るだけでもその活躍が描かれるドラマには期待が膨らむのではないだろうか。
これほどの前置きを書きながら、湖東湖北の歴史をメインに紹介している本稿では直接蔦屋重三郎に関わることができない。窮余の策として重三郎が活躍した「田沼時代」から「寛政の改革」の頃を記して行きたいと考えている。身勝手な発言であるが、私(古楽)が長年興味を持ち続けた分野が田沼時代であるため話が飛躍してしまう可能性が否めないのはお許しいただきたい。
さて、歴史上でも珍しい個人名に「時代」が付く「田沼時代」とはどのように考えれば良いのであろうか? 簡単に言えば「田沼意次が実権を握っていた時代」となるが意次自身は江戸幕府の組織に組み込まれた老中のひとりであり、しかも老中首座に登ってはいない。つまり独裁者として幕府を動かしたのではないのだ。では田沼意次はどのようにして幕政を動かしていたのかと言えば、将軍の信頼と有力大名との閨閥関係の構築である。
前者について、意次の父・田沼意行が下級藩士でありながら徳川吉宗に認められ吉宗が紀州藩主から江戸幕府八代将軍へと立場を変えたときに紀州藩から連れて行った家臣であり、のちに吉宗自ら意次を九代将軍となる家重の小姓に抜擢した。意次自身も家重によく仕え家重が亡くなるときに十代将軍家治に対して「主殿(主殿頭・意次の官位)は、またうどの者(全との人・有能な者の意)なり、行々こころを添えて召仕はるべし」と遺言したとの逸話が残っている。家治はこの遺言を守り、意次を重用し続け老中職を任せることになったのだ。
後者について、身分の低い家から立身出世を遂げた者に周囲が冷たいため、意次は自分の子ども達を有力大名と縁付かせてゆく。嫡男田沼意知の正室は田沼時代を通して老中首座であった松平康福の娘を迎えている。また他の息子たちも大名家へ養子に出した。そして意次の次女(宝池院)は与板藩主井伊直朗に嫁ぎ、直朗は彦根藩主井伊直幸の八男・直広を婿養子に迎えていたため、田沼意次と井伊家にも閨閥として繋がりが出来ていたのだ。
2025年大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』の主人公は蔦屋重三郎である。この名前を聞いてどんな人物であるのかをすぐに答えられる方は少ないのではないだろうか? しかし名前は知らなくても彼が日本史に残したものは私たちの記憶に刻みつけられている。それは私たちが想像する江戸文化にぴったり符号するからである。
蔦屋重三郎をひと言で表すならば版元。江戸時代の出版社であるが、当時の版元は文化人の発掘からプロデュース、印刷、販売の全てを行なっていた。重三郎も「耕書堂」という屋号でこの全てを行なっており、重三郎が育てた文化人は浮世絵師では喜多川歌麿・東洲斎写楽・葛飾北斎など、作家では山東京伝・十返舎一九・曲亭馬琴などが挙げられる。この名前を見るだけでもその活躍が描かれるドラマには期待が膨らむのではないだろうか。
これほどの前置きを書きながら、湖東湖北の歴史をメインに紹介している本稿では直接蔦屋重三郎に関わることができない。窮余の策として重三郎が活躍した「田沼時代」から「寛政の改革」の頃を記して行きたいと考えている。身勝手な発言であるが、私(古楽)が長年興味を持ち続けた分野が田沼時代であるため話が飛躍してしまう可能性が否めないのはお許しいただきたい。
さて、歴史上でも珍しい個人名に「時代」が付く「田沼時代」とはどのように考えれば良いのであろうか? 簡単に言えば「田沼意次が実権を握っていた時代」となるが意次自身は江戸幕府の組織に組み込まれた老中のひとりであり、しかも老中首座に登ってはいない。つまり独裁者として幕府を動かしたのではないのだ。では田沼意次はどのようにして幕政を動かしていたのかと言えば、将軍の信頼と有力大名との閨閥関係の構築である。
前者について、意次の父・田沼意行が下級藩士でありながら徳川吉宗に認められ吉宗が紀州藩主から江戸幕府八代将軍へと立場を変えたときに紀州藩から連れて行った家臣であり、のちに吉宗自ら意次を九代将軍となる家重の小姓に抜擢した。意次自身も家重によく仕え家重が亡くなるときに十代将軍家治に対して「主殿(主殿頭・意次の官位)は、またうどの者(全との人・有能な者の意)なり、行々こころを添えて召仕はるべし」と遺言したとの逸話が残っている。家治はこの遺言を守り、意次を重用し続け老中職を任せることになったのだ。
後者について、身分の低い家から立身出世を遂げた者に周囲が冷たいため、意次は自分の子ども達を有力大名と縁付かせてゆく。嫡男田沼意知の正室は田沼時代を通して老中首座であった松平康福の娘を迎えている。また他の息子たちも大名家へ養子に出した。そして意次の次女(宝池院)は与板藩主井伊直朗に嫁ぎ、直朗は彦根藩主井伊直幸の八男・直広を婿養子に迎えていたため、田沼意次と井伊家にも閨閥として繋がりが出来ていたのだ。









