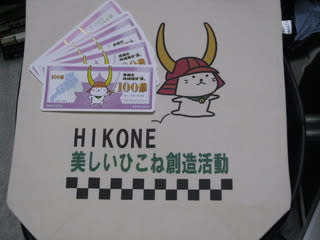萬延元年(1860)4月28日、月番老中の安藤信正の役宅に井伊愛麿(直憲)が召し出されました。
彦根藩は、愛麿の名代として南部丹波守が安藤邸に行き、愛麿の家督相続許可の達しを受けました。同時に愛麿は彦根藩主として直弼の遺領30万石(これに預かり5万石で35万石)を受いだのです。
(南部丹波守は、七戸藩主南部信誉の事だと考えられるのですが、なぜこの時に井伊家の名代になったのかが、管理人の調査不足で分かりません)
幕府からの文書には
『其方え遺領被下候頃合之義、先格の振合も有之候處掃部頭勤役中、格別精勤致し、其上先般御内沙汰之趣、厚相心得、家来末々迄、心得違之義無之、聊も御苦労相掛ざる段、於愛麿も、教諭方行届候故之義と被思召、家柄之義、旁出格之譯を以、遺領速に被仰出候事に候条、被得其意、京都守護之義をも、厚被相心得在所表手當方之儀、此上猶更手厚に致し、非常之節、手抜無之様、彌厳重に被申付幾久敷可被相勤候』(『櫻田義擧録』より転記)
とあります。
これらの文章は、ほぼ雛型通りに書かれる物なのですが、彦根藩への遺領相続通達の中に“京都守護之義”との文言があり、これは初めて書かれたもので、直弼が京都守護を公言しそれを幕府も認めた形が観てとれます。
この日より、井伊直憲は13歳にして彦根藩35万石と京都守護の責任を双肩に負う立場となったのです。
彦根藩は、愛麿の名代として南部丹波守が安藤邸に行き、愛麿の家督相続許可の達しを受けました。同時に愛麿は彦根藩主として直弼の遺領30万石(これに預かり5万石で35万石)を受いだのです。
(南部丹波守は、七戸藩主南部信誉の事だと考えられるのですが、なぜこの時に井伊家の名代になったのかが、管理人の調査不足で分かりません)
幕府からの文書には
『其方え遺領被下候頃合之義、先格の振合も有之候處掃部頭勤役中、格別精勤致し、其上先般御内沙汰之趣、厚相心得、家来末々迄、心得違之義無之、聊も御苦労相掛ざる段、於愛麿も、教諭方行届候故之義と被思召、家柄之義、旁出格之譯を以、遺領速に被仰出候事に候条、被得其意、京都守護之義をも、厚被相心得在所表手當方之儀、此上猶更手厚に致し、非常之節、手抜無之様、彌厳重に被申付幾久敷可被相勤候』(『櫻田義擧録』より転記)
とあります。
これらの文章は、ほぼ雛型通りに書かれる物なのですが、彦根藩への遺領相続通達の中に“京都守護之義”との文言があり、これは初めて書かれたもので、直弼が京都守護を公言しそれを幕府も認めた形が観てとれます。
この日より、井伊直憲は13歳にして彦根藩35万石と京都守護の責任を双肩に負う立場となったのです。