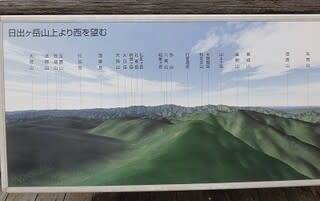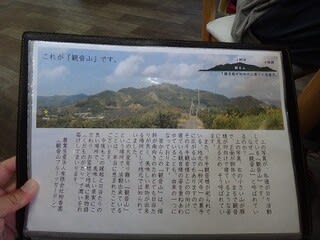え~、すこし小ネタを書いておきましょう。
たいした小ネタでもないのですが、
最近我が家で起こった
しょうもない出来事の紹介です。
歩き旅ブログがつづくので、
ちょっと気分直しです。
でも読んでね。
まず第1話です。
先日、敬老の日を前にしたときのことです。
こんなことがありました。
doironは地元町会の
老人会に入っています。
とはいえ高齢者たちと集まって
何かをしようとかいう意図は
あまりありません。
忘年会とかで、町会の年より連中と
お付き合い程度だと思っています。
でも気の合った同世代近辺の仲間とは、
麻雀したり、焼肉したりで
遊んではいるんですがね。
先日、老人会の役割も
打診されたんですが、
これはもう断りましたねえ。
もうそんなに高齢者たちを
まとめるなんてできないし、
そもそもこれ以上の役割を
もつということ自体が
かなり無謀なことです。
あいつに頼んだら何でもしてくれるぞ、
なんてこれ以上思われてはなりません。
そんな呼びかけが車の運転中に
あったのですが、
これはもうあわてて
サービスエリアに入って、
丁寧にお断りしました。
というような経過もあって、
老人会の活動そのものは
薄―く取り組んでいるのですが、
先日の敬老の日を前に
家に帰るとカステラが
届いていました。
老人会の取り組みとして
配っているようです。
カステラねえ~といって
不満そうにしていたら、
ミセスがカステラが好きで
喜んでいましたねえ。
母親と二人でよくカステラを
買って食べていたんやと
聞いて驚きです。
老人会の会長さん、
来年はこんなカステラなんかも
ありますよとか
教えてあげようかなあ。
いやいやそんな余計なことを
言ってはいけませんね。
「そしたら今度計画してよ」
なんて絶対言われそうやもんね。
カステラありがとうございましたと、
今度会ったら言って
おくことにしましょう。
次の話題です。
いまは買い物に行くのも、
持ち物が大変ですね。
先日スーパーに出かけるときです。
車に乗ったら、
「ああマスク持って行かないとねえ」
と慌てて取りに戻ります。
マスクを口にして、
さあでは出かけるかと
エンジンをかけたときに
「ああ、ビニール袋を持って行かなくちゃ」
とまたまたあわてて取りに行きます。
よしよしこれでOKだと
ようやく出発です。
車をとめて買い物して、
買い物袋を持って
支払いだと思ったところで、
なんと財布を持ってくるのを
忘れていました。
慌てて何とか携帯で支払いを
すますことができてよかったです。
こんな話を、ともだちからも
聞きましたねえ。
忘れてはならないもの。
マスク、フクロ、携帯、財布、
車のカギと一回買い物に行くだけでも、
気の抜けない昨今です。
そして最後の話題です。
まもなくdoironは
GOTOトラベルで、
広島旅行に行く予定です。
駅前ビジネスの宿泊費がなんと
一人1000円台という超安さ。
原爆関連の施設やもしかしたら
親戚かもしれない反戦者が
なくなった広島刑務所、
ジダンが教えてくれた
お好み焼きのお店と、
ウサギが大量にいるという
大久野島に行く予定です。
まあこういうキャンペーンは
しっかりと利用させてもらいましょ。
そして近々国のサービスで
GOTOイートとか始まりますよねえ。
ん?もう始まっているのかな?
よくわかりませんが。
そんなキャンペーンの話が
テレビで話題になったりしています。
GOTOキャンペーンで
旅行に行って、このキャンペーンで
黒毛和牛のステーキ食べて
とか楽しそうに紹介してますねえ。
「これっていいよなあ。
僕らも黒毛和牛を食べに行こかあ」
とミセスにいったら、
「なんぼキャンペーンでも
贅沢言ったらあかんで。
黒毛和牛なんか食べに行かんと、
お家で薄毛和牛でも食べとき」
だって。
そ、そんな牛っているんですか
と思わず聞いてしまった
doironだったのでした。
以上、小ネタ3話でした。おしまい