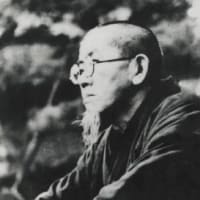このところずっと、習字のお手本として、芭蕉さんの「奥の細道」を毛筆で書いたものを横に置いて練習している。何度も何度も繰り返し同じところを読むし、旧仮名遣いだし、毛筆で書いているお手本が活字ではなく行書だったり草書だったりするので、昔の人が書いたものを読んでいるのに近い。「月日は百代の過客にして、行き交う人も又旅人也」という一文だけでも数十回は繰り返し書いているのである。
で、疲れたらテオを連れて長い散歩に出る。日差しが強いので、日向を歩くと汗ばむほど暑い。真っ黒いテオはゼエゼエ舌を出しているが、それでも早く散歩に行こうと誘ってくる。家の中より外の方が100倍も楽しいのだろう。


ぼんやり歩いていると、いろんなことが頭に浮かんでくる。考えなくてもいいことも結構考えたりして、習字に疲れた頭にとっては気分転換になる。
昨日は歩きながら、ずっと読み書きについて考えていた。というのも1週間ほど前のニュース記事で、日本人は世界的に識字率が高いと言われていたが、なぜそんな神話が生まれたのかという話を読んだからだ。

江戸の終わりには寺子屋が盛んだった。それが明治になりそのまま小学校になった。だから日本の子供はそれなりに読み書きができた、というのが昔から言われていることだが、その根拠になっている調査が、1948年に16,820名を対象に実施された「日本人の読み書き能力調査」というもので、完全文盲は2%弱だったという結果だったからだ。
が、最近の調査では、しっかり読み書きできるということと、本当はちゃんと読めていないし書けていないのだが本人は読み書きできていると思っている、いわゆる読み書きの格差が指摘されている。どういうことかというと、同じ本を読んでも深く理解できる人とできない人、自分の考えを書くことができる人とできない人がいるということである。


「つれづれなるままにひぐらし すずりにむかひてこころにうつりゆくよしなしごとを、そこはかとなくかきつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ」
これは有名な吉田兼好の「徒然草」の書き出しだが、小学一年生に読ませても、間違わずに読むことができるだろう。が、読むというのは本当はそういうことではないのである。読むというのは、当然のことながらそれを書いた人の思いを汲み取るということでもある。
同じように、字が書けるからと言って、自分の思いをきちんと文章に表せるというのは別次元のことだ。
ところが、多くの人は「私は読み書きができる」と単純に思い込んでいる。だから「読むのは得意だが文章を書くのは苦手」とか「読むのは苦手だけど書くのは好き」というふうなことを言う。読むことと書くことには、同じ知識と技術と工夫がいることには考えが及ばない。
「読み書き」の大変さを、習字を始めると嫌と言うほど思い知る。読めない書けない、これが自分の実力だと毎日痛感する。
で、疲れたらテオを連れて長い散歩に出る。日差しが強いので、日向を歩くと汗ばむほど暑い。真っ黒いテオはゼエゼエ舌を出しているが、それでも早く散歩に行こうと誘ってくる。家の中より外の方が100倍も楽しいのだろう。


ぼんやり歩いていると、いろんなことが頭に浮かんでくる。考えなくてもいいことも結構考えたりして、習字に疲れた頭にとっては気分転換になる。
昨日は歩きながら、ずっと読み書きについて考えていた。というのも1週間ほど前のニュース記事で、日本人は世界的に識字率が高いと言われていたが、なぜそんな神話が生まれたのかという話を読んだからだ。

江戸の終わりには寺子屋が盛んだった。それが明治になりそのまま小学校になった。だから日本の子供はそれなりに読み書きができた、というのが昔から言われていることだが、その根拠になっている調査が、1948年に16,820名を対象に実施された「日本人の読み書き能力調査」というもので、完全文盲は2%弱だったという結果だったからだ。
が、最近の調査では、しっかり読み書きできるということと、本当はちゃんと読めていないし書けていないのだが本人は読み書きできていると思っている、いわゆる読み書きの格差が指摘されている。どういうことかというと、同じ本を読んでも深く理解できる人とできない人、自分の考えを書くことができる人とできない人がいるということである。


「つれづれなるままにひぐらし すずりにむかひてこころにうつりゆくよしなしごとを、そこはかとなくかきつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ」
これは有名な吉田兼好の「徒然草」の書き出しだが、小学一年生に読ませても、間違わずに読むことができるだろう。が、読むというのは本当はそういうことではないのである。読むというのは、当然のことながらそれを書いた人の思いを汲み取るということでもある。
同じように、字が書けるからと言って、自分の思いをきちんと文章に表せるというのは別次元のことだ。
ところが、多くの人は「私は読み書きができる」と単純に思い込んでいる。だから「読むのは得意だが文章を書くのは苦手」とか「読むのは苦手だけど書くのは好き」というふうなことを言う。読むことと書くことには、同じ知識と技術と工夫がいることには考えが及ばない。
「読み書き」の大変さを、習字を始めると嫌と言うほど思い知る。読めない書けない、これが自分の実力だと毎日痛感する。