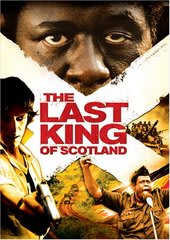THE QUEEN
2006年/英・仏・イタリア/104分
監督 スティーヴン・フリアーズ
脚本 ピーター・モーガン
出演 ヘレン・ミレン/エリザベス女王 マイケル・シーン/トニー・ブレア ジェームズ・クロムウェル/フィリップ殿下 シルヴィア・シムズ/クィーン・マザー(皇太后) アレックス・ジェニングス/チャールズ皇太子
................................. . . . 本文を読む
THE LAST KING OF SCOTLAND
2006年/米国・英国/125分
監督 ケヴィン・マクドナルド
原作 ジャイルズ・フォーデン 『スコットランドの黒い王様』(新潮社刊)
脚本 ジェレミー・ブロック ピーター・モーガン
撮影 アンソニー・ドッド・マントル
出演 フォレスト・ウィッテカー/イディ・アミン ジェームズ・マカヴォイ/ニコラス・ギャリガン ケリー・ワシントン . . . 本文を読む
THE PASSION OF THE CHRIST
2004年/米・イタリア/127分
監督: メル・ギブソン
製作: メル・ギブソン
脚本: メル・ギブソン ベネディクト・フィッツジェラルド
撮影: キャレブ・デシャネル
音楽: ジョン・デブニー
出演:ジム・カヴィーゼル/イエス・キリスト マヤ・モルゲンステルン/イエスの母マリア
モニカ・ベルッチ/マグダラのマリア . . . 本文を読む
「ウェールズの山」(1995年/英/99分)
THE ENGLISHMAN WHO WENT UP A HILL BUT CAME DOWN A MOUNTAIN
【監督】 クリストファー・マンガー
【製作】 サラ・カーティス
【脚本】 クリストファー・マンガー
【撮影】 ヴァーノン・レイトン
【音楽】 スティーヴン・エンデルマン
【出演】 ヒュー・グラント/アンソン タラ・フ . . . 本文を読む
シネマディクト10周年記念企画。3時間23分という長尺ものは久しぶり。疲れました…。
あの有名な、ワグナーの「ワルキューレの騎行」に乗せてヘリコプターが海岸の村を襲撃するシーンは、やはりスクリーンでこその迫力ですね。鳥肌が立ちます。本当は鳥肌なんて立ってはいけないのだろうけれど、あの高揚感を抑えることはできない。
ただ、その鳥肌も、空中のヘリコプターからの視点で見ているときだけ。カメラの視線が . . . 本文を読む
映画の舞台は西アフリカのシエラレオネ。15世紀にポルトガル人が来航し、ポルトガル語で「ライオンの山」を意味するシエラレオネと呼ばれるようになります。その後、英国人が植民地化し、解放奴隷の移住による国家建設が進みました。1961年の独立後も、クリオと呼ばれる彼らの子孫がこの国のエリート層を形成しています。数度のクーデタを経て確立された一党独裁体制に対して、1990年代からRUF(革命統一戦線)が抵抗 . . . 本文を読む
2000年秋、東京・上野の国立科学博物館で「ダイヤモンド展」が開催されました。そのころ東京で勤務していた私は、毎日「科博」の裏側の通りを自転車で通っていたのですが、ちょっとミーハー的な感覚で「ダイヤモンド展」にも立ち寄ったものでした。
科博の企画展ですから、もちろん「ダイヤモンド」という鉱物への科学的なアプローチの展示もあったのですが、ほとんどの来館者は、総計5000カラットにも及ぶ世界有数のダ . . . 本文を読む
アイルランドを舞台とする映画といえば、独立運動の英雄の生涯を描いた「マイケル・コリンズ」を思い出します。それと全く同時期のアイルランドを舞台としながらも、より「民衆」側にアプローチしたのがこの映画です。 原題は"THE WIND THAT SHAKES THE BARLEY"。邦題はそれをそのまま訳したものですが、これはアイルランドの「レベル・ソングrebel song」の一つです。レベル・ソン . . . 本文を読む
旧ドイツ民主共和国(東ドイツ)が物語の舞台です。この国の社会主義体制が崩壊、つまり東西ドイツの統一(1990年)から16年かけて、ようやくその体制の裏側が描かれることになりました。一言で言えば、東ドイツという国がいかに異常な「監視国家」であったかということです。
東ドイツを描いた映画といえば、私の好きな映画の一つでもある「グッバイ、レーニン!」があります。「善き人のためのソナタ」の脚本・監督であ . . . 本文を読む
「墨攻」の原作は、森秀樹作画、脚本久保千太郎による同名漫画。その漫画にはさらに原作があって、酒見賢一の同名小説です。私はどれも未読ですが、映画を見て読んでみたくなりましたね。映画では原作にないキャラクターも登場しているらしいですが…。
この映画、中国・日本・香港・韓国の合作です。主なスタッフの関わりを整理してみると、
■中国…製作のホアン・チェンシン、梁王役のワン・チーウェン、逸悦(いつえつ) . . . 本文を読む
歴史の中でもっとも面白いのは、ある国家が安定した政権を保っている時よりも、むしろ分裂、群雄割拠の時代だとよく言われます。日本史で言えば戦国時代、ヨーロッパ史では近代前半、中国史では、春秋戦国時代・三国時代…。そんな「激動の時代」が面白いのは、いろいろなタイプの「人間」が覇を競っていたからにほかなりません。
中国の春秋戦国時代とは、紀元前770年から紀元前221年までの約550年間の動乱の時代を指 . . . 本文を読む
■内戦勃発、そして1994年。
独立後もフツvsツチの抗争は続きました。少数派のツチは、ブルンジやウガンダに逃げ込み、大量の難民を生みました。1973年、フツ族のハビャリマナ国防相が無血クーデタに成功、大統領に就任します。彼は一党独裁体制を敷き、ツチ族に対する圧政を行いました。これに対して、国外に亡命していたツチ族を中心として結成されたルワンダ愛国戦線(RPF)が、ウガンダからルワンダ国内に侵攻 . . . 本文を読む
■ルワンダとは?
ルワンダ共和国Republic of Rwandaは、アフリカのほぼ中央部、西隣がコンゴ、北隣はウガンダと、民族対立やら内戦やらで長く紛争が続いた、きな臭い一帯のど真ん中に位置しています。ルワンダとは、「大きな国」という意味らしい。面積は北海道の約3分の1、人口は約900万人です。「ルムンバの叫び」という映画は、コンゴの内戦を描いたものですが、そちらでもルワンダの内戦のことが少 . . . 本文を読む
32歳という若さで死んでしまったことで、彼の生涯のほとんどは戦いに費やされることになりました。彼の軍事的才能は遺憾なく発揮されました。彼は司令官でありながら、常に自ら先頭に立って戦いました。命の危険にさらされたのも一度や二度ではありません。しかし、そうやって征服した領土を実際に統治していくことは彼にはできませんでした。彼の政治的才能は未知数のままなのです。彼はいったいどんな「統治」をしたかったので . . . 本文を読む
「アレキサンダー」
こういう歴史映画が公開されるたび、なんで「今」?と思います。なんで今、アレキサンダー大王なのか? この映画の公開は2005年ですが、紀元前4世紀、今から2,300年も前の人物がなぜ今取り上げられるのか?しかもメガホン取ったのはご存じ「社会派」のオリバー・ストーン。アレキサンダーの「征服戦争」を米国のイラク戦争と重ね合わせる人も多いようですが、どうなんでしょう? ちょっと意味合 . . . 本文を読む