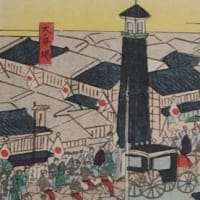21 藤沢
314 藤沢地区の火の見櫓と消防庫のツーショット
22 古町
315
古町の火の見櫓も消防庫を跨ぐというこの町のオーソドックスな型(タイプ)だ。
両足をできるだけ外側に向けてひざを曲げ、この火の見櫓のような立ち方をしてみると、外側にひざが突き出て尻が下にさがりやすいことが容易にわかる。ひざを曲げないで立っている場合とは全く違って、キツイ。
実際、この火の見櫓の脚部の折れ曲がっているところ、即ちひざに相当するところには、櫓の荷重(自重)を受けて外側に開こうとする力がはたらく。それで下の写真のように、スラブを貫通させることで、その力に抵抗させているのだ。
わざわざ脚をスラブに貫通させているのは(いや、施工順序からすれば、脚が貫通するようにスラブをつくっているのはと書くべきだろう)このような理由による。

23 東塩沢
316


24 西塩沢
317

25
318
背の低い火の見櫓。見張り台は踊り場と同じつくり方で櫓の外に飛び出している。

梯子の下端を接地させないのはこの町の標準仕様のようだが、一体何故だろう・・・。
26 芦田(たぶん)
319
前回もこのタイプの火の見櫓を見た。このフォルムには何故か惹かれる。マッキントッシュの椅子のデザインにどこか通じるような気がするなあ。