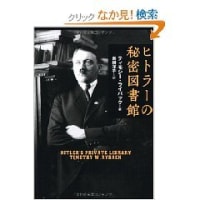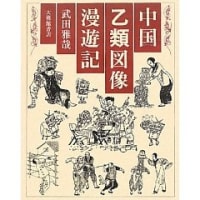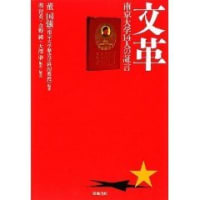戦国時代は信仰の時代だったという。本書は、日々、不安定な激動の生活の中で神仏にすがる人々信仰の諸相を具体的に描いて目から鱗の指摘が多々あった。第一章は川中島の合戦における甲斐の武田信玄と信濃の上杉謙信のそれぞれの側の戦勝祈願の実態について述べている。例えば、川中島の合戦は五回行なわれているが、三回目の弘治三年(1557)の出陣前の一月、上杉謙信は八幡社の宝前(神仏の前)に願文を捧げ、武田信玄が信濃の国で行った悪事の数々を並べ立て、出陣がいかに正当であるかを縷々述べて戦の正当性を力説している。信玄のような者がいかに神仏を崇拝したとしても、国を奪い、諸家、万民を悩ませた者の願いを神仏が叶えるはずがないと断言し、勝利の暁には土地を寄進することを約束している。八幡神は戦の神であるから、謙信の戦勝祈願は切実なものだったと言える。一方、信玄の方も同様の祈願をしており、戦闘に際しては常に大名の手で戦勝祈願が行なわれたと著者は断言している。
また戦場では、死を覚悟した武士たちが、しばしば「南無阿弥陀仏」の文字を記した阿弥陀如来の名号や「南無法蓮華経」の「法華の題目」を身につけて、戦死の際に仏に守られて成仏を期するために携行されるのが本来の趣旨であったが、「矢よけの名号」として加護を祈るためのお守りでもあったようだ。
こうした中で鎌倉新仏教の中の浄土真宗はその教義の分かりやすさもあって、急速に庶民の間に普及していったが、「一向一揆」の主体となった本願寺教団の実態について、その「反権力性」は本当かどうかについて議論したのが第二章である。本願寺門徒の権力者への抵抗と言えば、織田信長と抗争した石山合戦が有名だが、真宗内部では、本願寺派が信長と対立していたが、親鸞の教義を継承する真宗高田派と三門徒派は信長に味方して戦っているから、真宗が「反権力」とは言えないと著者は言う。また、「一向一揆」という言葉は江戸時代の資料にはじめて現れる言葉で、戦国・近世初頭では本願寺門徒の一揆を「一揆」「土一揆」と呼ぶのが、一般的であった。「一向宗」とは念仏の呪力を能くする山伏や陰陽師が広めたもので、それが越前国吉崎に参集して、そこで伝道していた本願寺蓮如のもとに集まって信者になったもので、彼らは自分たちの宗旨を「一向宗」であると思っていた。
以上、信長対一向一揆という構図は近世の軍記物に引っ張られた論で、信長に最初から本願寺撲滅の意図があったとは断定できないという。私もそう簡単なものではないと思う。
また、第三章と第四章はキリスト教の伝来について、書かれているが、基本的にキリスト教が仏教と似ているところがあり、受け入れが比較的容易だったとある。またイエズス会の宣教師たちは宣教に当たって仏教の排斥を主眼として、墓の破壊など他の宗教に対する非寛容性があったため、秀吉の伴天連追放令に繋がった。宣教師は基本的に帝国主義の尖兵であったという事実を改めて教えてくれる。そして最後に戦国時代に人々が「天道」という観念になじんでいたと言う。1603年刊行の『日葡辞書』では、「天の道、または(天の)秩序と摂理。以前は、この語で我々はデウスを呼ぶのが普通であった。けれども(その時にも)異教徒は(上記の)第一の意味以上に思い至っていたとは思われない」とあり、イエズス会やキリシタンがデウスを「天道」と呼んでいたことがわかる。著者は、「天道」ついて、「人間の運命をうむをいわさず決定する摂理」で「仏神と等値」。「目上を敬い目下を慈しめ、正直であれ、など世俗道徳の実践を促す」「祈祷など外面の行為よりも内面の倫理こそ大切とする点」とまとめている。その「天道」を実践すべく、人々はいろいろの宗教に帰依していったのである。
「天道」で有名なのが、司馬遷の「天道是耶、非耶」「(善を行なって禍を得、悪を行なって福を得ることがある)天道は果たして正しいのか正しくないのか」(史記 伯夷伝)だが、これは上記の神仏と同義だが、戦国人は『史記』を読んでいたのだろうか。
また戦場では、死を覚悟した武士たちが、しばしば「南無阿弥陀仏」の文字を記した阿弥陀如来の名号や「南無法蓮華経」の「法華の題目」を身につけて、戦死の際に仏に守られて成仏を期するために携行されるのが本来の趣旨であったが、「矢よけの名号」として加護を祈るためのお守りでもあったようだ。
こうした中で鎌倉新仏教の中の浄土真宗はその教義の分かりやすさもあって、急速に庶民の間に普及していったが、「一向一揆」の主体となった本願寺教団の実態について、その「反権力性」は本当かどうかについて議論したのが第二章である。本願寺門徒の権力者への抵抗と言えば、織田信長と抗争した石山合戦が有名だが、真宗内部では、本願寺派が信長と対立していたが、親鸞の教義を継承する真宗高田派と三門徒派は信長に味方して戦っているから、真宗が「反権力」とは言えないと著者は言う。また、「一向一揆」という言葉は江戸時代の資料にはじめて現れる言葉で、戦国・近世初頭では本願寺門徒の一揆を「一揆」「土一揆」と呼ぶのが、一般的であった。「一向宗」とは念仏の呪力を能くする山伏や陰陽師が広めたもので、それが越前国吉崎に参集して、そこで伝道していた本願寺蓮如のもとに集まって信者になったもので、彼らは自分たちの宗旨を「一向宗」であると思っていた。
以上、信長対一向一揆という構図は近世の軍記物に引っ張られた論で、信長に最初から本願寺撲滅の意図があったとは断定できないという。私もそう簡単なものではないと思う。
また、第三章と第四章はキリスト教の伝来について、書かれているが、基本的にキリスト教が仏教と似ているところがあり、受け入れが比較的容易だったとある。またイエズス会の宣教師たちは宣教に当たって仏教の排斥を主眼として、墓の破壊など他の宗教に対する非寛容性があったため、秀吉の伴天連追放令に繋がった。宣教師は基本的に帝国主義の尖兵であったという事実を改めて教えてくれる。そして最後に戦国時代に人々が「天道」という観念になじんでいたと言う。1603年刊行の『日葡辞書』では、「天の道、または(天の)秩序と摂理。以前は、この語で我々はデウスを呼ぶのが普通であった。けれども(その時にも)異教徒は(上記の)第一の意味以上に思い至っていたとは思われない」とあり、イエズス会やキリシタンがデウスを「天道」と呼んでいたことがわかる。著者は、「天道」ついて、「人間の運命をうむをいわさず決定する摂理」で「仏神と等値」。「目上を敬い目下を慈しめ、正直であれ、など世俗道徳の実践を促す」「祈祷など外面の行為よりも内面の倫理こそ大切とする点」とまとめている。その「天道」を実践すべく、人々はいろいろの宗教に帰依していったのである。
「天道」で有名なのが、司馬遷の「天道是耶、非耶」「(善を行なって禍を得、悪を行なって福を得ることがある)天道は果たして正しいのか正しくないのか」(史記 伯夷伝)だが、これは上記の神仏と同義だが、戦国人は『史記』を読んでいたのだろうか。