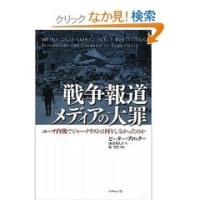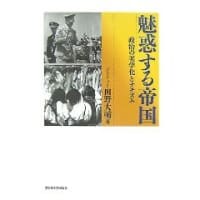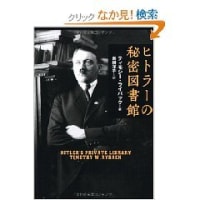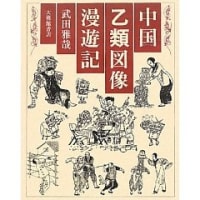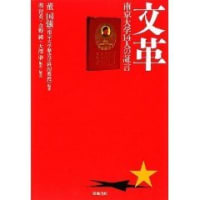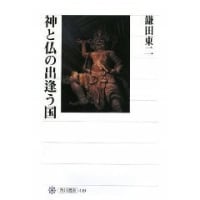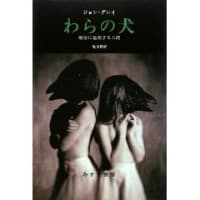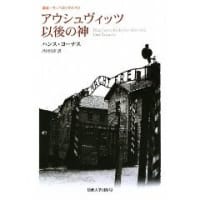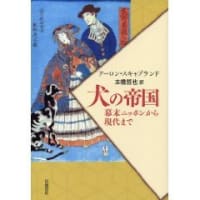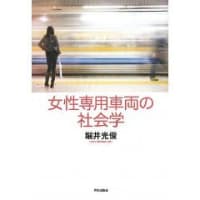敗戦直後、旧満州の日本人兵士ら約60万人がソ連軍に連行され、長期間の収容所生活を送った「シベリア抑留」。零下30度を超える極寒の冬、飢餓・重労働の中で約6万人が死亡したこの悲劇は、今も完結していないという思いで、著者は帰還者の無念を静かな筆致で淡々と描く。収容所内の模様は石原吉郎などが著作で詳細を語っているが、日本兵の無念を思うと涙がこみ上げてくる。
ソ連の対日参戦はヤルタ会談で決定した。アメリカのトルーマン大統領は日本の降伏をスムーズに実現するためにソ連に対日参戦を要求したのである。この情報を関東軍はいち早くキャッチしたが、満州居留民を保護するどころか、あろうことか自分達が真っ先に逃げ出したのだ。その後の引揚者の悲劇は歴史書の通りだ。日本兵達はソ連軍の捕虜になり、シベリアへ送られて強制労働に駆り立てられる。スターリンはシベリア開発に捕虜を使うことを予め決めており、日本兵もそのために連行された。本来捕虜を強制労働に使うことは国際条約で禁止されているのだが、日本兵はそのような教育を受けておらず、状況を甘受する傾向が強かった。その結果、他国の捕虜に比べて唯々諾々とソ連軍の指示に盲従するという、人間の誇りを喪失するような言動が目立った。それはソ連の共産主義教育によって洗脳された兵士が、収容所で権力闘争を展開し同僚の兵士を次々打倒して行ったことでも例証できる。これは帰国後も続き、社会問題になった。なんとピュアーな人間であることか。ドイツ軍の捕虜などは、課せられたノルマもいやいややる態度で、敵の言いなりになることは無かったという。こういう傾向は、米軍の捕虜になった日本兵にも見られ、米兵に一種の感動を与えたという。神風特攻隊の狂気と従順な捕虜との落差は、日本人はいったいどうなってんだろうと思わせたであろう。日本政府も先ほどのスターリンの捕虜政策に追随するかのように、日本兵のシベリア抑留を認める文書を出していたことが、本書で紹介されているが、驚きと言わざるを得ない。
その理由を、大量の兵士が帰国すると日本の混乱はますます大きくなり、雇用等の問題がたちまち浮上するということであった。兵士も兵士なら、為政者も為政者という感じだ。この卑屈さ・姑息さはどうだろう。戦後64年このメンタリティーは払拭されたであろうか。いや、シベリア帰還者に対する日本政府の対応を見る限り未だしの感がする。
ソ連の対日参戦はヤルタ会談で決定した。アメリカのトルーマン大統領は日本の降伏をスムーズに実現するためにソ連に対日参戦を要求したのである。この情報を関東軍はいち早くキャッチしたが、満州居留民を保護するどころか、あろうことか自分達が真っ先に逃げ出したのだ。その後の引揚者の悲劇は歴史書の通りだ。日本兵達はソ連軍の捕虜になり、シベリアへ送られて強制労働に駆り立てられる。スターリンはシベリア開発に捕虜を使うことを予め決めており、日本兵もそのために連行された。本来捕虜を強制労働に使うことは国際条約で禁止されているのだが、日本兵はそのような教育を受けておらず、状況を甘受する傾向が強かった。その結果、他国の捕虜に比べて唯々諾々とソ連軍の指示に盲従するという、人間の誇りを喪失するような言動が目立った。それはソ連の共産主義教育によって洗脳された兵士が、収容所で権力闘争を展開し同僚の兵士を次々打倒して行ったことでも例証できる。これは帰国後も続き、社会問題になった。なんとピュアーな人間であることか。ドイツ軍の捕虜などは、課せられたノルマもいやいややる態度で、敵の言いなりになることは無かったという。こういう傾向は、米軍の捕虜になった日本兵にも見られ、米兵に一種の感動を与えたという。神風特攻隊の狂気と従順な捕虜との落差は、日本人はいったいどうなってんだろうと思わせたであろう。日本政府も先ほどのスターリンの捕虜政策に追随するかのように、日本兵のシベリア抑留を認める文書を出していたことが、本書で紹介されているが、驚きと言わざるを得ない。
その理由を、大量の兵士が帰国すると日本の混乱はますます大きくなり、雇用等の問題がたちまち浮上するということであった。兵士も兵士なら、為政者も為政者という感じだ。この卑屈さ・姑息さはどうだろう。戦後64年このメンタリティーは払拭されたであろうか。いや、シベリア帰還者に対する日本政府の対応を見る限り未だしの感がする。