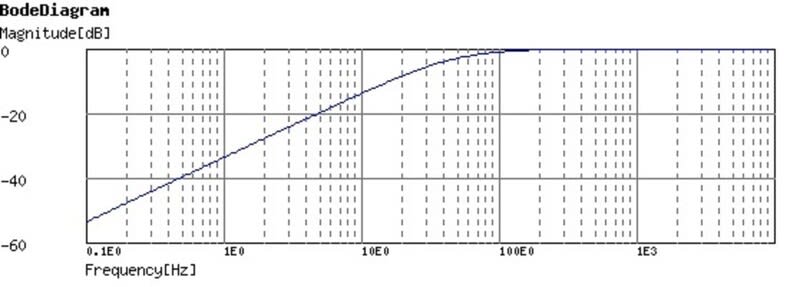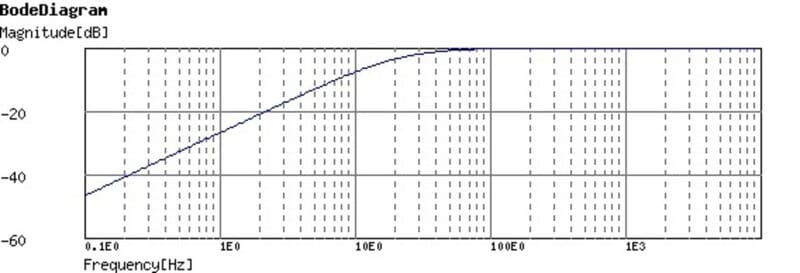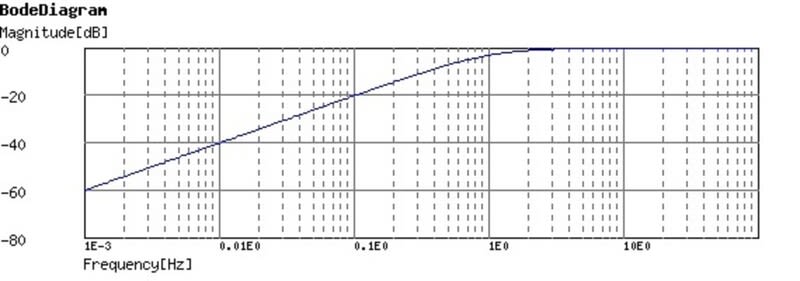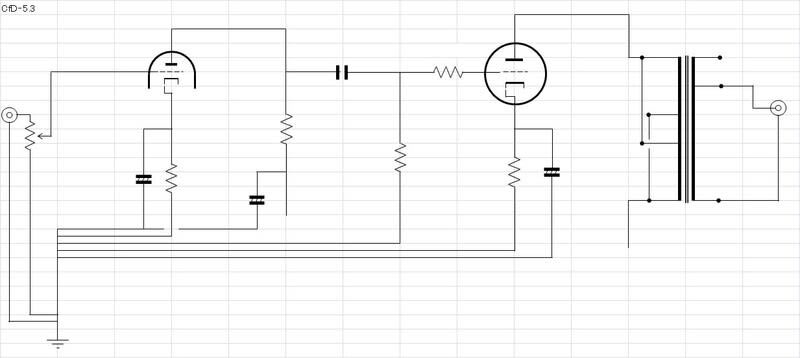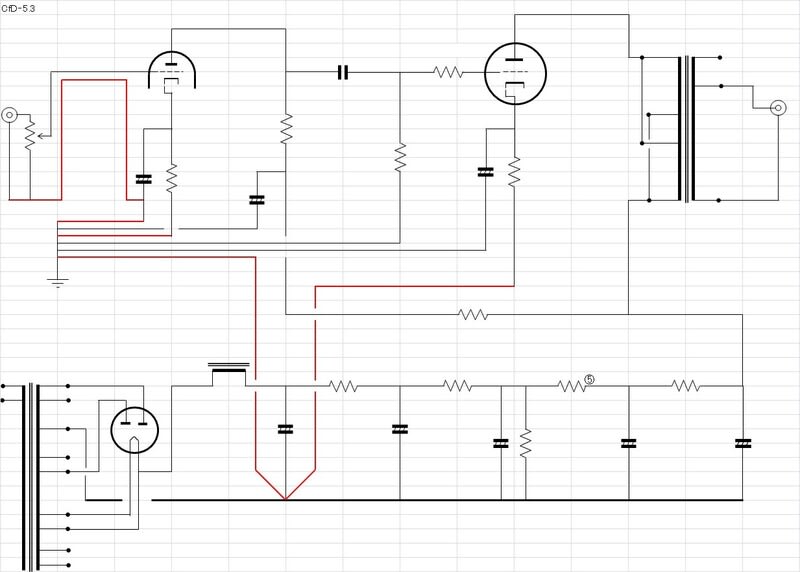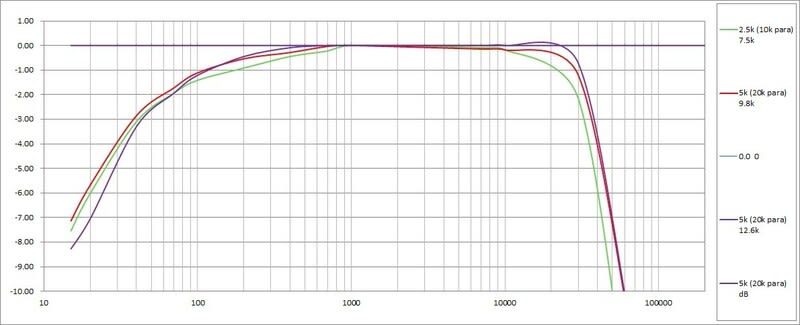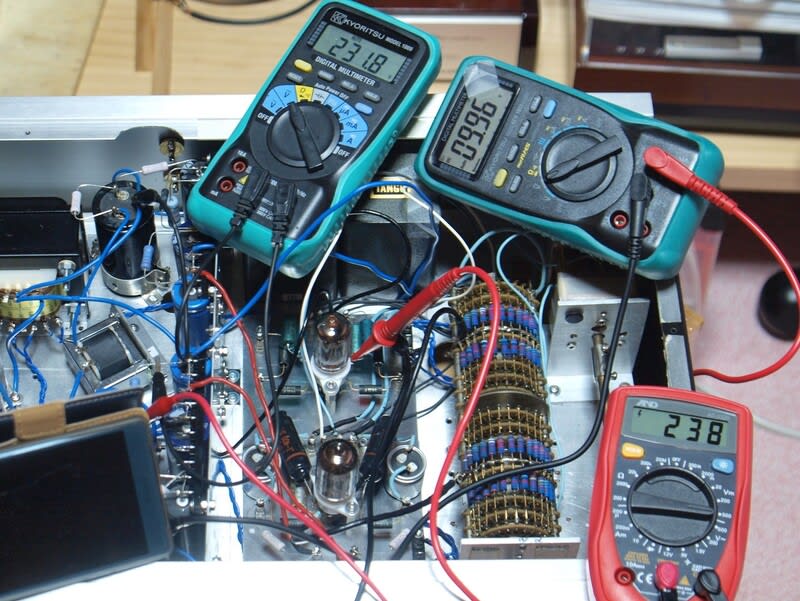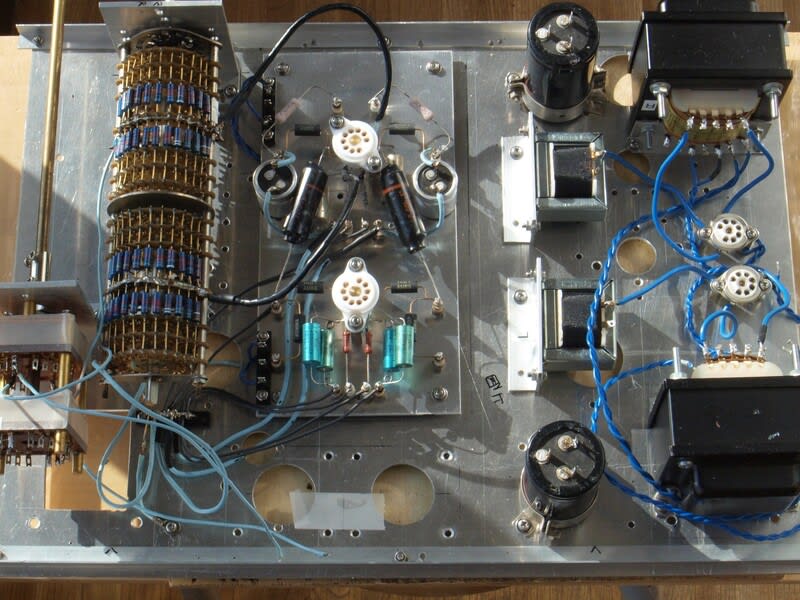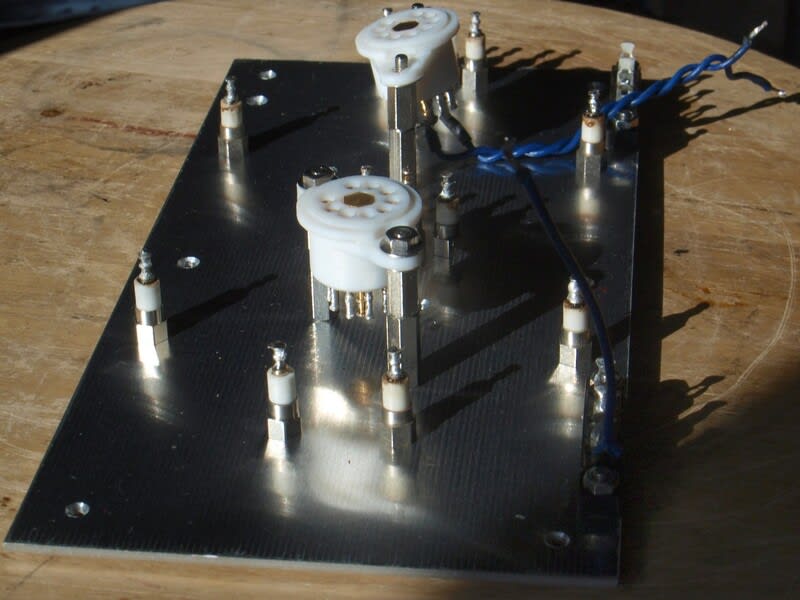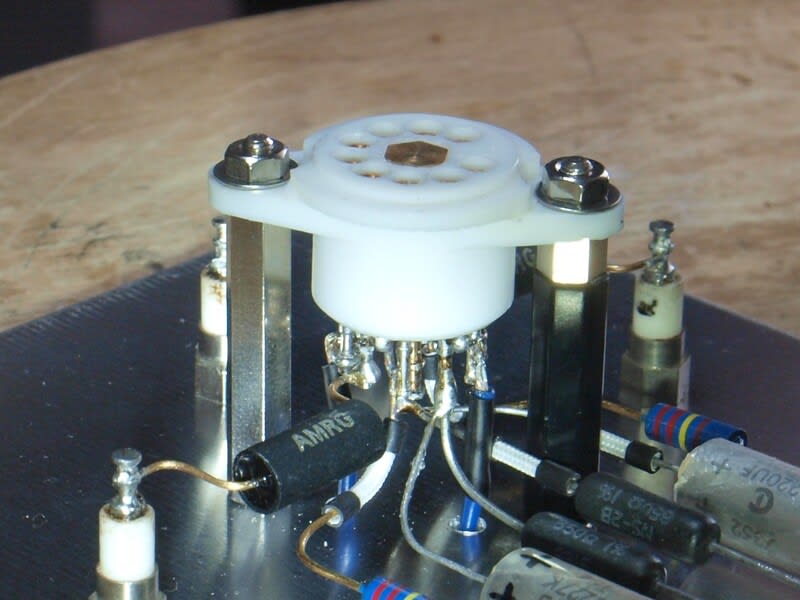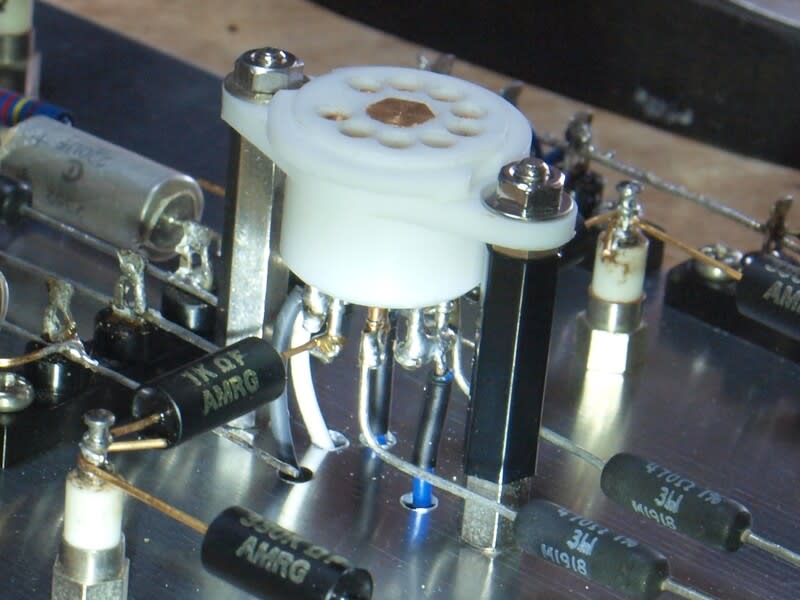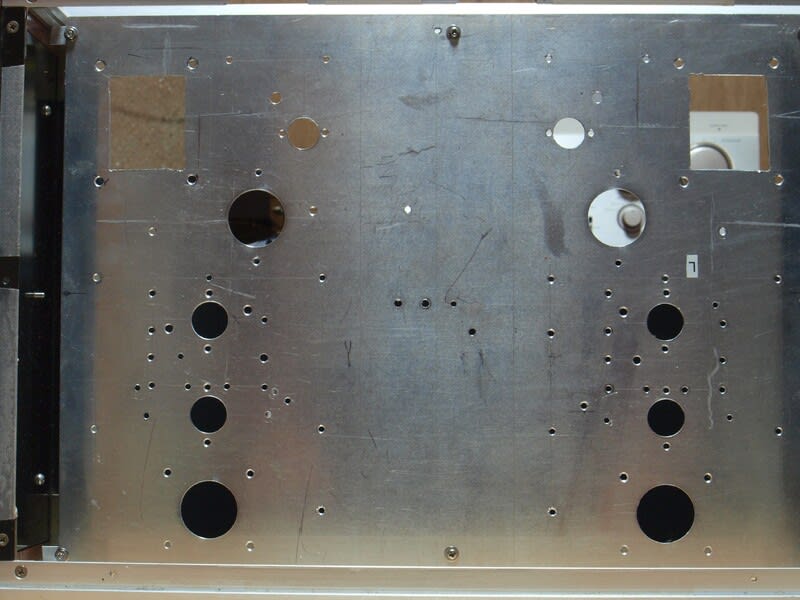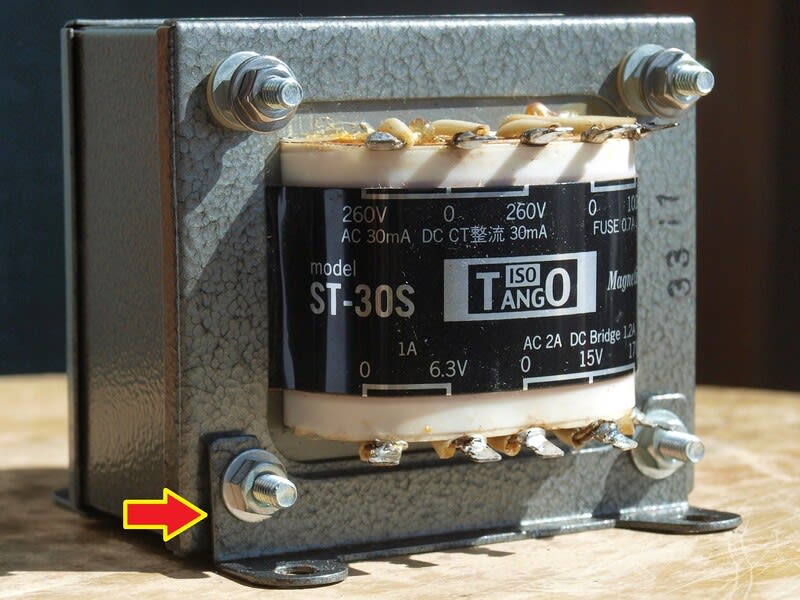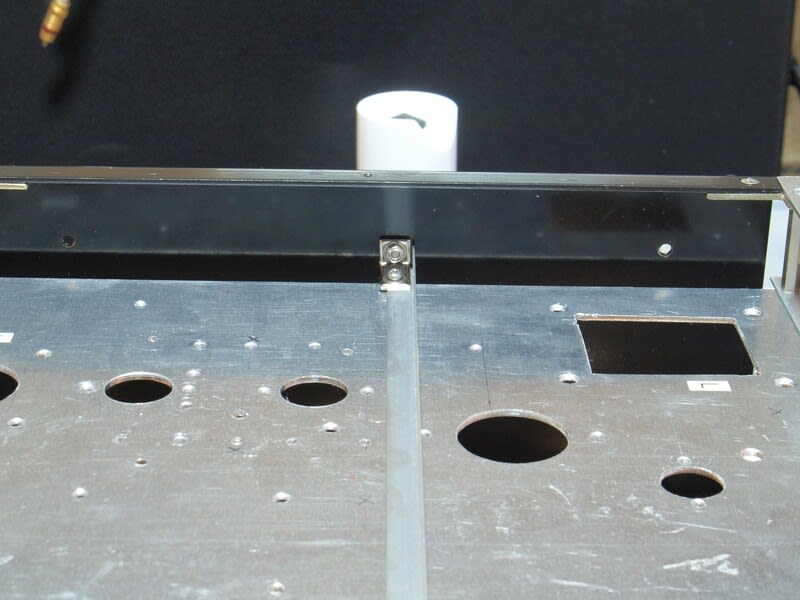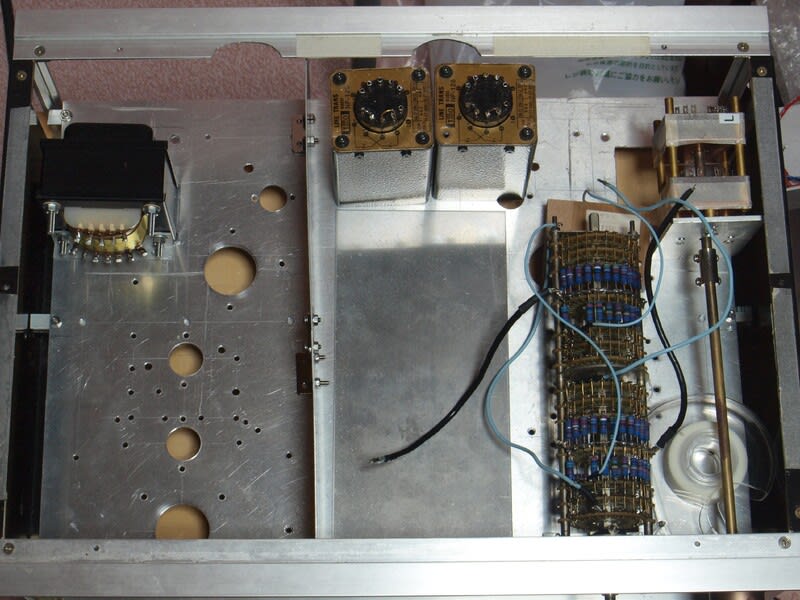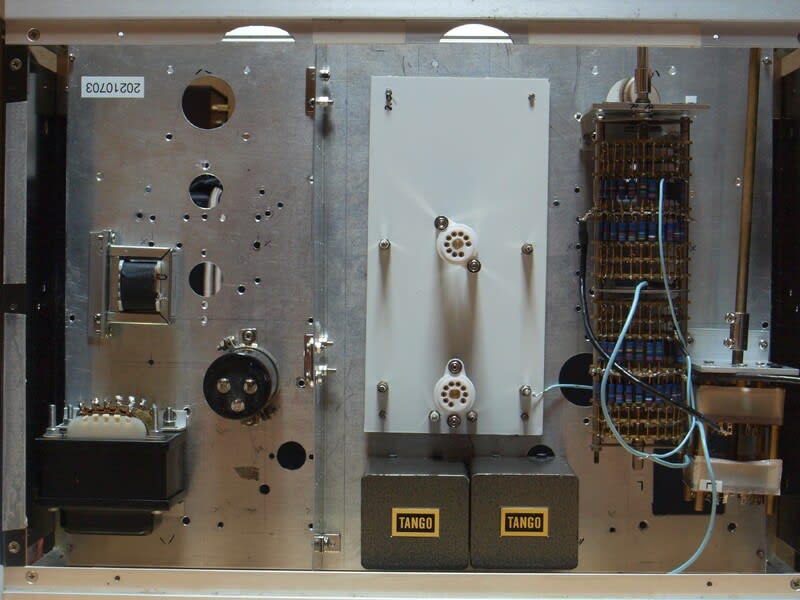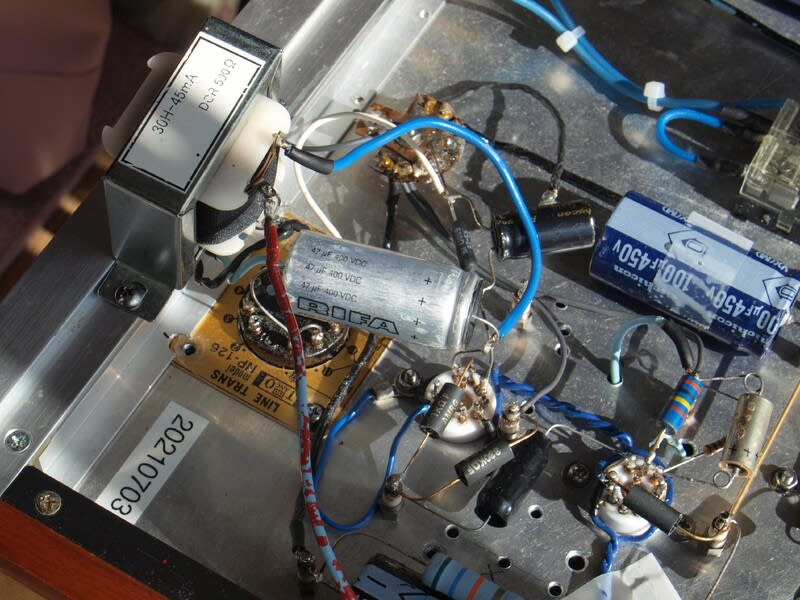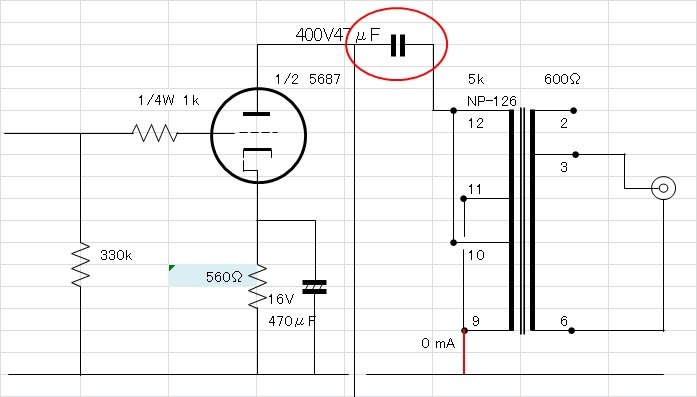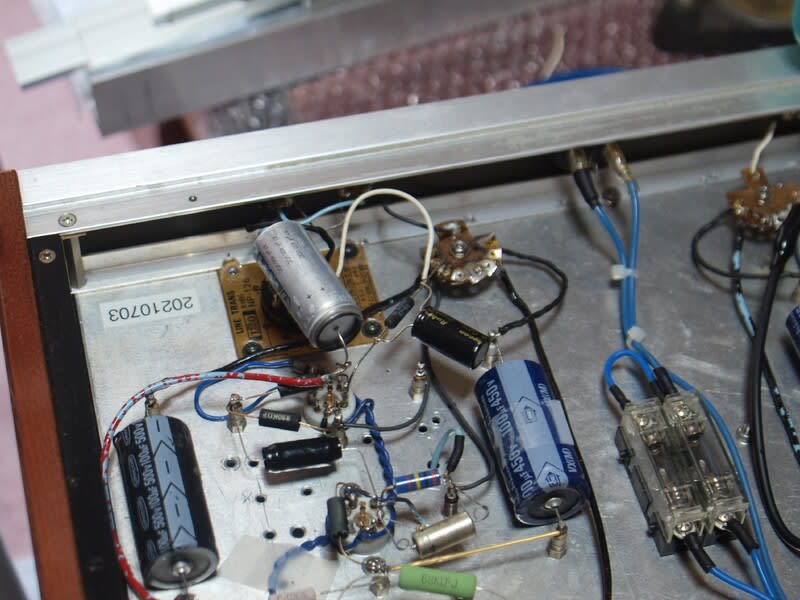では鳴らしてみた。
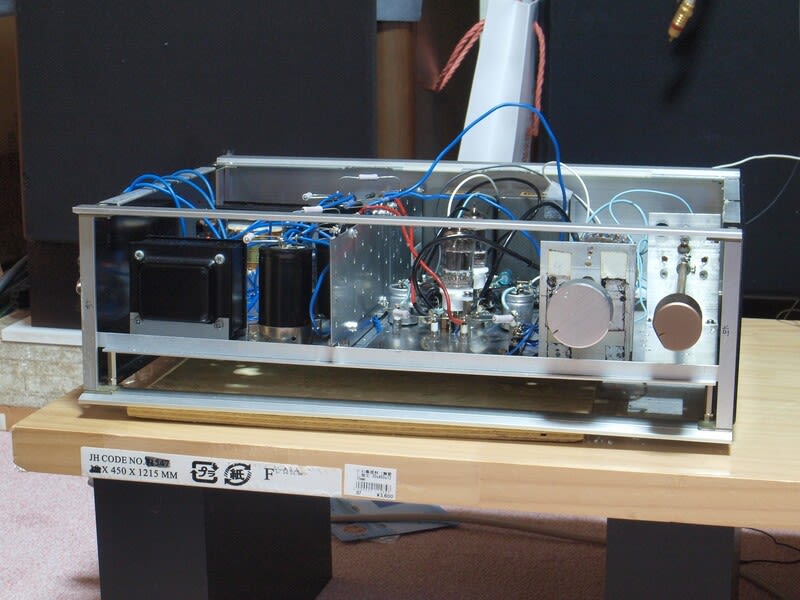
結構良い感じだ。
位相ずれの音が広がりひゅんひゅん飛んでくる。
声も良い。
音場も広がる。
ああ良いわ。
音量を上げてみた。
低音が無い。がっくり。
ええ?こんなだった?こないだの試作の時はもっと良かったはずだが。
カップリングコンデンサーを0.1μFから0.47μFに交換してみた。
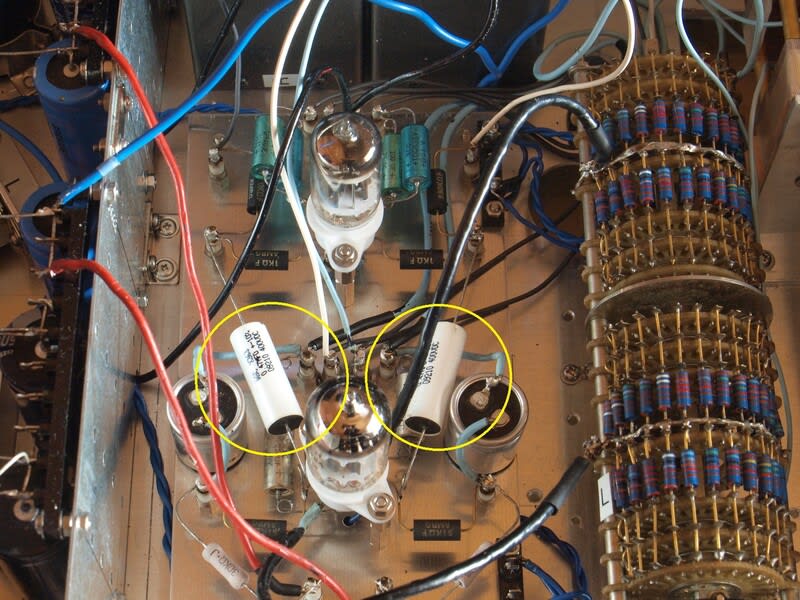
低域が少し厚くなったかな。けどまだまだ。
プリの出力段のカソードパスコンCkに470μFをワニ口で追加してみた。
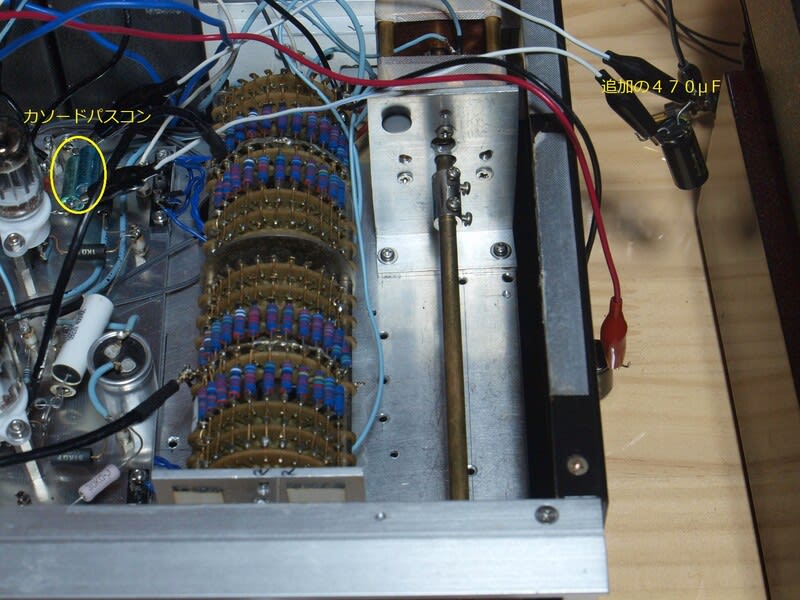
これはほとんど変わらない。
OPTのタップを換えて一次側20kΩから10kに変えてみた。
これもあまり変わらない。なんかチリチリした感じで良くない。
計算したら、プリ出力段の負荷が5k弱。
ならパワーの初段グリッド抵抗Rg11.6kΩを18kΩにした。
これは18kΩに33kΩを抱かせていたので33kΩを外したのだが、Lchのパワーをひっくり返したら、チリチリ、っと音がした。
プル側の抵抗のハンダを忘れてリード線の弾力で挟んでたか、外れてたかもしれない。

・・・18kΩの抵抗の足にハンダの跡がない。
作業を終えて、これでプリ出力段の負荷が8k弱になる。
これで音出ししたが、低域はあまり変わらなかった。
輪郭はそこそこ、形はかっちりわかる低域なのだが、厚みがない。足に例えると、着地点・接地面がぼやけて霞んでいる感じ?
シングルは高音のシャンシャンした音のフォーカスが合った感じで声に変な音色が乗らず純粋な音だ。
ただ、低域がそれらにバランスせず、弱い。
PPの暴力的な、部屋を揺るがすような低域が欲しいが中高域に音色が乗る感じ。
ここを立てればあちらが立たず、トレードオフな感じ。
思えばこの低音:ウーファーの駆動力が欲しくてPPでずっとやってきたのだが、ここに来てシングルの声の良さも思い出した。
両方取るってのは、出来ないのかなぁ。
もう少し考えよう。
いやぁ、楽しい。
20220213