

赤黒のHPのレゲエ・コーナーを見ていると、面白そうなブツが見つかった。CORN-FED
なるレーベルが、かつてリリースした「CD-R」のデッド・ストックが入荷したということで、
そのラインナップの中には気になるものが多々あったのだ。
未だにCD化されないブツは何種もあるし、ミスティ・イン・ルーツの7インチや12インチを
これでもかと集めた2枚組の編集盤まである。気が付けば7枚も買っていた。(笑)
10年に日本でのCD化で「世界初CD化」が実現されたジャッキー・ミットゥの「STEPPING
TIGER」も既にCD-R化されて世に出ていたのか・・・。今回のデッド・ストックの入荷は
レゲエ好きに大いにアピールしたようで、HPに掲載されてから4、5日でほぼ売り切れに
なったものが多いようだ。
CORN-FEDのことなど何も知らなかったのだが、到着したブツは04年から05年あたりに
制作されたようで、あのころの私はまだ目利き目配りが足りなかったということか。
CDRの盤面にはそれぞれの盤のオリジナル・レーベルを踏襲した印刷がなされており、
音質も上等。ほとんどの盤にオリジナル・アルバム未収録の12インチ音源やバージョンが
ボーナス・トラックとして収録されているのもうれしい。
掲載写真左は オーバーナイト・プレイヤーズが80年にリリースした「BABYLON
DESTRUCTION」。スタジオに集まった面子がその場限りで使用した名前のようで、
アルバムはこの1枚のみ。1曲目の『SHAKA THE GREAT』は様々なコンピレーション盤に
収録されている名曲。清流を進む舟の櫂のようにアコースティック・ギターが紡ぐフレーズが
印象的で、この曲が気に入らなければこの先聴く必要が無い、と言い切ってもいい名アレンジ
が施されている。全体にとても聴きやすく、ちょっとした仕掛けも楽しい盤で、チープな
シンセやハーモニカ、トランペットといった楽器の使い方がとても効果的である。
右の盤はサンズ・オブ・ジャーが、これも80年にリリースした「REGGAE HIT SHOWCASE」。
コーラス・グループであるが、後半はダブになるショーケース仕様なので一曲で二度美味しい。
こちらのバックは正にオール・スター総登場といった感じである。日本盤がリリースされて
ライナーでも書こうものなら、面子を書くだけでそれなりの字数が稼げるだろう。(笑)
ショーケースといっても1曲目の『MESERET』はボーカルが無いので、純然たるダブ・インスト
と捉えることができるのだが、ここではリードのトランペットが格好良く何かの劇伴でも
使えそうな感じである。曲によってはダブに変わるやいなやテンポが変わるものもあって
緩急の変化も面白い。勿論、ボーカル・グループとしての聴き処もちゃんとある好盤。
まだまだ未CD化のダブ盤はたくさんある。CD-Rでも構わないから、どんどんリリースして
ほしいものだ。













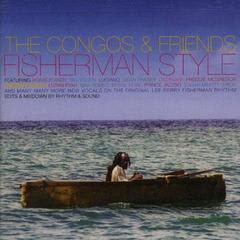
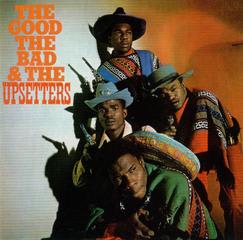

 さて、今回のアルバム・タイトルであるが
さて、今回のアルバム・タイトルであるが



 「100 YEARS AFTER」と題されたこの
「100 YEARS AFTER」と題されたこの
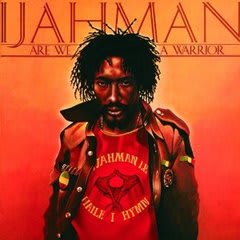 同じセッツションから生まれた2枚の
同じセッツションから生まれた2枚の
 もう、本当にこのジャケでCD化して欲しいくらい
もう、本当にこのジャケでCD化して欲しいくらい







 でもダブもいいんだよねぇ。(笑)
でもダブもいいんだよねぇ。(笑)












