

シアターコクーンで蜷川幸雄演出の「ミシマダブル」=「サド侯爵夫人」「わが友ヒットラー」を通しで観劇してきた。
「サド侯爵夫人」は2008年10月に「女方:篠井英介×演出:鈴木勝秀シリーズ」の第二弾で観ている。それを蜷川幸雄がどう料理するのかは観たかったが、「わが友ヒットラー」に抵抗があった。戯曲を買う時もわざわざその2本を収録した新潮文庫版を避けて河出文庫版を買ったくらいだ。
今回も逡巡している間にBunkamuraプレミアム会員先行予約期間を過ぎてeプラスで買うはめになり、今日は今日で出がけに母娘の葛藤をやっていたので、家を出るのが遅くなり遅刻。

それでも「サド侯爵夫人」は話の内容がわかっているので、全く苦にならずに世界に入れた。篠井英介主演の舞台と同様にオールメールでの上演は、実にこの戯曲にぴったりだと痛感。詳細の感想はまた今度。

夜の部の「わが友ヒットラー」までに時間があるので、戯曲を読んで予習しておこうと東急本店7階に最近オープンした「丸善&ジュンク堂書店」へ。劇場ロビーでも売ってはいたが、この書店をのぞいてみたかったということもあって行ってきた。ブックファースト文化村通り店が取り壊されてH&Mビルに建て替えられてしまった後、大きな書店がなくて寂しかったのだが、これでBunkamura近辺に来た時に立ち寄ることができるのが嬉しい。
ハヤカワ演劇文庫のコーナーも揃っていて、思わずトム・ストッパードの「コースト・オブ・ユートピア」まで買ってきてしまった。

東急本店の筋向いのビルの2階に「ガスト」もできたので、若者たちに混じってひとり御飯。早速「わが友ヒットラー」の戯曲を超斜め読み。おかげでこの台詞劇にラクラクついていけた。

帰りの電車の中で巻末にあった三島による自作解題を読んで、ようやく納得した。以下、東京新聞・昭和43年12月27日付記事より引用。
「戯曲『サド侯爵夫人』を書いたときから、私にはこれと対をなす作品を書きたいという気持が芽生えた。『サド』は女ばかりの登場人物で、フランス・ロココの一杯道具で、18世紀の怪物サドが中心、『わが友ヒットラー』は男ばかりの登場人物で、ドイツ・ロココの一杯道具で、20世紀の怪物ヒットラーが中心というわけだ。フランス革命とナチス革命が背後にある点でも、2作は似ている。似ていて十分コントラストがきいていなければならない。(中略)芝居のこまかい機巧よりも、ますます能のような単純簡素な構造を私は愛するようになった。舞台技巧などというものは、意識的に避けて書いたのである。その代りに緊迫感が出ていたら成功だと思うが、そのへんは作者自身にはよくわからない。」

そうか、蜷川幸雄は三島の意図を組んでこの一対の作品を「ミシマダブル」として交互上演する企画を立てたのか!と納得したのだった。

それに「サド侯爵夫人」の音楽としてクラシックとともに流れていた能の鼓や能管の音も三島へのオマージュというわけか!!と合点した。
そして、あんなに食わず嫌いをしていた「わが友ヒットラー」が実によかった。今回は「サド侯爵夫人」よりも面白かった。詳しい感想はまた書くつもりだが、悩んだ末に両方観ることにして正解だったと思う。

新潮文庫版のこの戯曲集もおすすめだ。これで420円なんて安いし有難い。
(2/27追記)
帰宅してから2作品共通のプログラムを読み始めたが、それぞれの作品解説のページにはいずれも新潮文庫の自作解題のところにあった三島の文章が添えられていた。上記に引用したものは「わが友ヒットラー」のページにあった。













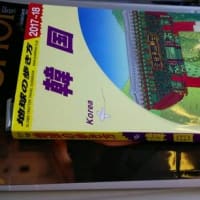
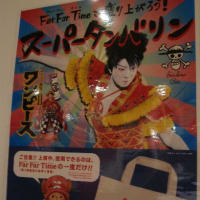

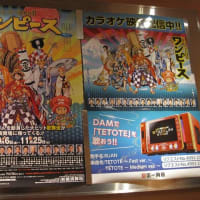
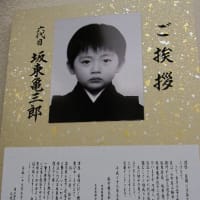
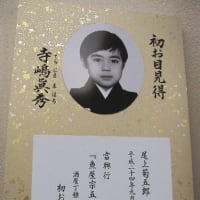

三島作品は舞台が一番よいでしょうね。
映像だとちょっとキツい時があります(笑)
今回の企画は平幹二朗さんが蜷川さんに焚き付けて実現したもののようです。「篠井英介×鈴木勝秀シリーズ」の舞台とはずいぶん違ったものになっていました。ヒガシのルネはあまり美しくもなく、なんだろうと思って観ていたら二幕最後の「アルフォンスは私だったのです」という台詞で、その顔はまさにルネが理想として描いているサド侯爵の顔に見えたのです。これこそがヒガシの起用のねらいかもと思ってしまったくらいです。ですから篠井さんのルネとは全く別物でした。
三島はやはり演劇の人のようで、歌舞伎との関わり、新劇の中での活躍は、短い45年の生涯でぎゅっと凝縮された高密度ハイテンションのものだったのだなぁと今回つくづく思わされました。