
「秋月」というと、すぐに思い浮かべるのは「秋月の乱」であろう。
300年近く続いた徳川幕府が倒れ、版籍奉還がなされ、明治の新政府が発足した。明治の維新は武士を中心とした無血革命であったが、同時に武士をなくすことでもあった。
士農工商と身分は一応最も高いとされた武士だが、禄高はなくなり実質は無給となったのだった。商売による金儲けは卑しいと思われていたので、プライドの高い旧武士の多くは金儲けもままならなかった。ましてや、鍬や鎌を持って農業をするものもそういない。
時代が変わったとはいえ、「武士は食わねど高楊枝」などといつまでも言っていられない時期が続いた。そんな旧武士である士族による不満が各地で鬱積していた。
やがて明治7(1874)年、「佐賀の乱」を皮切りに、士族による新政府への反乱が九州・山口の各地で起こることになる。この乱で、新政府の中枢を担っていた江藤新平(前参議・初代司法卿)、島義勇(前侍従・秋田県権令)が死刑・梟首となった。
明治9(1876)年、廃刀令が発布される。武士の魂とされた刀も取り上げられ、一般市民となんら変わらない立場になった旧武士たちは、新政府に向かって散発的に立ち上がった。
その年、熊本・神風連の乱、福岡・秋月の乱、山口・萩の乱が起こり、翌明治10(1877)年の鹿児島・西南の役の西郷隆盛の死によって、やっと収まることになる。
その秋月へ、地元の友人の車で行くことにした。
佐賀から鳥栖を過ぎるとすぐに福岡県である。小郡の先が秋月だ。秋月はかつて甘木市にあったのだが、今は朝倉市と名を変えていた。
秋月は、秋月の乱以後衰退し、城があるわけでもないので鄙びた村として忘れ去られていた。しかし、城跡周辺やその近くの杉の馬場あたりは古(いにしえ)の風情が残っていて、筑前の小京都として、この一帯は桜の名所にもなっている。(写真)
そして、最近この秋月を思い出させたのが、今年(2011年)2月にドラマとして放映された「遺恨あり」(出演:藤原竜也、小澤征悦、松下奈緒)であろう。この話は、「日本最後の仇討ち」というものだ。
物語は、日本が大きく揺れ動いていた幕末の期。藩主の命を受け秋月藩の行く末を模索していた馬廻り役臼井亘理は、秋月に帰郷した日に暗殺される。その当時幼かった嫡男の六郎が、長じて父の敵を討つという実話である。既に明治13年であった。
江戸幕府の武士の時代であれば、父の仇討ちは美談であったが、文明開化の時代、もはや単なる殺人と見なされる。
日本最後の敵討ちは、旧秋月藩士の手でおこなわれたのだ。
秋月の4月は、桜が満開であった。
秋月の乱も、遺恨ありも、その面影を見つけ出せなかったが、散る桜だけが儚さを伝えていた。
しかし、何といっても僕がこの秋月で思いつくのは、「秋月へ」である。
丸元淑生の小説「秋月へ」である。
1978年の芥川賞候補作になったこの小説は、1980年に出版された。著者の前作「鳥はうたって残る」を読んでいた僕は、すぐにこの本を手にしたのだった。
と言っても、「秋月へ」は秋月が物語の舞台ではない。秋月の乱に参加した曾祖父の子、おそらく著者の、戦前から戦中、戦後を生きた少年時代の回想の話である。舞台は秋月の近くの筑豊・田川だが、秋月は伏流としてあるのだった。
詳しい内容を忘れた後も、このタイトルがいつまでも僕の心に残っていた。
そして、秋月へ行く前日に、町の図書館で偶然この本が置いてあるのを見つけて、再び読んでみた。30年たっても瑞々しい文体は、色あせてはいない。
その丸元淑生は、その後文学を捨てたのか、なぜか栄養学のほうへ行ってしまい、今はもういない。
その日、秋月を後にし、九重、阿蘇へ向かった。
300年近く続いた徳川幕府が倒れ、版籍奉還がなされ、明治の新政府が発足した。明治の維新は武士を中心とした無血革命であったが、同時に武士をなくすことでもあった。
士農工商と身分は一応最も高いとされた武士だが、禄高はなくなり実質は無給となったのだった。商売による金儲けは卑しいと思われていたので、プライドの高い旧武士の多くは金儲けもままならなかった。ましてや、鍬や鎌を持って農業をするものもそういない。
時代が変わったとはいえ、「武士は食わねど高楊枝」などといつまでも言っていられない時期が続いた。そんな旧武士である士族による不満が各地で鬱積していた。
やがて明治7(1874)年、「佐賀の乱」を皮切りに、士族による新政府への反乱が九州・山口の各地で起こることになる。この乱で、新政府の中枢を担っていた江藤新平(前参議・初代司法卿)、島義勇(前侍従・秋田県権令)が死刑・梟首となった。
明治9(1876)年、廃刀令が発布される。武士の魂とされた刀も取り上げられ、一般市民となんら変わらない立場になった旧武士たちは、新政府に向かって散発的に立ち上がった。
その年、熊本・神風連の乱、福岡・秋月の乱、山口・萩の乱が起こり、翌明治10(1877)年の鹿児島・西南の役の西郷隆盛の死によって、やっと収まることになる。
その秋月へ、地元の友人の車で行くことにした。
佐賀から鳥栖を過ぎるとすぐに福岡県である。小郡の先が秋月だ。秋月はかつて甘木市にあったのだが、今は朝倉市と名を変えていた。
秋月は、秋月の乱以後衰退し、城があるわけでもないので鄙びた村として忘れ去られていた。しかし、城跡周辺やその近くの杉の馬場あたりは古(いにしえ)の風情が残っていて、筑前の小京都として、この一帯は桜の名所にもなっている。(写真)
そして、最近この秋月を思い出させたのが、今年(2011年)2月にドラマとして放映された「遺恨あり」(出演:藤原竜也、小澤征悦、松下奈緒)であろう。この話は、「日本最後の仇討ち」というものだ。
物語は、日本が大きく揺れ動いていた幕末の期。藩主の命を受け秋月藩の行く末を模索していた馬廻り役臼井亘理は、秋月に帰郷した日に暗殺される。その当時幼かった嫡男の六郎が、長じて父の敵を討つという実話である。既に明治13年であった。
江戸幕府の武士の時代であれば、父の仇討ちは美談であったが、文明開化の時代、もはや単なる殺人と見なされる。
日本最後の敵討ちは、旧秋月藩士の手でおこなわれたのだ。
秋月の4月は、桜が満開であった。
秋月の乱も、遺恨ありも、その面影を見つけ出せなかったが、散る桜だけが儚さを伝えていた。
しかし、何といっても僕がこの秋月で思いつくのは、「秋月へ」である。
丸元淑生の小説「秋月へ」である。
1978年の芥川賞候補作になったこの小説は、1980年に出版された。著者の前作「鳥はうたって残る」を読んでいた僕は、すぐにこの本を手にしたのだった。
と言っても、「秋月へ」は秋月が物語の舞台ではない。秋月の乱に参加した曾祖父の子、おそらく著者の、戦前から戦中、戦後を生きた少年時代の回想の話である。舞台は秋月の近くの筑豊・田川だが、秋月は伏流としてあるのだった。
詳しい内容を忘れた後も、このタイトルがいつまでも僕の心に残っていた。
そして、秋月へ行く前日に、町の図書館で偶然この本が置いてあるのを見つけて、再び読んでみた。30年たっても瑞々しい文体は、色あせてはいない。
その丸元淑生は、その後文学を捨てたのか、なぜか栄養学のほうへ行ってしまい、今はもういない。
その日、秋月を後にし、九重、阿蘇へ向かった。













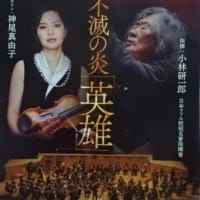

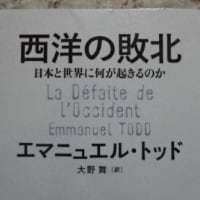









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます