
*影の存在
すぐ近くの図書館のカフェコーナーで、コーヒーを飲みながらいっとき本を読んで(最近は時々こういう時間を作っている)、図書館を出た。カラスでも鳴いてよさそうな淡い夕暮れ時だった。
いつも通っている見慣れた路上に出た際、私はおもむろに自分の足元を見まわした。私の“影”がちゃんとあるのかを確かめるために。
というのも、今読み終わりつつある(すでに読み終わった)本というのが村上春樹の「街と不確かな壁」という小説で、2部(3部構成になっている)の最後にこう綴ってあるのだ。
「ねえ、わかった? わたしたちは二人とも、ただの誰かの影にすぎないのよ」
物語の主人公は、いつの間にか自分の影を失くしていた。失くした影は別の世界にいた。影はもう一つの別の世界で、影の持ち主とは別に生きていた。
私(筆者)も、最近は影をないがしろにしていたなあと思いなおし、自分の影をさりげなく、それでも注意ぶかく探したのだった。影の存在を確認するために。
考えるに、影はなぜあるのだろう。
影は変幻自在だ。大きくもなれば小さくもなり、角度を変えれば自分の前に行ったり後ろに行ったりする。ぼくのことは気にしなくていいよとばかりの動き、行動だ。
影の存在を強く意識したことはなかったけど、影は何の役にたっているのだろう。なくても何不自由しないようにも思える。
影を失くしたら、どうなのだろう。あるいは、私に黙って影が出ていってしまったら。
それでも私は、何ごともなかったように生きていくのだろうか。
*村上春樹の、40年前の喉に刺さった魚の棘のような小説
村上春樹がデビューしたての頃の1980年に、雑誌「文芸」に著者3作目の中編小説「街と、その不確かな壁」を発表した。
そのとき村上は内容的に納得がいかず、この小説を書籍化はしないでいた。2023年発表の新作「街とその不確かな壁」(新潮社)の「あとがき」によれば、村上の書かれた小説で書籍化していないのはこの作品だけであった。
しかし、最初からこの作品は彼にとって重要な要素が含まれていると感じていて、いつかじっくり手を入れて書き直そうと思っていた。
そして1982年、本格的長編小説「羊をめぐる冒険」を書きあげた。
それから「街と、その不確かな壁」を書き直すつもりで着手した小説、二つのストーリーを並行して交互に進行させていく「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」ができあがり、1985年に出版する。
これらは、村上春樹作品を象徴する代表作といえる。
しかし歳月が経過し、作家としての経験を積み、年を重ねるにつれ、村上はそれだけで「街と、その不確かな壁」に決着をつけたとは思えなくなり、新たに筆をとった。
時は、新型コロナウィルスがパンデミックとして猛威を振るい始めた2020年のことである。社会も個人も、閉塞を余儀なくされていた状況のときであった。このことは、おそらく何かを意味しているに違いないと村上は述べている。
最初作品が発表されてから40年がたっていた。
*私と私の影の物語、「街とその不確かな壁」
「きみがぼくにその街を教えてくれた。」
こうやって、この六百数十頁もの長い物語は始まる。主人公のぼくは17歳で、彼女のきみは16歳。
「街は高い壁にまわりを囲まれているの」ときみは語りだす。
「本当のわたしが生きて暮らしているのは、高い壁に囲まれたその街の中なの」ときみは言う。
「じゃあ、今ぼくの前にいるきみは、本当のきみじゃないんだ」、当然ながらぼくはそう尋ねる。
「ええ、今ここにいるわたしは、本当のわたしじゃない。その身代わりにすぎないの。ただの移ろう影のようなもの」
高い壁に囲まれた街を話すきみ(彼女)は、ある日、ぼく(主人公)の前から突然消えたようにいなくなる。いつまでたっても消息が知れないきみのことを思い待ち続けながらも、年月は過ぎていく。
いつしか40代になった私(主人公)は、ある日、もう一つの世界である君(彼女)が話していた高い壁に囲まれた街に落ちる(行きつく)。
その街は、時間の止まったような影のない世界である。私は、街の入口で自分の影と離される。私はその街で、16歳のままの少女である君のいる図書館で、<夢読み>として働くことになる。そして、次第にその街に慣れ親しんでいく。
彼女と私(主人公)が行きついた、もう一つの世界の概要を記しておこう。
街は、高い煉瓦の壁に囲まれていて、その内側には街の唯一の出入り口である門衛小屋がある。
街は腎臓の形に似た外周を持ち、街の中央を緩やかに蛇行しながら一本の美しい川が流れている。ひっそりとした街中にはひっそりと家々があり、一冊の書物も置かれていない図書館がある。
静かで時が止まったような街で、壁の上を飛べる鳥を除いて、人以外の生物では生命力の乏しい単角獣がいるだけである。
※「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」も、二つの物語(世界)が交互に進行する。その「世界の終り」の章は、壁に囲まれた街で、一角獣が生息している。
壁に囲まれた街は、閉塞された街である。かといって、私は不幸でも不満でもない。私の役目である<夢読み>の仕事も順調だし、なにより君(少女)がいる。
壁の中の生活にも慣れてきたころ、街を散策した私は、やがてその街から抜け出す入口のようなものを発見する。(1部)
*現実から抜け出し、別の世界で生きる!
物語の2部では、主人公の私は40代半ばの中年サラリーマンになっている。結婚はしていない独身である。まだ17歳のときの君(少女)のことを忘れていないし、君が話した壁に囲まれた街のことも頭の片隅にある。
私はそれまで勤めていた会社を辞め、これといった理由はないのだが、どこか図書館で勤めようと思いたつ。
そして、たまたまであるが何かに導かれるように、東北(福島県)の田舎の小さな図書館に職を得る。そこで、前の図書館長である老人との友好的だが奇妙な交流が始まる。その人は、現実にはすでにいない人であった。
そして、その図書館へは、現実社会にそぐわない少年が本を読みに頻繁に通ってきていた。その少年は、壁に囲まれた街(もう一つの世界)へ行こうと思うようになる。そして、少年は突然姿を消す。
3部は、壁に囲まれた街に残った(中年の)私のその後である。
壁の中の街で、私は元の街での図書館に通っていた少年を見つける。少年と話をしているうちに、私は元の世界に戻ろうと思う。
*地図を描き、穴に落ちてみる、物語の世界
物語のもう一つの世界である壁に囲まれた街は、ほとんど人影のない、死んだような世界である。時は動いているのだが時間がない、それゆえ街の時計には文字盤はあるが針がない。
不気味だが、感情がないので一概に不幸とは言えない、影のない世界。
現実の世界ともう一つの世界である壁に囲まれた街を行き来するということに、何を見出したらいいのか。
こちらの世界ではない、あちらの世界とは…と考えてみる。今住んでいるところとは異なる地図を描き、風景を想像する。そこには今抱いているのとは違った価値観、幸福感がある。その他、異なった些細な事例を思い描く。
小説、物語の醍醐味は、自分の思いもよらない世界に導かれることにある。
例えば、見過ごしがちだった影というものを認識するように、穴の奥、あるいは井戸の底における未知の世界への通路という村上春樹が作るメタファーの物語は、今までの小説とは違った水路を開発していて、思いもよらない異なった景色の世界へ誘い込む。
※ブログ→「穴の向こう側に行く旅、「騎士団長殺し」(2017-10-10)
https://blog.goo.ne.jp/ocadeau3/e/256a2ef466173e16bc44bf4d8b60e573
※ブログ→「図らずも、「穴」に落ちるという体験」(2017-11-27)
https://blog.goo.ne.jp/ocadeau3/m/201711
私は村上春樹の恋愛小説、例えば彼の作品で最も売れたとされる「ノルウェーの森」や「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」などは、どうして彼がこんな小説を書くのだろうと首を傾げたのだが、現実を超脱した長編小説の多くは、想像力と脳を躍動させる。
ありそうもない物語でも、奇想天外なSFや浅薄なファンタジーにならないのは、彼の比喩・暗喩を塗せた稀有な文体による、独自の突破力にあるといえるだろう。それゆえ、ありそうもない話として出発した物語が、いつしかあってもよさそうな話に運びさられるのである。
村上春樹は「あとがき」で、最後にホルヘ・ルイス・ボルヘスの言葉に倣い、次のように締めくくっている。
「要するに、真実というのはひとつの定まった静止の中にではなく、不断の移行=移動する相の中にある。それが物語というものの神髄ではあるまいか」
すぐ近くの図書館のカフェコーナーで、コーヒーを飲みながらいっとき本を読んで(最近は時々こういう時間を作っている)、図書館を出た。カラスでも鳴いてよさそうな淡い夕暮れ時だった。
いつも通っている見慣れた路上に出た際、私はおもむろに自分の足元を見まわした。私の“影”がちゃんとあるのかを確かめるために。
というのも、今読み終わりつつある(すでに読み終わった)本というのが村上春樹の「街と不確かな壁」という小説で、2部(3部構成になっている)の最後にこう綴ってあるのだ。
「ねえ、わかった? わたしたちは二人とも、ただの誰かの影にすぎないのよ」
物語の主人公は、いつの間にか自分の影を失くしていた。失くした影は別の世界にいた。影はもう一つの別の世界で、影の持ち主とは別に生きていた。
私(筆者)も、最近は影をないがしろにしていたなあと思いなおし、自分の影をさりげなく、それでも注意ぶかく探したのだった。影の存在を確認するために。
考えるに、影はなぜあるのだろう。
影は変幻自在だ。大きくもなれば小さくもなり、角度を変えれば自分の前に行ったり後ろに行ったりする。ぼくのことは気にしなくていいよとばかりの動き、行動だ。
影の存在を強く意識したことはなかったけど、影は何の役にたっているのだろう。なくても何不自由しないようにも思える。
影を失くしたら、どうなのだろう。あるいは、私に黙って影が出ていってしまったら。
それでも私は、何ごともなかったように生きていくのだろうか。
*村上春樹の、40年前の喉に刺さった魚の棘のような小説
村上春樹がデビューしたての頃の1980年に、雑誌「文芸」に著者3作目の中編小説「街と、その不確かな壁」を発表した。
そのとき村上は内容的に納得がいかず、この小説を書籍化はしないでいた。2023年発表の新作「街とその不確かな壁」(新潮社)の「あとがき」によれば、村上の書かれた小説で書籍化していないのはこの作品だけであった。
しかし、最初からこの作品は彼にとって重要な要素が含まれていると感じていて、いつかじっくり手を入れて書き直そうと思っていた。
そして1982年、本格的長編小説「羊をめぐる冒険」を書きあげた。
それから「街と、その不確かな壁」を書き直すつもりで着手した小説、二つのストーリーを並行して交互に進行させていく「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」ができあがり、1985年に出版する。
これらは、村上春樹作品を象徴する代表作といえる。
しかし歳月が経過し、作家としての経験を積み、年を重ねるにつれ、村上はそれだけで「街と、その不確かな壁」に決着をつけたとは思えなくなり、新たに筆をとった。
時は、新型コロナウィルスがパンデミックとして猛威を振るい始めた2020年のことである。社会も個人も、閉塞を余儀なくされていた状況のときであった。このことは、おそらく何かを意味しているに違いないと村上は述べている。
最初作品が発表されてから40年がたっていた。
*私と私の影の物語、「街とその不確かな壁」
「きみがぼくにその街を教えてくれた。」
こうやって、この六百数十頁もの長い物語は始まる。主人公のぼくは17歳で、彼女のきみは16歳。
「街は高い壁にまわりを囲まれているの」ときみは語りだす。
「本当のわたしが生きて暮らしているのは、高い壁に囲まれたその街の中なの」ときみは言う。
「じゃあ、今ぼくの前にいるきみは、本当のきみじゃないんだ」、当然ながらぼくはそう尋ねる。
「ええ、今ここにいるわたしは、本当のわたしじゃない。その身代わりにすぎないの。ただの移ろう影のようなもの」
高い壁に囲まれた街を話すきみ(彼女)は、ある日、ぼく(主人公)の前から突然消えたようにいなくなる。いつまでたっても消息が知れないきみのことを思い待ち続けながらも、年月は過ぎていく。
いつしか40代になった私(主人公)は、ある日、もう一つの世界である君(彼女)が話していた高い壁に囲まれた街に落ちる(行きつく)。
その街は、時間の止まったような影のない世界である。私は、街の入口で自分の影と離される。私はその街で、16歳のままの少女である君のいる図書館で、<夢読み>として働くことになる。そして、次第にその街に慣れ親しんでいく。
彼女と私(主人公)が行きついた、もう一つの世界の概要を記しておこう。
街は、高い煉瓦の壁に囲まれていて、その内側には街の唯一の出入り口である門衛小屋がある。
街は腎臓の形に似た外周を持ち、街の中央を緩やかに蛇行しながら一本の美しい川が流れている。ひっそりとした街中にはひっそりと家々があり、一冊の書物も置かれていない図書館がある。
静かで時が止まったような街で、壁の上を飛べる鳥を除いて、人以外の生物では生命力の乏しい単角獣がいるだけである。
※「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」も、二つの物語(世界)が交互に進行する。その「世界の終り」の章は、壁に囲まれた街で、一角獣が生息している。
壁に囲まれた街は、閉塞された街である。かといって、私は不幸でも不満でもない。私の役目である<夢読み>の仕事も順調だし、なにより君(少女)がいる。
壁の中の生活にも慣れてきたころ、街を散策した私は、やがてその街から抜け出す入口のようなものを発見する。(1部)
*現実から抜け出し、別の世界で生きる!
物語の2部では、主人公の私は40代半ばの中年サラリーマンになっている。結婚はしていない独身である。まだ17歳のときの君(少女)のことを忘れていないし、君が話した壁に囲まれた街のことも頭の片隅にある。
私はそれまで勤めていた会社を辞め、これといった理由はないのだが、どこか図書館で勤めようと思いたつ。
そして、たまたまであるが何かに導かれるように、東北(福島県)の田舎の小さな図書館に職を得る。そこで、前の図書館長である老人との友好的だが奇妙な交流が始まる。その人は、現実にはすでにいない人であった。
そして、その図書館へは、現実社会にそぐわない少年が本を読みに頻繁に通ってきていた。その少年は、壁に囲まれた街(もう一つの世界)へ行こうと思うようになる。そして、少年は突然姿を消す。
3部は、壁に囲まれた街に残った(中年の)私のその後である。
壁の中の街で、私は元の街での図書館に通っていた少年を見つける。少年と話をしているうちに、私は元の世界に戻ろうと思う。
*地図を描き、穴に落ちてみる、物語の世界
物語のもう一つの世界である壁に囲まれた街は、ほとんど人影のない、死んだような世界である。時は動いているのだが時間がない、それゆえ街の時計には文字盤はあるが針がない。
不気味だが、感情がないので一概に不幸とは言えない、影のない世界。
現実の世界ともう一つの世界である壁に囲まれた街を行き来するということに、何を見出したらいいのか。
こちらの世界ではない、あちらの世界とは…と考えてみる。今住んでいるところとは異なる地図を描き、風景を想像する。そこには今抱いているのとは違った価値観、幸福感がある。その他、異なった些細な事例を思い描く。
小説、物語の醍醐味は、自分の思いもよらない世界に導かれることにある。
例えば、見過ごしがちだった影というものを認識するように、穴の奥、あるいは井戸の底における未知の世界への通路という村上春樹が作るメタファーの物語は、今までの小説とは違った水路を開発していて、思いもよらない異なった景色の世界へ誘い込む。
※ブログ→「穴の向こう側に行く旅、「騎士団長殺し」(2017-10-10)
https://blog.goo.ne.jp/ocadeau3/e/256a2ef466173e16bc44bf4d8b60e573
※ブログ→「図らずも、「穴」に落ちるという体験」(2017-11-27)
https://blog.goo.ne.jp/ocadeau3/m/201711
私は村上春樹の恋愛小説、例えば彼の作品で最も売れたとされる「ノルウェーの森」や「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」などは、どうして彼がこんな小説を書くのだろうと首を傾げたのだが、現実を超脱した長編小説の多くは、想像力と脳を躍動させる。
ありそうもない物語でも、奇想天外なSFや浅薄なファンタジーにならないのは、彼の比喩・暗喩を塗せた稀有な文体による、独自の突破力にあるといえるだろう。それゆえ、ありそうもない話として出発した物語が、いつしかあってもよさそうな話に運びさられるのである。
村上春樹は「あとがき」で、最後にホルヘ・ルイス・ボルヘスの言葉に倣い、次のように締めくくっている。
「要するに、真実というのはひとつの定まった静止の中にではなく、不断の移行=移動する相の中にある。それが物語というものの神髄ではあるまいか」













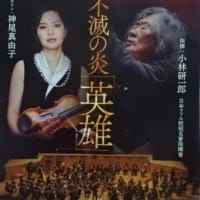

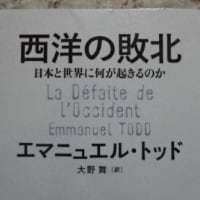









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます