
条件(第149回)
「一緒に楽しく食事をできるかどうか」が、結婚相手を決めるときに大事な条件だ、と、とある新書に書いてあった。「結婚する」ということは、これから先の生活を共にするということ。そして、楽しい生活を共に構築できるかどうかを確認するポイントとして、結婚前に確かめられるのは「食事」、ということだった。そう考えると、我々コンビはまったく問題がなかったように思う。むしろ問題がなさすぎて、コンビ活動開始と同時に食べ過ぎてふっくらしてしまった、という黒歴史すらあるほどだ。

「結婚」に関わらず、「ごはんを美味しく食べられる」かどうかは、その時々の生活を反映している気がする。腹ペコの場合は、特にそれが顕著だ。「最近ごはんが美味しいなあ」と感じるときは、楽しく暮らせている場合が多い。一方で、ちょっとくらいの難問なら「おいしいごはん」で乗り越えることもできる。できるだけ「美味しいごはん」を食べ続けられるように、4月からも「ほどほど」をテーマにがんばりたいと思う。










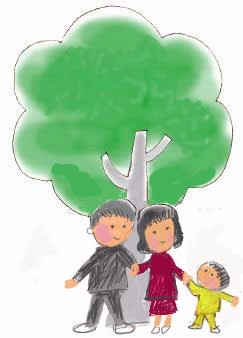 そばにいること(第148回)
そばにいること(第148回)
 公式裏ブログ「
公式裏ブログ「 自己肯定観1
自己肯定観1 啓蒙【第145回】
啓蒙【第145回】





