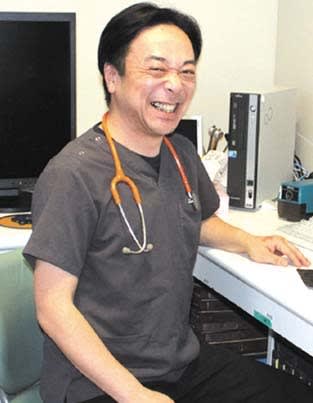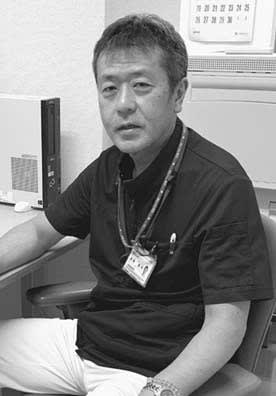第73号の特集は「病院薬剤師に聞くポリファーマシーとフォーミュラリー」。
高齢者は高血圧や糖尿病など、複数の慢性疾患が併発し、その病状は加齢とともに重症化する傾向にあることから服用する薬が多くなる。このような多剤服用患者のうち有害事象がすでに起こっていたり、起きやすい状態となっていることを「ポリファーマーシー」(多剤併用)と呼んでいる。
また、調剤医療費を抑えるための取り組みとして注目されているのが「フォーミュラリー」だ。フォーミュラリーとは医療機関において医学的妥当性や経済性などを踏まえて作成する医薬品の使用方針を意味するものとして用いられている。
ポリファーマーシーの取り組みを開始したり、フォーミュラリーを導入する病院は増加傾向にある。病院薬剤師を取材した。
国立病院機構函館病院(加藤元嗣院長)では入院患者の持参薬を用い多剤併用の状況について調査を行った。調査を担当した薬剤部製剤主任の鈴木秀峰さんに話を聞いた。鈴木さんは「不適切な服用による薬剤治療機会の喪失や特に高齢者における有害事象の発現の要因としてポリファーマシーが社会的問題となっていますが、この問題のあるポリファーマシーに医療者、特に薬剤師が介入し改善していくことが求められています」と話す。そこで同病院ではポリファーマシーへ積極的に介入するため、入院患者の処方薬剤の使用状況について調査を行った。 ポリファーマシーの患者は79人で、使用薬剤数中央値は8剤だった。処方施設数の平均は1・6施設。41・4%の患者が複数施設からの処方を受けていて、施設数が増えるのに従い使用薬剤平均値・ポリファーマシー率とも増加する傾向にあった。お薬手帳の使用による使用薬剤数の減少とポリファ
ーマシー率の改善はみられなかった。お薬手帳の持参率は68・1%。全国平均の使用率97・1%に比べ低かった。

国立病院機構函館病院薬剤部製剤主任の鈴木秀峰さん。
同病院には8人の薬剤師が在籍している。
40兆円を突破した医療費は高齢化を背景に2040年度まで増加し続けると予想されている。膨張する医療費とどう向き合うのか。医療費を見直す取り組みが欠かせないが、調剤医療費を抑えるための取り組みとして注目されているのが「フォーミュラリー」だ。フォーミュラリーとは医療機関において医学的妥当性や経済性などを踏まえて作成する医薬品の使用方針を意味するものとして用いられている。市立函館病院(森下清文院長)は昨年、院内フォーミュラリーを作成し、医薬品に関する院内の使用推奨基準を設けて実施している。同病院薬局薬局長の長浜谷耕司さんは「フォーミュラリーは院内における標準薬物治療を推進するために作成しました。フォーミュラリーを推進することによって、重症例や難治症例に対しての有効や新薬を使用できる環境を維持するため、既存治療の費用対効果を重視することに繋がるものです」と話す。

市立函館病院薬局薬局長の長浜谷耕司さん。
同病院には26人の薬剤師が在籍している。
患者が入院する際の薬剤師による持参薬のチェックは後発医薬品の使用促進等により、その重要性は高くなっている。函館五稜郭病院(中田智明病院長)薬剤科長で精神科専門薬剤師の佐野知子さんは「患者さんが入院予約で来院した際、手術や出血を伴う検査で入院する場合には、安全に手術や検査が行われるよう抗血小板薬、抗凝固薬服用の有無を確認し、休薬指導を行っています」と話す。
同病院では昨年9月から院外処方箋に臨床検査値とがん化学療法レジメン名(薬剤の投与量、投与時間、投与方法、投与順、投与日などが時系列的に記載されたもの)の印字を行っている。処方箋の左半分は従来の処方箋で、右半分が薬の副作用確認や薬の量を調整する際に必要な検査値などが記されている。2010年に岐阜大学医学部附属病院が外来処方箋に検査値を印字して以来、全国の病院で院外処方箋への検査値の記載やレジメン名の記載する取り組みが進められ、薬物療法の適正化・安全性が向上するとの報告が多数されているが、道南圏では実施している病院がなかった。

函館五稜郭病院薬剤科長の佐野知子さん。
「保険薬局への検査値情報提供で、有効で安全な薬物療法を提供します」。
函館新都市病院(原口浩一院長)の薬剤科科長で医薬品情報管理室室長の紺野昌洋さんは「高齢者は内臓疾患以外にも整形外科領域の疾患、さらには不眠症なども併発しているケースが多いです」と話す。
「入院する際には薬剤師が持参薬を確認しています。複数の疾患に対しては、それぞれの診療科の担当医師が個別に治療方針を決定していることから、相加的に薬剤が増えるケースが多いことはわかっていました。そこで入院患者の服用薬剤数を調べることにしました」。調査は2014年10月から15年9月までの1年間。「調査の対象者は1282人になりました。その結果、定期的に6剤以上を服用している、いわゆるポリファーマシー(多剤併用)状態にある患者さんは約57%にも上ることが明らかになりました。平均剤数は6・6種類です。ポリファーマシーは併用薬剤数がいくつ以上であればという明確な定義はありませんが、一般には4〜6剤以上を示す場合が多いです」。
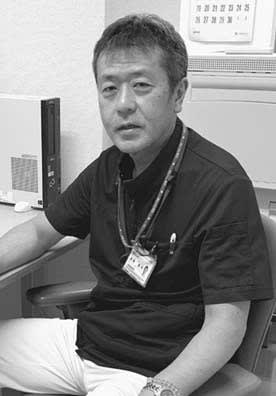
函館新都市病院薬剤科科長の紺野昌洋さん。
「患者さんの自宅での服薬(治療)の実態を知ることが大切です」。
函館渡辺病院(三上昭廣理事長)の薬剤部は患者への適切で安全な薬物療法の遂行を目的に、調剤業務では電子カルテ内処方支援や調剤監査システムを用いた調剤、がん化学療法および中心静脈栄養に用いる注射薬の無菌調製などを実施。病棟業務(薬剤師の病棟担当制)を通して、医師や看護師、作業療法士、理学療法士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉
士など様々な職種とのカンファレンスに参加し、連携を強化して退院支援も活発に行っている。薬剤部長の原田雅史さんは「ポリファーマシー(多剤併用)については、一般科と精神科では患者さんの状況は異なっています」と話す。
「一般科の高齢の患者さんはいくつもの疾患を同時に罹患するケースが多いことから、複数の医療機関・診療科を掛け持ちで受診し、その結果としてポリファーマシーになることが少なくありません。薬剤が多くなると、飲み忘れがあ
ったり、薬物有害事象発生の頻度も高くなります。入院時の持参薬は薬剤師がすべて確認していますが、6剤以上を服用していてポリファーマシー状態にある患者さんはいます。多剤服用によって有害事象が懸念される場合には、主治医と相談して薬の種類を減らすこともあります」。

函館渡辺病院薬剤部長の原田雅史さん。
同病院には14人の薬剤師が在籍している。