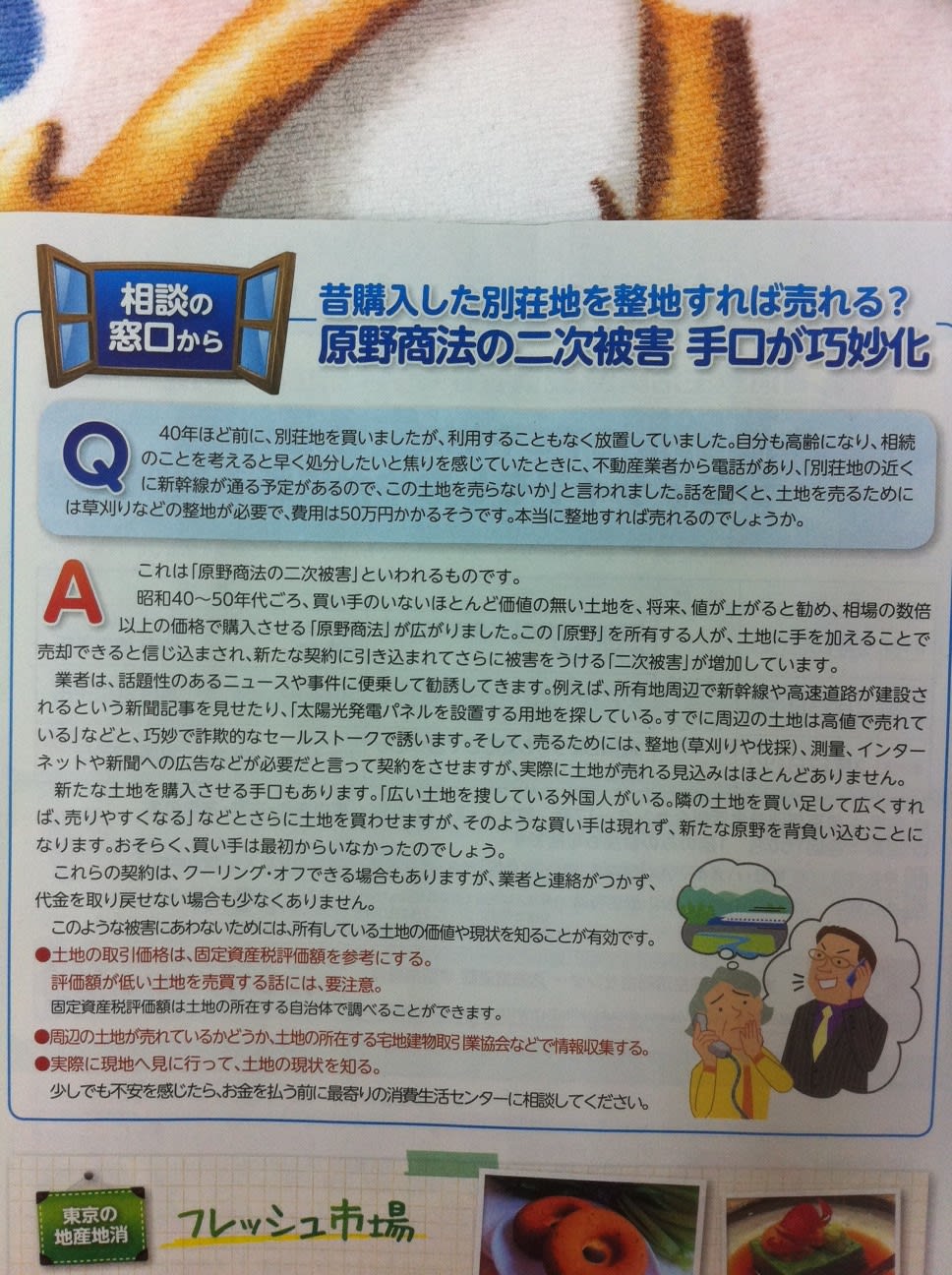以下、仮訳が公表されました。
*****内閣官房ホームページより*****
◾TPP協定の暫定仮訳の公表について(平成28年1月7日)
TPP協定については、未だTPP交渉参加12か国間で協定条文の法的精査の作業が行われていますが(平成28年1月7日現在)、同協定に対する御理解を一層深めていただくため、本体規定(附属書を除きます。)について法的精査中の条文案に基づいて作成した「暫定仮訳」を公表いたします。
この「暫定仮訳」は、法的精査の最終段階にある平成27年12月末時点の条文案に基づき作成されたものであり、最終的な条文に基づくものではありません。そのため、和訳の内容も暫定的な仮訳であることにつき御留意願います。
⇒ http://www.cas.go.jp/jp/tpp/naiyou/tpp_zanteikariyaku.html
◾TPP交渉参加国との間で作成する文書(暫定仮訳)の公表について(平成28年1月7日)TPP交渉参加国との間で作成する文書(暫定仮訳)について掲載しています。
TPP協定に関連して、次の二国間文書を作成する方向で相手国政府との間で調整が進められていますが(平成28年1月7日現在)、これらの文書に対する御理解を一層深めていただくため、調整中の文書案に基づいて作成した「暫定仮訳」を公表いたします。
この「暫定仮訳」は、平成27年12月末時点の調整中の案文に基づき作成されたものであり、最終的な文書に基づくものではありません。そのため、和訳の内容も暫定的な仮訳であることにつき御留意願います。
⇒ http://www.cas.go.jp/jp/tpp/naiyou/tpp_sl_zanteikariyaku.html
予想できたことではありますが。
働く除染作業員にしても、検診結果が悪く働くことが出来なければ、生活の糧を失う。
雇う側も、特に下請けの場合、働くひとがいないと仕事をとってこれない。
働く側も、雇う側も、虚偽の診断書を作成する力学が働くこととなる。
このことに歯止めをかけるのは、医師の役割、そして正義感をもった労働基準監督官。
*******************************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014081902000108.html
【社会】
除染作業員の診断書偽造 下請け「こちらで用意」
2014年8月19日 朝刊
被ばく労働と健康診断 原発や除染など被ばく労働をする作業員の健康を守るため、雇用会社は通常の健康診断のほかに、雇用時や就業後半年ごとなどに、通常の健康診断とは別に白血球数など詳細な健康診断を受けさせなくてはならないと法令で定められている。雇用会社は、詳細な診断結果を記した健康診断書(《除染等》電離放射線健康診断個人票)を保管し、所轄の労働基準監督署長に報告しなくてはならない。
東京電力福島第一原発事故に伴う国直轄の福島県田村市の除染作業で、下請け会社が作業員の健康診断書を偽造し、健康診断を受けさせずに作業をさせていたことが分かった。被ばくの危険がある労働は、詳細な血液検査などの健康診断が義務付けられている。法令に違反するだけでなく、作業員の健康への影響が懸念される。
下請け会社は、鹿島(東京都港区)を中心とした共同事業体の仕事を請け負っていた松栄ワークス(横浜市、破産手続き中)。鶴見労働基準監督署(神奈川県)は今年六月、同社が四十代の男性作業員を雇う際、健康診断を受けさせなかったなどとして是正の指導をした。
複数の作業員によると、二〇一二年八月、福島県郡山市の事務所などに集まった際、同社社員らから「健康診断を受けたことにしてください。診断日を(教えるので)覚えておいて」と言われ、田村市の山間部の除染に当たった。
三十代の男性は「誕生日に受けたことにして」と言われ、日付を書いたメモを渡された。事前に同社に健康診断が必要かと問い合わせた作業員らは、「必要ない」「こちらで用意します」と言われたという。
四十代の男性は同年十一月に事務所に呼ばれたとき、心当たりのない自分の健康診断書があるのを見つけた。一通は「健康診断書」と書かれ、医師名として女性の名前と印があったが病院名はなかった。もう一通は「除染等電離放射線健康診断個人票」と書かれ、福島県内に実在する病院名と医師名のスタンプなどが押されていた。
男性が医師に確かめると、スタンプも印鑑も病院で使われているものとは違い、数字の筆跡も医師のものではなかった。
医師は「うちの診断書ではない。私の名前をかたった偽物です」と断言したという。取材に対し、医師は「取材には応じられない。男性らに聞いてほしい」と話した。
松栄ワークスの社長には再三連絡を試みたが回答はなかった。元請けの鹿島は「作業員の健康診断の受診状況はコピーの提出を受けて確認していた。まさか偽造とは思わなかった」とコメントした。
発注者である環境省の担当者は「労働管理は各業者に対応してもらっている。労働者から相談があれば、元請けに確認を取らせ、改善要請する」と話した。
損害賠償額1円。
罰則付きの禁酒令の形で出された場合は、当然に違法だと思いますが、例えば、職員の不祥事をなくすためにやむにやまれず通知の形で出された場合の許容の限度がどのように判断されるか注目されます。
全体責任に賛否両論あります。
起きた不祥事が甚大な場合は、組織全体で、その問題点を考え直すことは必要であり、禁酒令という形は不適切であったとは言え、その考え直しているということを、公の組織であるならば、市民に示すこともまた求められます。
*****************************
http://www.asahi.com/articles/ASG773HNRG77TIPE00C.html
「禁酒令は人権侵害」 職員、福岡市を提訴
渡辺純子
2014年7月8日05時25分
福岡市の高島宗一郎市長が2年前に全職員の自宅外飲酒を禁じた「禁酒令」により人権を侵害されたとして、男性職員(49)が市を相手取り、損害賠償を求める訴訟を福岡地裁に起こした。禁酒令については県弁護士会が今年3月、「人権侵害にあたる違法な通知」として市に勧告している。
提訴は4日付。訴状によると、原告の男性は禁酒令に「単なる訓示規定以上の強制力があった」としたうえで、「業務時間外の飲酒は個人の自由のはず。憲法で保障された自由権を侵害され、多大な精神的苦痛を被(こうむ)った」と主張。損害額については、金銭的な評価が難しいとして慰謝料名目で1円としている。
男性職員は7日、朝日新聞の取材に対し、「禁酒令が違法なのか適法なのか、司法にはっきり結論を出してほしい」と話した。市側は「提訴された事実を承知していないので、コメントできる状況ではない」としている。
高島市長は職員の飲酒がらみの不祥事を防ごうと、2012年5月21日、全職員に1カ月間の自宅外禁酒を通知した。県弁護士会は今年3月、職員2人からの人権救済申し立てを受け、禁酒令について「公権力による私生活への干渉で、自由権を著しく侵害する重大な人権侵害」と認定。このような通知をしないよう市に勧告した。(渡辺純子)
刑事弁護の論点1 被告人が凶悪犯罪の真犯人であると考えられる場合の弁護について
1、誠実義務(弁護士法1条2項)、誠実協議義務、守秘義務
弁護士には、民法上の受任者としての善管注意義務(民法644条)を前提に、誠実義務(弁護士法1条2項)がある。刑事事件では、孤立し、防御に疲れ絶望した被告人を、依頼者の単なる「代理人」あるいは利益の代弁者に留まらず、「保護者」として、最善の弁護活動(弁護士職務基本規定46条)をすることが求められる。また、最善の弁護活動を保障するため、弁護人には全ての訴訟行為について包括的代理権が与えられている(大判昭和6年7月22日、最大決昭和63年2月17日)。
誠実義務を尽くすには、防御方針と弁護方針を立てるため率直で突っ込んだ協議の機会をもつ誠実協議義務と、信頼感の基礎となる、本人の明かした秘密の一切が、本人の承諾なくして第三者に対して漏れることがないという絶対の信頼をよせることができることが必須であり、そのための守秘義務(弁護士法23条)が欠かせない。
守秘義務が解除される「正当な理由」は、非常に限定的であり、依頼者につき殺人等の人身被害に関する重大犯罪の企図が明確で、その実行行為が差し迫っている旨の秘密を弁護士が知ったときに、これを防止するために秘密開示を行うような極限的な場合である。
2、消極的真実義務
真実義務の名の下に、弁護人に対して被告人に不利な方向での「真実」発見(刑訴法1条)に関する証拠や情報を自ら積極的に提出開示する義務を課すこと(積極的真実義務)は、弁護人は誠実義務と秘密保持義務を負っているのであり、否定される(職務基本規定5条、同規定82条1項)。
他方、弁護人は被告人の利益を擁護する目的に出た行為であっても、裁判所による真実発見を妨害するために、積極的に不利な証拠を隠滅したり、虚偽の証拠を提出するなどして事実を歪める行為をしてはならないという義務(消極的真実義務)を有する。例えば、不当、不正な手段で被告人に不利な証拠の提出を妨げたり、証拠を偽造、隠滅しない、あるいは偽証をさせたり虚偽証拠の提出をしないことである。
一方、裁判所の訴訟指揮や検察官の証拠調べ請求等に対して刑事訴訟法上の権利として意見を述べたり反対すること、証人に対して反対尋問することなどは弁護人としての本来の正当な任務の遂行であり、「真実発見を妨害する行為」などにはあたらない。また、検察官の主張する事実や、裁判所が判決によって認定する事実とは異なる事実の主張と立証(そのための証拠収集活動や調査活動を含む)を展開することも弁護人の本来的職務の遂行であるから、「事実を歪める行為」となるわけではない。
3、被告人による「真犯人」であることの告白への対応
被告人による「真犯人」の告白を、絶対的真実であるとは言えない。身代わり犯人であることもある。否認して争うことにより長期勾留あるいは保釈困難の結果を招くのではないかという恐怖ないし危惧が、やむなく有罪を認めると告白する場合もある。
4、全人的ケア
凶悪犯罪を犯した被告人大は、責任能力を有していたかどうかが疑われうることがある。精神鑑定が必要な場合があるかもしれないし、少なくとも精神科医師や心理士による心のケアが必要であった事案であると考える。弁護人は、それら適切なケアをできる体制をコーディネートする役割を担うと考える。
また、犯罪被害者のためにどのように償っていくべきか、残された家族とどのように接していけばよいか、残された家族の今後はどのようにしていくべきか等を、被告人と共に考えることも「保護者」として行うべきである。
以上
刑事弁護の論点2 被告人が凶悪犯罪の真犯人である等考えられて、国選弁護人として自己の良心に反する被告人の弁護をする場合について
1、決して行ってはならないこと
被告人の承諾が無いのに、弁護人の正義感やその他の個人的価値観を優先させて、有罪を前提とした弁護活動や、犯罪の成立を求める方向での弁護活動を行うことは許されない。
裁くのは裁判官であって、決して、弁護人ではない。
2、「控訴理由なし」と控訴趣意書に記載した控訴審弁護人Y(以下、「被告Y」という。)の不法行為責任(東京地判昭和38年11月28日)
控訴審からはじめて凶悪犯罪の被告人の国選弁護人として選任された被告Yは、もともと、弁護権の本質は、被告人の権利利益に対する不当な侵害を排除し、守ることにあると考えていた。
原審の訴訟記録9冊を閲覧しても原審の訴訟手続になんら不当な権利侵害が存在しない以上、控訴理由なき旨の控訴趣意書を提出しても、弁護権を行使しているとし、また、控訴理由を発見することができないのによい加減な控訴趣意書を作成することは弁護士としての良心の許すところではないので、結局控訴理由なき旨の控訴趣意書を提出せざるを得なかったと主張している。
裁判所は、事後審の性格を有する控訴審における国選弁護人の義務を①原審の訴訟記録の法定の調査義務(最小限の調査義務)、②例外的事実または刑の量定についての事情に関する訴訟記録外の法定の調査義務(少なくとも被告人の面接をすること)、③適当な控訴理由を発見することができなかった旨の法の定めのない告知義務、④被告人の名においてする控訴趣意書の作成について必要な技術的援助を惜しまないが、それ以上被告人の期待するごとき協力をすることができないことを告げて被告人の善処を求める法の定めのない義務の4つの作為義務があるとした。
その上で、本件では、裁判所は、被告Yがなしたことは①のみであり、②③④の作為義務が不履行であるのであるから過失があり、その過失によって被告人の控訴権が侵害され、結果、被告人は精神上の苦痛を受けた。その苦痛は、加害者に対して慰謝料の支払い義務を認めるに値する程度の損害と認定をした。
3、自己の良心に反する被告人の弁護人として、それでも、なすべきこと
被告人は、裁判が確定するまでは無罪と推定され、防御のために事実を争うための訴訟行為をなす権利が認められている。
弁護人が、被告人の展開する弁解弁明にそって検察官立証の矛盾や不備を指摘したり、法律上有利な主張が可能であればそれを用いて無罪の弁護をすることは、当然の職務であり許容される。
以上
第1 被告弁護士の倫理的義務違反について
1、被告弁護士は、倫理的義務に違反するか
ミネソタ州最高裁判所は、原告スポールディング側提起した損害賠償請求訴訟に対して、被告側の代理人となった弁護士(以下、「被告弁護士」という。)の倫理的義務に関して、「倫理や法的義務の規定は被告に不利な事実を原告又は原告の弁護士に知らせたり裁判所に通知することを要求していないが、当時の和解が大動脈瘤を考慮したものではないことが明確になった以上、裁判所は和解を無効とすることができる。」と判示している。(和解は、無効であるということであるが、そのまま訴訟が係属して判決が出された場合は、その判決まで無効ということまでいうのかは明らかではない。また、和解がなされたときは、スポールディングは未成年であった。もし、成人であったとしたら、同様の結論であったかも不明である。)
上記判示は、倫理義務違反はないとしているが、日本の弁護士倫理の考え方に沿うのであれば、被告弁護士は、倫理的義務に反していたと私は考える。
以下、その理由を考えて行く。
2、弁護士の誠実義務
弁護士は、誠実義務を有している。弁護士法1条が、第1項で、弁護士の使命が基本的人権の擁護と、社会正義の実現にあることを宣言した上で、第2項で「弁護士は前項の使命に基づき、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない」と定められている。「弁護士倫理」(H6年制定、H17年まで弁護士の倫理の基準として機能)第4条でも「弁護士は、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行う」と定め、この規定は、現行の弁護士職務基本規定5条「弁護士は真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。」ということに引き継がれている。
3、被告弁護士が、倫理的義務に反することの理由について
社会正義の実現に使命があるのであれば、被告弁護士は、スポールディングに大動脈乖離があることを被告らに説明し、スポールディングのわかっている限りの病状に合わせた和解の評価をうけられるように仕向ける必要があった。それが、保険会社の一社にのみ大動脈乖離の事実を伝えたに終わっている。スポールディング自身が大動脈乖離のことを知る前に、大動脈が破裂し、死に至ることもあり得た。その場合は、被告弁護士が責められるかどうかは別にしても、大動脈乖離の情報の秘匿が、スポールディングの早期発見のチャンスを奪っていることは確かである。本当に情報の秘匿が許されるのであろうか。
さて、短期的には、保険会社は、大動脈乖離の症状をいれずにスポールディングに和解金を払うことになり、当初は、払う額自体は少なく抑えることができたであろうが、長期的には、和解が無効とされたことで、一度で和解や裁判が済むべき所、再度1審裁判所に差し戻されたのであり、時間的にも大きなロスを被ることになってしまった。
原告側が、原告弁護士も含め、大動脈乖離の情報を得るべく証拠開示をもとめることが出来たのにしないことを奇貨として、情報を秘匿せしめた被告弁護士の行動は、「代理人的性格」に重きを置くがあまり、「司法機関的性格」を忘れ、倫理的義務違反をなしたと言えるのではないか。
第2 社会は、被告弁護士のような弁護士を求めているのか
Spaulding caseでは、被告弁護士は、保険会社の費用で賄われ、弁護士の選任自体も保険会社が行っていた。
保険会社は、たとえ、弁護士倫理義務違反ぎりぎりの行動をしたとしても、被告弁護士のような、実は、短期的にでも支払う保険料を少なくすることに重点を置く弁護士を求めているのかもしれない。
いや、食うか食われるかの実社会において、被告弁護士のようなタイプのほうが、弁護士として企業にとっては望まれるのかもしれない。
それは、なぜなのだろうか。3つの要因が考えられると思う。
1、悪貨は良貨を駆逐する原理が働くため
正義や社会の公正をいくら声高に叫んだとしても、ひとや企業は、1円でも多くの利益をもたらす弁護士を良いと考えがちである。
すると、オファーも断然、被告弁護士のようなタイプに集まる。
弁護士職業も、ボランティアではなのだから、収益を上げる必要がある。それでないと、事務所費用や事務員費用が賄えず、結局、自らの事業を回せないこととなる。
大衆受けのするほうに、弁護士が流れ、ますます、社会正義や公正を目指すひとの職が減る流れは、止めようにも止まらない。
社会正義や公正に反する弁護士活動のなされることが、尊重される社会の機運や民度を挙げて行く必要がある。そのためにも、社会に対し、憲法学や法律学の基礎的な知識や法的思考方法の基本を、情報発信する不断の努力が必要であると考える。
2、倫理は、教育で芽生えさせるには限界があるため
もともと、弁護士倫理を学んでいない弁護士が、倫理に添った活動ができないし、さらに、たとえ、倫理を学んでも、知識の様に学んだからすぐ使えるものでもない。
倫理は、そのひとが生まれてからの成育環境、家庭環境、友達関係、先生との出会い、宗教観などで育まれるものである。付け焼き刀で身に着くものでは決してない。
かと言って、できないからと言って、放置してよい理由にもならない。
教育には一定の限界があるし、倫理を規定においても倫理と法律がなじまない部分もあって、法的拘束力で割り切ることができない部分が残ることとなる。
弁護士ひとりひとりのまさに、倫理観に期待するほかない。
3、党派性(「代理人的性格」)に偏重しすぎるため
依頼者の依頼に応え、依頼者の利益を最大化したいがために、倫理をも忘れて活動をすることも考えられる。
公判の攻防がし烈になればなるほど、依頼者側に有利になるように行動したくなるのがひとの嵯峨であろう。民事訴訟法2条信義誠実義務違反、弁護士職務基本規定5条真実尊重義務違反、同75条偽証のそそのかし違反となるところであるものの、証言予定者が不利な証言をしようとしている場合に、より有利な証言にかえるようにアドバイスすることもありうる話である。
しかし、弁護士は、弁護士法1条1項「公益的役割」(公益性)及び「当事者その他の関係人の依頼等によって法律事務を行うことを職務とする」(同3条1項)という「当事者の代理人としての役割」(党派性)の一見矛盾する両者のバランスを取らねばならない。すなわち、「当事者の代理人としての役割」の限界を画すものが「公益的役割」である。
従って、弁護士は、依頼者との信頼関係に基づく善管注意義務により、最大限の努力を傾注して依頼者の権利実現または利益擁護に邁進すべきだが、そのために社会的正義その他の規範に違反しまたは公益ないし公的価値に抵触することは許されない(加藤新太郎『弁護士役割論』)。弁護士として、守るべき一線を、個々の具体的なケースにおいて自ら明確にして行動する必要があるであろう。
第3 Spaulding caseでの医療倫理について
私は、医師のであり、弁護士倫理を考えることで、医師の倫理をあらためて考え直す機会を得ている。
Spaulding caseに出てくる医師の行動は、医療倫理の観点から、どうあるべきであったか。
医学分野においては、医師には、病気を治すこと(cure)だけでなく、患者のQOLを高め、その患者が社会生活を豊かに送れることができるようになるという、全人的医療(care)を他職種連携の下に達成していくことが、常に目標としてある。
しかし、残念ながら、Spaulding caseでいうのであれば、被告側の医師の行動は、あるべきケアの真逆であった。すなわち、原告の大動脈乖離を発見したのであれば、破裂すると生命の危険を来す重大疾患であるのだから、その治療を受けさせるように行動すべきであった。自分の役割は、被告側に依頼された診断をしたことで終えたとして、患者を放置することは医師として決して許されないと考える。
以上
企業の上層部の部長が、不正をして売り上げが上がるようにしていたことを、4年間見抜くことができずにいたことについて、代表取締役に内部統制システム構築違反があるか。
一審、高裁と、内部統制システム構築義務違反がありとの判決が出されました。
この最高裁判決で、破棄自判して、内部統制システム構築義務違反はないとされ、会社側が勝訴しました。
一審、高裁と、会社の内部統制システムは、上層部が企図すれば容易に不正行為が行われるような欠陥があったものと認定。
最高裁は、通常予想される不正行為を防止しうる程度の管理体制は構築されており、また、以前に同様の不正行為が起こっていなかった以上、問題の部長らの不正を予見すべき特段の事情も認められないと判示。
<最高裁判決の該当部分>
「しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
前記事実関係によれば,本件不正行為当時,上告人は,
①職務分掌規定等を定めて事業部門と財務部門を分離し,
②C事業部について,営業部とは別に注文書や検収書の形式面の確認を担当するBM課及びソフトの稼働確認を担当するCR部を設置し,それらのチェックを経て財務部に売上報告がされる体制を整え,
③監査法人との間で監査契約を締結し,当該監査法人及び上告人の財務部が,それぞれ定期的に,販売会社あてに売掛金残高確認書の用紙を郵送し,その返送を受ける方法で売掛金残高を確認することとしていた
というのであるから,
上告人は,通常想定される架空売上げの計上等の不正行為を防止し得る程度の管理体制は整えていたものということができる。
そして,本件不正行為は,C事業部の部長がその部下である営業担当者数名と共謀して,販売会社の偽造印を用いて注文書等を偽造し,BM課の担当者を欺いて財務部に架空の売上報告をさせたというもので,
営業社員らが言葉巧みに販売会社の担当者を欺いて,監査法人及び財務部が販売会社あてに郵送した売掛金残高確認書の用紙を未開封のまま回収し,
金額を記入して偽造印を押捺した同用紙を監査法人又は財務部に送付し,
見掛け上は上告人の売掛金額と販売会社の買掛金額が一致するように巧妙に偽装するという,
通常容易に想定し難い方法によるものであったということができる。
また,本件以前に同様の手法による不正行為が行われたことがあったなど,上告人の代表取締役であるAにおいて本件不正行為の発生を予見すべきであったという特別な事情も見当たらない。
さらに,前記事実関係によれば,売掛金債権の回収遅延につきBらが挙げていた理由は合理的なもので,販売会社との間で過去に紛争が生じたことがなく,監査法人も上告人の財務諸表につき適正であるとの意見を表明していたというのであるから,財務部が,Bらによる巧妙な偽装工作の結果,販売会社から適正な売掛金残高確認書を受領しているものと認識し,直接販売会社に売掛金債権の存在等を確認しなかったとしても,財務部におけるリスク管理体制が機能していなかったということはできない。
以上によれば,上告人の代表取締役であるAに,Bらによる本件不正行為を防止するためのリスク管理体制を構築すべき義務に違反した過失があるということはできない。」
なお、破棄されることととなった、原審及び第1審の判決理由。
<最高裁判決の該当部分>
「原審は,次のとおり判断して,被上告人の請求を一部認容すべきものとした。
(1) 本件不正行為当時,
C事業部は幅広い業務を分掌し,BM課及びCR部が同事業部に直属しているなど,上告人の組織体制及び本件事務手続にはBらが企図すれば容易に本件不正行為を行い得るリスクが内在していたにもかかわらず,
上告人の代表取締役であるAは,上記リスクが現実化する可能性を予見せず,
組織体制や本件事務手続を改変するなどの対策を講じなかった。
また,
財務部は,長期間未回収となっている売掛金債権について,販売会社に直接売掛金債権の存在や遅延理由を確認すべきであったのにこれを怠り,
本件不正行為の発覚の遅れを招いたもので,
このことは,
Aが財務部によるリスク管理体制を機能させていなかったことを意味する。
したがって,Aには,上告人の代表取締役として適切なリスク管理体制を構築すべき義務を怠った過失がある。
(2) 上告人の代表取締役であるAの上記過失による不法行為は,
上告人の職務を行うについてされたものであるから,
上告人は,会社法350条に基づき,被上告人に生じた損害を賠償すべき責任を負う。」
*****************************************************************
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090709152854.pdf
主文
原判決を破棄し,第1審判決中上告人敗訴部分を取り消
す。
前項の部分につき,被上告人の請求を棄却する。
訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
理由
上告代理人上甲悌二,同清水良寛の上告受理申立て理由第3ないし第7について
1 本件は,上告人の従業員らが営業成績を上げる目的で架空の売上げを計上し
たため有価証券報告書に不実の記載がされ,その後同事実が公表されて上告人の株
価が下落したことについて,公表前に上告人の株式を取得した被上告人が,上告人
の代表取締役に従業員らの不正行為を防止するためのリスク管理体制を構築すべき
義務に違反した過失があり,その結果被上告人が損害を被ったなどと主張して,上
告人に対し,会社法350条に基づき損害賠償を請求する事案である。被上告人
は,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)261条3項,78条2
項が準用する民法(平成18年法律第50号による改正前のもの)44条1項に基
づく請求をするが,会社法の制定により,同法にこれと同内容の規定である350
条が設けられ,同法の施行前に生じた事項にも適用されるものとされた(会社法附
則2項)ので,同法施行後は同法350条に基づく請求をするものと解される。
2 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1) 上告人は,ソフトウェアの開発及び販売等を業とする株式会社であり,平
成15年2月に東京証券取引所(以下「東証」という。)第2部に上場した。A
は,上告人設立以降現在まで上告人の代表取締役の地位にある。
- 2 -
(2) 被上告人は,平成16年9月13日及び翌14日,証券会社を通じて上告
人の株式を取得した者である。
(3) 上告人の事業は,注文に応じてソフトウェアの受託開発等を行うソフトウ
ェア事業と大学向けの事務ソフト等の既製品を開発し販売するパッケージ事業に大
別され,パッケージ事業本部にはC事業部が設置されている。
(4) Bは,平成12年4月に上告人のC事業部の部長に就任した。当時,C事
業部には,Bが部長を兼務する営業部のほか,注文書や検収書の形式面の確認を担
当するBM課(ビジネスマネージメント課)及び事務ソフトの稼働の確認を担当す
るCR部(カスタマーリレーション部)が設置されていた。また,当時の上告人の
職務分掌規定によれば,財務部の分掌業務は,資金の調達と運用・管理,債権債務
の管理等とされ,C事業部の分掌業務は,営業活動,営業事務(受注管理事務,債
権管理事務,売掛金の管理及び不良債権に対する処理方針の決定を含む。)等とさ
れていた。
(5) 上告人のパッケージ事業は,上告人が,顧客であるD株式会社ほか1社
(以下,2社を単に「販売会社」という。)に事務ソフト等の製品を販売し,販売
会社がエンドユーザーである大学等に更にこれを販売するというものである。平成
12年当時のパッケージ事業における事務手続(以下「本件事務手続」という。)
の流れは,以下のとおりであった。
アC事業部の営業担当者が販売会社と交渉し,合意に至ると販売会社が注文書
を営業担当者に交付する。営業担当者は,注文書をBM課に送付し,同課は受注処
理を行った上,営業担当者を通じて販売会社に検収を依頼する。
イCR部の担当者が,販売会社の担当者及びエンドユーザーである大学の関係
- 3 -
者と共に,納品された事務ソフトの検収を行う。
ウBM課は,販売会社から検収書を受領した上,売上処理を行い,上告人の財
務部に売上報告をする。財務部は,BM課から受領した注文書,検収書等を確認
し,これを売上げとして計上する。
(6) Bは,高い業績を達成し続けて自らの立場を維持するため,平成12年9
月以降,C事業部の営業担当者である部下数名(以下「営業社員ら」という。)に
対し,後日正規の注文が獲得できる可能性の高い取引案件について,正式な注文が
ない段階で注文書を偽造するなどして実際に注文があったかのように装い,売上げ
として架空計上する扱い(以下「本件不正行為」という。)をするよう指示した。
Bの指示を受けて行われた本件不正行為の手法は,次のとおりであった。
ア営業社員らは,偽造印を用いて販売会社名義の注文書を偽造し,BM課に送
付した。
イBM課では,偽造に気付かず受注処理を行って検収依頼書を作成し,営業社
員らに交付した。しかし,検収依頼書は販売会社に渡ることはなく,営業社員らに
よって検収済みとされたように偽造され,BM課に返送された。実際には大学に対
して製品は納品されておらず,CR部担当者によるシステムの稼働の確認もされて
いなかったが,B及び営業社員ら(以下「Bら」という。)は,納品及び稼働確認
がされているかのような資料を作成した。
ウBM課では,検収書の偽造に気付かず売上処理を行い,財務部に売上げの報
告をした。財務部は,偽造された注文書及び検収書に基づき売上げを計上した。
エ財務部は,毎年9月の中間期末時点で,売掛金残高確認書の用紙を販売会社
に郵送し,確認の上返送するよう求めていた。また,毎年3月の期末時点には,上
- 4 -
告人との間で監査契約を締結していた監査法人も,売掛金残高確認書の用紙を販売
会社に郵送し,確認の上返送するよう求めていた。ところが,営業社員らは,Bの
指示を受けて,販売会社の担当者に対し,上告人等から封書が郵送される可能性が
あるが,送付ミスであるから引き取りにいくまで開封せずに持っていてほしいなど
と申し向け,これを販売会社から回収した上,用紙に金額等を記入し,販売会社の
偽造印を押捺するなどして販売会社が売掛金の残高を確認したかのように偽装し,
財務部又は監査法人に送付していた。財務部及び監査法人は,偽造された売掛金残
高確認書において上告人の売掛金額と販売会社の買掛金額が一致していたため,架
空売上げによる債権を正常債権と認識していた。
(7) Bらは,当初は契約に至る可能性が高い案件のみを本件不正行為の対象と
していたが,次第に可能性が低い案件についても手を付けざるを得なくなり,売掛
金の滞留残高は増大していった。
(8) 財務部は,回収予定日を過ぎた債権につき,C事業部から売掛金滞留残高
報告書を提出させていたが,Bらは,回収遅延の理由として,大学においてシステ
ム全体の稼働が延期されたことや,大学における予算獲得の失敗及び大学は単年度
予算主義であるため支払が期末に集中する傾向が強いことなどを挙げていた。財務
部は,これらの理由が合理的であると考え,また,販売会社との間で過去に紛争が
生じたことがなく,売掛金残高確認書も受領していると認識していたことから,売
掛金債権の存在について特に疑念を抱かず,直接販売会社に照会等をすることはし
なかった。また,監査法人も,平成16年3月期までの上告人の財務諸表等につき
適正であるとの意見を表明していた。
(9) 上告人は,監査法人から売掛金残高の早期回収に向けた経営努力が必要で
- 5 -
ある旨の指摘を受け,代表取締役であるAが販売会社と売掛金残高について話をし
たところ,双方の認識に相違があることが明らかになり,平成16年12月ころ,
本件不正行為が発覚した。
(10) 上告人は,平成17年2月3日付けでBを懲戒解雇処分とし,その後刑事
告発した。Bは,有印私文書偽造・同行使の罪で起訴され,有罪判決を受けた。
(11) 上告人は,平成17年2月10日,複数年度にわたりBらによる本件不正
行為が行われていたこと,それにより同16年9月ころまでの上告人のパッケージ
事業の売上高に影響が生ずること,そのためパッケージ事業については多額の損失
計上を余儀なくされるが,上告人グループの売上高の約80%を占めるソフトウェ
ア事業については影響はないことなどを公表し,同17年3月期の業績予想を修正
した。東証は,上告人から過去の有価証券報告書を訂正する旨の報告を受け,同年
2月10日,上場廃止基準(財務諸表に虚偽記載があること)に抵触するおそれが
あるとして,上告人の株式を監理ポストに割り当てることとした。これらの事実が
新聞報道された後,上告人の株価は大幅に下落した。
3 原審は,次のとおり判断して,被上告人の請求を一部認容すべきものとし
た。
(1) 本件不正行為当時,C事業部は幅広い業務を分掌し,BM課及びCR部が
同事業部に直属しているなど,上告人の組織体制及び本件事務手続にはBらが企図
すれば容易に本件不正行為を行い得るリスクが内在していたにもかかわらず,上告
人の代表取締役であるAは,上記リスクが現実化する可能性を予見せず,組織体制
や本件事務手続を改変するなどの対策を講じなかった。また,財務部は,長期間未
回収となっている売掛金債権について,販売会社に直接売掛金債権の存在や遅延理
- 6 -
由を確認すべきであったのにこれを怠り,本件不正行為の発覚の遅れを招いたもの
で,このことは,Aが財務部によるリスク管理体制を機能させていなかったことを
意味する。したがって,Aには,上告人の代表取締役として適切なリスク管理体制
を構築すべき義務を怠った過失がある。
(2) 上告人の代表取締役であるAの上記過失による不法行為は,上告人の職務
を行うについてされたものであるから,上告人は,会社法350条に基づき,被上
告人に生じた損害を賠償すべき責任を負う。
4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
前記事実関係によれば,本件不正行為当時,上告人は,①職務分掌規定等を定め
て事業部門と財務部門を分離し,②C事業部について,営業部とは別に注文書や検
収書の形式面の確認を担当するBM課及びソフトの稼働確認を担当するCR部を設
置し,それらのチェックを経て財務部に売上報告がされる体制を整え,③監査法人
との間で監査契約を締結し,当該監査法人及び上告人の財務部が,それぞれ定期的
に,販売会社あてに売掛金残高確認書の用紙を郵送し,その返送を受ける方法で売
掛金残高を確認することとしていたというのであるから,上告人は,通常想定され
る架空売上げの計上等の不正行為を防止し得る程度の管理体制は整えていたものと
いうことができる。そして,本件不正行為は,C事業部の部長がその部下である営
業担当者数名と共謀して,販売会社の偽造印を用いて注文書等を偽造し,BM課の
担当者を欺いて財務部に架空の売上報告をさせたというもので,営業社員らが言葉
巧みに販売会社の担当者を欺いて,監査法人及び財務部が販売会社あてに郵送した
売掛金残高確認書の用紙を未開封のまま回収し,金額を記入して偽造印を押捺した
- 7 -
同用紙を監査法人又は財務部に送付し,見掛け上は上告人の売掛金額と販売会社の
買掛金額が一致するように巧妙に偽装するという,通常容易に想定し難い方法によ
るものであったということができる。
また,本件以前に同様の手法による不正行為が行われたことがあったなど,上告
人の代表取締役であるAにおいて本件不正行為の発生を予見すべきであったという
特別な事情も見当たらない。
さらに,前記事実関係によれば,売掛金債権の回収遅延につきBらが挙げていた
理由は合理的なもので,販売会社との間で過去に紛争が生じたことがなく,監査法
人も上告人の財務諸表につき適正であるとの意見を表明していたというのであるか
ら,財務部が,Bらによる巧妙な偽装工作の結果,販売会社から適正な売掛金残高
確認書を受領しているものと認識し,直接販売会社に売掛金債権の存在等を確認し
なかったとしても,財務部におけるリスク管理体制が機能していなかったというこ
とはできない。
以上によれば,上告人の代表取締役であるAに,Bらによる本件不正行為を防止
するためのリスク管理体制を構築すべき義務に違反した過失があるということはで
きない。
5 以上と異なる原審の判断には判決の結論に影響を及ぼすことが明らかな法令
の違反がある。論旨は理由があり,原判決は,その余の点につき判断するまでもな
く,破棄を免れない。そして,以上説示したところによれば,被上告人の上告人に
対する請求は理由がないから,第1審判決中これを認容した部分を取り消し,同部
分につき被上告人の請求を棄却すべきである。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
- 8 -
(裁判長裁判官甲斐中辰夫裁判官涌井紀夫裁判官宮川光治裁判官
櫻井龍子裁判官金築誠志)
1、経営判断の原則とは
経営判断の原則(以下、「同原則」という。)とは、取締役・執行役の行為の結果として会社に損害が生じたような場合において、任務懈怠の有無を判断する際に、裁判所は、経営判断には、事後的に介入しないというルールをいう。
2、同原則の必要性
同原則が必要とされる理由は、企業経営にはリスクが伴い、むしろ、リスクのある事業を行うことにこそ株式会社という制度の役割であり、そのような株式会社の活動を通じて資本主義経済が発展することから、経営判断への事後的な介入が容易に行われれば、そのような株式会社の存在価値が損なわれる可能性があることによる。また、裁判官や一般の株主は、経営判断に関して、経営者よりも優れた能力を有するともいえないことによる。
3、同原則に関して、取締役の善管注意義務違反の有無の判断における基準
取締役の業務についての善管注意義務違反又は忠実義務違反の有無の判断に当たっては、
1)取締役によって当該行為がなされた当時における会社の状況及び会社を取り巻く社会、経済、文化等の情勢の下において、
2)当該会社の属する業界における通常の経営者の有すべき知見及び経験を基準として、
3)前提としての事実認識に不注意な誤りがなかったか否か
及び
4)その事実に基づく行為の選択決定に不合理がなかったか否か
という観点から、当該行為をすることが著しく不合理と評価されるか否かによるべきである(東京地判平成16・9・28)。
従って、善管注意義務に違反しないとされるためには、
①当該行為が経営判断上の専門的判断に委ねられた事項についてのものであること、
②意思決定の過程に著しい不合理性がないこと、
③意思決定の内容に著しい不合理性がないこと
の3つが要求される(最判平成22・7・15)こととなる。
実際の判例:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100715143943.pdf
<東京高等裁判所H20.10.29の判断>
原審は,上告人らの善管注意義務違反の有無について次のとおり判断して,
上告人らに対し参加人に連帯して1億2640万円及び遅延損害金の支払を命ずる
限度で,被上告人の請求を認容した。
〇本件買取価格は,Aの株式1株当たりの払込金額が5万円であったことから,これと同額に設定されたものであり,それより低い額では買取りが円滑に進まないといえるか否かについて十分な調査,検討等がされていないこと,
〇既にAの発行済株式の総数の3分の2以上の株式を保有していた参加人において,当時の状態を維持した場合と比較してAを完全子会社とすることが経営上どの程度有益な効果を生むかという観点から検討が十分にされていないこと,
〇本件買取価格の設定当時のAの株式の1株当たりの価値は株式交換のために算定された評価額等から1万円であったと認めるのが相当であること
等からすれば,本件買取価格の設定には合理的な根拠又は理由を見出すことはできず,上告人らは,取締役としての善管注意義務に違反して,その任務を怠ったものである。
<上記高裁判断を覆した、最高裁H22.7.15の判断>
しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は次のとおりである。
前記事実関係によれば,本件取引は,AをBに合併して不動産賃貸管理等の事業
を担わせるという参加人のグループの事業再編計画の一環として,Aを参加人の完
全子会社とする目的で行われたものであるところ,このような事業再編計画の策定
は,完全子会社とすることのメリットの評価を含め,将来予測にわたる経営上の専
門的判断にゆだねられていると解される。
そして,この場合における株式取得の方法や価格についても,
取締役において,株式の評価額のほか,取得の必要性,参加人の財務上の負担,株式の取得を円滑に進める必要性の程度等をも
総合考慮して決定することができ,
その決定の過程,内容に著しく不合理な点がない限り,取締役としての善管注意義務に違反するものではないと解すべきである。
以上の見地からすると,
〇参加人がAの株式を任意の合意に基づいて買い取ることは,円滑に株式取得を進める方法として合理性があるというべきであるし,
〇その買取価格についても,Aの設立から5年が経過しているにすぎないことからすれば,払込金額である5万円を基準とすることには,一般的にみて相応の合理性がないわけではなく,
〇参加人以外のAの株主には参加人が事業の遂行上重要であると考えていた加盟店等が含まれており,買取りを円満に進めてそれらの加盟店等との友好関係を維持することが今後における参加人及びその傘下のグループ企業各社の事業遂行のために有益であったことや,非上場株式であるAの株式の評価額には相当の幅があり,事業再編の効果によるAの企業価値の増加も期待できたことからすれば,株式交換に備えて算定されたAの株式の評価額や実際の交換比率が前記のようなものであったとしても,買取価格を1株当たり5万円と決定したことが著しく不合理であるとはいい難い。
〇そして,本件決定に至る過程においては,参加人及びその傘下のグループ企業各社の全般的な経営方針等を協議する機関である経営会議において検討され,弁護士の意見も聴取されるなどの手続が履践されているのであって,その決定過程にも,何ら不合理な点は見当たらない。
以上によれば,
本件決定についての上告人らの判断は,参加人の取締役の判断として著しく不合理なものということはできないから,上告人らが,参加人の取締役としての善管注意義務に違反したということはできない。
5 以上と異なる見解の下に,本件決定についての上告人らの判断に参加人の取
締役としての善管注意義務違反があるとして被上告人の請求を一部認容した原審の
判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があ
り,原判決中,上告人ら敗訴部分は破棄を免れない。そして,以上説示したところ
によれば,同部分に関する被上告人の請求は理由がないから,同部分について被上
告人の請求を棄却した第1審判決は正当であり,同部分についての被上告人の控訴
は棄却すべきである。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
*********最高裁ホームページより**************************
主文
原判決中,上告人ら敗訴部分を破棄する。
前項の部分につき,被上告人の控訴を棄却する。
控訴費用,上告費用及び参加によって生じた訴訟費用
は,被上告人の負担とする。
理由
上告代理人手塚裕之ほかの上告受理申立て理由(ただし,排除されたものを除
く。)について
1 本件は,上告補助参加人(以下「参加人」という。)の株主である被上告人
が,参加人の取締役である上告人らに対し,上告人らが,A(以下「A」とい
う。)の株式を1株当たり5万円の価格で参加人が買い取る旨の決定をしたことに
つき,取締役としての善管注意義務違反があり,会社法423条1項により参加人
に対する損害賠償責任を負うと主張して,同法847条に基づき,参加人に連帯し
て1億3004万0320円及び遅延損害金を支払うことを求める株主代表訴訟で
ある。
2 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1) 参加人は,Aを含む傘下の子会社等をグループ企業として,不動産賃貸あ
っせんのフランチャイズ事業等を展開し,平成18年9月期時点で,連結ベースで
総資産約1038億円,売上高約497億円及び経常利益約43億円の経営規模を
有していた。
(2) Aは,主として,備品付きマンスリーマンション事業を行うことなどを目
的として平成13年に設立された会社であり,設立時の株式の払込金額は5万円で
あった。Aの株式は,発行済株式の総数9940株の約66.7%に相当する66
30株を参加人が保有していたが,参加人が,上記(1)の事業の遂行上重要である
と考えていた上記フランチャイズ事業の加盟店等(以下「加盟店等」という。)も
これを引き受け,保有していた。
(3) 参加人は,機動的なグループ経営を図り,グループの競争力の強化を実現
するため,完全子会社に主要事業を担わせ,参加人を持株会社とする事業再編計画
を策定し,平成18年5月ころ,同計画に沿って,関連会社の統合,再編を進めて
いた。Aについては,参加人の完全子会社であるB(以下「B」という。)に合併
して不動産賃貸管理業務等を含む事業を担わせることが計画された。
(4) 参加人には,社長の業務執行を補佐するための諮問機関として,役付取締
役全員によって構成され,参加人及びその傘下のグループ各社の全般的な経営方針
等を協議する経営会議が設置されている。平成18年5月11日に開催された経営
会議には,上告人Y が代表取締役1 として,上告人Y2及び同Y3が取締役として出
席し,AとBとの合併に関する議題が協議された。そして,その席上,① 参加人
の重要な子会社であるBは,完全子会社である必要があり,そのためには,AもB
との合併前に完全子会社とする必要があること,② Aを完全子会社とする方法
は,参加人の円滑な事業遂行を図る観点から,株式交換ではなく,可能な限り任意
の合意に基づく買取りを実施すべきであること,③ その場合の買取価格は払込金
額である5万円が適当であることなどが提案された。参加人から,上記提案につき
助言を求められた弁護士は,基本的に経営判断の問題であり法的な問題はないこ
と,任意の買取りにおける価格設定は必要性とバランスの問題であり,合計金額も
それほど高額ではないから,Aの株主である重要な加盟店等との関係を良好に保つ
- 3 -
必要性があるのであれば許容範囲である旨の意見を述べた。
協議の結果,上記提案のとおり1株当たり5万円の買取価格(以下「本件買取価
格」という。)でAの株式の買取りを実施することが決定され(以下「本件決定」
という。),併せて,当時参加人との間で紛争が生じており買取りに応じないこと
が予想された株主については,株式交換の手続が必要となる旨の説明がされ,了承
された。
(5) 参加人は,Aを完全子会社とするために実施を予定していた株式交換に備
え,監査法人等2社に株式交換比率の算定を依頼した。提出された交換比率算定書
の一つにおいては,Aの1株当たりの株式評価額が9709円とされ,他の一つに
おいては,類似会社比較法による1株当たりの株主資本価値が6561円ないし1
万9090円とされた。
(6) 参加人は,平成18年6月9日ころから同月29日までの間に,本件決定
に基づき,参加人以外のAの株主のうち,買取りに応じなかった1社を除く株主か
ら,株式3160株を1株当たり5万円,代金総額1億5800万円で買い取った
(以下,これらの買取りを「本件取引」と総称する。)。
(7) その後,参加人とAとの間で株式交換契約が締結され,Aの株式1株につ
いて,参加人の株式0.192株の割合をもって割当交付するものとされた。
3 原審は,上告人らの善管注意義務違反の有無について次のとおり判断して,
上告人らに対し参加人に連帯して1億2640万円及び遅延損害金の支払を命ずる
限度で,被上告人の請求を認容した。
本件買取価格は,Aの株式1株当たりの払込金額が5万円であったことから,こ
れと同額に設定されたものであり,それより低い額では買取りが円滑に進まないと
- 4 -
いえるか否かについて十分な調査,検討等がされていないこと,既にAの発行済株
式の総数の3分の2以上の株式を保有していた参加人において,当時の状態を維持
した場合と比較してAを完全子会社とすることが経営上どの程度有益な効果を生む
かという観点から検討が十分にされていないこと,本件買取価格の設定当時のAの
株式の1株当たりの価値は株式交換のために算定された評価額等から1万円であっ
たと認めるのが相当であること等からすれば,本件買取価格の設定には合理的な根
拠又は理由を見出すことはできず,上告人らは,取締役としての善管注意義務に違
反して,その任務を怠ったものである。
4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は次の
とおりである。
前記事実関係によれば,本件取引は,AをBに合併して不動産賃貸管理等の事業
を担わせるという参加人のグループの事業再編計画の一環として,Aを参加人の完
全子会社とする目的で行われたものであるところ,このような事業再編計画の策定
は,完全子会社とすることのメリットの評価を含め,将来予測にわたる経営上の専
門的判断にゆだねられていると解される。そして,この場合における株式取得の方
法や価格についても,取締役において,株式の評価額のほか,取得の必要性,参加
人の財務上の負担,株式の取得を円滑に進める必要性の程度等をも総合考慮して決
定することができ,その決定の過程,内容に著しく不合理な点がない限り,取締役
としての善管注意義務に違反するものではないと解すべきである。
以上の見地からすると,参加人がAの株式を任意の合意に基づいて買い取ること
は,円滑に株式取得を進める方法として合理性があるというべきであるし,その買
取価格についても,Aの設立から5年が経過しているにすぎないことからすれば,
- 5 -
払込金額である5万円を基準とすることには,一般的にみて相応の合理性がないわ
けではなく,参加人以外のAの株主には参加人が事業の遂行上重要であると考えて
いた加盟店等が含まれており,買取りを円満に進めてそれらの加盟店等との友好関
係を維持することが今後における参加人及びその傘下のグループ企業各社の事業遂
行のために有益であったことや,非上場株式であるAの株式の評価額には相当の幅
があり,事業再編の効果によるAの企業価値の増加も期待できたことからすれば,
株式交換に備えて算定されたAの株式の評価額や実際の交換比率が前記のようなも
のであったとしても,買取価格を1株当たり5万円と決定したことが著しく不合理
であるとはいい難い。そして,本件決定に至る過程においては,参加人及びその傘
下のグループ企業各社の全般的な経営方針等を協議する機関である経営会議におい
て検討され,弁護士の意見も聴取されるなどの手続が履践されているのであって,
その決定過程にも,何ら不合理な点は見当たらない。
以上によれば,本件決定についての上告人らの判断は,参加人の取締役の判断と
して著しく不合理なものということはできないから,上告人らが,参加人の取締役
としての善管注意義務に違反したということはできない。
5 以上と異なる見解の下に,本件決定についての上告人らの判断に参加人の取
締役としての善管注意義務違反があるとして被上告人の請求を一部認容した原審の
判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があ
り,原判決中,上告人ら敗訴部分は破棄を免れない。そして,以上説示したところ
によれば,同部分に関する被上告人の請求は理由がないから,同部分について被上
告人の請求を棄却した第1審判決は正当であり,同部分についての被上告人の控訴
は棄却すべきである。
- 6 -
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官白木勇裁判官宮川光治裁判官櫻井龍子裁判官
金築誠志裁判官横田尤孝)
と疑問を抱きたくなるような判決です。
誰もが営業の自由(憲法22条1項)http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/0ba5ea65166fb79d77f24ba4e5e0af61を有しているとはいえ、子ども達の健全発育環境整備の公共の福祉のほうが、重要なはず。
*************
日本国憲法
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
判決文全文を読んで確認する必要あり。
「判決は、公共施設の近隣で一定の営業規制をすることは「重要な公共の福祉に合致するもので必要かつ合理的だ」と判断。
そのうえで、
①府条例はキャバクラなどの接待飲食店の案内と、性風俗店の案内を区別せずに規制している
②案内所の営業禁止範囲の方が風俗店の禁止範囲(70メートル)よりも大きい――の2点を指摘。」
と、記事にはあります。
「①の接待飲食店の案内と性風俗店の案内の区別」というが、府側も「案内所の影響力は風俗店とは比較にならないほど強い」と主張しているように、形式的にも実質においても同質のものといえるのではないだろうか。
******************************************
http://www.asahi.com/articles/ASG2T54Z3G2TPLZB013.html
風俗案内所、公共施設から200M規制は違憲 京都地裁
2014年2月26日15時41分
京都市内の繁華街で客に風俗店を紹介する風俗案内所を経営していた男性(33)が、学校や診療所などの公共施設から200メートル以内で案内所の営業を禁ずる京都府条例の規定は違憲だなどとして、府を相手に営業権の確認を求めた訴訟の判決が25日、京都地裁であった。栂村明剛(つがむらあきよし)裁判長は「規定は府民の営業の自由を合理的裁量を超えて制限するもので違憲・無効だ」と判断。公共施設から70メートル離れた場所での営業を認めた。
風俗営業法に関連して2010年11月に施行された府風俗案内所規制条例は、公共施設から200メートル以内で風俗案内所を営業することを禁じ、違反者への刑事罰も設けている。男性は11年2月に同条例違反容疑で逮捕され、起訴猶予処分となり案内所を閉店した。
判決は、公共施設の近隣で一定の営業規制をすることは「重要な公共の福祉に合致するもので必要かつ合理的だ」と判断。そのうえで、①府条例はキャバクラなどの接待飲食店の案内と、性風俗店の案内を区別せずに規制している②案内所の営業禁止範囲の方が風俗店の禁止範囲(70メートル)よりも大きい――の2点を指摘。「明確な根拠が認められない」と述べ、府側の「案内所の影響力は風俗店とは比較にならないほど強い」とする主張を退けた。
風俗案内所を規制する条例は京都府のほか、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県などにもある。
京都府警監察官室は「判決文を見ていないのでコメントできない」としている。(藤原学思)
《風俗関連の法令に詳しい小西一郎弁護士(東京弁護士会)の話》 風俗案内所はここ数年、反社会的勢力の資金源としてみられ始め、規制が強まっていた。「案内所潰し」が進む中で、過度に営業の自由を制限する条例に司法が待ったをかけた形だ。同様の条例を定める他地域にも影響がある。
銀座、新宿、渋谷、池袋等で勝っても、それでは不十分なのだろう。
街頭の聴衆には、訴えることができても、個々の街、個々の地域での訴えが浸透しなかったのが敗因であったのではないかと思う。
反面、そういう個々の街、個々の地域には、組織票が根付いている。
この組織票を握るひとの心を動かせなかった。
聴衆が集まる人気を、マスコミも敢えて報道をしなかった。
短い選挙戦で、広大な東京都全域の個々の街、個々の地域のひとの心を動かすことができて、初めて勝利がある。
逆に、組織で固められると、選挙前から、その陣営の圧勝の結果が見て取れることとなってしまう。
*********東京新聞(2014/02/11)*****************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014021102000129.html
【政治】
街頭人気 票に直結せず 「小泉氏演説目当て」「脱原発具体策欠け」
2014年2月11日 朝刊
九日に投開票された東京都知事選は、元厚生労働相の舛添要一氏の大勝で幕を閉じた。選挙戦では「原発即時ゼロ」を訴えた元首相の細川護熙(もりひろ)氏が街頭演説で舛添氏よりも多くの聴衆を集める場面が目立ったが、結果は舛添氏のダブルスコアでの勝利。なぜ、こうした逆転現象は起こったのか-。 (宇田薫)
選挙期間中、最後の日曜となった二日午後。東京・銀座四丁目の交差点で行われた細川氏の街頭演説では、開始前から聴衆が選挙カーの周りに続々と集まった。細川氏を支援する小泉純一郎元首相がマイクを握ると、聴衆は一気に盛り上がり、「そうだ、そうだ」と声援があちこちから上がった。約三十分前に同じ場所で舛添氏も街頭演説し、安倍晋三首相や山口那津男公明党代表が応援に駆けつけたが、聴衆の人数も熱気も、細川氏陣営の方が上回った。
しかし、選挙結果は細川氏の約九十五万六千票に対し、舛添氏は倍以上の約二百十一万三千票を獲得した。街頭での盛り上がりと得票との大きな差に、細川氏は敗戦を受けた九日夜の記者会見で「街頭演説と選挙結果との落差が大きい。努力不足を痛感した」と、当惑を隠せなかった。
明治学院大の川上和久教授(政治心理学)は「細川氏の街頭演説に来た人たちの目当ては小泉氏であり、小泉氏が目立ちすぎて、候補者本人である細川氏の存在がかすんでしまった」と指摘。さらに「有権者は脱原発の政策に関心を持って集まったのに、細川氏が演説の中で原発ゼロ後の具体的な社会像を示せず、期待を裏切ってしまった」と分析する。
また、慶応大大学院の曽根泰教(やすのり)教授(政治学)も「(細川氏の演説を聞いても)原発を再稼働せずに、ゼロを続けた後の具体的な政策はなく、逆に、有権者に無責任ととらえられたのではないか」と話す。
*************************
本日、労働基準監督官『ダンダリン』のドラマ http://www.ntv.co.jp/dandarin/ 、最終回ですね。残念。
人生で、はまったドラマはいままで一つ『愛という名のもとに』だけでしたが、このドラマが二つ目です。
労働基準監督官は、動くことでひとを幸せにするはず…
労働基準監督官 段田凛さん、頑張れ。
********過去 10話のまとめ******
実際の題名ではなく、各話、自分の感じたことを一行で述べています。
「ダンダリン」の活躍を援護する社会。第1話 会社にしがみつくのではなく、命にしがみつけ
ダンダリンの活躍を援護する社会。第2話労働基準法41条名ばかり店長
ダンダリンの活躍を援護する社会。第3話 労働基準監督官はルール それ以下でもそれ以上でもない。
ダンダリンの活躍を援護する社会。第4話 内定切りは解雇と同じ。 労働基準法104条2項
ダンダリン活躍を援護する社会。第5話労働者と雇い主のwin-win。そのためには労働者に手段が要る。
ダンダリンの活躍を援護する社会。第6話最低賃金の半分も行かない時給で外国人労働者が働く環境とは
ダンダリンの活躍を援護する社会。第7話行政解剖の前に死亡画像診断Aiを。
ダンダリンの活躍を援護する社会。第8話 ブラック企業 会社嫌なら会社を→×辞める○変える。
ダンダリンの活躍を援護する社会。第9話請負契約は事業主となること。雇用ではない。
ダンダリンの活躍を援護する社会。第10話えん罪を起こしてくるやつはいる。
最低賃金の半分も行かない時給で外国人労働者が働く。
彼ら労働者は、作業場のそとにでることも日本人と接触することも、禁止されている。
閉鎖された空間で、労働基準監督官は、彼らの敵とまで洗脳されてしまう。
ダンダリンのとった手は、これは思いつきませんでした。
あっぱれ。
労働基準監督官が店員に扮して外国屋台を夜中に作業場の真ん前に作り、においにつられて、労働者が出てくる。母国の味を楽しんでもらう、その時に、彼らから情報を得る。
情報から隔離されると、怖いものです。
いかに正しい情報を、彼らに伝えるか、日本の課題です。
日本で働く限り、日本人であれ外国人であれ、労働者の賃金は、同じ。
*****過去のダンダリン*****
実際の題名ではなく、各話、自分の感じたことを一行で述べています。
「ダンダリン」の活躍を援護する社会。第1話 会社にしがみつくのではなく、命にしがみつけ
ダンダリンの活躍を援護する社会。第2話労働基準法41条名ばかり店長
ダンダリンの活躍を援護する社会。第3話 労働基準監督官はルール それ以下でもそれ以上でもない。
ダンダリンの活躍を援護する社会。第4話 内定切りは解雇と同じ。 労働基準法104条2項
ダンダリン活躍を援護する社会。第5話労働者と雇い主のwin-win。そのためには労働者に手段が要る。
ダンダリンの活躍を援護する社会。第6話最低賃金の半分も行かない時給で外国人労働者が働く環境とは
ダンダリンの活躍を援護する社会。第7話行政解剖の前に死亡画像診断Aiを。
ダンダリンの活躍を援護する社会。第8話 ブラック企業 会社嫌なら会社を→×辞める○変える。
ダンダリンの活躍を援護する社会。第9話請負契約は事業主となること。雇用ではない。
ダンダリンの活躍を援護する社会。第10話えん罪を起こしてくるやつはいる。
若いころから育て上げた職人が、菓子屋を辞めたいと。
自分の作りたい味が、数をつくることが優先されできずにいる。
退職すると、損害賠償訴訟5000万円(先の注文のための材料費などが無駄になる損害、販売予約に対応できない営業利益など)を請求すると脅す菓子屋の店長。
お互いの感情のもつれが、話を悪い方に導く。
民事訴訟となれば、労働監督官の出番ではなくなる。
ダンダリンは、知恵を授ける。
その店の人気商品である彼しかつくれないレシピを特許出願。
彼が辞めると、人気商品が売れなくなる。
そこで、社労士が調整に入って、彼はとどまり、彼の雇用の環境は改善した。
もし、戦う手段を手にしていなければ、訴訟でやられた可能性がある。
なかなか難しいところではあるが、手段は必要。
基礎知識としては、「退職願い」と「退職届け」は、大きく違うということ。
***************************
民法
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
*****過去のダンダリン*****
実際の題名ではなく、各話、自分の感じたことを一行で述べています。
「ダンダリン」の活躍を援護する社会。第1話 会社にしがみつくのではなく、命にしがみつけ
ダンダリンの活躍を援護する社会。第2話労働基準法41条名ばかり店長
ダンダリンの活躍を援護する社会。第3話 労働基準監督官はルール それ以下でもそれ以上でもない。
ダンダリンの活躍を援護する社会。第4話 内定切りは解雇と同じ。 労働基準法104条2項
ダンダリン活躍を援護する社会。第5話労働者と雇い主のwin-win。そのためには労働者に手段が要る。
ダンダリンの活躍を援護する社会。第6話最低賃金の半分も行かない時給で外国人労働者が働く環境とは
ダンダリンの活躍を援護する社会。第7話行政解剖の前に死亡画像診断Aiを。
ダンダリンの活躍を援護する社会。第8話 ブラック企業 会社嫌なら会社を→×辞める○変える。
ダンダリンの活躍を援護する社会。第9話請負契約は事業主となること。雇用ではない。
ダンダリンの活躍を援護する社会。第10話えん罪を起こしてくるやつはいる。
労働基準監督署 課長の同級生が社長の零細の工作所での事故。
労働衛生安全法上、事業場に安全管理者の配置義務があるのに、おかずにいたら、そこで転落事故。
転落者を病院に運ぶ救急要請の前に、まず、安全管理者の到着をまっていた。
安全管理者がいなかったことがばれるから。
旧友の工作所だから、目をつぶるか。
このまま、書類送検されるとただでも経営が危ないのに会社が倒産し、労働者が行き場を失うことになる。
臨検では、労働者全員が、転落事故の時、社長である安全管理者は、現場にいたと詳細に答えた。
十人いれば、十人異なる証言があってしかるべきが、全員が一致していた。
あたかも、リハーサルをしたかのように。
だれも、社長を裏切らなかった。
実は、このことは、逆に怪しいということ。
ダンダリンの選択は、温情をかけるのではなく、ルールとして動くことであった。
結果、会社は破産。でも労働者全員をひきとる会社は、社長の配慮でみつかった。
彼は、必ず再生するはず。
*****過去のダンダリン*****
実際の題名ではなく、各話、自分の感じたことを一行で述べています。
「ダンダリン」の活躍を援護する社会。第1話 会社にしがみつくのではなく、命にしがみつけ
ダンダリンの活躍を援護する社会。第2話労働基準法41条名ばかり店長
ダンダリンの活躍を援護する社会。第3話 労働基準監督官はルール それ以下でもそれ以上でもない。
ダンダリンの活躍を援護する社会。第4話 内定切りは解雇と同じ。 労働基準法104条2項
ダンダリン活躍を援護する社会。第5話労働者と雇い主のwin-win。そのためには労働者に手段が要る。
ダンダリンの活躍を援護する社会。第6話最低賃金の半分も行かない時給で外国人労働者が働く環境とは
ダンダリンの活躍を援護する社会。第7話行政解剖の前に死亡画像診断Aiを。
ダンダリンの活躍を援護する社会。第8話 ブラック企業 会社嫌なら会社を→×辞める○変える。
ダンダリンの活躍を援護する社会。第9話請負契約は事業主となること。雇用ではない。
ダンダリンの活躍を援護する社会。第10話えん罪を起こしてくるやつはいる。