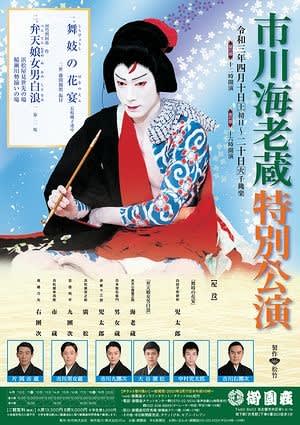人形浄瑠璃・文楽 「曽根崎心中」 (10月16日 岐阜市民会館大ホール)
コロナ緊急事態宣言が明けて古典芸能の公演も中止されることなく無事開催されている。先週の御園座の歌舞伎に続いて、今回は文楽を観るために岐阜市民会館へ。買ってあったチケットは夜の部の「曽根崎心中」。人形浄瑠璃文楽は、歌舞伎の題材にされることも多い古典芸能。人形浄瑠璃が始まったのは江戸時代、徳川綱吉の時代に大阪において、というから自分が思っていた程古い時代のものではない。そもそも”文楽”は人形浄瑠璃を行う団体のひとつで(文楽座)、大正時代以降は唯一となったため、文楽と人形浄瑠璃は同義に語られることが多いとのこと。
老母を先に会場に送り届け、市役所の駐車場に車を停めて会場入り。大ホールだが1階席のみで、ついこの間まで緊急事態宣言が出ていたとあってまだ1つおきの間引き客席だが、思ったよりも多くの観客が集まっていた。まずは簡単な文楽の歴史と演題の内容の説明があった(→古典芸能のほとんどは話の筋を事前にちゃんと理解した上で楽しむことがほとんど)。舞台袖には太夫(たゆう・浄瑠璃を語る人)の台詞が逐一表示される縦型の字幕機械があり(名称は”Gマーク”と言うのだとか・笑)、これが古い言葉の理解をとても楽にしてくれて良かった。便利になってるんだなァ。
一体の人形に3人の人形遣いが付く。舞台脇の床(とこ)には太夫と太棹の三味線方(奏者)。人形遣いのひとりは完全に顔出しで操作している。それが物語とともに人形の方に感情移入していくとだんだん人形遣いの存在が視野から消えていくのが面白い。それほど人形の動きは滑らかでリアルで艶めかしく、これを3人で息を合わせて操作するのは凄いものだ。人形の表情も瞼の開け閉じがあるくらいで無表情なはずなのに、だんだんこちらの方が勝手に表情を見るようになるのが興味深い。馴染みの話(心中物)なので理解もし易かったし楽しめた。太夫と三味線方は最初に紹介もあって拍手も受けるが、人形遣いは名も告げられず、その仕事に徹するのみで幕を引かれる。なんと報われない役だろう…(そういう所がかっこいいんだけれど)。機会があったら他の物語も観てみたい。
【夜の部】
「解説」
豊竹希太夫
「曽根崎心中」
<生玉社前の段>
竹本三輪太夫、鶴澤清馗
<天満屋の段>
竹本錣太夫、竹澤宗助
<天神森の段>
お初・竹本藤太夫、鶴澤清介
徳兵衛・豊竹希太夫、鶴澤清公
豊竹亘太夫、鶴澤清方
[人形役割]
手代徳兵衛・豊松清十郎
丁稚長蔵・桐竹勘次郎
天満屋お初・桐竹勘十郎
油屋九平次・吉田玉輝
田舎客・吉田簑之
遊女・吉田簑紫郎
遊女・吉田玉誉
天満屋亭主・桐竹紋吉
女中お玉・吉田簑一郎
[人形部]
吉田玉彦、桐竹勘介、吉田和馬、吉田玉峻
桐竹勘昇、吉田清之助、吉田和登