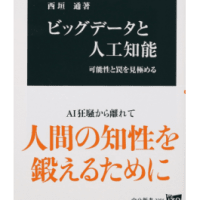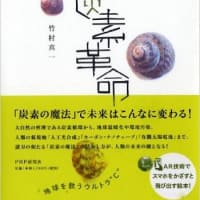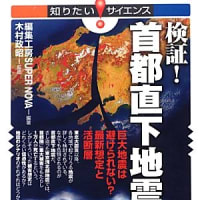国立極地研究所の西山尚典助教、小川泰信教授を中心とする、東北大学、電気通信大学、産業技術総合研究所などの研究グループは、北極スバールバル諸島のロングイヤービンにおける観測から、世界で初めて波長1.1µmで発光するオーロラを撮像することに成功した。
同成果は、空の明るい夏の時期や昼間など、地上からの観測の難しい「日照下オーロラ」の撮像につながる技術であり、多様なオーロラの生成メカニズムの解明への貢献が期待される。
これまでのオーロラの光学観測は、緑色や赤色、青色といったヒトの目が認識できる可視光線と呼ばれる波長を使うことで発展してきた。
古くは1地点の観測点で取得した画像データの解析が主流であったが、2000年以降、北米や北欧における地上光学観測の多点化・ネットワーク化が進むと、地理的に隣り合う画像データをつなぎ合わせることでグローバルなオーロラ現象(経度幅 ~100°)の分析が可能となった。
しかしながら、地上光学観測ネットワークはオーロラ出現領域を「地理的には」カバーしている一方で、夜が明けて、観測点が昼に近づいてくると、空が明るすぎるため、微弱な発光であるオーロラの検出が難しいという問題がある。
その解決策の一つと期待されているのが、可視光線よりも波長の長い短波長赤外領域(1.0µm -1.6µm)によるオーロラ観測。
この波長帯では、太陽光は可視光線よりも地上に届きにくい性質があり、またオーロラ自体は、可視光線にも劣らない明るいオーロラが存在することが1970-80年代の研究で明らかになっている。
しかし、1990年代以降、この波長帯を使ったオーロラの研究はほとんど実施されておらず、短波長赤外領域を用いたオーロラ観測における技術革新やその実証が待たれていた。
同研究グループは、短波長赤外領域の光に感度を持つInGaAs検出器をオーロラ観測用に導入し、光学系は監視カメラ用のレンズなどを利用することで、比較的安価ながらも高性能な分光器とカメラを開発した。
これらの観測機器をスバールバル諸島のロングイヤービンに設置し、波長1.1µmで光るオーロラの撮像と分光観測を世界で初めて成功させ(2023年1月21日現地時刻の19時45分前後)、30秒以下の高い時間分解能での測定能力を実証した。
また大型レーダーであるEuropean Incoherent Scatter Svalbard Radar(ESR)との同時観測データの解析から、短波長赤外オーロラの発光する中心高度が100km - 120kmであることを突き止め、宇宙空間より降り込むエネルギーの比較的高い電子がこの発光に直接寄与していることを示した。
InGaAs検出器は、食品や半導体、歴史的美術品などの多岐に渡る非破壊検査での需要が高く、その性能は近年著しく向上し続けている。
現在のオーロラ観測は可視光線によるものが主流だが、InGaAs検出器の技術躍進に加えて、短波長赤外領域では「空が可視光線より暗い」「雲などの影響を受けにくい」といった特色を考えると、今後は短波長赤外領域によるオーロラ観測がますます重要となるであろう。
同研究で初めて実証された技術は、地上からの観測の難しい「日照下オーロラ」の撮像につながる技術であり、多様なオーロラの生成メカニズムの解明への貢献が期待される。
今回は夜間の撮像を報告したが、現在太陽活動の長期的な上昇期にあり、日照の時間帯に強いオーロラ現象が今後出現することで、現装置による日照下オーロラの観測の機会もあると考えられる。
また、米国の研究グループによって、米国のマクマード南極基地から50km高度まで飛翔する大型気球に搭載させたInGaAsカメラを用いて日照下オーロラを撮像するミッションの準備が進められており、地上観測だけではなく大型気球や科学衛星などのプラットフォームへの応用を進めることで、地球の大気・オーロラに加えて太陽系惑星の大気観測にも大きな貢献が予想されている。<国立極地研究所(極地研)>
同成果は、空の明るい夏の時期や昼間など、地上からの観測の難しい「日照下オーロラ」の撮像につながる技術であり、多様なオーロラの生成メカニズムの解明への貢献が期待される。
これまでのオーロラの光学観測は、緑色や赤色、青色といったヒトの目が認識できる可視光線と呼ばれる波長を使うことで発展してきた。
古くは1地点の観測点で取得した画像データの解析が主流であったが、2000年以降、北米や北欧における地上光学観測の多点化・ネットワーク化が進むと、地理的に隣り合う画像データをつなぎ合わせることでグローバルなオーロラ現象(経度幅 ~100°)の分析が可能となった。
しかしながら、地上光学観測ネットワークはオーロラ出現領域を「地理的には」カバーしている一方で、夜が明けて、観測点が昼に近づいてくると、空が明るすぎるため、微弱な発光であるオーロラの検出が難しいという問題がある。
その解決策の一つと期待されているのが、可視光線よりも波長の長い短波長赤外領域(1.0µm -1.6µm)によるオーロラ観測。
この波長帯では、太陽光は可視光線よりも地上に届きにくい性質があり、またオーロラ自体は、可視光線にも劣らない明るいオーロラが存在することが1970-80年代の研究で明らかになっている。
しかし、1990年代以降、この波長帯を使ったオーロラの研究はほとんど実施されておらず、短波長赤外領域を用いたオーロラ観測における技術革新やその実証が待たれていた。
同研究グループは、短波長赤外領域の光に感度を持つInGaAs検出器をオーロラ観測用に導入し、光学系は監視カメラ用のレンズなどを利用することで、比較的安価ながらも高性能な分光器とカメラを開発した。
これらの観測機器をスバールバル諸島のロングイヤービンに設置し、波長1.1µmで光るオーロラの撮像と分光観測を世界で初めて成功させ(2023年1月21日現地時刻の19時45分前後)、30秒以下の高い時間分解能での測定能力を実証した。
また大型レーダーであるEuropean Incoherent Scatter Svalbard Radar(ESR)との同時観測データの解析から、短波長赤外オーロラの発光する中心高度が100km - 120kmであることを突き止め、宇宙空間より降り込むエネルギーの比較的高い電子がこの発光に直接寄与していることを示した。
InGaAs検出器は、食品や半導体、歴史的美術品などの多岐に渡る非破壊検査での需要が高く、その性能は近年著しく向上し続けている。
現在のオーロラ観測は可視光線によるものが主流だが、InGaAs検出器の技術躍進に加えて、短波長赤外領域では「空が可視光線より暗い」「雲などの影響を受けにくい」といった特色を考えると、今後は短波長赤外領域によるオーロラ観測がますます重要となるであろう。
同研究で初めて実証された技術は、地上からの観測の難しい「日照下オーロラ」の撮像につながる技術であり、多様なオーロラの生成メカニズムの解明への貢献が期待される。
今回は夜間の撮像を報告したが、現在太陽活動の長期的な上昇期にあり、日照の時間帯に強いオーロラ現象が今後出現することで、現装置による日照下オーロラの観測の機会もあると考えられる。
また、米国の研究グループによって、米国のマクマード南極基地から50km高度まで飛翔する大型気球に搭載させたInGaAsカメラを用いて日照下オーロラを撮像するミッションの準備が進められており、地上観測だけではなく大型気球や科学衛星などのプラットフォームへの応用を進めることで、地球の大気・オーロラに加えて太陽系惑星の大気観測にも大きな貢献が予想されている。<国立極地研究所(極地研)>