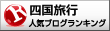松山市の興聖寺で『義士祭』
今日、12月14日松山市で「松山義士祭」が行われた。
元禄14年(1701)浅野内匠頭の江戸城松の廊下の刃傷から、同15年(1703)大石内蔵助良雄達の吉良邸討ち入り、同16年(1703)の浪士の切腹に至るまでの一連の事件は、今日まで歴史上のみならず、書籍、映画、演劇、講談と多岐にわたる分野に取り上げられている。
討ち入りした46人(寺坂吉衛門を除く)は、泉岳寺で内匠頭の墓前に上野介の首級を供えた後、幕府大目付けへ自首し、細川、水野、毛利、伊予松山藩に預けられ、伊予松山藩には、大石主税ら10名を江戸藩邸へ収容し、切腹まで面倒をみた。この内大高源吾、木村岡右衛門の切腹の介錯をした藩士宮原久太夫は両名の遺髪を藩主の許しを得て、松山にある自分の菩提寺である興聖寺(こうしょうじ)へ二人の墓を建立し納め供養した。その墓は現在も残っている。
昭和39年(1964)両名と宮原の供養と地元の発展を願って、興聖寺史跡顕彰会が発足し、同年12月14日第1回松山義士祭が挙行された。その後主催は末広町商工会を経て同町会へ移行し現在まで松山の師走の風物詩として今年第47回を迎えた。
文献によると伊予松山藩での待遇は、幕府の意向を気にしつつ丁重に扱ったようで、食事は伊予松山藩が一番良かった(一汁二采)と当時の記録がある。
切腹後の遺体は布団に包み、泉岳寺へ移送し埋葬されている。また切腹の介錯は細川、水野家では、浪士一人につき一人としたが、伊予松山、毛利家では二人につき一人の介錯であった。
宮原久太夫は20人扶持と軽輩ではあったが、武士道に厚く剣の腕もあり、義士受け取りの徒歩頭の中にもその名前が伝えられている。ご子孫は現在も健在である。
なお、播州赤穂から、手厚くお持て成しをした御礼にと櫨の木が送られており松山道後にある、湯築城外堀土塁に植え道後地区土地改良区が大切に保存して現在も健在である。
註:興聖寺の資料より
参考:伊予松山藩がお預かりの赤穂十士氏名は下記の通り
大石 主税良金 部屋住(大石内蔵助良雄長男) 15歳
堀部 安兵衛武庸 二百石馬廻 33歳
中村 勘助正辰 百石祐筆 44歳
木村 岡右衛門貞行 百五十石代官 45歳
岡野 金右衛門包秀 部屋住(亡父二百石物頭) 23歳
不破 数右衛門正種 先知百石普請奉行 23歳
菅谷 半之丞政利 百石代官 43歳
千馬 三郎兵衛光忠 三十石宗門改 50歳
貝賀 弥左衛門友信 十両三人扶持蔵奉行 53歳
大高 源吾忠雄 二十石五人扶持近習 31歳

12月14日第47回松山義士祭が行われた興聖寺・・近くには正岡子規縁の子規堂がある。

義士祭が行われた興聖寺境内

木村岡衛門・大高源吾のお墓にお供え物を献上、その横に介錯をした宮原久太夫のお墓がある。

木村岡衛門と大高源吾、二人の墓所で興聖寺の住職が読経を挙げながら関係者が供養をした。

松山市の有識者、地元商店街関係者が一同に集まり、興聖寺本堂で供養を行い献句も行った。

討入そばを頂きながら当時の義士達を偲んでいた。
そばを食べながら、この時代は忠義心がありいい時代であったが、昨今忠義のちもなくなり殺伐とした世の中になった。
せめて、祖先を敬い親、先輩を労わる気持ちを持って欲しい・・・と言っていた。

木村岡右衛門は、漢詩に秀でていて、吉良邸討入の際、兜頭巾の裏に漢詩を縫い込んでいたと伝えられる。その漢詩の記念石碑
また、大高源吾は、宝井其角に俳諧を学び、俳号を「子葉」と号し元禄16年2月4日伊予松山藩邸で切腹を命ぜられ、その死に臨んで次の句を遺して清く自刃した。
「梅てのむ 茶屋も有りへし死出の山」

伊予松山藩江戸屋敷で、大石主税等10名を預かり丁重に持て成した御礼にと
播州赤穂から贈られた「ハゼ」の木、道後湯築城跡外堀土塁に植え地元の道後土地改良区が今も大切に保存管理している。
一昨年、赤穂市に何故松山に御礼としてハゼの木を贈ったのか文書で照会したが理由が分からないので調査の上連絡するとあったが、未だ回答がない。

平成14年12月14日、討ち入り300年記念祭が挙行された時松山随一の繁華街「銀天街」で義士行列をした。
今日、12月14日松山市で「松山義士祭」が行われた。
元禄14年(1701)浅野内匠頭の江戸城松の廊下の刃傷から、同15年(1703)大石内蔵助良雄達の吉良邸討ち入り、同16年(1703)の浪士の切腹に至るまでの一連の事件は、今日まで歴史上のみならず、書籍、映画、演劇、講談と多岐にわたる分野に取り上げられている。
討ち入りした46人(寺坂吉衛門を除く)は、泉岳寺で内匠頭の墓前に上野介の首級を供えた後、幕府大目付けへ自首し、細川、水野、毛利、伊予松山藩に預けられ、伊予松山藩には、大石主税ら10名を江戸藩邸へ収容し、切腹まで面倒をみた。この内大高源吾、木村岡右衛門の切腹の介錯をした藩士宮原久太夫は両名の遺髪を藩主の許しを得て、松山にある自分の菩提寺である興聖寺(こうしょうじ)へ二人の墓を建立し納め供養した。その墓は現在も残っている。
昭和39年(1964)両名と宮原の供養と地元の発展を願って、興聖寺史跡顕彰会が発足し、同年12月14日第1回松山義士祭が挙行された。その後主催は末広町商工会を経て同町会へ移行し現在まで松山の師走の風物詩として今年第47回を迎えた。
文献によると伊予松山藩での待遇は、幕府の意向を気にしつつ丁重に扱ったようで、食事は伊予松山藩が一番良かった(一汁二采)と当時の記録がある。
切腹後の遺体は布団に包み、泉岳寺へ移送し埋葬されている。また切腹の介錯は細川、水野家では、浪士一人につき一人としたが、伊予松山、毛利家では二人につき一人の介錯であった。
宮原久太夫は20人扶持と軽輩ではあったが、武士道に厚く剣の腕もあり、義士受け取りの徒歩頭の中にもその名前が伝えられている。ご子孫は現在も健在である。
なお、播州赤穂から、手厚くお持て成しをした御礼にと櫨の木が送られており松山道後にある、湯築城外堀土塁に植え道後地区土地改良区が大切に保存して現在も健在である。
註:興聖寺の資料より
参考:伊予松山藩がお預かりの赤穂十士氏名は下記の通り
大石 主税良金 部屋住(大石内蔵助良雄長男) 15歳
堀部 安兵衛武庸 二百石馬廻 33歳
中村 勘助正辰 百石祐筆 44歳
木村 岡右衛門貞行 百五十石代官 45歳
岡野 金右衛門包秀 部屋住(亡父二百石物頭) 23歳
不破 数右衛門正種 先知百石普請奉行 23歳
菅谷 半之丞政利 百石代官 43歳
千馬 三郎兵衛光忠 三十石宗門改 50歳
貝賀 弥左衛門友信 十両三人扶持蔵奉行 53歳
大高 源吾忠雄 二十石五人扶持近習 31歳

12月14日第47回松山義士祭が行われた興聖寺・・近くには正岡子規縁の子規堂がある。

義士祭が行われた興聖寺境内

木村岡衛門・大高源吾のお墓にお供え物を献上、その横に介錯をした宮原久太夫のお墓がある。

木村岡衛門と大高源吾、二人の墓所で興聖寺の住職が読経を挙げながら関係者が供養をした。

松山市の有識者、地元商店街関係者が一同に集まり、興聖寺本堂で供養を行い献句も行った。

討入そばを頂きながら当時の義士達を偲んでいた。
そばを食べながら、この時代は忠義心がありいい時代であったが、昨今忠義のちもなくなり殺伐とした世の中になった。
せめて、祖先を敬い親、先輩を労わる気持ちを持って欲しい・・・と言っていた。

木村岡右衛門は、漢詩に秀でていて、吉良邸討入の際、兜頭巾の裏に漢詩を縫い込んでいたと伝えられる。その漢詩の記念石碑
また、大高源吾は、宝井其角に俳諧を学び、俳号を「子葉」と号し元禄16年2月4日伊予松山藩邸で切腹を命ぜられ、その死に臨んで次の句を遺して清く自刃した。
「梅てのむ 茶屋も有りへし死出の山」

伊予松山藩江戸屋敷で、大石主税等10名を預かり丁重に持て成した御礼にと
播州赤穂から贈られた「ハゼ」の木、道後湯築城跡外堀土塁に植え地元の道後土地改良区が今も大切に保存管理している。
一昨年、赤穂市に何故松山に御礼としてハゼの木を贈ったのか文書で照会したが理由が分からないので調査の上連絡するとあったが、未だ回答がない。

平成14年12月14日、討ち入り300年記念祭が挙行された時松山随一の繁華街「銀天街」で義士行列をした。