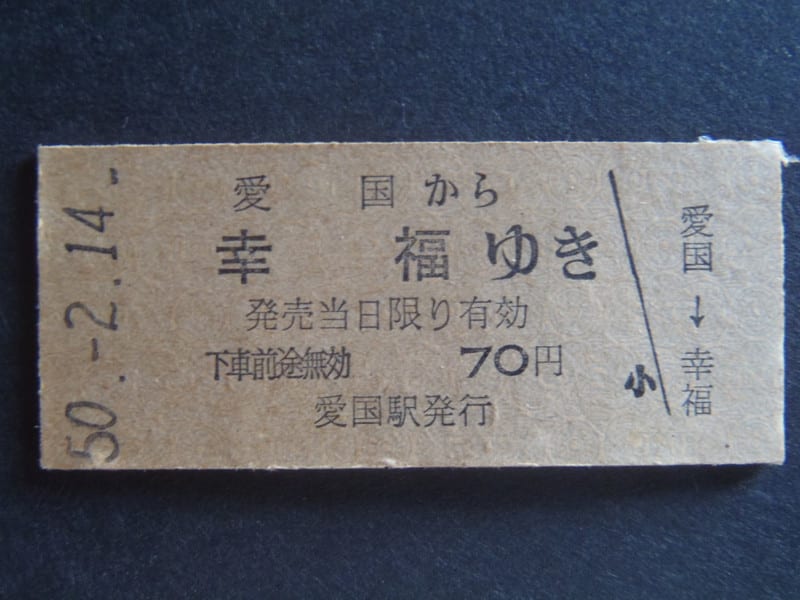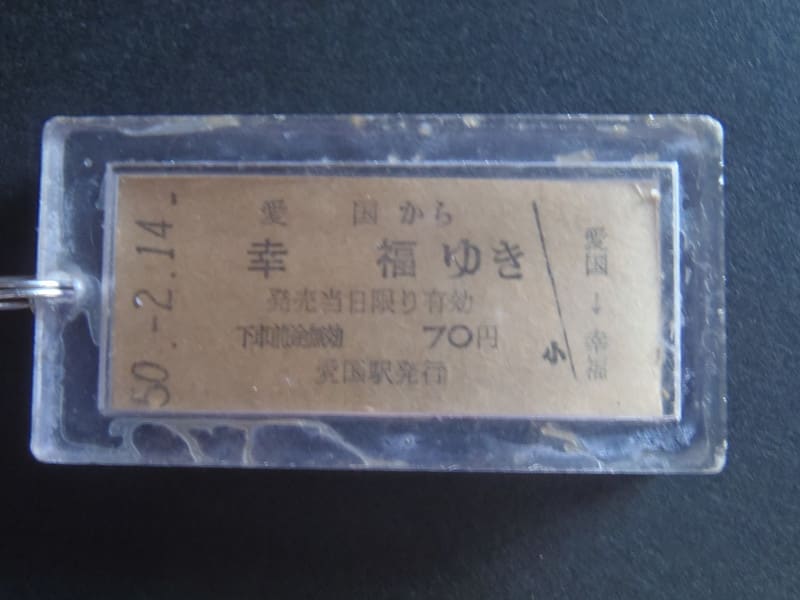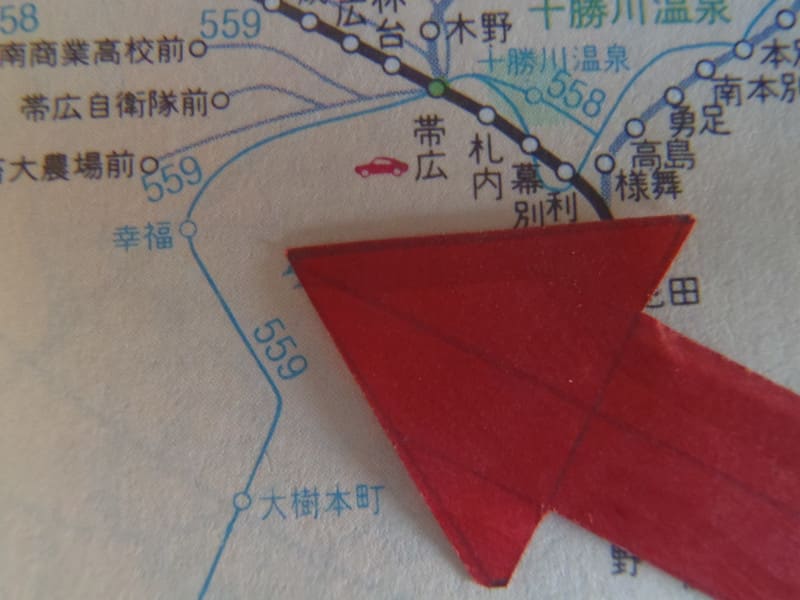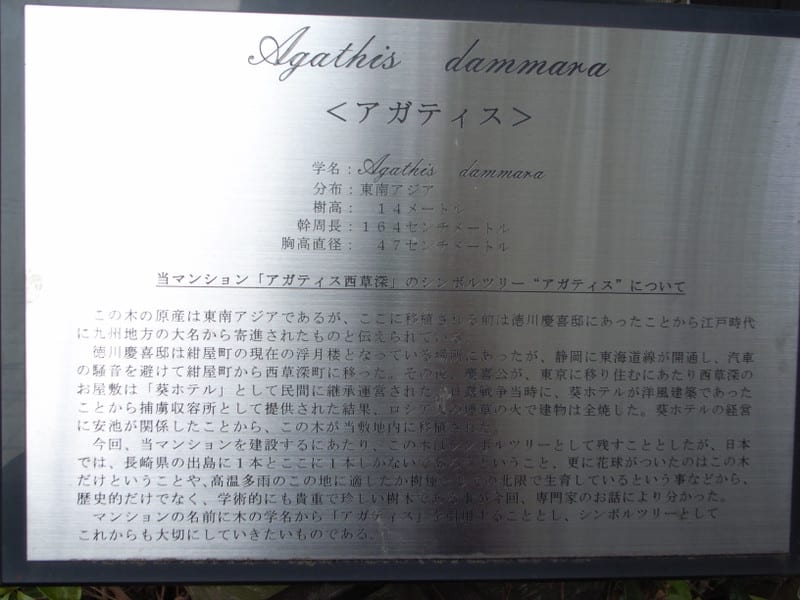【今日の 古いもの 再び】
出てきた出てきた、レコードだ。
物置の奥から出てきました。昔母の在所で「もう捨てる」といったものをワシが貰ってきたのだ。

きったない木の箱に突っ込んであったので、もう全面的に埃まるけ。
風呂場で洗って干したところ。全部で35枚、どういった材質かわからないがとにかく重い!全部で7.5Kgもあった。


直径25cmもあるのに片面1曲だけ。この写真のレコードを良く見ると分るが文字が右から書いてある。
タイトル「なすまやしかや話世」左読みではもちろん読めないが
右からでも意味不明。歌っているのは市丸と言う昔の芸者。
B面は「「なば出の水・病いたひ逢」と書いてある。「水の出ばな」ってなに?
ではもう一枚

これは「夜月根利大」歌っているのは「夫義端田」しかもレーベルには本人の写真つき。「歌行流」であるぞ。
紙のレコードジャケットも面白いぞ。
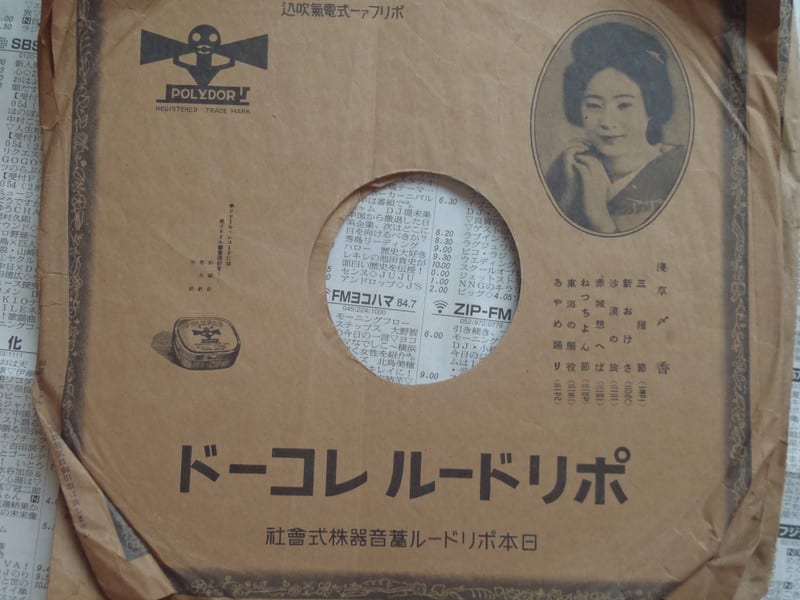
このジャケットは「社会式株器音畜ルードリポ本日」のもので浅草の芸者「〆香」(しめか)の歌だ。
「込吹氣電式ーァフリポ」と誇らしく書いてある。
今は無い(こんなレコード会社知らんかった)「社会式株器音畜本日大」「ドーコレートッニ」だそうだ。
その他「ドーコレ クチーョシ」と「アビムロコ」もあり面白い。
これらはみんな明日川越し市の博物館へ持っていくつもりだ。はたして貰ってくれるものか。
あー、最新のPCで文を右から書くのは疲れます。
マイクロソフトさん「よいしほてっ作をドーワき書右」
青空球児好児の往年の漫才
「よきすがたなあ」「よもくぼ」「れそいかとんほ」を思い出しちゃうぜ。
ホントに疲れました。
「いましお」
出てきた出てきた、レコードだ。
物置の奥から出てきました。昔母の在所で「もう捨てる」といったものをワシが貰ってきたのだ。

きったない木の箱に突っ込んであったので、もう全面的に埃まるけ。
風呂場で洗って干したところ。全部で35枚、どういった材質かわからないがとにかく重い!全部で7.5Kgもあった。


直径25cmもあるのに片面1曲だけ。この写真のレコードを良く見ると分るが文字が右から書いてある。
タイトル「なすまやしかや話世」左読みではもちろん読めないが
右からでも意味不明。歌っているのは市丸と言う昔の芸者。
B面は「「なば出の水・病いたひ逢」と書いてある。「水の出ばな」ってなに?
ではもう一枚

これは「夜月根利大」歌っているのは「夫義端田」しかもレーベルには本人の写真つき。「歌行流」であるぞ。
紙のレコードジャケットも面白いぞ。
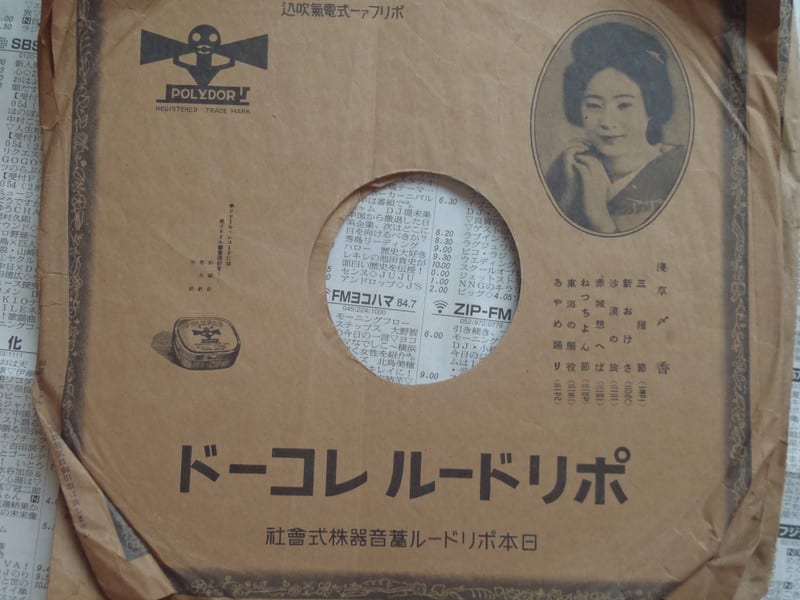
このジャケットは「社会式株器音畜ルードリポ本日」のもので浅草の芸者「〆香」(しめか)の歌だ。
「込吹氣電式ーァフリポ」と誇らしく書いてある。
今は無い(こんなレコード会社知らんかった)「社会式株器音畜本日大」「ドーコレートッニ」だそうだ。
その他「ドーコレ クチーョシ」と「アビムロコ」もあり面白い。
これらはみんな明日川越し市の博物館へ持っていくつもりだ。はたして貰ってくれるものか。
あー、最新のPCで文を右から書くのは疲れます。
マイクロソフトさん「よいしほてっ作をドーワき書右」
青空球児好児の往年の漫才
「よきすがたなあ」「よもくぼ」「れそいかとんほ」を思い出しちゃうぜ。
ホントに疲れました。
「いましお」