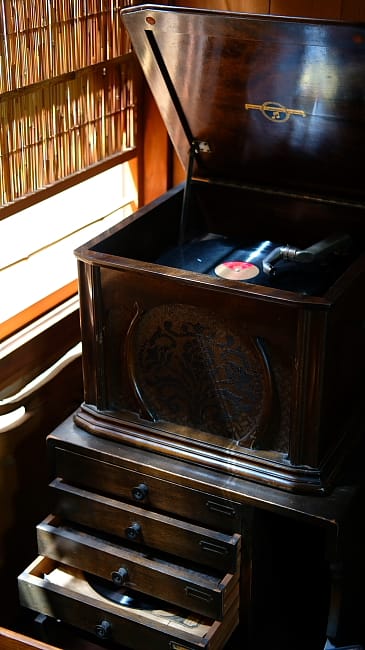元は
実業家であり政治家としても活躍した
田中源太郎の別荘

当時は
喜鶴亭と称されていた

命名したのは三条実美

12,000坪もの敷地を有する
広大な屋敷であった

田中源太郎の死後
この屋敷は
後に京福電鉄となった
京都電燈の重役の所有となる

この八瀬の地まで
路線が引かれた理由もその辺りにあるらしい

前出の
「喜鶴亭」の名で
高級料亭として営業していた

廃業後
岐阜市の浄土真宗無量寿山光明寺がこの屋敷を買収

ここが寺院となったのは平成17年から

巡ると

元は山荘であると納得する

実業家であり政治家としても活躍した
田中源太郎の別荘

当時は
喜鶴亭と称されていた

命名したのは三条実美

12,000坪もの敷地を有する
広大な屋敷であった

田中源太郎の死後
この屋敷は
後に京福電鉄となった
京都電燈の重役の所有となる

この八瀬の地まで
路線が引かれた理由もその辺りにあるらしい

前出の
「喜鶴亭」の名で
高級料亭として営業していた

廃業後
岐阜市の浄土真宗無量寿山光明寺がこの屋敷を買収

ここが寺院となったのは平成17年から

巡ると

元は山荘であると納得する