
窯詰め開始。
備前焼は釉薬を掛けない『無釉焼締め』が最大の特徴です。その器に模様を描く事が出来る最大の要素が、窯詰めでの計算です。その他の要因として土の耐火度、金属の含有量、灰の種類……。それらのコンビネーションによって、備前焼の発色が生まれます。
『偶然の産物』ではあるけれど、『必然の算術』が必要。
ワラのあたった部分が緋色のラインとなる『ヒダスキ』
燃料の木から出る灰が溶けて、自然の釉薬となる『ゴマ』
燃えた熾き(おき)と反応して出来る『サンギリ』
その他に、ボタモチ・抜け・コゲ・緋色・紫蘇色・青備前・玉だれ・カセゴマ……と、様々な発色をします。
窯の前は、数ヶ月前に作ったものから、つい最近作ったものまで、色々な種類のものであふれています。それらをセッティングして窯詰めしていく。同じ形でも数種類の土を使い分けている場合もあるので注意。
窖窯(あながま)は正面の焚き口が窯の出入り口を兼ねている。、その為、窯の一番奥から詰める事となる。エッチラ、オッチラとトンネルを上がっていく。忘れ物があるとまた下って、登ってを繰り返さないといけない。一体、何往復するのだろう。
窯詰めの最初の頃は、体が慣れていない為に、頭や背中をぶつけたりする。
そして、いつもの事ながら、初日終了の頃は、足が笑っている……。












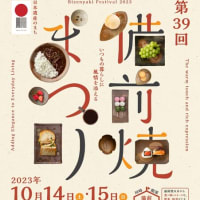
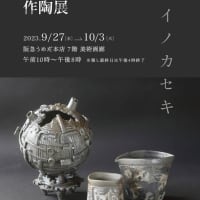



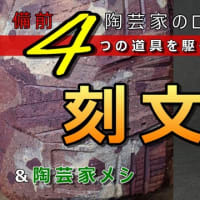
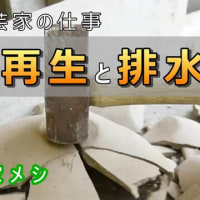
ヒダスキ・ゴマ・サンギリ・ボタモチ・青備前・玉ダレ等は
知ってましたが・・・ほんといろいろな発色があるんですね。
私が、今教室で作っているのは釉薬を使うモノ。。。
もっともっと上手くなったら、いつか備前を体験してみたいです。。。
釜出しが見てみたいなぁ。。。(*^m^*)
ご案内いたしましょう(*^o^*)/~~
めっちゃ嬉しいんですが・・・。。。
ご迷惑では???
最初から思えば何年越しやら……。
がんばりまする。(*^ー')b
お楽しみ(?)に……。
7月末頃になるかと思います。
実はお世話になり始める前から、結構ブログの方には
お邪魔させていただいていました。
いつも、なるほど~っと思いながら拝見しております。
窯詰め、窯焚きは大変ですが、楽しいですよね。
焚いているときは、もうしばらくいいやと思うけれど
焚きおわると、次はどうやろうなんて考えている自分が
います。中毒ですね。
これから暑い日が続きますが、頑張って下さい。
その節はお世話になりました。
おかげさまでなんとかネット社会に復帰です。
窯出し楽しみにしております。
カエルちゃんみたいなぁ。(*^o^*)
すっっっっっごい楽しみです♪