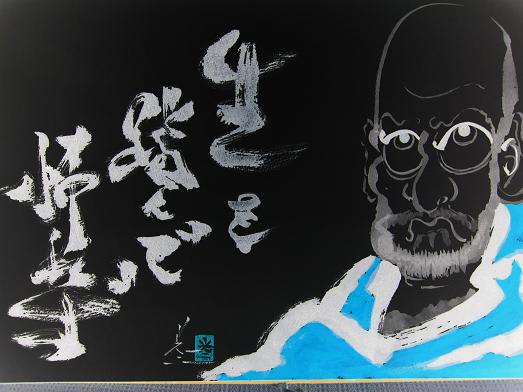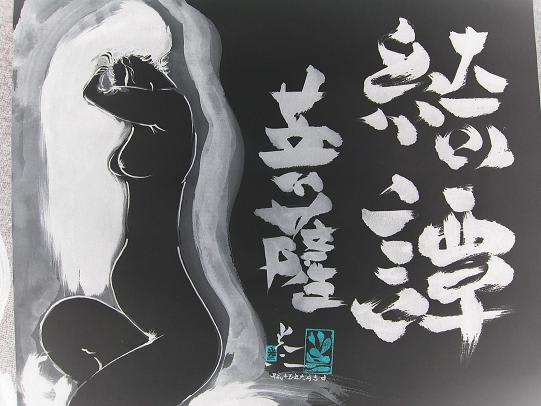岩に咲く椿。
椿に咲かれた岩。
岩椿か。椿岩か。
コペルニクスさんとプトレマイオスさん。
優秀さに甲乙は無い。
天が動くのか。地が動くのか。
神はこのような不細工なものをつくるはずがない。
完全なる神がサイコロ博打のような事をするはずが無い。
という先入観との戦い。パラダイムシフト。
椿はたぶん。誰かが慰みに岩の穴に入れたのだろうなぁ。
しかしだ。岩の上には椿が咲いている限りは。もしや。
もしやもしやの。
3回転半捻り降りのウルトラDをやってのけたのかもしれませんぞ。
椿氏。
着地。ぴたりと決まりました。9.999999.
ぐらいの確率。
またまたはたまた。
この岩には穴が開いているのだ。
一枝一輪。渾身の開花ではあるまいか。
根性椿氏。
実証してみる根性があたしには無い。
ばかなやつだとお思いでしょうが。
ばかなやつほど新しい事を欲しがるものでございやす。
理由なぞつけずに、そのまんま楽しむのがよいこともまま。
あるのであります。