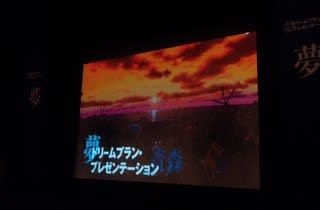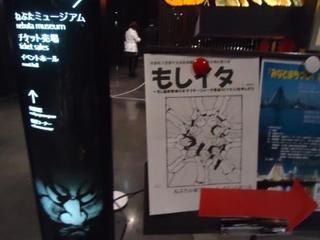先日、五所川原市立三輪(みつわ)小学校で行われた「選択理論」の学習会に参加してきました。
講師は、選択理論を日本で初めて取り入れた学校(クォリティ・スクール)である神奈川県立相模向陽館高等学校の校長・伊藤昭彦さん。参加者は、三輪小学校の教職員、PTA、その他一般参加者を含めて約60人。伊藤さんから、実践・演習をとおして「選択理論」の基本と実際を学びました。&nbs . . . 本文を読む
記憶に残る年が必ずしも歴史に残るとは限らないわけですが、東日本大震災の起こった2011年は、少なくとも日本人にとっては、間違いなく記憶にも歴史にも残る1年になりそうです。
「今年の漢字」は「絆」でした。震災からの復興そして再生に向けて、日本だけでなく、世界中の人たちが暖かい支援の手を差し伸べてくれました。「お互いさま」という考え方は、日本の専売特許ではなく、世界共通のものなんだな . . . 本文を読む
2日間、県の自治研修所で「課題解決のための思考力養成研修」を受講してきました。
それにしても、「問題解決」って、古くて新しいテーマだよなあと思う。毎日の生活の中でも私たちは様々な問題を抱え、そしてそれを無意識の中で一つずつ解決しながら生きているんだけど、その手順をちゃんと検証することはまずない。
問題というのは、「理想(目標)と現実のギャップ」とよく言われますが . . . 本文を読む
大阪のダブル選挙で、「橋下派」が勝利をおさめました。まあ、大阪府が大阪都になろうがなるまいが、それはどうでもいいんですが、問題は、あの「教育基本条例」です。この12月府議会で可決される見通しです。いよいよ大阪の教育があの妙な条例によって変えられていくのかと思うと、子どもたちや教員が気の毒でしょうがない。
橋下さん、やっぱりどこか勘違いしているとしか言いようがありませんね。政治が教 . . . 本文を読む
昨日は、生き生きとした高校生たちに出会うことができましたが、今日は、高校生に負けないくらい夢を追いかけている大人の皆さんの話を聞いてきました。「ドリームプランプレゼンテーション青森2011」。
県内在住の9人の若者(じゃない方も?)たちが、いろいろな立場から語る夢。ただ「語る」だけではありません。9つの夢は、それぞれに音楽を付けた10分間のフォト・ストーリーに予めまとめられていて、プレゼンテータ . . . 本文を読む
青森中央高校演劇部による被災地応援公演「もしイタ ~もし高校野球の女子マネージャーが青森の『イタコ』を呼んだら」。
そんなつもりはなかったのに、またもや高校生たちに泣かされてしまいました。さすが青森中央高校演劇部。2度も日本一になっただけのことはある。
「被災地応援公演」とあるように、この芝居は、東日本大震災の被災地の皆さんの応援のためにつくられました。今日の青森市での公演を含め、11月下旬か . . . 本文を読む
前から見たい見たいと思っていた、青森県立田子高校の「田子神楽」。念願かなって、ようやく見ることができました。そして、そのあまりの美しさ、優雅さに、ほんとうに心を動かされました。
田子高校の郷土芸能部は、この「田子神楽」と、南部地方に古くから伝わる盆踊り「ナニャドヤラ」を組み合わせた演目「田子の杜(もり)の芸能」で、平成22年、宮崎県で開催された全国高等学校総合文化祭の郷土芸能部門で、県勢初の最優 . . . 本文を読む
ほとんど毎日のように、子どもの虐待の報道を目にする昨今。記事を読むたび、なぜ?どうしてこんなことになるのか?と悲しくいたたまれない気持ちになります。
虐待をテーマにした小説『永遠の仔』の著者天童荒太さんが、先日の新聞で、長い時間をかけて「虐待の社会」を変えていく必要がある、と主張しています(2011年9月6日付け産経新聞)。
天童さんは、『永遠の仔』に関する取材の中で、これまで話しても掲載され . . . 本文を読む
「自助、共助、公助」とは、「災害時にあなたを助けてくれるのは誰か」を考える時によく使われる言葉です。
「自助」とは、災害が発生したときにまず自分自身の身の安全を守ること。この場合、守るのは「自分自身」だけでなく、「家族」も含まれます。正確な情報を得て、安全な場所に避難する、危険な場所には何があっても近づかない、といったことですね。学校なら、地震だったらまずは揺れが収まるまで机の下に隠れる、といっ . . . 本文を読む
『つなみ─被災地のこども80人の作文集』『』≫Amazon.co.jp
(文藝春秋8月臨時増刊号)。
こういう本を読むのは本当にいたたまれない。
いたたまれないけれど、でも、子どもたちがいろんな角度から投げてくる直球を、大人はしっかり受け止めなければならないと思います。
津波の襲来。街を呑み込みながら押し寄せる黒い波を見て、どんなにか怖かったことでしょう。
「友だちだって、一人流されたし、 . . . 本文を読む
先週から、インターハイ(「北東北総体」)が始まって、ねぶたの町にも選手らしい高校生の集団をちらほら見かけます。
7月28日、皇太子殿下ご臨席のもと、盛大に開会式が行われましたが、セレモニー終了後、これまでこの大会を支えてきた高校生実行委員や、開会式を盛り上げてくれた高校生たちと殿下との「御交流会」がありました。
前日から入念なリハーサルをしてきたのですが、やっぱり、「ホンモノ」の殿下を前にして . . . 本文を読む
とある県の事業の報告会に行ってきました。2年間にわたる事業の成果を報告し、今後の展望を…という性格の催しなんだろうと思いますが、「成果」はともかく、「今後の展望」があまり見えない報告会でした。
事業としては、いくつかの先進的な「モデル的な研究実践」を実施して、その成果を県内各地に普及させる…というお決まりのパターンです。この種の事業は、いかに「県内各地に普及」させるかという部分が一番の「肝」だと . . . 本文を読む
青森市内のある中学校で、期末試験の保健体育の試験問題に「不適切な問題」があったというニュースが、新聞・テレビなどの全国版でも流れていました。
その問題とは、
・『用具を準備しチャイム前に着席すること』は99.9%できていますが、ごく稀にできないで指導されている人がいました。誰ですか?
・『マット運動の時、服装を守って(ハーフパンツ)授業を受ける』ことは99%できていますが、時々減点されている人が . . . 本文を読む
朝日の池澤夏樹さんの連載「終わりと始まり」。12月8日付けは、「死んだ子供たちのために 閉鎖空間という地獄」。10月下旬に起こった群馬県の小学校6年生、上村明子さんの自殺、その1ヶ月後に起きた札幌の中学校2年生の少女の自殺。
痛ましいことである。
子供に選挙権を与えないのは判断力が未熟であるからだ。同じ論法から言えば、仮に人には自殺の権利があるとしても、子供はその権利を与えられるべきではない。子 . . . 本文を読む
中島義道『うるさい日本の私』で問題にしているのは、街なかにおける「騒音」です。駅やデパートのアナウンス、選挙運動の連呼、宣伝スピーカーから流れる音楽など、聞きたくない人にも聞こえてしまう「騒音」はいらない、と中島氏は口を酸っぱくして説く。「バスや電車といった公共の乗物、デパートや駅の構内、海水浴場、観光地といった公共の場所で、彼は耳障りで不必要と思われる音、つまり音楽(BGM)、マイクでの呼びかけ . . . 本文を読む