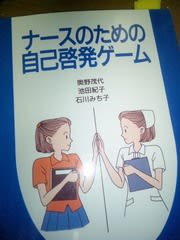宇宙飛行士の山崎直子さんのインタビュー記事を読む機会がありました(金融広報中央委員会「くらし塾きんゆう塾」2014年冬号)。ロケットで初めて宇宙空間に飛び出した瞬間、船内が無重力状態になった時の感動について、山崎さんは語る。
「体がふわっと浮き上がっていきました。同時に塵や埃までもが宙に浮き、それらが光に照らされて美しく輝いて見えたのです。とうとう宇宙に来たという感激と感謝とともに、表現しがたい . . . 本文を読む
少し前ですが、ある雑誌(「教育ジャーナル」)で、鹿児島県与論町の教育がシリーズで紹介されていました。与論町のある与論島は、鹿児島県の最南端、沖縄本島からわずか28kmのところに位置する隆起珊瑚礁の島です。人口は約5,400人。こども園が3園、小学校3校、中学校と高校が1校ずつ。
与論の教育は、高校を卒業して島を離れる(「島立ち」というそうです)子どもたちにどんな力を育てるかに尽きるという。その根 . . . 本文を読む
「教育再生なくして国家再生ない」─第二次安部内閣がぶち上げた教育再生実行会議の委員でもある八木秀次氏(高崎経済大学教授)のこんな見出しの「正論」が産経新聞に掲載されていました(2013年2月1日付け)。
八木氏は、30年も前のレーガン大統領時代の米国の教育改革を引き合いに出して、当時の「危機に立つ国家」の認識は、今の日本と同じだと言う。米国が「抜本的な教育改革」によって経済や国際的地位を立て直し . . . 本文を読む
先日の「内外教育」に、「子どもの指し手感覚」という興味深いエッセイが載っていました。中学生の「修学旅行のグループ編成」を題材にして、子どもの自主性について考えるという内容です。
修学旅行のグループ編成というのは悩ましい問題です。仲間はずれが出ることを心配して、多くの担任は恨みっこなしの「くじ引き」という選択肢を選びます。しかし、とある中学校の学級活動で、「好きな者同士でグループをつくる」という案 . . . 本文を読む
文化人類学者の上田紀行さんが1989年に著した『覚醒のネットワーク』は、何かにつけひも解いてはそのたびに新たな気づきを得られる本の一つです。
十数年前、私が高校から総合社会教育センターに異動になって担当したあるセミナーで、その上田紀行さんと、この本を世に送り出してくれたカタツムリ社の加藤哲夫さんのお二人を講師としてお招きしたことがありました。このお二人の講演、今考えても、なんて奥が深かったんだろ . . . 本文を読む
横浜町立南部小学校で開催された「演劇ワークショップ」の様子を先日見学させていただきましたが、この取組は、もともと文部科学省の「児童生徒のコミュニケーション能力の育成に資する芸術表現体験事業」の一環として行われているものです。
南部小学校では、今年度すでに、6月にも今回と同じ講師(田野邦彦さん、渡辺香奈さん)をお招きして、3日間のワークショップを開催しています。その内容を、同校の中野正喜校長先生が . . . 本文を読む
文部科学省の「児童生徒の問題行動調査」によると、2011年度に全国の学校が把握したいじめ件数は7万231件にのぼるそうです。
都道府県別の集計を見ると、その「差」に改めて驚きますね。写真では切れてますが、児童生徒一千人あたりの認知件数で一番多いのは熊本県の32.9件。一番少ないのは、お隣の佐賀県の0.6件。その差はなんと約55倍です。実件数で見ても、熊本は6,832件で佐賀は68件。どう見て . . . 本文を読む
前にも紹介したことがある財団法人日本青少年研究所の国際比較調査。昨年、日本、米国、中国、韓国の4カ国の高校生を対象に実施した調査(高校生の生活意識と留学に関する調査)で、またまた日本の高校生の「自分への自信のなさ」が浮き彫りになっています。
たとえば、「私は他の人々に劣らず価値のある人間である」という問いに「当てはまる」と回答した高校生の割合。
日本 39.7%
米国 79.7%
中国 86. . . . 本文を読む
今日のセミナー、「不登校・高校中退・発達障がい ~青年期を見据えた学齢期における支援のあり方とは~」。北海道教育大学札幌校准教授、平野直己さんの講演「子どもたちを取り巻いている“まなざし”」と、平野さんを交え、主催者の家庭訪問サポート「つがる・つながる」金澤拓紀さんがコーディネートを務めるパネルディスカッションという構成。
平野さんは、これまで少年鑑別所に . . . 本文を読む
病院という世界には、病院独特のルールみたいなものがあって、医師も看護師も入院患者も付き添いも見舞い客も、みんなそのルールに否応なく縛られている。ここ数ヶ月、ある大病院に通っているうちに、だんだん分かってきました。
病院の使命は、患者の病を治して社会復帰させること。その目標に向かって、関係する人みんながそれぞれに自分の役割を果たしています。医師や看護師さんが親身になって治療にあたっ . . . 本文を読む
facebook経由で知ったネット記事、『2030年までに技術革新によって全ての仕事の50%が消滅する!! 社会の変化と「消える仕事」「新しい仕事」をまとめてみた』。
急速な技術革新で、電力業界、自動車産業、製造業といった多くの分野で「消える職業」が出てくるだろうというもの。「技術革新」というのは、ほとんどがコンピュータとかインターネットなど情報通信技術なのですが、「ロボット」と . . . 本文を読む
先日の選択理論(クオリティスクール)の講座で知り合った方からの紹介で、今日、Love Aomoriプロジェクト主催の勉強会があるというので、仕事をさっさと片付けて、雪の中、ワ・ラッセへ出かけてみました。
選択理論心理士で、米国グラッサー協会認定のインストラクター、渡邊奈都子さんを招いての大人の学びの場。テーマは、「大切な相手との絆を深める3つの法則」。パートナーとのつながりについ . . . 本文を読む
先日、何十年かぶりで学校給食をいただきました。メニューは、五目ちらし、ワカメと粗引きソーセージのスープ、牛乳。皿に載っている具をご飯にかけると五目ちらしになるのであーる。見た目、ちょっとさびしいような気もしますが、でもさすがに栄養バランスのしっかりとれたメニューです。自校給食だけあって、味も申し分ない。決して、「変な給食」ではありません。あ、でもそういえば、子どもたちのお楽しみのデザートっぽいのが . . . 本文を読む
「ヘリウム・リング」というワーク。伊藤昭彦校長は、チーム・ビルディングに向けて、「教職員の思いを一つにする」ためによくこれをやっていたそうです。今回の学習会で実際に私たちも体験することができました。
プラスチック製の軽いフラフープを十数人が囲み、それぞれ人差し指1本で支える。一人も指を離すことなく、全員で息を合わせてそれを下に降ろしていき、地面に着地させる。以前、新聞紙を丸めて筒 . . . 本文を読む
前回紹介した神奈川県立相模向陽館高等学校は、単位制による多部制定時制課程の普通科高校で、生徒の入学時はこんな感じだそうです。
・4割強が小・中学校時に不登校を経験
・3割強が経済的に苦しい家庭状況
・1割強が外国につながりがある
・9割強が学力不振
こういう学校って、よく「教育困難校」なんて呼ばれるけれど、なんだかいやな言い方ですよね。大人の立場から見て、 . . . 本文を読む