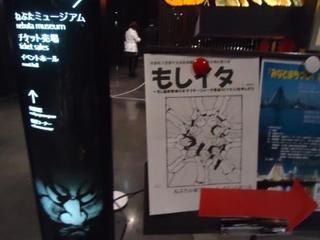
青森中央高校演劇部による被災地応援公演「もしイタ ~もし高校野球の女子マネージャーが青森の『イタコ』を呼んだら」。
そんなつもりはなかったのに、またもや高校生たちに泣かされてしまいました。さすが青森中央高校演劇部。2度も日本一になっただけのことはある。
「被災地応援公演」とあるように、この芝居は、東日本大震災の被災地の皆さんの応援のためにつくられました。今日の青森市での公演を含め、11月下旬から12月にかけて、気仙沼市、大船渡市、釜石市、久慈市と被災地での公演が予定されているようです。この芝居を被災地の皆さんが観てどう感じるのか、大いに興味があるところです。というか、被災地の皆さんだけでなく、一人でも多くの人に観てもらいたい芝居だなと思います。たぶん、この作品も、全国大会に出たら最優秀賞は間違いないでしょう。
まず、タイトルが秀逸。言うまでもなく、映画にもなった「もし高校野球の女子マネージャーがドラッガーの『マネジメント』を読んだら」をパクったもの。もちろん、芝居の内容も、この物語が下敷きにされています。つまり、「ある弱小野球部のマネージャーが一念発起して野球部を甲子園に連れていくためにがんばる」というストーリー。元の作品は、そのためにドラッガーの「マネジメント」の考え方と手法が使われるのですが、こちらはなぜか「イタコ」。
「イタコ」って、恐山などで死者の「口寄せ」をしてくれる婆さま、ですが、時に、青森といえばイタコを連想する人も決して少なくない、強烈な「青森のイメージ」の一つ。「イタコ」を持ち出したのは、この芝居が青森からの発信であるというメッセージ。これも一つの戦略なのでしょう。
そして、もうひとつ、「イタコ」を登場させる理由があります。「口寄せ」というのは、死者の霊を呼び出し、自分の体をその人の魂に託して語らせるもの。東日本大震災の膨大な数の死者のほとんどは、自分の死を予期せぬまま無念のうちに亡くなってしまった方だろうと思います。生き残った家族や友人たちに伝えたいことがたくさんあるだろうと思います。イタコなら、そんな彼らの思いを伝えることができる…。
舞台装置や小道具を一切使わず、27名の高校生の生身の体だけで勝負。照明や音響といった効果もなく、BGMや効果音は出演者が自ら肉声で発する。演じられるスペースさえあればどこでも上演します、と「被災地での上演を想定したもの」とチラシにあるとおり、話題性も豊富です。でも、確かに、それだけの生々しい迫力はありました。まさにこれが芝居の原点。たぶん、高校生のパワーだからできることなんだろうと思う。そして、そのパワーを100%引き出す演出力。テンポ、セリフの面白さ、場面の転換術、一人ひとりの演技力、すべての要素がほぼ完璧に絡み合い、60分間の見ごたえのあるドラマが展開される。


(写真は渡辺源四郎商店店主日記より)
それにしても、演じる高校生たちのなんと生き生きしていることか。芝居の中で、重要なキーワードとして、「好きな野球ができる幸せ」というフレーズがありましたが、彼らこそ、「好きな演劇ができる幸せ」に十分浸っていることが伝わってきました。「日本を元気に」とか「観客に元気を与える」なんてあえて言われなくても、彼らを見ているだけで、こっちもがんばろうという気になります。
もう一度言いますが、この芝居は本当に一人でも多くの人に見てもらいたいと思う。まずは、被災地で、しっかりメッセージを伝えてきてほしいなと思います。
そんなつもりはなかったのに、またもや高校生たちに泣かされてしまいました。さすが青森中央高校演劇部。2度も日本一になっただけのことはある。
「被災地応援公演」とあるように、この芝居は、東日本大震災の被災地の皆さんの応援のためにつくられました。今日の青森市での公演を含め、11月下旬から12月にかけて、気仙沼市、大船渡市、釜石市、久慈市と被災地での公演が予定されているようです。この芝居を被災地の皆さんが観てどう感じるのか、大いに興味があるところです。というか、被災地の皆さんだけでなく、一人でも多くの人に観てもらいたい芝居だなと思います。たぶん、この作品も、全国大会に出たら最優秀賞は間違いないでしょう。
まず、タイトルが秀逸。言うまでもなく、映画にもなった「もし高校野球の女子マネージャーがドラッガーの『マネジメント』を読んだら」をパクったもの。もちろん、芝居の内容も、この物語が下敷きにされています。つまり、「ある弱小野球部のマネージャーが一念発起して野球部を甲子園に連れていくためにがんばる」というストーリー。元の作品は、そのためにドラッガーの「マネジメント」の考え方と手法が使われるのですが、こちらはなぜか「イタコ」。
「イタコ」って、恐山などで死者の「口寄せ」をしてくれる婆さま、ですが、時に、青森といえばイタコを連想する人も決して少なくない、強烈な「青森のイメージ」の一つ。「イタコ」を持ち出したのは、この芝居が青森からの発信であるというメッセージ。これも一つの戦略なのでしょう。
そして、もうひとつ、「イタコ」を登場させる理由があります。「口寄せ」というのは、死者の霊を呼び出し、自分の体をその人の魂に託して語らせるもの。東日本大震災の膨大な数の死者のほとんどは、自分の死を予期せぬまま無念のうちに亡くなってしまった方だろうと思います。生き残った家族や友人たちに伝えたいことがたくさんあるだろうと思います。イタコなら、そんな彼らの思いを伝えることができる…。
舞台装置や小道具を一切使わず、27名の高校生の生身の体だけで勝負。照明や音響といった効果もなく、BGMや効果音は出演者が自ら肉声で発する。演じられるスペースさえあればどこでも上演します、と「被災地での上演を想定したもの」とチラシにあるとおり、話題性も豊富です。でも、確かに、それだけの生々しい迫力はありました。まさにこれが芝居の原点。たぶん、高校生のパワーだからできることなんだろうと思う。そして、そのパワーを100%引き出す演出力。テンポ、セリフの面白さ、場面の転換術、一人ひとりの演技力、すべての要素がほぼ完璧に絡み合い、60分間の見ごたえのあるドラマが展開される。


(写真は渡辺源四郎商店店主日記より)
それにしても、演じる高校生たちのなんと生き生きしていることか。芝居の中で、重要なキーワードとして、「好きな野球ができる幸せ」というフレーズがありましたが、彼らこそ、「好きな演劇ができる幸せ」に十分浸っていることが伝わってきました。「日本を元気に」とか「観客に元気を与える」なんてあえて言われなくても、彼らを見ているだけで、こっちもがんばろうという気になります。
もう一度言いますが、この芝居は本当に一人でも多くの人に見てもらいたいと思う。まずは、被災地で、しっかりメッセージを伝えてきてほしいなと思います。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます